関宮 大久保からハチ高原・鉢伏山
コース難易度
初級
- 日帰り
- 5時間5分
コースガイド
テクニック度 |
|
山行日数 |
日帰り |
歩行時間 |
5時間5分 |
歩行距離 |
|
最大高低差 |
|
水場 |
|
トイレ |
登山と高原歩きを満喫できるパノラマコースとして人気のあるハチ高原・鉢伏山は、天候に恵まれれば登山経験のない方でも歩くことができるでしょう。学校登山でもよく利用されるコースです。ここでは、学校登山などで歩かれている鉢伏山の周遊コースではなく、ハチ高原の西端から高原をまるごと歩いて鉢伏山に登る、大パノラマコースをご案内します。多少の歩きごたえがある、充実したコースです。
アクセスは、八鹿駅から全但バスに乗り、終点の鉢伏で下車します。マイカー利用の場合は、大久保周辺の駐車場を利用するとよいでしょう。バスを降りたら、左手の民宿街の坂を登ります。福屋別館を過ぎ、集落を抜けるとすぐに分岐があります。ここで左の沢沿いの道へ進み、橋を渡ってさらに沢沿いをたどります。沢が左へ曲がる地点で沢から離れ、右の斜面に続く道に入ります。この道は、地元の植林管理道で、標高1,019mの鞍部まで続いています。
道中は、ササが繁る道から杉林の急登へと変わります。特に降雨後は滑りやすいため、慎重に歩き、スローペースを心がけましょう。この区間が全行程のなかで最もきつい部分です。標高900m付近まで登ると、視界が開けた草原に出ます。ここからは、これから歩くなだらかな稜線を見渡すことができ、新緑の季節や晩秋の頃に訪れるのがおすすめです。
標高1,019mの鞍部に到着すると、左手には氷ノ山、右手には鉢伏山が広がります。ここから高丸山に向かい、なだらかな道を進みます。左手には、青ヶ丸、中ノ丸、仏ノ尾など北但馬の山々を望むことができます。高丸山を越えると、鉢伏山への登りが始まります。傾斜がきつい登りですが、山頂に到着すると、振り返ったときに見える氷ノ山の姿が印象的です。
下山は、南隣のピークを巻くようにして下り、林道を通ってハチ高原へと向かいます。ハチ高原交流促進センターから農道を下ると大久保の集落に出ることができ、鉢伏バス停へと戻ります。
アクセスは、八鹿駅から全但バスに乗り、終点の鉢伏で下車します。マイカー利用の場合は、大久保周辺の駐車場を利用するとよいでしょう。バスを降りたら、左手の民宿街の坂を登ります。福屋別館を過ぎ、集落を抜けるとすぐに分岐があります。ここで左の沢沿いの道へ進み、橋を渡ってさらに沢沿いをたどります。沢が左へ曲がる地点で沢から離れ、右の斜面に続く道に入ります。この道は、地元の植林管理道で、標高1,019mの鞍部まで続いています。
道中は、ササが繁る道から杉林の急登へと変わります。特に降雨後は滑りやすいため、慎重に歩き、スローペースを心がけましょう。この区間が全行程のなかで最もきつい部分です。標高900m付近まで登ると、視界が開けた草原に出ます。ここからは、これから歩くなだらかな稜線を見渡すことができ、新緑の季節や晩秋の頃に訪れるのがおすすめです。
標高1,019mの鞍部に到着すると、左手には氷ノ山、右手には鉢伏山が広がります。ここから高丸山に向かい、なだらかな道を進みます。左手には、青ヶ丸、中ノ丸、仏ノ尾など北但馬の山々を望むことができます。高丸山を越えると、鉢伏山への登りが始まります。傾斜がきつい登りですが、山頂に到着すると、振り返ったときに見える氷ノ山の姿が印象的です。
下山は、南隣のピークを巻くようにして下り、林道を通ってハチ高原へと向かいます。ハチ高原交流促進センターから農道を下ると大久保の集落に出ることができ、鉢伏バス停へと戻ります。
山と高原地図ホーダイ
道迷いの不安を軽減 登山専用地図アプリ

紙地図60年以上の信頼をスマホで
複雑な登山道も、正確な地図で不安を軽減。
登山の専門家が調査した正確なルートやコースタイム、見どころ情報までを一つにまとめました。
紙地図「山と高原地図」として60年以上の信頼を重ねてきた情報が、アプリ「山と高原地図ホーダイ」で。
今すぐダウンロードして安全登山を楽しみましょう。
登山の専門家が調査した正確なルートやコースタイム、見どころ情報までを一つにまとめました。
紙地図「山と高原地図」として60年以上の信頼を重ねてきた情報が、アプリ「山と高原地図ホーダイ」で。
今すぐダウンロードして安全登山を楽しみましょう。
掲載書籍
-
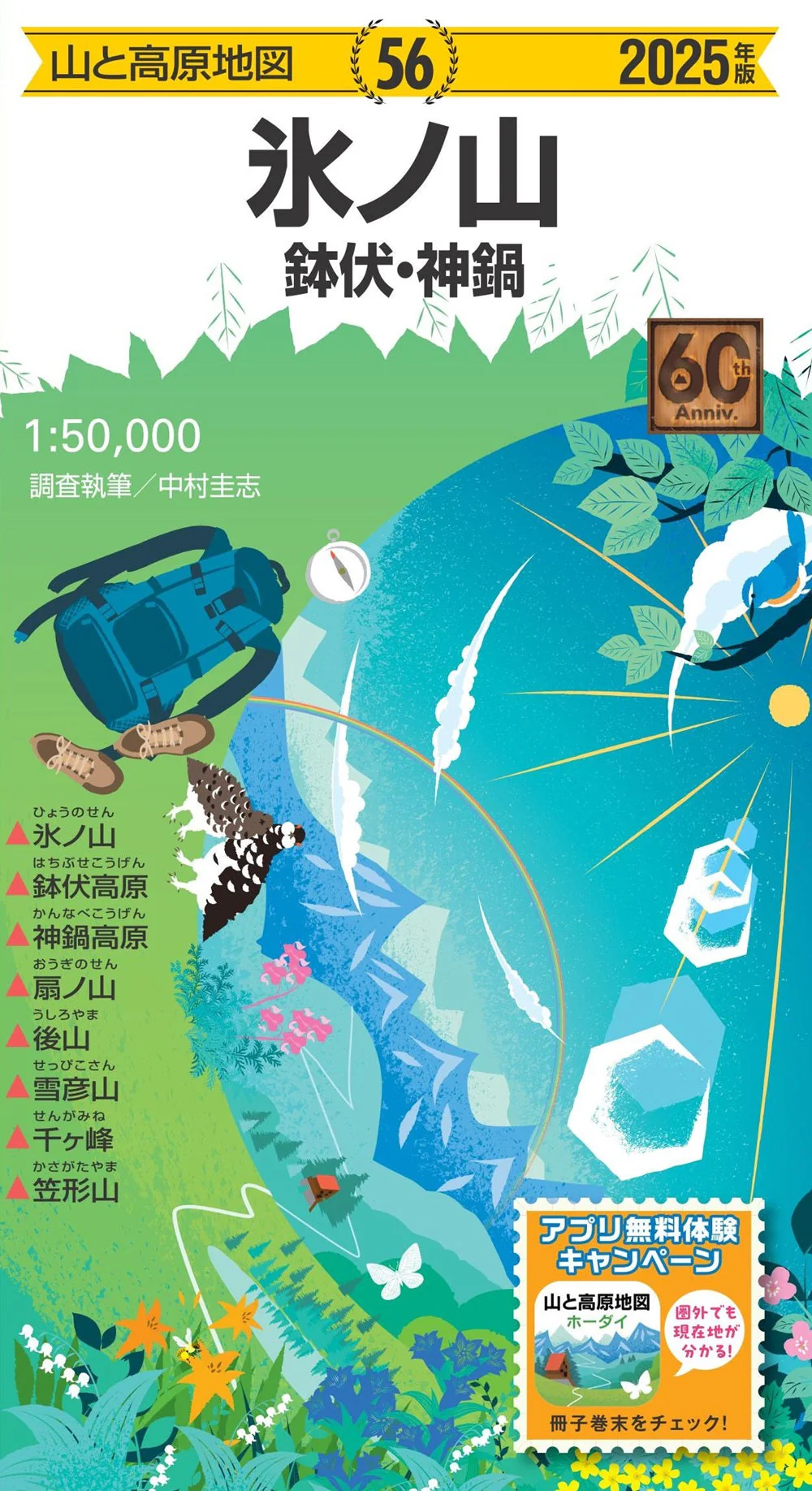 氷ノ山 鉢伏・神鍋 2025
氷ノ山 鉢伏・神鍋 2025






