岩殿山登山ガイド 稚児落としを経て断崖絶壁の絶景と歴史を歩くコース

山梨県大月市にそびえる岩殿山(いわどのさん)は、標高634メートルと低山ながら「秀麗富嶽十二景」や「山梨百名山」に選ばれる名峰です。鏡岩と呼ばれる大きな岩壁が特徴で、断崖を望むスリルある登山コースが魅力。初心者でも歩きやすい道から、岩場の緊張感を味わえる道まで変化に富み、幅広い登山者に親しまれています。
とくに稚児落としから見下ろす眺望は圧巻で、富士山や大月の町並みを一望できます。登山経験を積みたい初心者や、手軽に岩場歩きを体験したい方にもおすすめです。
この記事では、JR中央本線・大月駅を出発し、稚児落としや兜岩、鏡岩を経て岩殿山へ登る代表的なコースをご紹介します。実際の歩行記録をもとに、コースの特徴や見どころ、安全に楽しむためのポイントを詳しく解説していきます。
目次
岩殿山の見どころと魅力 歴史と絶景を味わえる登山コース

岩殿山は、切り立った岩壁と富士山の展望で知られる大月市の象徴的な山。麓から見上げると、ひときわ目を引くのが鏡岩と呼ばれる断崖で、JR中央本線・大月駅周辺からもその姿を確認できます。
山頂や鏡岩の展望スペースに立つと、富士山をはじめ、高川山や雁ヶ腹摺山など山梨を代表する山々が一望でき、登山者を魅了する絶景が広がります。
春には桜や山ツツジが山肌を彩り、山麓の「丸山公園」や「岩殿山ふれあいの館」周辺でも花見を楽しめるのも魅力です。

さらに岩殿山は、断崖の地形を活かして築かれた戦国期の要害「岩殿城(いわどのじょう)」の跡地でもあります。山頂は本丸跡にあたり、登山道には巨大な岩を利用した揚城戸跡や、平坦地に広がる馬場跡など、多くの遺構が点在。登山とともに歴史探訪も楽しめるのが、岩殿山ならではの魅力です。
岩殿山登山コースの始点・大月駅へのアクセス方法

岩殿山の登山コースは、JR中央本線・大月駅を起点に歩き始めるのが一般的です。電車・車ともにアクセスしやすく、首都圏からの日帰り登山にも適しています。
電車の場合はJR中央本線のほか、富士山麓電気鉄道の富士急行線が利用できます。車の場合は大月駅前ロータリーの駐車場(30分ごと200円)が便利です。駅周辺にはコインパーキングも点在しているため、満車の場合は周辺駐車場を利用すると安心です。
大月駅から登山口の「稚児落とし口」までは徒歩で約30分。市街地を抜けて向かう道は、登山前のウォーミングアップにもなります。なお、バスを利用して登山口付近へ行くことも可能ですが、便数は限られるため、利用の際は必ず事前に時刻表を確認しておきましょう。
大月駅から登山口付近までのバスアクセス
大月駅から富士急バス・西奥山行きに乗車し、「浅利公民館前」で下車すると、稚児落とし口まで徒歩約5分で到着します(運賃230円)。
また、下山後に畑倉登山口方面へ出た場合は、徒歩10分ほどで「岩殿上」バス停に着きます。ここから大月駅へ戻るバスがあり、運賃は200円です。登山の計画にあわせて利用すると移動がスムーズになります。
岩殿山登山コース詳細 稚児落としから断崖を歩くスリルあるルート

岩殿山の登山では、天神山から稚児落としを経由する周回コースが定番です。今回は、大月駅を起点に左回りで天神山・稚児落としを通り、兜岩や岩殿城跡を巡って岩殿山山頂へ。下山は畑倉登山口を経て大月駅に戻るルートをご紹介します。
コース上には案内板が多く設置されているため、道迷いの心配は少なく安心して歩けます。見どころも豊富で、歴史遺構や断崖絶壁の展望を楽しめるのが魅力です。
ハイライトは稚児落としと兜岩周辺。断崖の縁を歩くスリルある区間で、鎖場や岩場が続きます。装備を整えて臨めば初心者でも挑戦可能ですが、滑りにくいトレッキングシューズや手袋の着用が望ましいでしょう。安全第一で歩けば、スリルと絶景を同時に楽しめる登山コースです。
タイムスケジュール
コースデータ
・難易度:ふつう(岩場・鎖場あり)
・歩行距離:7.8km
・所要時間:約6時間(休憩含む)
・最大高低差:310m
・トイレ:大月駅にあり
・登山者の多さ:やや少なめ
登山記録メモ(8月下旬の例)
・時期:8月下旬
・天候:晴れ
・気温:最高30℃/最低20℃
・体感メモ:日中は暑く熱中症リスクが高いため、こまめな水分・塩分補給と休憩が必要
登山時の注意点
・鏡岩の落石により、強瀬ルート・岩殿ルートは通行止めです。最新情報は大月市ホームページで必ず確認してください。
・荒天時は規制外のエリアでも土砂崩れの危険があります。天候と登山道の状況を事前に確認しましょう。
・冬季は積雪により危険が増すため、初心者は冬の登山を避けるのが無難です。
大月駅から稚児落とし口へ 市街地を抜けて登山開始

JR中央本線・大月駅からは、市街地を抜けて天神山方面へ向かい、稚児落とし口まで歩いていきます。およそ30分の道のりは、登山前のウォーミングアップにちょうどよい距離です。道中は山に囲まれた緑豊かな景色や住宅街が広がり、これから登る岩殿山や天神山を望むと登山への意欲も高まります。

しばらく進むと道路右側に下り坂があり、その先に浅利川にかかる小さな橋が見えてきます。この分岐はやや分かりにくいため、地図アプリや登山地図でルートを確認しながら進むのがおすすめです。

橋を渡ったら正面の民家へ進み、脇の細い坂道を登ると登山口に到着します。ここからが稚児落としへと続く登山道の始まりです。

坂道を登ると本格的な山道に入ります。夏場は草木が茂って足元が見えにくくなるため、トレッキングポールを使うと歩きやすいでしょう。やがて岩殿山方面を示す標識と、右側に階段が見えてきます。手すりは老朽化の恐れがあるため、手をかける際は十分注意してください。

階段を上がるとロープと鎖が設置された急坂が続きます。ここからはグローブを装着し、鎖やロープを活用しながら登っていきます。段差の大きな岩や木の根、落ち葉で滑りやすい箇所も多いため慎重な歩行が必要です。

途中には展望が開ける場所があり、ひと息つきながら景色を楽しめます。この日は真夏で気温も高く、水分と塩分をこまめに補給しながら進みました。さらに登山道を歩いていくと、木々の間から遠くの山並みや稚児落としの姿が見えてきます。いよいよコースの核心部へと向かう実感が湧いてきました。
稚児落としから天神山・兜岩へ 断崖と尾根道を抜ける変化に富んだ道

登山開始からおよそ1時間で稚児落としに到着します。高さ150メートルの断崖が切れ落ち、足元をのぞくと背筋がすくむほどの迫力。目の前には雄大な山並みが広がり、険しい登山道を乗り越えた先にだけ見られる絶景が待っています。
「稚児落とし」という名は、戦国時代の岩殿城にまつわる悲しい伝承に由来します。落城の際、追っ手に見つかるのを恐れた母親が泣き出した稚児を崖から落としたという話で、ここからこの名がついたと伝えられています(諸説あり)。物語に思いを馳せつつ、ここで10分ほど休憩して体力を整えました。

稚児落としの足元は大きな岩になっており、足を踏み外すと危ないため慎重に岩を下ります。岩場を歩いた先に道標があり、天神山方面へと向かいます。

途中の開けた場所からは、先ほど通過した稚児落としを振り返ることができ、自分が歩いてきた断崖の高さを実感しました。

ここからは尾根歩きが続きます。左右は深い谷になっているため、足元に注意して歩きましょう。

稚児落としを出発しておよそ25分、天神山山頂に到着天神山の山頂に到着。木々に囲まれて展望はありませんが、呼吸を整えつつ次の目的地・兜岩を目指します。

兜岩へ向かう道中は、急な傾斜にロープが張られた区間があり、慎重に進む必要があります。夏場は木々に遮られて眺望が少ないものの、尾根道のアップダウンが続き、登山らしい緊張感を味わえます。

さらに進むと道標が現れ、兜岩を横切る「トラバースルート」と、左側の迂回路に分かれます。現在は崩落によりトラバースルートが通行止めのため、迂回路を進みます。

迂回路は足場が狭く急斜面で、倒木も多く歩きづらい区間。ロープを頼りに一歩ずつ進み、慎重に兜岩へと近づいていきます。
兜岩の展望と鎖場歩き 緊張感ある岩場を越えて岩殿城跡へ

兜岩に到着しました。木々の隙間からは開放感のある眺望が広がり、稚児落としより標高はやや低いものの、大月市街や周囲の山々を間近に望むことができます。急斜面を登ってきた疲れを癒やすように、兜岩横の小さなスペースで10分ほど休憩をとりました。体力を回復させたら、岩殿山山頂を目指して出発します。

途中には「鎖場コース」と「林間コース」の分岐があります。今回はスリルを求めて鎖場へ進みました。岩場は垂直に近い切り立った地形で、慎重な判断と装備が求められます。分岐直後からロープが設置されており、小石や砂で滑りやすいため木の根を頼りに下ります。

続いて大木に巻かれた鎖を使い、狭い岩の割れ目を下りていきます。ほぼ垂直の岩場には梯子もありますが、間隔が狭く歩きにくいため鎖を活用するのが安全です。岩のくぼみに足をかけ、鎖を離さず慎重に通過しましょう。

鎖場を抜けると尾根伝いの道になり、再びロープ区間が現れます。先ほどより傾斜は緩やかですが、足元は小石や木の根で滑りやすいため油断は禁物です。

やがて「築坂(つきさか)」と書かれた看板が現れます。ここはかつて岩殿城の入り口にあたる場所で、歴史を感じながら歩けるポイントです。さらに木の階段を登ると、右手が崖になった細い道に変わり、緊張感を伴う区間が続きます。

分岐点に到着すると、正面の階段は岩殿山山頂へ、右手は強瀬登山口へ通じる道ですが現在は通行止めです。

階段を進むと「揚城戸跡(あげきどあと)」に到着します。ここは岩殿城の第二の関門にあたり、巨大な岩を利用して築かれた城門跡です。攻め込むには不利な狭い地形と監視に適した構造が、岩殿城を難攻不落としたことを物語っています。

さらに階段を進むと道標が現れ、左へ行けば西側に展望が開けるビュースポット。眼下に広がる景色を眺めつつ、山頂への最後の登りへと備えます。
三ノ丸展望台と岩殿山山頂へ 鏡岩の断崖と本丸跡からの大展望

階段を登りきると、岩殿山三ノ丸展望台に到着します。断崖絶壁の鏡岩の上に位置し、岩殿山で最も眺望に優れたスポットのひとつです。東屋やベンチが整備され、崖側には安全のための柵も設置されており、休憩にも最適な場所です。

眼下には桂川や中央自動車道、大月駅を中心とした市街地が広がり、その周囲を山並みが穏やかに取り囲みます。空気が澄んだ日には、正面に富士山をはっきり望むこともでき、秀麗富嶽十二景に選ばれた美しい景色を堪能できます。

展望台の周辺には大きな石碑や馬場跡、倉屋敷跡、用水地跡などが残り、かつて岩殿城が築かれていた時代を偲ぶことができます。歴史散策と絶景を同時に楽しめるのもこの場所の魅力です。

展望台からさらに10分ほど進むと、標高634メートルの岩殿山山頂に到着。山頂は広々としており、三ノ丸展望台以上に視界が開けています。高川山と杓子山の間からは雄大な富士山を望むことができ、登山者の人気撮影スポットになっています。

ここで記念撮影を楽しみつつ、休憩を兼ねて行動食をとりました。今回は大月名物「厚焼木の実煎餅」を味わい、山椒の効いた素朴な味わいに疲れが和らぎました。登山では、その土地ならではの名物を行動食に取り入れるのもおすすめです。
畑倉登山口へ下山 大月駅を目指して下山開始

山頂からの景色を十分に堪能したら、畑倉登山口へ下山を開始します。山頂には道標が整備されており、進む方向が分かりやすく安心です。

曲がりくねった坂道や尾根道を下りますが、見た目以上に滑りやすいため焦らずゆっくり進みましょう。山頂から約15分で分岐点に到着します。

正面の道は行き止まりで、「鬼の岩屋」と呼ばれる岩殿山の伝承にまつわる場所へ続いています。寄り道は片道3分ほどなので、体力に余裕があれば立ち寄るのもおすすめです。

分岐からさらに進むと畑倉登山口に到着します。ここには登山者カウンターが設置されており、岩殿山の主要な出発点として利用する人も多い登山口です。

登山口からは一般道を歩いて大月駅へ。舗装路に変わると、登山の終わりを実感します。途中で猿の群れに遭遇することもあり、自然の豊かさを感じさせてくれます。

大月駅に到着すれば、約6時間の岩殿山登山は終了。断崖絶壁や富士山の展望を楽しみながら、岩殿城跡の歴史にも触れられる充実の一日となりました。
岩殿山登山におすすめの服装・持ち物まとめ 安全に楽しむための装備チェック
稚児落としや兜岩など断崖絶壁を歩く岩殿山の登山では、安全に歩くための服装と持ち物が欠かせません。とくに初心者の方は、最低限の装備を整えておくことで安心感が大きく変わります。ここでは、岩殿山登山に適した服装例と、日帰り登山に必要な持ち物リストをご紹介します。
季節を問わず快適に歩ける服装例

・ベースレイヤー(インナー)
・速乾性Tシャツ(夏向け)
・登山パンツ
・登山用靴下
岩殿山は鎖場や岩場を含むため、動きやすく安全性の高い服装を選ぶことが重要です。夏は汗をかきやすいので速乾性のある服がベスト。冬は重ね着をして体温調節しやすいスタイルにすると快適に歩けます。
岩殿山登山に持っていきたい必携アイテム

登山道は整備されていますが、転倒や悪天候など不測の事態に備えて装備を整えておきましょう。
必携アイテム
・飲み物(500ml~1L以上、夏は多めに)
・軽食・行動食(チョコやナッツ。夏は塩分補給タブレットやソフトキャンディーを加えると熱中症対策にもなる)
・タオル、手ぬぐい
・日焼け止め、帽子(つば付きがおすすめ)
・レインウェア(急な雨に必ず備える)
・スマートフォン+モバイルバッテリー
・地図アプリまたは紙地図(オフラインで確認できるもの)
・救急セット(絆創膏、常備薬など)
あると便利な装備品
・トレッキングポール
・登山用グローブ
・サングラス
・虫よけスプレー
・クマ鈴、ホイッスル
・携帯トイレ、ティッシュ、ゴミ袋
・エマージェンシーシート
とくに岩殿山で欠かせないのが登山用グローブです。鎖や岩をしっかりつかむため、手のひらに滑り止めがついたタイプが効果的。手のひらの痛みや小さな擦り傷を防ぎ、鎖場を安全に通過するための必須装備といえます。
岩殿山登山の後に立ち寄りたい温泉・グルメスポット
岩殿山登山の拠点となる大月駅周辺には、登山帰りに立ち寄れる飲食店やカフェが点在しています。少し足を延ばせば、地元の名物グルメや温泉宿もあり、下山後の楽しみを広げてくれます。ここではおすすめの立ち寄りスポットをご紹介します。
月Cafe

大月駅を出てすぐ目の前にある「月Cafe」は、洋館風の外観が印象的なカフェ。店内は落ち着いたBGMが流れ、カジュアルな雰囲気の中でフードやデザートを楽しめます。電車に乗る前に気軽に立ち寄れるのも魅力です。
アクセス:JR中央本線大月駅から徒歩すぐ
営業時間:カフェ8:00~11:00、レストラ11:00~14:30・17:00~21:00
休業日:火曜
HP:大月観光協会ホームページ
吉田屋

大月名物の手打ちうどんを味わうなら「吉田屋」へ。初代から受け継がれた伝統の製法で作られるうどんは、素朴で懐かしい味わいが特徴です。人気の「肉きんぴら月見うどん」をはじめ、コシのある麺が登山後の体を優しく温めてくれます。
お食事処ひろさと

ボリューム満点の定食や麺類を楽しめる「お食事処ひろさと」は、登山客や地元の人に親しまれる食事処。名物「メガオムライス」をはじめ、豊富なメニューが揃い、疲れた体をしっかり満たしてくれます。落ち着いた雰囲気の店内で、ゆったりと過ごせるのも魅力です。
真木温泉

登山の疲れをしっかり癒したいなら「真木温泉」での宿泊がおすすめです。広大な敷地にわずか16室のみという贅沢な純和風旅館で、すべての客室に専用露天風呂を備えています。効能豊かな温泉は神経痛や肩こりに効果が期待され、美容にも良いと評判です。
四季折々の庭園を眺めながら、川のせせらぎに包まれて過ごす時間は格別。日帰り入浴は不可のため、宿泊して登山の疲れをゆっくり癒す滞在を楽しんでみてはいかがでしょうか。
アクセス:中央本線大月駅から富士急バスハマイバ前行きで15分、辻下車後徒歩5分
営業時間:チェックイン15:00 チェックアウト10:00※宿泊予約受付8:00~21:00(日帰り入浴不可)
休業日:なし ※休館情報はHPを確認
HP:真木温泉公式サイト
岩殿山登山のよくある質問(Q&A)

岩殿山は初心者からベテランまで幅広い登山者に人気がありますが、実際に登る前には「難易度は?」「どの季節が良い?」「トイレはあるの?」といった疑問を持つ方も多いはずです。ここでは、登山計画を立てるうえでよくある質問をまとめました。
Q. 岩殿山は登山初心者でも登れますか?
A. 登山道はよく整備されており、初心者でも問題なく登れます。スリルを味わいたい場合は、稚児落としや兜岩周辺の鎖場に挑戦するのがおすすめです。ただし滑りにくい靴とグローブを必ず用意しましょう。
Q. 展望スポットはどこにありますか?
A. 岩殿山の山頂と、鏡岩上にある三ノ丸展望台が代表的なスポットです。富士山や大月市街、周囲の名峰を一望でき、特に天気の良い日には大パノラマを楽しめます。また、稚児落としからの断崖絶壁の眺めも見逃せません。
Q. どの季節に登るのがおすすめですか?
A. 4〜5月の春は桜や山ツツジが咲き、登山者に人気のシーズンです。秋も紅葉が美しくおすすめです。一方で12月以降は積雪やアイスバーン、強風など危険が多いため、初心者は冬の登山を避けましょう。
Q. トイレや休憩所はありますか?
A. トイレは登山コース上にはありません。登山前に大月駅や周辺施設で必ず済ませておきましょう。休憩所は三ノ丸展望台や山頂などに整備されていますが、稚児落としや兜岩周辺にはないため注意が必要です。
岩殿山登山で断崖と城跡を巡りながらステップアップ

山梨百名山や秀麗富嶽十二景に選ばれる岩殿山は、標高634mと低山ながら見どころの多い人気の山です。山麓から見上げる鏡岩の断崖、山頂からの富士山や山梨の名峰を望む絶景、さらに岩殿城跡を巡る歴史探訪など、一度の登山で多彩な魅力を楽しめます。
断崖絶壁や岩場を歩くスリルある登山道は、歩き切ったときに大きな達成感を与えてくれます。景色や歴史に触れながら挑戦できるため、登山経験を積みたい初心者や、ステップアップを目指す方にもおすすめです。体力やレベルに合わせてコースを選び、必要な装備を整えて計画的にチャレンジしてみてください。
なお、岩殿山の登山道には通行止めや規制がかかっている区間もあります。登山前には必ず最新の情報を確認し、安全を第一に楽しみましょう。
登山計画には、最新の登山道情報を確認できる「山と高原地図ホーダイ」アプリの活用も便利です。ルート確認や危険箇所のチェックに役立てながら、安心・安全な岩殿山登山を楽しんでください。
【もしもの時のために・・・】紙地図も携行しよう
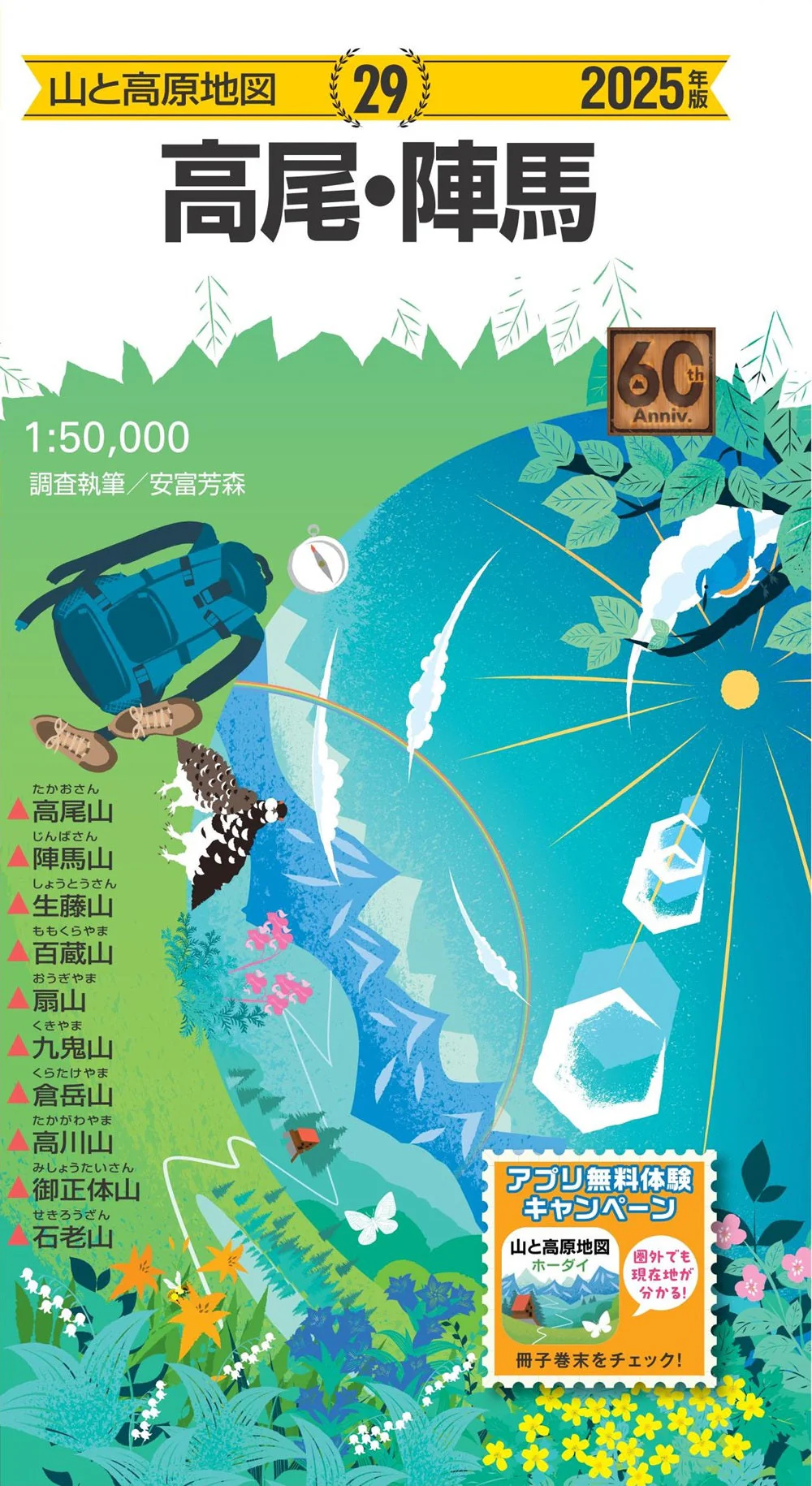

登山の専門家が調査した正確なルートやコースタイム、見どころ情報までを一つにまとめました。
紙地図「山と高原地図」として60年以上の信頼を重ねてきた情報が、アプリ「山と高原地図ホーダイ」で。
今すぐダウンロードして安全登山を楽しみましょう。





