クラ谷道〜雨乞岳往復
コース難易度
中級
- 3時間0分
コースガイド
鈴鹿第二の高峰の雨乞岳は、向かいあう御在所山や鎌ヶ岳のアルペン的な景観とは対照的に、長い尾根を四方に広げてどっしりと座っている。ふところの深いスケールの大きさと、山頂周辺に広がるササ原の山稜の圧倒的な明るさが、多くの登山者を惹きつけている。
テクニック度 |
|
山行日数 |
|
歩行時間 |
3時間0分 |
歩行距離 |
|
最大高低差 |
|
水場 |
|
トイレ |
雨乞岳はふところの深いスケールの大きな山だけに、各コースとも高度差があり、長い道のりとなります。武平峠コース、稲ヶ谷コース、フジキリ谷の千種越コース、フジキリ谷から西尾根の大峠コースなどがありますが、これらの中でよく歩かれているのは武平峠コースとフジキリ谷からの千種越の2つのコースです。この人気のある両コースを使って日帰りで歩こうとすると、マイカーの場合は2台以上で1台を下山口に回送するか、公共交通機関利用の場合はタクシーを利用しなければなりません。2012年版まで紹介していた武平峠コースから杉峠、愛知川源流へ下りコクイ谷を周回するコースは、近年の豪雨でコクイ谷が荒れて道が不明瞭になっているため、マイカー利用が可能な武平峠からクラ谷を通る往復コースを紹介したいと思います。
鈴鹿スカイラインには路線バスは走っていないため、武平峠からの道はマイカーのみの登山コースとなります。雨乞岳往復だけなら湯の山温泉から登り始めても往復可能ですが、かなりハードなコースになります。
武平峠トンネルの西側、滋賀県側に駐車スペースがあり、峠谷の橋から登り始めます。檜の植林帯の中の道で、左の斜面は伐採地のカヤトの原になっていますが、登るにつれて自然林も増えてきます。沢谷峠までは山腹道で、小さな谷をいくつか横断するためアップダウンが多く、また道が崩れているところもあり、あまり歩きやすい道ではありません。
沢谷峠は知らないうちに越えてしまうような峠で、自然林に包まれた谷を下るとクラ谷の分岐に着きます。左へ谷を少し登ってから右へ小さな尾根を越え、山腹を巻きながら下ってクラ谷に入ります。ところどころ道が崩れているので注意が必要です。クラ谷は炭焼きの窯跡が多い雑木林の美しい谷です。谷が次第に広く浅くなり源流状になると、道は右の尾根に詰めます。尾根に上がったところは雨乞岳と七人山とのコルで、左へ雑木林の尾根を登っていきます。樹林からササの道に変わり傾斜が強くなります。登るにつれてササが低くなり眺望が開けてくると東雨乞岳の頂上に着きます。頂上は丸い広場状で、すぐ目の前にはササの山稜が続き、雨乞本峰がそびえ立っています。
広々としたササ尾根を10分あまり登ると雨乞岳に到着します。頂上からは東側の展望が開けていますが、東雨乞岳の方が広く眺望も優れています。頂上の東北のササの中には山名の由来となった雨乞いの行われた「大峠の澤」があり、カエルの声が聞こえてきます。
山頂からは東・西・北の三方に、ササ原のゆったりと広がる大きな尾根が延びています。北に山稜を下り切ったところが杉峠で、この峠は滋賀県側のフジキリ谷と愛知川源流から根の平峠を越えて三重県側へ至る千種越の道です。時間に余裕があり1泊2日の行程とする場合は、フジキリ谷へ下れば途中に2箇所の簡易避難小屋があります。また愛知川源流へ下れば鉱山跡やコクイ谷出合の良いテント場があります。山頂からは他にも西へ尾根を辿って大峠からフジキリ谷へ下るコースや、東雨乞岳とのコルから稲ヶ谷へ下るコースがありますが、いずれも山慣れた人向きのコースです。ここでは武平峠へ往復するコースとするため、往路を戻ります。
鈴鹿スカイラインには路線バスは走っていないため、武平峠からの道はマイカーのみの登山コースとなります。雨乞岳往復だけなら湯の山温泉から登り始めても往復可能ですが、かなりハードなコースになります。
武平峠トンネルの西側、滋賀県側に駐車スペースがあり、峠谷の橋から登り始めます。檜の植林帯の中の道で、左の斜面は伐採地のカヤトの原になっていますが、登るにつれて自然林も増えてきます。沢谷峠までは山腹道で、小さな谷をいくつか横断するためアップダウンが多く、また道が崩れているところもあり、あまり歩きやすい道ではありません。
沢谷峠は知らないうちに越えてしまうような峠で、自然林に包まれた谷を下るとクラ谷の分岐に着きます。左へ谷を少し登ってから右へ小さな尾根を越え、山腹を巻きながら下ってクラ谷に入ります。ところどころ道が崩れているので注意が必要です。クラ谷は炭焼きの窯跡が多い雑木林の美しい谷です。谷が次第に広く浅くなり源流状になると、道は右の尾根に詰めます。尾根に上がったところは雨乞岳と七人山とのコルで、左へ雑木林の尾根を登っていきます。樹林からササの道に変わり傾斜が強くなります。登るにつれてササが低くなり眺望が開けてくると東雨乞岳の頂上に着きます。頂上は丸い広場状で、すぐ目の前にはササの山稜が続き、雨乞本峰がそびえ立っています。
広々としたササ尾根を10分あまり登ると雨乞岳に到着します。頂上からは東側の展望が開けていますが、東雨乞岳の方が広く眺望も優れています。頂上の東北のササの中には山名の由来となった雨乞いの行われた「大峠の澤」があり、カエルの声が聞こえてきます。
山頂からは東・西・北の三方に、ササ原のゆったりと広がる大きな尾根が延びています。北に山稜を下り切ったところが杉峠で、この峠は滋賀県側のフジキリ谷と愛知川源流から根の平峠を越えて三重県側へ至る千種越の道です。時間に余裕があり1泊2日の行程とする場合は、フジキリ谷へ下れば途中に2箇所の簡易避難小屋があります。また愛知川源流へ下れば鉱山跡やコクイ谷出合の良いテント場があります。山頂からは他にも西へ尾根を辿って大峠からフジキリ谷へ下るコースや、東雨乞岳とのコルから稲ヶ谷へ下るコースがありますが、いずれも山慣れた人向きのコースです。ここでは武平峠へ往復するコースとするため、往路を戻ります。
周辺の山
山と高原地図ホーダイ
道迷いの不安を軽減 登山専用地図アプリ

紙地図60年以上の信頼をスマホで
複雑な登山道も、正確な地図で不安を軽減。
登山の専門家が調査した正確なルートやコースタイム、見どころ情報までを一つにまとめました。
紙地図「山と高原地図」として60年以上の信頼を重ねてきた情報が、アプリ「山と高原地図ホーダイ」で。
今すぐダウンロードして安全登山を楽しみましょう。
登山の専門家が調査した正確なルートやコースタイム、見どころ情報までを一つにまとめました。
紙地図「山と高原地図」として60年以上の信頼を重ねてきた情報が、アプリ「山と高原地図ホーダイ」で。
今すぐダウンロードして安全登山を楽しみましょう。
掲載書籍
-
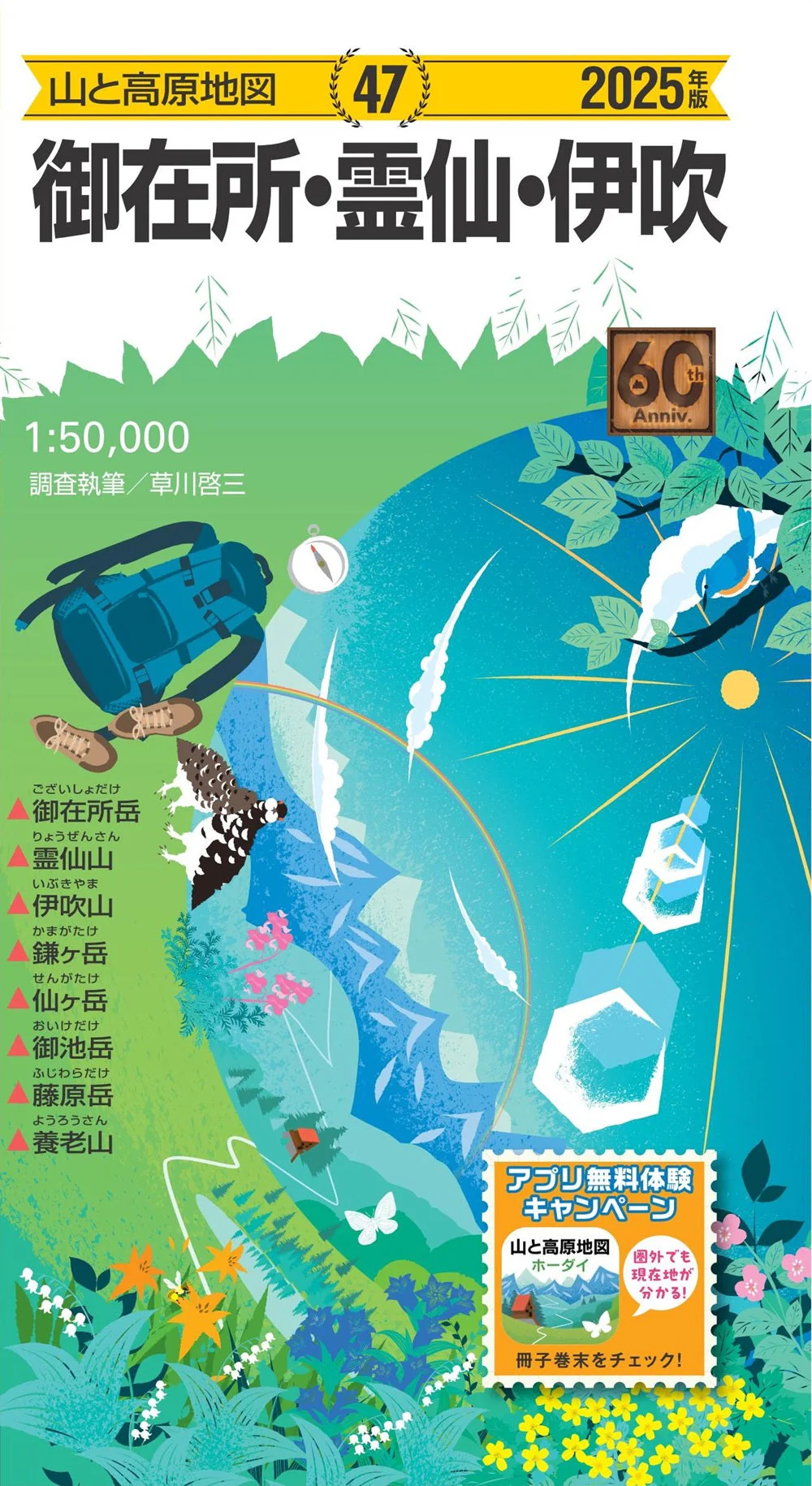 御在所・霊仙・伊吹 2025
御在所・霊仙・伊吹 2025




