月居山から袋田の滝へ
コース難易度
初級
- 日帰り
- 2時間40分
- 7.5km
コースガイド
日本三名瀑の袋田の滝を挟んで生瀬富士と相対する山。山頂鞍部の月居峠には史跡が多く、南峰には月居城址があります

テクニック度 |
難易度の目安 難易度の目安
テクニック度
|
山行日数 |
日帰り |
歩行時間 |
2時間40分 |
歩行距離 |
7.5km |
最大高低差 |
308m |
水場 |
なし |
トイレ |
袋田駅 |
JR水郡線の袋田駅からスタートします。大子町営第一駐車場までの行程は大円地から奥久慈男体山へ(コースガイド)を参照してください。駐車場を過ぎて見返橋を渡って分岐を右へ、そこに月居山登山口のサインがあるのでここを入って行きます。この辺りからは生瀬富士が良く見えます。農家レストランみらんど袋田のそばを抜けると車道に出ます。車道を渡り「月居山登山口 七曲り」方面に進みます。最初はジグザグ道でしばらく登って行くと林道に出ます。林道をさらに行くと奥久慈自然休養林の看板が現れ、登山道は左側に分岐して登って行きます。登山道を進むと、袋田自然研究路の看板があり袋田の滝方面からの登山道が合流するので、ここは右に進みます。途中で大岩がゴロゴロしている場所にでます。これは1864年の元治甲子の変と言われる内乱で、諸生党が天狗党側に月居峠から岩を落として攻撃した跡です。月居峠はもうすぐです。
月居峠は十字路になっていて、真っ直ぐ行くと月居古道を通って国道461号へ、北側に登れば月居山北峰経由で袋田の滝に出ます。右側に曲がって南へ登れば月居城址のある月居山南峰、さらには奥久慈男体山までの縦走路になっています。時間が許せば月居山北峰まで往復しましょう。月居観音堂の横を通り徳川斉昭公の歌碑を見て月居山北峰に立ちます。
月居峠からは月居山南峰に登ります。かつては月居城のあった南峰は樹木が繫茂して展望はありませんが、紅葉の時期には素晴らしい光景を見る事ができます。
峠からは来た道を少し戻り袋田自然研究路の看板の所は直進します。コンクリートの張られた道で雨の日などは滑りやすいので注意して下りて行きます。途中で生瀬富士の見える場所を通り滝見茶屋の前に着きます。少し手前に男体山・月居山登山口の石の道標が立っています。時間に余裕があれば袋田の滝をぜひ見学して行きましょう。
滝見茶屋前を右へ、滝川をゆれる吊り橋で名瀑を鑑賞しましょう。吊り橋を渡った場所からでも滝は十分に見ることができますが、利用料金を払いエレベーターで観瀑台に上がればさらに素晴らしい袋田の滝を見学できます。この場合はトンネルを通って滝本バス停方面に行く事が出来ます。観瀑台を利用しない場合は吊り橋で来た道を滝見茶屋まで戻り、道なりに行けば滝本バス停に行けます。土産物屋街を抜けると左手に滝本バス停がありますが、バスの便数は少ないので袋田駅まで往路を戻ります。
月居峠は十字路になっていて、真っ直ぐ行くと月居古道を通って国道461号へ、北側に登れば月居山北峰経由で袋田の滝に出ます。右側に曲がって南へ登れば月居城址のある月居山南峰、さらには奥久慈男体山までの縦走路になっています。時間が許せば月居山北峰まで往復しましょう。月居観音堂の横を通り徳川斉昭公の歌碑を見て月居山北峰に立ちます。
月居峠からは月居山南峰に登ります。かつては月居城のあった南峰は樹木が繫茂して展望はありませんが、紅葉の時期には素晴らしい光景を見る事ができます。
峠からは来た道を少し戻り袋田自然研究路の看板の所は直進します。コンクリートの張られた道で雨の日などは滑りやすいので注意して下りて行きます。途中で生瀬富士の見える場所を通り滝見茶屋の前に着きます。少し手前に男体山・月居山登山口の石の道標が立っています。時間に余裕があれば袋田の滝をぜひ見学して行きましょう。
滝見茶屋前を右へ、滝川をゆれる吊り橋で名瀑を鑑賞しましょう。吊り橋を渡った場所からでも滝は十分に見ることができますが、利用料金を払いエレベーターで観瀑台に上がればさらに素晴らしい袋田の滝を見学できます。この場合はトンネルを通って滝本バス停方面に行く事が出来ます。観瀑台を利用しない場合は吊り橋で来た道を滝見茶屋まで戻り、道なりに行けば滝本バス停に行けます。土産物屋街を抜けると左手に滝本バス停がありますが、バスの便数は少ないので袋田駅まで往路を戻ります。
山と高原地図ホーダイ
道迷いの不安を軽減 登山専用地図アプリ

紙地図60年以上の信頼をスマホで
複雑な登山道も、正確な地図で不安を軽減。
登山の専門家が調査した正確なルートやコースタイム、見どころ情報までを一つにまとめました。
紙地図「山と高原地図」として60年以上の信頼を重ねてきた情報が、アプリ「山と高原地図ホーダイ」で。
今すぐダウンロードして安全登山を楽しみましょう。
登山の専門家が調査した正確なルートやコースタイム、見どころ情報までを一つにまとめました。
紙地図「山と高原地図」として60年以上の信頼を重ねてきた情報が、アプリ「山と高原地図ホーダイ」で。
今すぐダウンロードして安全登山を楽しみましょう。
掲載書籍
-
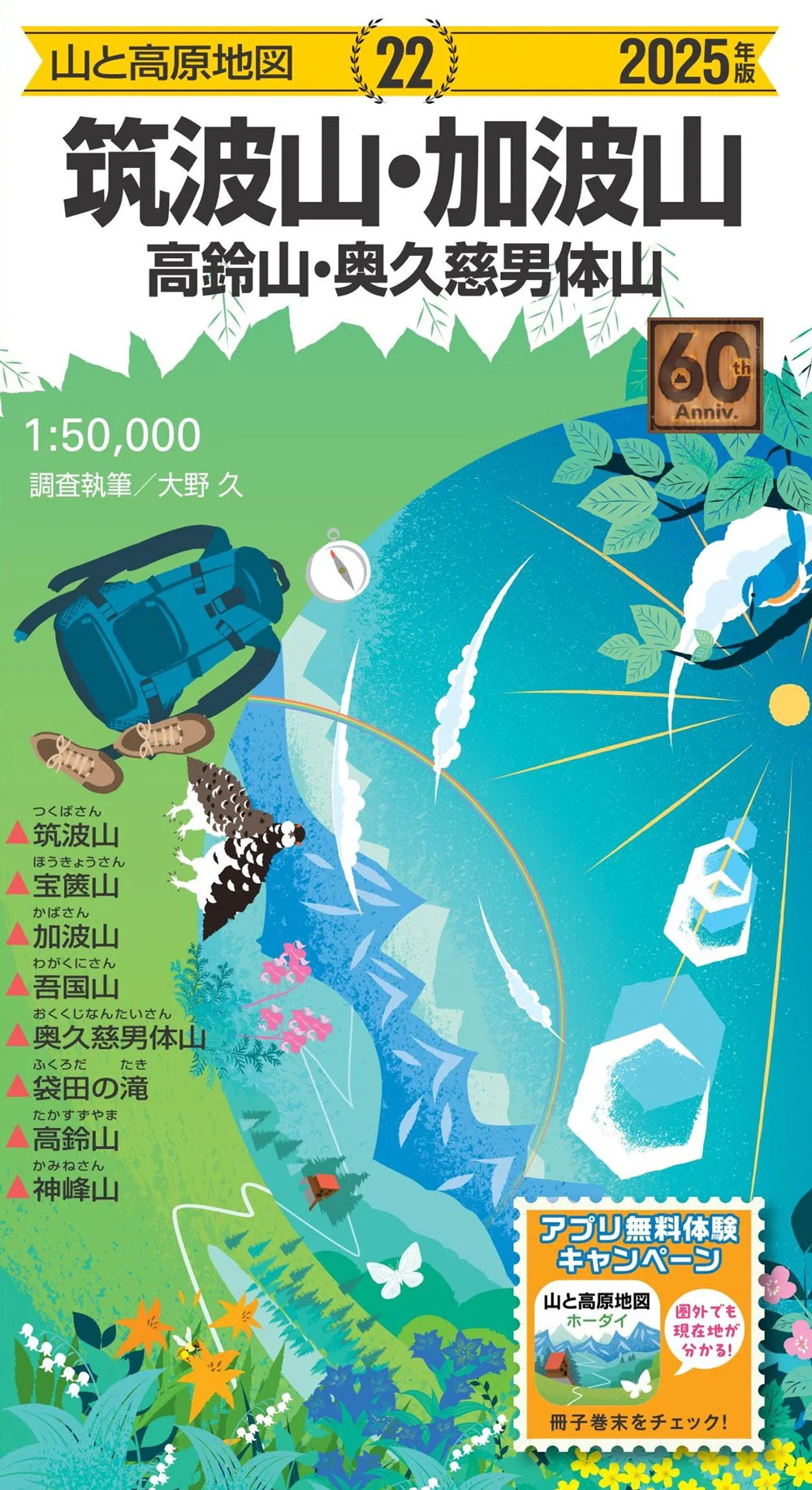 筑波山・加波山 高鈴山・奥久慈男体山 2025
筑波山・加波山 高鈴山・奥久慈男体山 2025









