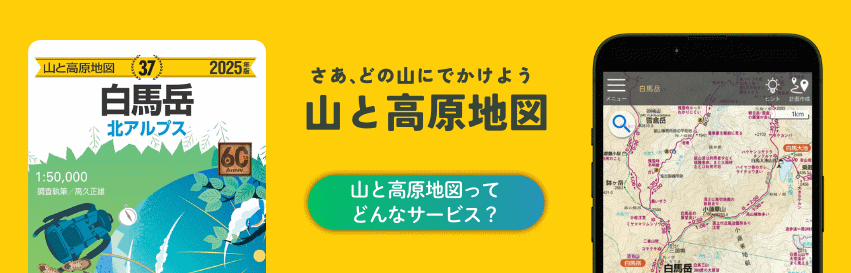登山の食べ物と飲み物の選び方 初心者が知るべき9つの基本

初めての登山では、「何を食べればいいの?」「どのくらい飲み物を持っていけばいいの?」といった疑問を抱く方も多いはず。適切な飲食は、無事に山を歩ききるための大切な要素です。
空腹のままでは体力が落ち、エネルギー切れで足が止まってしまうことも。また、こまめな水分補給を怠ると、脱水や熱中症のリスクが高まります。特に初心者の場合は、ちょっとしたミスが大きなトラブルにつながることもあるため、正しい知識を身につけておくことが重要です。
この記事では、登山初心者の方が知っておきたい「山での食べ物と飲み物の選び方・持ち方・タイミング」について、わかりやすく解説します。山での時間を快適に、そして安全に楽しむために、ぜひ参考にしてみてください。
目次
Q1.登山前には何を食べたらいい?スタート前のエネルギー補給が重要です

登山当日の朝、「食べすぎると動きにくそう」と朝食を軽く済ませてしまう方もいるかもしれません。しかし、登山は長時間にわたって体を動かし続ける有酸素運動。エネルギーを多く消費するため、朝食をしっかり摂っておくことがとても大切です。
とはいえ、出発直前にお腹いっぱい食べてしまうと、かえって体が重く感じたり、気分が悪くなることも。 スタートの1〜2時間前を目安に、消化のよい炭水化物を中心に食べるのがおすすめです。ごはんやパン、バナナなどが登山前の朝食としてよく選ばれています。
朝食を抜いたり軽すぎたりすると、歩行中にエネルギー不足で体調を崩す「シャリバテ」に陥るリスクも。ふらつきや頭痛、極端な疲労感などの原因にもなりかねません。安心して登山を楽しむためにも、「しっかり食べてから登る」ことを基本にしましょう。
Q2.行動食は何を持っていけばいい?登山中にエネルギーを切らさない工夫を

山では個包装タイプのほうが便利
登山では長時間にわたって体を動かすため、途中でエネルギーが不足しないように「行動食(こうどうしょく)」をこまめにとることが大切です。行動食とは、歩きながらでも手軽にエネルギー補給ができる食べ物のこと。朝食をしっかり食べていても、登山中にシャリバテ(エネルギー切れ)を起こすことがあるため、事前の準備は欠かせません。
行動食として人気があるのは、食べやすく、カロリーが高めのお菓子類です。たとえば以下のようなものがよく選ばれています。
- ・柿の種やおせんべいなどの塩気があるスナック
- ・飴やチョコレート、ひと口ようかんといった甘いもの
- ・バランス栄養食(クッキータイプやバータイプ)
これらはザックのサイドポケットなどに入れておけば、立ち止まらずに手軽に取り出して食べられます。ひと口サイズで片手でも食べやすいものを選ぶのがポイントです。
また、一緒に登山する仲間とおすすめの行動食をシェアしたり、自分に合った補給タイミングを試したりするのも楽しみのひとつ。登山スタイルに合わせて、工夫しながら選んでみましょう。
Q3.行動食に向かない食べ物は?カロリーと消化のバランスに注意

登山中の行動食は「手軽にエネルギー補給できること」が第一条件。逆に、カロリーが低すぎたり、消化に時間がかかったりするものは、行動食としては不向きです。
たとえば、こんにゃくゼリーや寒天系の食品は、少量で満腹感が得られる一方で、カロリーがほとんどないためエネルギー補給になりません。また、脂っこいものや食物繊維が多すぎるものも、消化に負担がかかるため避けたほうが安心です。
行動食は「おいしさ」も大切ですが、目的はあくまで登山中の栄養補給とエネルギー維持。満腹感だけでなく、しっかりとカロリーを摂取できるかを基準に選ぶようにしましょう。
Q4.行動食はいつ食べる?登山中のベストな補給タイミングとは

ポケットに入れておくとすぐに取り出せる
登山中の行動食は、決まった時間に食べる必要はありませんが、エネルギー切れを防ぐために「こまめに少しずつ」が基本です。たとえば、休憩中には空腹を感じていなくても、少しでも口にしておくと疲れにくくなります。次の行動への備えとして、意識的に補給するのがポイントです。
また、歩行中に「ちょっと疲れてきたな」「お腹がすいてきたかも」と感じたら、立ち止まらずに歩きながら食べるのもOK。そのためにも、行動食はザックのサイドポケットやウエストポーチなど、すぐに取り出せる場所に入れておくと便利です。
ただし、行動食の目的はあくまで栄養補給。食べすぎるとお腹が重くなったり、消化に負担がかかることもあるので、適量を意識することも忘れずに。
Q5.登山に必要な飲み物の量は?体重や時間から目安を計算しよう

登山中の水分補給は、エネルギー補給と同じくらい大切です。水分が不足すると、脱水症状や熱中症を引き起こすリスクも。では、どれくらいの量を持っていけばいいのでしょうか?
一般的には「1日に約2Lの水分が必要」と言われており、より具体的には以下の計算式が目安になります。
体重(kg) × 行動時間(時間) × 5mL = 必要な水分量(mL)
たとえば、体重60kgの人が6時間歩く場合は、60kg × 6時間 × 5mL = 1800mL(=約1.8L)となります。
もちろんこれはあくまで目安であり、気温や湿度、汗のかきやすさなどによって必要な水分量は変わってきます。暑い時期や標高の高いエリアでは、さらに多めに持っておくと安心です。
また、飲み物は1本の大きなボトルにまとめるよりも、2本以上に分けて持つほうが実用的。たとえば、すぐ飲めるペットボトルと、保温・保冷機能のあるボトルを組み合わせて持つと、状況に応じて使い分けができて便利です。飲み物の種類は水・お茶・スポーツドリンクなど、お好みでOK。夏は冷たい飲み物でリフレッシュ、寒い季節には温かいお茶やスープが体を温めてくれます。
最初は多めに持っていき、登山経験を重ねる中で「自分にちょうどいい量」を見つけていくのがおすすめです。万が一に備え、余裕を持った準備を心がけましょう。
Q6.水分補給のタイミングとペースは?のどが渇く前にこまめに飲もう

ハイドレーションボトルは簡単に水分補給ができる
登山中の水分補給は、行動食と同じく「計画的にこまめに」が基本です。のどが渇いてからでは遅いと言われるように、軽い脱水症状はすでに始まっている可能性があります。休憩中は、のどが渇いていなくても少しずつでも水分をとるようにしましょう。「渇きを感じる前に飲む」ことを意識することで、体調を安定させることができます。
また、歩行中にのどの渇きを感じた場合は、休憩を待たずに適宜水分をとることが大切です。ただし、一度に大量に飲むのは避け、数口ずつこまめに飲むのがポイント。お腹が重くなったり、体が冷えてしまう原因になることもあるため、適量を守ることが大事です。
「ザックから水筒を取り出すのが面倒」と感じる方には、ハイドレーションシステムの利用もおすすめ。水筒ではなく袋状のボトルとチューブを使い、歩きながらでも簡単に水分補給ができる優れたアイテムです。こまめな飲水を習慣化しやすくなるため、特に夏場の登山では重宝します。
水分補給の習慣は、疲労や熱中症を予防するうえでもとても大切です。自分に合った方法で、登山中のこまめな水分摂取を心がけましょう。
Q7.登山道の湧き水は飲んでも大丈夫?安全な水の見分け方

登山中に見かける「湧き水」や「水場」。のどが渇いていると、つい飲みたくなってしまいますが、すべての水が安全というわけではありません。
登山道に設けられた「水場」でも、管理された施設であることが確認できない場合は、そのまま飲むのは避けたほうが無難です。きちんと整備された山小屋や休憩所の水道なら比較的安心ですが、自然湧出の水や小川の水は、場所によって衛生状態に大きな差があります。
特に注意したいのが、沢や渓流の水です。見た目が澄んでいても、野生動物の排せつ物や雑菌、寄生虫が混ざっている可能性があり、体調を崩す原因になることも。初心者のうちは「自然の水=飲める」と考えず、基本的には自分で持参した飲料や、山小屋・売店で購入したものを飲むようにしましょう。
浄水器や煮沸によって安全に飲めるようにする方法もありますが、それには知識と装備が必要です。登山に慣れるまでは、あらかじめ必要な水分をしっかり用意していくのが安心です。
Q8.水分をとるとトイレが心配…どう対処すればいい?

登山道の携帯トイレブース
「登山中にトイレが近くなったら困りそう」と、水分補給を控える方もいますが、水を我慢することは脱水症状や熱中症のリスクを高めるため非常に危険です。登山中は、こまめに少量ずつ水分をとることが基本。一度にたくさん飲むよりも、少しずつ補給することで体への負担が減り、結果的にトイレの回数も増えにくくなるとされています。
とはいえ、登山道のトイレ事情は山域によって大きく異なるため、出発前にトイレの場所を確認しておくことが安心につながります。近年では携帯トイレの設置が推奨されているエリアもあり、準備しておくとより安心です。
どうしても我慢できない場面に備えて、屋外で排泄を行う場合のマナーも理解しておくことが大切です。やむを得ずトイレ以外の場所で用を足す際は、登山道から離れた人目につかない場所を選び、ティッシュや衛生用品は必ず持ち帰りましょう。自然環境への配慮と、次にその場所を訪れる人への思いやりが求められます。
無理な我慢をせず、水分補給とトイレ対策をセットで考えることが、快適で安全な登山の第一歩です。
Q9.登山中にビールはOK?飲むなら「タイミング」が大切です

山頂で景色を眺めながら飲むビール。開放感も相まって、格別なおいしさがありますよね。でも、登山中の飲酒は基本的にNGです。とくに日帰り登山では、下山まで安全に歩ききることが最優先。万が一の転倒や判断ミスを防ぐためにも、アルコールは行動がすべて終わったあとに楽しむのが原則です。
テント泊や山小屋泊の登山でも、飲酒は目的地に到着してから。標高2,000mを超える山では気圧や酸素濃度の影響で酔いが回りやすく、高山病を引き起こすリスクもあるため注意が必要です。
気分が高揚する山の中では、つい一杯…という気持ちにもなりますが、登山はあくまで安全第一。アルコールは下山後のお楽しみにとっておきましょう。
登山中の食べ物と飲み物、正しく備えて安心・快適な山歩きを

登山では、「何を食べるか」「どのくらい飲むか」が、快適さや安全性に大きく影響します。体力を維持するための行動食や水分補給は、タイミングや内容がとても重要。のどが渇く前に少しずつ水をとる、こまめにエネルギーを補給するなど、ちょっとした工夫が快適な山歩きにつながります。
また、トイレや水場、飲酒に関する疑問も、事前に知っておくことで余計な不安を減らすことができます。初心者ほど「備え」の意識が安全につながるもの。無理をせず、自分のペースで、必要なものをしっかり準備して山に向かいましょう。
山での飲食は、体調管理だけでなく、楽しさを深める要素にもなります。しっかり食べて、しっかり飲んで、心地よい登山のひとときを過ごしてください。
登山・キャンプなどアウトドア分野を専門とするフリーライター。アウトドア総合メディア『SotoLover』などで登山初心者向けの解説記事を多数執筆。豊富な実体験をもとに、初めての山歩きでも安心して楽しめるノウハウをわかりやすく発信している。
TEXT:吉田正之

登山の専門家が調査した正確なルートやコースタイム、見どころ情報までを一つにまとめました。
紙地図「山と高原地図」として60年以上の信頼を重ねてきた情報が、アプリ「山と高原地図ホーダイ」で。
今すぐダウンロードして安全登山を楽しみましょう。