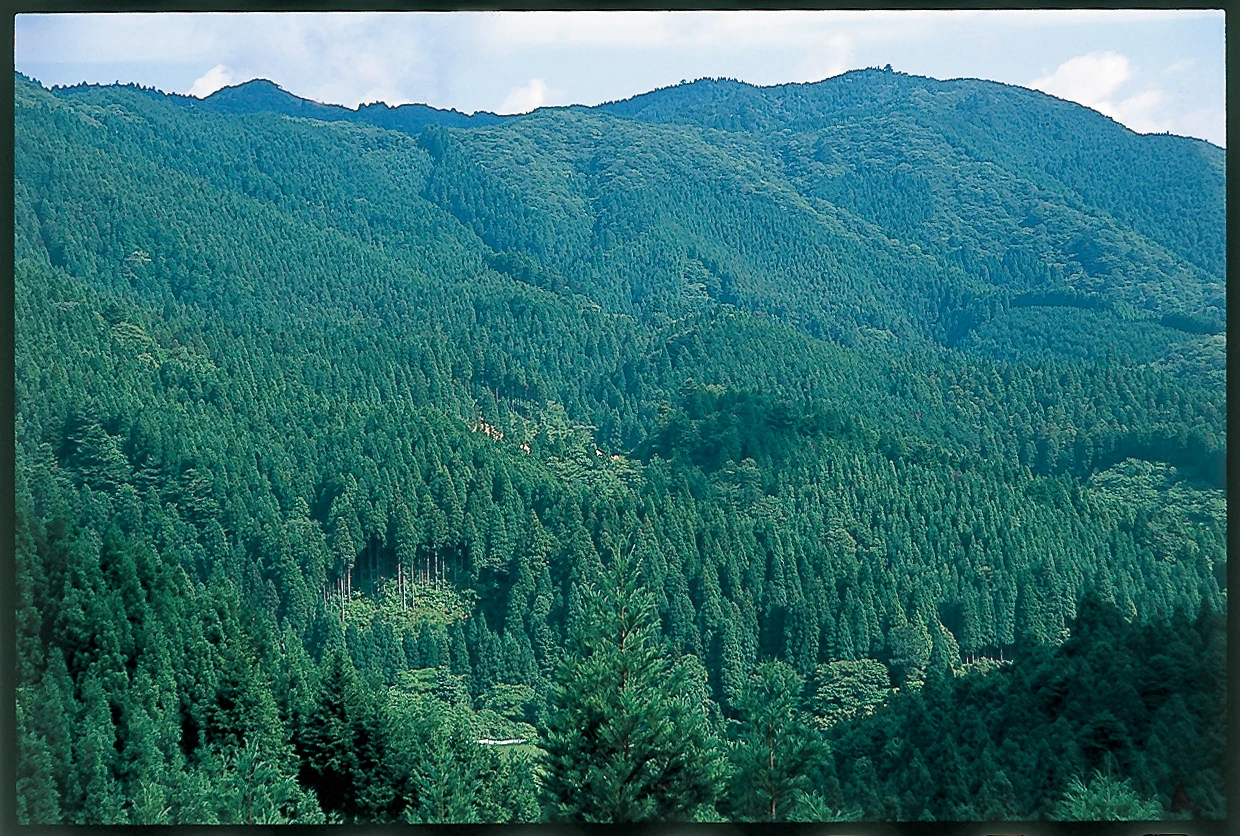【京都府】の登山コースガイド
京都府
検索結果30件中
21-30件
-
魚谷山
- 5時間45分
魚谷山
- 5時間45分
三条大橋から鴨川の上流に目をやると、たおやかな北山の山並みが遠望できます。その山並みのまんなか付近に位置するのが魚谷山です。 雲ヶ畑の出合橋バス停から中津川沿いに林道を登っていくと、松尾谷への分岐があります。魚谷峠へと続く松尾谷を左に見送り、そのまま登っていくと、貴船山に続く滝谷峠と柳谷峠への分岐に差しかかります。この分岐のひとつ手前の沢が細ヶ谷で、ここにも登山道があります。細ヶ谷の道は、先述の分岐を左にとったアズキ坂経由の道といずれ合流するため、どちらを進んでも問題ありません。 道中では、森の中の岩に埋め込まれた今西錦司のレリーフを見ることができます。沢沿いにどんどん登っていくと、柳谷峠に到着します。クマザサと自然林に覆われた、広くて気持ちのよい場所です。 ここで左に曲がり、深いクマザサの中を登っていくと、森に囲まれて展望のない魚谷山の山頂に着きます。魚谷峠は林道が交差する地点で、かつての書物に記述されていたような峠の趣は、今ではあまり見られません。 林道を横切って登山道に入り、標高831メートルの稜線に沿って狼峠を目指します。狼峠へは魚谷の林道を利用すると早く着きますが、この稜線は自然林が多く、気持ちのよい歩行が楽しめる道です。 狼峠は杉林に囲まれた、平凡ながら静かな峠です。ここを左に曲がり、急な坂を下っていくと、桟敷ヶ岳との境界をなす祖父谷川に出ます。飛び石で沢を渡ると、林道に合流します。 この祖父谷林道をどんどん下っていくと、出発点である雲ケ畑岩屋橋バス停に到着します。三条大橋から鴨川の上流に目をやると、たおやかな北山の山並みが遠望できます。その山並みのまんなか付近に位置するのが魚谷山です。 雲ヶ畑の出合橋バス停から中津川沿いに林道を登っていくと、松尾谷への分岐があります。魚谷峠へと続く松尾谷を左に見送り、そのまま登っていくと、貴船山に続く滝谷峠と柳谷峠への分岐に差しかかります。この分岐のひとつ手前の沢が細ヶ谷で、ここにも登山道があります。細ヶ谷の道は、先述の分岐を左にとったアズキ坂経由の道といずれ合流するため、どちらを進んでも問題ありません。 道中では、森の中の岩に埋め込まれた今西錦司のレリーフを見ることができます。沢沿いにどんどん登っていくと、柳谷峠に到着します。クマザサと自然林に覆われた、広くて気持ちのよい場所です。 ここで左に曲がり、深いクマザサの中を登っていくと、森に囲まれて展望のない魚谷山の山頂に着きます。魚谷峠は林道が交差する地点で、かつての書物に記述されていたような峠の趣は、今ではあまり見られません。 林道を横切って登山道に入り、標高831メートルの稜線に沿って狼峠を目指します。狼峠へは魚谷の林道を利用すると早く着きますが、この稜線は自然林が多く、気持ちのよい歩行が楽しめる道です。 狼峠は杉林に囲まれた、平凡ながら静かな峠です。ここを左に曲がり、急な坂を下っていくと、桟敷ヶ岳との境界をなす祖父谷川に出ます。飛び石で沢を渡ると、林道に合流します。 この祖父谷林道をどんどん下っていくと、出発点である雲ケ畑岩屋橋バス停に到着します。 -
雲取山
- 5時間0分
雲取山
- 5時間0分
花背高原前バス停で下車し、橋を渡って旧小学校の横を通る林道を登っていきます。左手にススキの原が広がるスキー場跡を見ながら、沢沿いの登山道を進みます。次第に傾斜が増していき、やがて道は直角に右へ折れ、山腹を巻くようにして進んでいきます。 登りきったところが寺山峠で、ここからの展望はありません。杉やアスナロの林の中を下っていくと、一ノ谷の出合に出ます。ここからは、ゆるやかな谷を目印に注意しながら登っていくと、広く明るい雲取峠に到着します。この峠は「フカンド峠」とも呼ばれており、東側は展望が開けていて、北側にはリョウブの純林が広がっています。夏には白い花が咲き誇り、爽やかな風景を楽しめます。 峠から武路谷に下る道は一部荒れているため、通行には注意が必要です。雲取山へは、南西側に続く稜線の右側をたどっていきます。山腹を巻き終え、ふたつ目の小さなピークが雲取山山頂です。山頂は狭く、樹木に覆われているため展望はききません。 下山は南側の二ノ谷への道を取りますが、西側の三ノ谷への道も山頂から分かれているため、道を間違えないよう注意が必要です。二ノ谷への下りは急坂から始まり、その後は高巻きも交えた沢沿いの道が続きます。立命館大学ワンダーフォーゲル部の山小屋を過ぎると、沢の中を進むゆるやかな道となり、一ノ谷出合まで続いていきます。 出合からは、造林地を下流に向かって歩いていくと、すぐに三ノ谷の出合に到着し、ここで林道に合流します。勢竜天満宮や京見坂への林道を左にやり過ごすと、芹生(せりょう)の里に着きます。 ここから貴船バス停までは舗装された道になりますが、芹生峠まで続く杉の美林や、峠からの展望、そして貴船川の清らかな流れなど、北山の魅力を感じられる心地よい道が続きます。花背高原前バス停で下車し、橋を渡って旧小学校の横を通る林道を登っていきます。左手にススキの原が広がるスキー場跡を見ながら、沢沿いの登山道を進みます。次第に傾斜が増していき、やがて道は直角に右へ折れ、山腹を巻くようにして進んでいきます。 登りきったところが寺山峠で、ここからの展望はありません。杉やアスナロの林の中を下っていくと、一ノ谷の出合に出ます。ここからは、ゆるやかな谷を目印に注意しながら登っていくと、広く明るい雲取峠に到着します。この峠は「フカンド峠」とも呼ばれており、東側は展望が開けていて、北側にはリョウブの純林が広がっています。夏には白い花が咲き誇り、爽やかな風景を楽しめます。 峠から武路谷に下る道は一部荒れているため、通行には注意が必要です。雲取山へは、南西側に続く稜線の右側をたどっていきます。山腹を巻き終え、ふたつ目の小さなピークが雲取山山頂です。山頂は狭く、樹木に覆われているため展望はききません。 下山は南側の二ノ谷への道を取りますが、西側の三ノ谷への道も山頂から分かれているため、道を間違えないよう注意が必要です。二ノ谷への下りは急坂から始まり、その後は高巻きも交えた沢沿いの道が続きます。立命館大学ワンダーフォーゲル部の山小屋を過ぎると、沢の中を進むゆるやかな道となり、一ノ谷出合まで続いていきます。 出合からは、造林地を下流に向かって歩いていくと、すぐに三ノ谷の出合に到着し、ここで林道に合流します。勢竜天満宮や京見坂への林道を左にやり過ごすと、芹生(せりょう)の里に着きます。 ここから貴船バス停までは舗装された道になりますが、芹生峠まで続く杉の美林や、峠からの展望、そして貴船川の清らかな流れなど、北山の魅力を感じられる心地よい道が続きます。 -
桑谷山
- 5時間0分
桑谷山
- 5時間0分
桑谷山(くわだにやま)には、その南に位置する大悲山峰定寺(みねじょうじ)の経典が山頂に埋められたという伝説があり、「経塚山(きょうづかやま)」とも呼ばれています。登山道は関西電力の高圧線巡視路を利用しているため、よく整備されており歩きやすくなっています。 大悲山口バス停で下車し、峰定寺の方へ約1kmほど歩くと、左手に新しい家と橋が見えてきます。その橋を渡り、桑谷沿いの林道を30分ほど進むと、右手に登山口の標識があります。ここから登山を開始します。 登山道は急な尾根道ですが、標高600m付近では見事な芦生杉の群落を目にすることができます。やがて道は斜面を巻いて東側の尾根に移り、高圧線の鉄塔に出ます。このあたりからは片波山や雲取山、滝谷山など、花背周辺の山々が一望できます。 少し登ると別の鉄塔があり、さらに尾根道を進んでいくと桑谷山の東峰に到着します。桑谷山は東峰と西峰からなる双耳峰で、三等三角点のある西峰まで往復します。頂上稜線の北側は伐採されており、三国岳方面への眺望が開けています。稜線には大きなブナやミズナラの木が点在し、自然林の美しさを堪能できます。 東峰に戻ったら、久多峠へと続く尾根道を下ります。東峰のすぐ東側にある鉄塔の手前から、北に延びる尾根へ進みます。道は次第に急な下りとなり、やがて岩場や梯子が現れ、シャクナゲが多く見られるエリアに入ります。 鞍部まで下りたのち、再び登り返すと最後の鉄塔の横に出ます。さらに尾根を下っていくと、桑谷山の北東面をよく見渡せる地点に出ます。やがて久多峠に到着し、ここからは舗装道路を能見川沿いに下っていくと、能見口バス停に到着します。 このルートでは、静かな自然林と眺望のバランスが楽しめ、京都北山の魅力を存分に味わえる山行となります。桑谷山(くわだにやま)には、その南に位置する大悲山峰定寺(みねじょうじ)の経典が山頂に埋められたという伝説があり、「経塚山(きょうづかやま)」とも呼ばれています。登山道は関西電力の高圧線巡視路を利用しているため、よく整備されており歩きやすくなっています。 大悲山口バス停で下車し、峰定寺の方へ約1kmほど歩くと、左手に新しい家と橋が見えてきます。その橋を渡り、桑谷沿いの林道を30分ほど進むと、右手に登山口の標識があります。ここから登山を開始します。 登山道は急な尾根道ですが、標高600m付近では見事な芦生杉の群落を目にすることができます。やがて道は斜面を巻いて東側の尾根に移り、高圧線の鉄塔に出ます。このあたりからは片波山や雲取山、滝谷山など、花背周辺の山々が一望できます。 少し登ると別の鉄塔があり、さらに尾根道を進んでいくと桑谷山の東峰に到着します。桑谷山は東峰と西峰からなる双耳峰で、三等三角点のある西峰まで往復します。頂上稜線の北側は伐採されており、三国岳方面への眺望が開けています。稜線には大きなブナやミズナラの木が点在し、自然林の美しさを堪能できます。 東峰に戻ったら、久多峠へと続く尾根道を下ります。東峰のすぐ東側にある鉄塔の手前から、北に延びる尾根へ進みます。道は次第に急な下りとなり、やがて岩場や梯子が現れ、シャクナゲが多く見られるエリアに入ります。 鞍部まで下りたのち、再び登り返すと最後の鉄塔の横に出ます。さらに尾根を下っていくと、桑谷山の北東面をよく見渡せる地点に出ます。やがて久多峠に到着し、ここからは舗装道路を能見川沿いに下っていくと、能見口バス停に到着します。 このルートでは、静かな自然林と眺望のバランスが楽しめ、京都北山の魅力を存分に味わえる山行となります。 -
峰床山・八丁平
- 6時間20分
峰床山・八丁平
- 6時間20分
八丁平は、関西では珍しい高層湿原であり、その背後にそびえる峰床山(みねとこやま)とあわせて、一帯は「京都市山村都市交流の森」として整備が進められています。 登山は、葛川中村バス停からスタートします。江賀谷沿いの林道に入り、終点の二俣まで歩きます。そこから木橋を渡って右俣に入ります。沢沿いの道は滑りやすいため、足元に注意しながら進みましょう。途中、道が二手に分かれますが、左側は廃道なので正面の道を進みます。やがて巨岩が現れ、その手前から左手の山腹に取り付くと、登り詰めたところが中村乗越です。 中村乗越からは、広く刈り開かれた道を下っていくと、八丁平の周回路に降り立ちます。この周回路を反時計回りに半周し、クラガリ谷口へ向かいます。クラガリ谷では、サワグルミ林の中を進んでいき、やがて鞍部に到達します。ここから北方向へ稜線をたどると、小さな広場となっている峰床山の山頂に着きます。山頂からは、東から南方面にかけて素晴らしい展望が広がっています。 下山は、東側の広葉樹の尾根を下っていき、オグロ坂峠にある祠の前に出ます。オグロ坂峠は、かつて京都と小浜を結んだ最短の交易路「鞍馬街道」のほぼ中間地点にあたります。ここから八丁平側には、昔の六尺道の名残も見ることができます。 峠の北面で、東の鎌倉山方面に分かれる道がありますが、今回はオグロ坂をそのまま下ります。途中には、トチ、イヌブナ、ミズナラ、アスナロなどの大木が立ち並び、美しい自然林の中を歩くことができます。やがて杉の造林地に入り、そこからひと息で林道に下り立ちます。 最後はオグロ谷沿いの林道を下り、久多の里自然環境活用センター前の橋を渡ります。そして久多川沿いの舗装道路を歩いていくと、梅ノ木バス停に到着します。 なお、車で入山される場合は、江賀谷林道には車で入ることができますが、オグロ坂側にはゲートがあるため、通行はできませんのでご注意ください。 このルートは、高層湿原、原生林、展望、歴史道と、京都北山の魅力がぎゅっと詰まった、充実の山歩きが楽しめます。八丁平は、関西では珍しい高層湿原であり、その背後にそびえる峰床山(みねとこやま)とあわせて、一帯は「京都市山村都市交流の森」として整備が進められています。 登山は、葛川中村バス停からスタートします。江賀谷沿いの林道に入り、終点の二俣まで歩きます。そこから木橋を渡って右俣に入ります。沢沿いの道は滑りやすいため、足元に注意しながら進みましょう。途中、道が二手に分かれますが、左側は廃道なので正面の道を進みます。やがて巨岩が現れ、その手前から左手の山腹に取り付くと、登り詰めたところが中村乗越です。 中村乗越からは、広く刈り開かれた道を下っていくと、八丁平の周回路に降り立ちます。この周回路を反時計回りに半周し、クラガリ谷口へ向かいます。クラガリ谷では、サワグルミ林の中を進んでいき、やがて鞍部に到達します。ここから北方向へ稜線をたどると、小さな広場となっている峰床山の山頂に着きます。山頂からは、東から南方面にかけて素晴らしい展望が広がっています。 下山は、東側の広葉樹の尾根を下っていき、オグロ坂峠にある祠の前に出ます。オグロ坂峠は、かつて京都と小浜を結んだ最短の交易路「鞍馬街道」のほぼ中間地点にあたります。ここから八丁平側には、昔の六尺道の名残も見ることができます。 峠の北面で、東の鎌倉山方面に分かれる道がありますが、今回はオグロ坂をそのまま下ります。途中には、トチ、イヌブナ、ミズナラ、アスナロなどの大木が立ち並び、美しい自然林の中を歩くことができます。やがて杉の造林地に入り、そこからひと息で林道に下り立ちます。 最後はオグロ谷沿いの林道を下り、久多の里自然環境活用センター前の橋を渡ります。そして久多川沿いの舗装道路を歩いていくと、梅ノ木バス停に到着します。 なお、車で入山される場合は、江賀谷林道には車で入ることができますが、オグロ坂側にはゲートがあるため、通行はできませんのでご注意ください。 このルートは、高層湿原、原生林、展望、歴史道と、京都北山の魅力がぎゅっと詰まった、充実の山歩きが楽しめます。 -
皆子山
- 4時間40分
皆子山
- 4時間40分
皆子山(みなこやま)は京都府の最高峰であり、その雄大な自然は多くの登山者を魅了しています。今回は、皆子山の北側を流れるツボクリ谷から登り、南東側の寺谷へと下る横断ルートをご紹介します。 登山の出発点は新道足尾谷橋バス停です。ここから北へ向かい、安曇川沿いの旧国道を西へと進みます。やがて「作業道足尾谷線」の林道に入り、終点まで進むと、登山道は沢沿いの道に変わります。 ルート中では三度木橋を渡りながら進み、目印としてテープが付けられたツボクリ谷出合に到着します。ただし、一つ手前の沢にも踏み跡があるため、間違えないようご注意ください。ここからは、右岸・左岸を何度か渡渉しながらツボクリ谷を詰めていきます。 途中、小滝を高巻く際には固定ロープが設置されており、ややスリルのある箇所もあります。やがて谷が開けてきて、大きなトチノキが姿を見せます。ここは、お弁当を広げるのにぴったりな、開放感のある場所です。 さらに3分ほど登ると、道は左に折れてツボクリ谷を離れ、皆子山へと突き上げる急な沢に入ります。曲がる地点には標識がありますが、見落としやすいため注意が必要です。この沢はやがてクマザサの茂るヤブ尾根へと変わり、しばらくすると傾斜が緩み、皆子山の山頂に飛び出します。 山頂からは、東側にわずかな展望がありますが、より素晴らしい景色は、下山ルート途中の稜線上、寺谷ルートの分岐点付近で楽しめます。ここからは、比良の山並みが目の前に広がる絶景が望めます。 寺谷への下り口は標識がなく、分かりづらいので慎重に探してください。最初はクマザサの中を抜けていき、やがて急な杉林の斜面となります。途中には大きな岩や、壊れかけた小屋などが見られ、自然の中に人の営みの跡が感じられます。 そのまま寺谷沿いに下っていくと、安曇川との出合いに出ます。ここで丸木橋を渡ると林道に合流します。林道に出てからは、安曇川沿いを30分ほど下っていけば、平(たいら)バス停に到着します。 このコースは、京都府最高峰の山を越える縦走ルートで、沢の登りや尾根の展望、静かな谷の下りなど、変化に富んだ魅力あふれる登山が楽しめます。皆子山(みなこやま)は京都府の最高峰であり、その雄大な自然は多くの登山者を魅了しています。今回は、皆子山の北側を流れるツボクリ谷から登り、南東側の寺谷へと下る横断ルートをご紹介します。 登山の出発点は新道足尾谷橋バス停です。ここから北へ向かい、安曇川沿いの旧国道を西へと進みます。やがて「作業道足尾谷線」の林道に入り、終点まで進むと、登山道は沢沿いの道に変わります。 ルート中では三度木橋を渡りながら進み、目印としてテープが付けられたツボクリ谷出合に到着します。ただし、一つ手前の沢にも踏み跡があるため、間違えないようご注意ください。ここからは、右岸・左岸を何度か渡渉しながらツボクリ谷を詰めていきます。 途中、小滝を高巻く際には固定ロープが設置されており、ややスリルのある箇所もあります。やがて谷が開けてきて、大きなトチノキが姿を見せます。ここは、お弁当を広げるのにぴったりな、開放感のある場所です。 さらに3分ほど登ると、道は左に折れてツボクリ谷を離れ、皆子山へと突き上げる急な沢に入ります。曲がる地点には標識がありますが、見落としやすいため注意が必要です。この沢はやがてクマザサの茂るヤブ尾根へと変わり、しばらくすると傾斜が緩み、皆子山の山頂に飛び出します。 山頂からは、東側にわずかな展望がありますが、より素晴らしい景色は、下山ルート途中の稜線上、寺谷ルートの分岐点付近で楽しめます。ここからは、比良の山並みが目の前に広がる絶景が望めます。 寺谷への下り口は標識がなく、分かりづらいので慎重に探してください。最初はクマザサの中を抜けていき、やがて急な杉林の斜面となります。途中には大きな岩や、壊れかけた小屋などが見られ、自然の中に人の営みの跡が感じられます。 そのまま寺谷沿いに下っていくと、安曇川との出合いに出ます。ここで丸木橋を渡ると林道に合流します。林道に出てからは、安曇川沿いを30分ほど下っていけば、平(たいら)バス停に到着します。 このコースは、京都府最高峰の山を越える縦走ルートで、沢の登りや尾根の展望、静かな谷の下りなど、変化に富んだ魅力あふれる登山が楽しめます。 -
天ヶ岳
- 5時間25分
天ヶ岳
- 5時間25分
大原・小出石からシャクナゲ尾根を登り、鞍馬へと至る尾根を下るコースをご紹介します。 出発は小出石バス停です。ここから国道477号を百井方面へ向かって約20分歩くと、左手に流れる高谷川に架かる橋が見えてきます。その橋を渡ると林道が延びており、50メートルほど進んだところに登山道の標識があります。 登山道は杉林の急登から始まりますが、やがて傾斜が緩やかになり、尾根道に入ります。標高が上がるにつれてシャクナゲが増えていき、とくに高圧線鉄塔の前後では群生が見られます。ゴールデンウィークの時期には、華やかな花々が尾根を彩り、見事な景観が楽しめます。 尾根道を登っていくと、やがて百井峠と寂光院を結ぶ「寂光院道」に合流します。ここで右に曲がり、岩が多く雑木林の続く道を辿って天ヶ岳を目指します。山頂付近は地形が複雑で、いくつか枝道もあるため、道に迷わないように注意が必要です。 天ヶ岳の山頂はササと杉林に囲まれており、展望はありません。しかし、南西に続く尾根を下っていくと、大きなアカマツが混じる雑木林に入り、歩いていてとても気持ちの良い道が続きます。途中の三又岳からは、鞍馬山や貴船山の展望を楽しむことができます。 やがて杉林に入ると、静原へ下る水谷との分岐に差し掛かります。ここでは右へ曲がり、さらに進んで標高524.8メートルの三角点では左へ曲がります。このあたりの尾根はクランク状に曲がっているので、ルートを見失わないように気をつけてください。 経塚を過ぎてどんどん下っていくと、薬王坂に出ます。ここには古い石段が残っており、かつての峠道の風情を感じることができます。薬王坂は、鞍馬と静原を結ぶだけでなく、かつて敦賀街道と鞍馬街道を横に繋いでいた重要な道でもありました。鞍馬寺と比叡山延暦寺の僧たちが行き来した歴史あるルートでもあります。 最後に、旧街道の雰囲気を残す鞍馬の家並みを通り抜け、叡山電鉄の鞍馬駅へと下ります。 このコースは、春の花、初夏の緑、秋の紅葉と、四季折々の自然を楽しむことができる魅力的なルートです。ゆっくりと歴史と自然を感じながら、北山の尾根歩きを満喫してみてください。大原・小出石からシャクナゲ尾根を登り、鞍馬へと至る尾根を下るコースをご紹介します。 出発は小出石バス停です。ここから国道477号を百井方面へ向かって約20分歩くと、左手に流れる高谷川に架かる橋が見えてきます。その橋を渡ると林道が延びており、50メートルほど進んだところに登山道の標識があります。 登山道は杉林の急登から始まりますが、やがて傾斜が緩やかになり、尾根道に入ります。標高が上がるにつれてシャクナゲが増えていき、とくに高圧線鉄塔の前後では群生が見られます。ゴールデンウィークの時期には、華やかな花々が尾根を彩り、見事な景観が楽しめます。 尾根道を登っていくと、やがて百井峠と寂光院を結ぶ「寂光院道」に合流します。ここで右に曲がり、岩が多く雑木林の続く道を辿って天ヶ岳を目指します。山頂付近は地形が複雑で、いくつか枝道もあるため、道に迷わないように注意が必要です。 天ヶ岳の山頂はササと杉林に囲まれており、展望はありません。しかし、南西に続く尾根を下っていくと、大きなアカマツが混じる雑木林に入り、歩いていてとても気持ちの良い道が続きます。途中の三又岳からは、鞍馬山や貴船山の展望を楽しむことができます。 やがて杉林に入ると、静原へ下る水谷との分岐に差し掛かります。ここでは右へ曲がり、さらに進んで標高524.8メートルの三角点では左へ曲がります。このあたりの尾根はクランク状に曲がっているので、ルートを見失わないように気をつけてください。 経塚を過ぎてどんどん下っていくと、薬王坂に出ます。ここには古い石段が残っており、かつての峠道の風情を感じることができます。薬王坂は、鞍馬と静原を結ぶだけでなく、かつて敦賀街道と鞍馬街道を横に繋いでいた重要な道でもありました。鞍馬寺と比叡山延暦寺の僧たちが行き来した歴史あるルートでもあります。 最後に、旧街道の雰囲気を残す鞍馬の家並みを通り抜け、叡山電鉄の鞍馬駅へと下ります。 このコースは、春の花、初夏の緑、秋の紅葉と、四季折々の自然を楽しむことができる魅力的なルートです。ゆっくりと歴史と自然を感じながら、北山の尾根歩きを満喫してみてください。 -
天ヶ森(ナッチョ)
- 4時間10分
天ヶ森(ナッチョ)
- 4時間10分
天ヶ森は大原の北に位置する展望の良い山です。百井分れバス停から国道477号を通って百井峠を目指します。国道とはいっても、林道のような道です。峠の手前には地蔵堂があり、百井峠にも古い地蔵があります。 京都市青少年村キャンプ場の跡を左手に見ながら、隠れ里の趣がある百井の集落に入ります。三叉路では大原方面へは行かず、そのまま進みます。小学校跡を30メートルほど過ぎたあたりに登山道の標識があります。 百井川に架かる橋を渡って川沿いに左の畦道を進み、杉林を抜けると、前ヶ畑峠から来る林道に合流します。林道を東へ進むと、2度の分岐があり、道標に従います。途中、686メートルの峠越えの山道(目印がたくさん付いています)が枝分かれしていますが、林道をそのまま進みます。 やがて、つづら折りとなる林道を登ったところに登山道の道標があります。雑木林の中の登山道をしばらく進むと、小出石に下る道の分岐があり、シカ除けの柵をくぐると、展望の開けた造林地に出ます。比叡山から途中越に続く山々や琵琶湖がよく見渡せます。すぐそばの山頂よりも、ここからの展望のほうが優れています。 小出石への分岐に戻り、シカ除けの柵を二度ほどくぐり抜けて、三谷へ下る作業道との分岐に出ます。よく手入れされた杉林に囲まれた広場になっており、休憩するのに良い場所です。 やがて、雑木林のなだらかな稜線から南の尾根に道が折れると、急な下り坂となります。最後は小出石バス停まで国道を歩いて戻ります。天ヶ森は大原の北に位置する展望の良い山です。百井分れバス停から国道477号を通って百井峠を目指します。国道とはいっても、林道のような道です。峠の手前には地蔵堂があり、百井峠にも古い地蔵があります。 京都市青少年村キャンプ場の跡を左手に見ながら、隠れ里の趣がある百井の集落に入ります。三叉路では大原方面へは行かず、そのまま進みます。小学校跡を30メートルほど過ぎたあたりに登山道の標識があります。 百井川に架かる橋を渡って川沿いに左の畦道を進み、杉林を抜けると、前ヶ畑峠から来る林道に合流します。林道を東へ進むと、2度の分岐があり、道標に従います。途中、686メートルの峠越えの山道(目印がたくさん付いています)が枝分かれしていますが、林道をそのまま進みます。 やがて、つづら折りとなる林道を登ったところに登山道の道標があります。雑木林の中の登山道をしばらく進むと、小出石に下る道の分岐があり、シカ除けの柵をくぐると、展望の開けた造林地に出ます。比叡山から途中越に続く山々や琵琶湖がよく見渡せます。すぐそばの山頂よりも、ここからの展望のほうが優れています。 小出石への分岐に戻り、シカ除けの柵を二度ほどくぐり抜けて、三谷へ下る作業道との分岐に出ます。よく手入れされた杉林に囲まれた広場になっており、休憩するのに良い場所です。 やがて、雑木林のなだらかな稜線から南の尾根に道が折れると、急な下り坂となります。最後は小出石バス停まで国道を歩いて戻ります。 -
経ヶ岳から三国岳へ
- 6時間40分
経ヶ岳から三国岳へ
- 6時間40分
昔の峠道、丹波越を通って経ヶ岳に登り、近江、山城、丹波国境に位置する三国岳へ縦走するコースを紹介する。針畑川の桑原橋バス停より橋を渡り、お堂の裏手の桧林から登山道が始まる。まっすぐに付けられた尾根道をどんどん登って行くと、稜線手前で道が右手の小沢に吸収されるところがある。ここが丹波越の茶屋跡といわれている。丹波越は近江の桑原と丹波の久多を繋ぐ山越えの道であるが、久多側はどこを道が通っていたのか不明であるということだ。稜線に出てから50分ほどで経ヶ岳山頂に着く。風化した経塚が、杉の木の下にひっそりと納められている。稜線を戻り、縦走路を三国岳へと向かう。三叉路で左に道を取ると、約10分で縦走路から外れたところに位置する三国岳山頂だ。山頂からは東側のみ展望がきく。ブナの大木まで戻り、岩谷峠をめざす。ここより針畑側へ下る尾根道もある。自然林に被われた稜線をしばらく行くと岩場があり、百里ヶ岳方面の展望が良いところがある。かつて古屋の人々が生活道として使っていた岩谷峠。そこより少し古屋側に下ったところには、石塔が立っている。シャクナゲが多い尾根道から沢に下り、保谷沿いの林道に合流して40分ほどで古屋郵便局前バス停に出る。昔の峠道、丹波越を通って経ヶ岳に登り、近江、山城、丹波国境に位置する三国岳へ縦走するコースを紹介する。針畑川の桑原橋バス停より橋を渡り、お堂の裏手の桧林から登山道が始まる。まっすぐに付けられた尾根道をどんどん登って行くと、稜線手前で道が右手の小沢に吸収されるところがある。ここが丹波越の茶屋跡といわれている。丹波越は近江の桑原と丹波の久多を繋ぐ山越えの道であるが、久多側はどこを道が通っていたのか不明であるということだ。稜線に出てから50分ほどで経ヶ岳山頂に着く。風化した経塚が、杉の木の下にひっそりと納められている。稜線を戻り、縦走路を三国岳へと向かう。三叉路で左に道を取ると、約10分で縦走路から外れたところに位置する三国岳山頂だ。山頂からは東側のみ展望がきく。ブナの大木まで戻り、岩谷峠をめざす。ここより針畑側へ下る尾根道もある。自然林に被われた稜線をしばらく行くと岩場があり、百里ヶ岳方面の展望が良いところがある。かつて古屋の人々が生活道として使っていた岩谷峠。そこより少し古屋側に下ったところには、石塔が立っている。シャクナゲが多い尾根道から沢に下り、保谷沿いの林道に合流して40分ほどで古屋郵便局前バス停に出る。 -
白尾山・鉢ヶ峰
- 5時間40分
白尾山・鉢ヶ峰
- 5時間40分
茅葺きの里として有名な美山町北地区の北西にある、白尾山と鉢ヶ峰を縦走するコースを紹介する。大内バス停前の細い車道を北に向かい、由良川にかかる橋を渡る。マイカーの人は橋の手前に駐車スペースがある。橋を渡って林道分岐を左に取る。沢の左岸の林道へ行かないように。林道終点で左の沢を行き、標識に従って右から来る沢沿いの道を登ると、植林地を抜けて自然林の尾根道に出る。597m地点まで登ると新設された林道のすぐ横に出る。展望が開け西に長老ヶ岳が見える。白尾山の山頂からは、南のホサビ山と北東の八ヶ峰方面の展望が良い。 北に延びる主稜線を下り鞍部をめざす。705mピークの少し北で尾根が分かれて、北へ延びる尾根に迷い込みやすいので注意しよう。鞍部から先は、左が檜の植林で右が自然林の尾根道が続く。692mピークで尾根が左に直角に曲がり、少し下って登り詰めると鉢ヶ峰頂上だ。桧に囲まれて展望はきかない。山頂からすぐの下りでは、南西に延びる尾根に迷い込みやすいので注意しよう。鞍部に戻り、津ノ本谷川沿いの登山道を下る。道が浸食されて不明瞭なところがあるから気を付けよう。小滝と大岩があるところまで下れば林道はすぐだ。もしも、林道ゲートに鍵がかかっていたらヨイショ!と乗り越える必要がある。北バス停までは、もうひとがんばりだ。茅葺きの里として有名な美山町北地区の北西にある、白尾山と鉢ヶ峰を縦走するコースを紹介する。大内バス停前の細い車道を北に向かい、由良川にかかる橋を渡る。マイカーの人は橋の手前に駐車スペースがある。橋を渡って林道分岐を左に取る。沢の左岸の林道へ行かないように。林道終点で左の沢を行き、標識に従って右から来る沢沿いの道を登ると、植林地を抜けて自然林の尾根道に出る。597m地点まで登ると新設された林道のすぐ横に出る。展望が開け西に長老ヶ岳が見える。白尾山の山頂からは、南のホサビ山と北東の八ヶ峰方面の展望が良い。 北に延びる主稜線を下り鞍部をめざす。705mピークの少し北で尾根が分かれて、北へ延びる尾根に迷い込みやすいので注意しよう。鞍部から先は、左が檜の植林で右が自然林の尾根道が続く。692mピークで尾根が左に直角に曲がり、少し下って登り詰めると鉢ヶ峰頂上だ。桧に囲まれて展望はきかない。山頂からすぐの下りでは、南西に延びる尾根に迷い込みやすいので注意しよう。鞍部に戻り、津ノ本谷川沿いの登山道を下る。道が浸食されて不明瞭なところがあるから気を付けよう。小滝と大岩があるところまで下れば林道はすぐだ。もしも、林道ゲートに鍵がかかっていたらヨイショ!と乗り越える必要がある。北バス停までは、もうひとがんばりだ。 -
八ヶ峰
- 4時間30分
八ヶ峰
- 4時間30分
八ヶ峰は、山頂より八つの国(能登、越前、近江、丹波、丹後、山城、若狭、加賀)が見渡せる展望の良さからその名が付いた。福井側の染ヶ谷から登り若丹国境尾根を縦走するコースを紹介する。登山口の八ヶ峰家族旅行村までバスの便がないので、マイカーかタクシーを使う。 木工実習館左横の林道の終点から登山道が始まる。杉林の尾根道は、やがて自然林となる。途中、林道を横断する箇所がある。登山口より50分ぐらいで、作業小屋やベンチがあるところに出る。このあたりより尾根はゆるやかになる。国境稜線に出てからは西に進路を取る。ひとつピークを越えて約30分で山頂に達する。山頂からの展望は素晴らしく、若狭湾や青葉山が良く見える。国境稜線を引き返して五波峠まで縦走する。ここは森林浴の森日本百選に選定されている森でブナ、カエデ、ミズナラなどの落葉広葉樹が美しい。ゆるやかな6つのピークを越えて峠を目指す。五波峠は昔の若狭街道のひとつである雲ヶ畑街道だが、今ではおおい町と南丹市美山町を結ぶ車道「遊車道ビレッジライン」が通っている。峠付近は広く駐車スペースがあるので、複数で登山に来た場合は車をここに回しておけば便利だ。徒歩の場合、旅行村あるいは南丹市美山町田歌まで、どちらも約6km、1時間半の車道歩きとなる。八ヶ峰は、山頂より八つの国(能登、越前、近江、丹波、丹後、山城、若狭、加賀)が見渡せる展望の良さからその名が付いた。福井側の染ヶ谷から登り若丹国境尾根を縦走するコースを紹介する。登山口の八ヶ峰家族旅行村までバスの便がないので、マイカーかタクシーを使う。 木工実習館左横の林道の終点から登山道が始まる。杉林の尾根道は、やがて自然林となる。途中、林道を横断する箇所がある。登山口より50分ぐらいで、作業小屋やベンチがあるところに出る。このあたりより尾根はゆるやかになる。国境稜線に出てからは西に進路を取る。ひとつピークを越えて約30分で山頂に達する。山頂からの展望は素晴らしく、若狭湾や青葉山が良く見える。国境稜線を引き返して五波峠まで縦走する。ここは森林浴の森日本百選に選定されている森でブナ、カエデ、ミズナラなどの落葉広葉樹が美しい。ゆるやかな6つのピークを越えて峠を目指す。五波峠は昔の若狭街道のひとつである雲ヶ畑街道だが、今ではおおい町と南丹市美山町を結ぶ車道「遊車道ビレッジライン」が通っている。峠付近は広く駐車スペースがあるので、複数で登山に来た場合は車をここに回しておけば便利だ。徒歩の場合、旅行村あるいは南丹市美山町田歌まで、どちらも約6km、1時間半の車道歩きとなる。