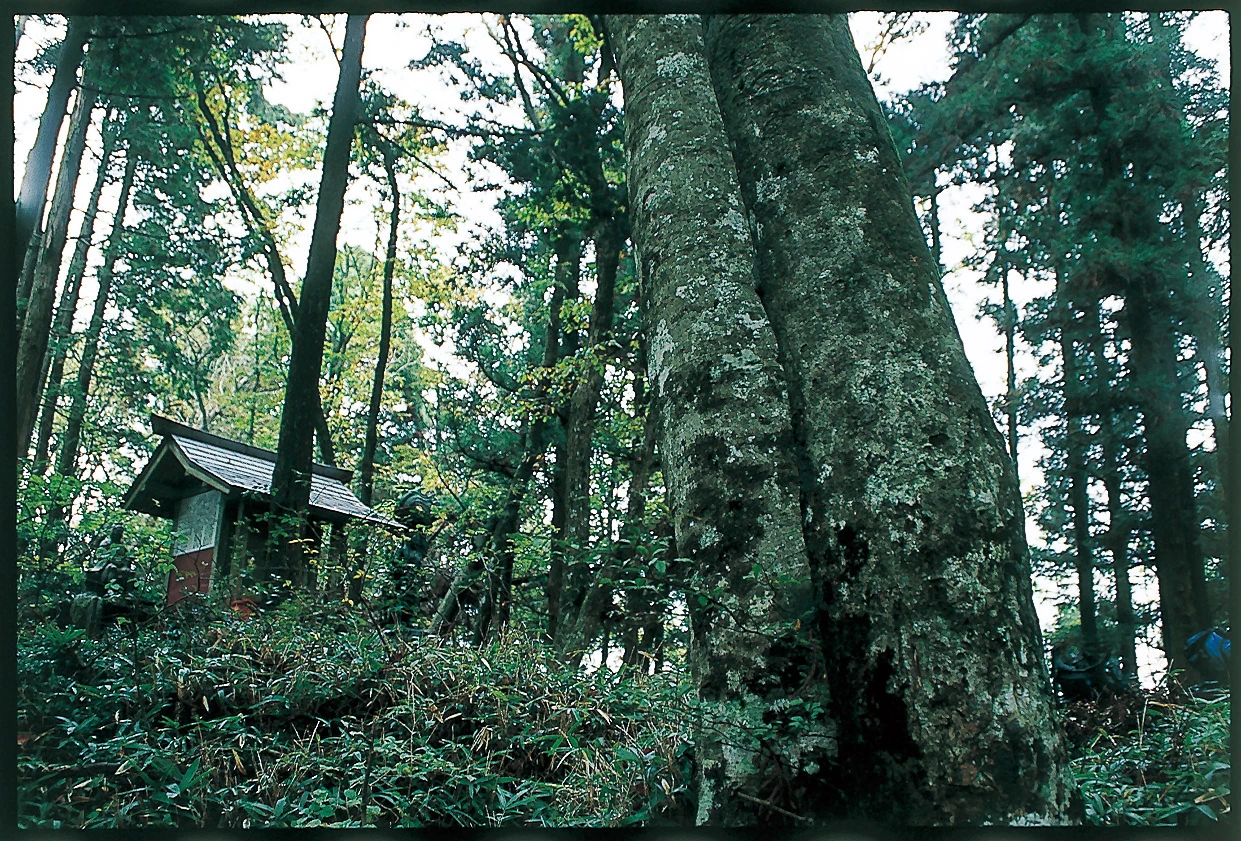【近畿】の登山コースガイド
近畿
検索結果171件中
21-40件
-
鎌尾根〜鎌ヶ岳〜カズラ谷道
- 5時間50分
鎌尾根〜鎌ヶ岳〜カズラ谷道
- 5時間50分
湯の山温泉と宮妻峡からは複数の登山コースがありますが、岩峰が続く鎌尾根は鎌ヶ岳の魅力をよく引き出す代表的なコースです。宮妻峡から登る場合、バス利用ではバス停の終点から距離が長いため時間的に無理があり、マイカー利用のコースとなります。公共交通機関を利用する場合は、湯の山温泉起点のコースが一般的です。湯の山側の登山道には、武平峠からの県境尾根道、長石尾根、三ツ口谷道、長石谷、馬の背尾根道などがあります。 宮妻峡キャンプ場には駐車場が整備されています。宮妻峡に沿った林道を約30分歩くと、水沢峠の登り口に到着します。この取り付きは中谷の橋を渡ってすぐの、小さな涸れ谷の横に道標がありますが、見落としやすいので注意が必要です。このあたりは地質が崩れやすいため、峠道は大きな谷沿いを避け、巧みに造られています。 道の一部には荒れている箇所もありますが、しっかりとした峠道が続きます。峠に近づくと岩に囲まれた狭い谷道となり、右側からはほとんど水のない大滝が落ちています。そこから左のガレ斜面に取り付き、本谷を巻いていきます。滑りやすい急斜面をジグザグに登ると、窓状の水沢峠に出ます。 峠からは北へ向かう滑りやすいガレの急斜面で道が始まり、すぐに樹林帯に入ります。痩せ尾根を通過し、峠から約20分で丸く刈り開かれた水沢岳(宮越山)の頂上に到着します。 ここからは鎌ヶ岳を眺めながら縦走路を進みます。最初はなだらかな山稜ですが、少し進むと大きなガレ場に出合います。ここは樹林帯との境目を下ってからガレ場を横断して通過し、その先はササの生い茂る尾根となります。自然林の気持ちの良い樹林帯が続きますが、前方には荒々しい山稜が見えてきます。 広い尾根が痩せてくると鎌尾根の岩稜が始まりますが、次々と現れる岩峰にはしっかりとした踏み跡があります。鎌ヶ岳の頂上までは小さな岩峰や痩せ尾根、ガレ場が続きますが、難しい箇所はありません。尖峰を眺めながら登るため変化に富み、楽しい道のりです。ただし、浮き石が多いため落石や滑落には十分注意して慎重に歩いてください。 岳峠手前で右に雲母峰や宮妻峡への道が分かれています。頂上直下の岳峠に着くと、頭上に覆いかぶさるような頂上岩峰に圧倒されます。右のルンゼを登り、尾根を左に辿ると頂上に到着します。祠のある頂上は南北に長く、広大な展望が広がっています。 岳峠に戻り、左へササの生い茂る歩きにくい斜面を横切って雲母峰への尾根に入ります。樹林帯の中のよく踏まれた美しい道を、岳峠から約20分ほど歩くと右に分かれるカズラ谷道と出合います。宮妻峡へはこのカズラ谷道を下りますが、谷の名前がついているものの、実際には尾根道です。深く掘り込まれた箇所では滑りやすい部分もありますが、全体的には安定した歩きやすいコースです。 川の流れの音が聞こえてくると、右手に高さ約20メートルの大きな滝が見え、やがてカズラ谷の両俣出合いに下り着きます。そこから流れに沿って5分ほど下ると林道に出て、宮妻峡キャンプ場の駐車場はすぐそばです。湯の山温泉と宮妻峡からは複数の登山コースがありますが、岩峰が続く鎌尾根は鎌ヶ岳の魅力をよく引き出す代表的なコースです。宮妻峡から登る場合、バス利用ではバス停の終点から距離が長いため時間的に無理があり、マイカー利用のコースとなります。公共交通機関を利用する場合は、湯の山温泉起点のコースが一般的です。湯の山側の登山道には、武平峠からの県境尾根道、長石尾根、三ツ口谷道、長石谷、馬の背尾根道などがあります。 宮妻峡キャンプ場には駐車場が整備されています。宮妻峡に沿った林道を約30分歩くと、水沢峠の登り口に到着します。この取り付きは中谷の橋を渡ってすぐの、小さな涸れ谷の横に道標がありますが、見落としやすいので注意が必要です。このあたりは地質が崩れやすいため、峠道は大きな谷沿いを避け、巧みに造られています。 道の一部には荒れている箇所もありますが、しっかりとした峠道が続きます。峠に近づくと岩に囲まれた狭い谷道となり、右側からはほとんど水のない大滝が落ちています。そこから左のガレ斜面に取り付き、本谷を巻いていきます。滑りやすい急斜面をジグザグに登ると、窓状の水沢峠に出ます。 峠からは北へ向かう滑りやすいガレの急斜面で道が始まり、すぐに樹林帯に入ります。痩せ尾根を通過し、峠から約20分で丸く刈り開かれた水沢岳(宮越山)の頂上に到着します。 ここからは鎌ヶ岳を眺めながら縦走路を進みます。最初はなだらかな山稜ですが、少し進むと大きなガレ場に出合います。ここは樹林帯との境目を下ってからガレ場を横断して通過し、その先はササの生い茂る尾根となります。自然林の気持ちの良い樹林帯が続きますが、前方には荒々しい山稜が見えてきます。 広い尾根が痩せてくると鎌尾根の岩稜が始まりますが、次々と現れる岩峰にはしっかりとした踏み跡があります。鎌ヶ岳の頂上までは小さな岩峰や痩せ尾根、ガレ場が続きますが、難しい箇所はありません。尖峰を眺めながら登るため変化に富み、楽しい道のりです。ただし、浮き石が多いため落石や滑落には十分注意して慎重に歩いてください。 岳峠手前で右に雲母峰や宮妻峡への道が分かれています。頂上直下の岳峠に着くと、頭上に覆いかぶさるような頂上岩峰に圧倒されます。右のルンゼを登り、尾根を左に辿ると頂上に到着します。祠のある頂上は南北に長く、広大な展望が広がっています。 岳峠に戻り、左へササの生い茂る歩きにくい斜面を横切って雲母峰への尾根に入ります。樹林帯の中のよく踏まれた美しい道を、岳峠から約20分ほど歩くと右に分かれるカズラ谷道と出合います。宮妻峡へはこのカズラ谷道を下りますが、谷の名前がついているものの、実際には尾根道です。深く掘り込まれた箇所では滑りやすい部分もありますが、全体的には安定した歩きやすいコースです。 川の流れの音が聞こえてくると、右手に高さ約20メートルの大きな滝が見え、やがてカズラ谷の両俣出合いに下り着きます。そこから流れに沿って5分ほど下ると林道に出て、宮妻峡キャンプ場の駐車場はすぐそばです。 -
クラ谷道〜雨乞岳往復
- 3時間0分
クラ谷道〜雨乞岳往復
- 3時間0分
雨乞岳はふところの深いスケールの大きな山だけに、各コースとも高度差があり、長い道のりとなります。武平峠コース、稲ヶ谷コース、フジキリ谷の千種越コース、フジキリ谷から西尾根の大峠コースなどがありますが、これらの中でよく歩かれているのは武平峠コースとフジキリ谷からの千種越の2つのコースです。この人気のある両コースを使って日帰りで歩こうとすると、マイカーの場合は2台以上で1台を下山口に回送するか、公共交通機関利用の場合はタクシーを利用しなければなりません。2012年版まで紹介していた武平峠コースから杉峠、愛知川源流へ下りコクイ谷を周回するコースは、近年の豪雨でコクイ谷が荒れて道が不明瞭になっているため、マイカー利用が可能な武平峠からクラ谷を通る往復コースを紹介したいと思います。 鈴鹿スカイラインには路線バスは走っていないため、武平峠からの道はマイカーのみの登山コースとなります。雨乞岳往復だけなら湯の山温泉から登り始めても往復可能ですが、かなりハードなコースになります。 武平峠トンネルの西側、滋賀県側に駐車スペースがあり、峠谷の橋から登り始めます。檜の植林帯の中の道で、左の斜面は伐採地のカヤトの原になっていますが、登るにつれて自然林も増えてきます。沢谷峠までは山腹道で、小さな谷をいくつか横断するためアップダウンが多く、また道が崩れているところもあり、あまり歩きやすい道ではありません。 沢谷峠は知らないうちに越えてしまうような峠で、自然林に包まれた谷を下るとクラ谷の分岐に着きます。左へ谷を少し登ってから右へ小さな尾根を越え、山腹を巻きながら下ってクラ谷に入ります。ところどころ道が崩れているので注意が必要です。クラ谷は炭焼きの窯跡が多い雑木林の美しい谷です。谷が次第に広く浅くなり源流状になると、道は右の尾根に詰めます。尾根に上がったところは雨乞岳と七人山とのコルで、左へ雑木林の尾根を登っていきます。樹林からササの道に変わり傾斜が強くなります。登るにつれてササが低くなり眺望が開けてくると東雨乞岳の頂上に着きます。頂上は丸い広場状で、すぐ目の前にはササの山稜が続き、雨乞本峰がそびえ立っています。 広々としたササ尾根を10分あまり登ると雨乞岳に到着します。頂上からは東側の展望が開けていますが、東雨乞岳の方が広く眺望も優れています。頂上の東北のササの中には山名の由来となった雨乞いの行われた「大峠の澤」があり、カエルの声が聞こえてきます。 山頂からは東・西・北の三方に、ササ原のゆったりと広がる大きな尾根が延びています。北に山稜を下り切ったところが杉峠で、この峠は滋賀県側のフジキリ谷と愛知川源流から根の平峠を越えて三重県側へ至る千種越の道です。時間に余裕があり1泊2日の行程とする場合は、フジキリ谷へ下れば途中に2箇所の簡易避難小屋があります。また愛知川源流へ下れば鉱山跡やコクイ谷出合の良いテント場があります。山頂からは他にも西へ尾根を辿って大峠からフジキリ谷へ下るコースや、東雨乞岳とのコルから稲ヶ谷へ下るコースがありますが、いずれも山慣れた人向きのコースです。ここでは武平峠へ往復するコースとするため、往路を戻ります。雨乞岳はふところの深いスケールの大きな山だけに、各コースとも高度差があり、長い道のりとなります。武平峠コース、稲ヶ谷コース、フジキリ谷の千種越コース、フジキリ谷から西尾根の大峠コースなどがありますが、これらの中でよく歩かれているのは武平峠コースとフジキリ谷からの千種越の2つのコースです。この人気のある両コースを使って日帰りで歩こうとすると、マイカーの場合は2台以上で1台を下山口に回送するか、公共交通機関利用の場合はタクシーを利用しなければなりません。2012年版まで紹介していた武平峠コースから杉峠、愛知川源流へ下りコクイ谷を周回するコースは、近年の豪雨でコクイ谷が荒れて道が不明瞭になっているため、マイカー利用が可能な武平峠からクラ谷を通る往復コースを紹介したいと思います。 鈴鹿スカイラインには路線バスは走っていないため、武平峠からの道はマイカーのみの登山コースとなります。雨乞岳往復だけなら湯の山温泉から登り始めても往復可能ですが、かなりハードなコースになります。 武平峠トンネルの西側、滋賀県側に駐車スペースがあり、峠谷の橋から登り始めます。檜の植林帯の中の道で、左の斜面は伐採地のカヤトの原になっていますが、登るにつれて自然林も増えてきます。沢谷峠までは山腹道で、小さな谷をいくつか横断するためアップダウンが多く、また道が崩れているところもあり、あまり歩きやすい道ではありません。 沢谷峠は知らないうちに越えてしまうような峠で、自然林に包まれた谷を下るとクラ谷の分岐に着きます。左へ谷を少し登ってから右へ小さな尾根を越え、山腹を巻きながら下ってクラ谷に入ります。ところどころ道が崩れているので注意が必要です。クラ谷は炭焼きの窯跡が多い雑木林の美しい谷です。谷が次第に広く浅くなり源流状になると、道は右の尾根に詰めます。尾根に上がったところは雨乞岳と七人山とのコルで、左へ雑木林の尾根を登っていきます。樹林からササの道に変わり傾斜が強くなります。登るにつれてササが低くなり眺望が開けてくると東雨乞岳の頂上に着きます。頂上は丸い広場状で、すぐ目の前にはササの山稜が続き、雨乞本峰がそびえ立っています。 広々としたササ尾根を10分あまり登ると雨乞岳に到着します。頂上からは東側の展望が開けていますが、東雨乞岳の方が広く眺望も優れています。頂上の東北のササの中には山名の由来となった雨乞いの行われた「大峠の澤」があり、カエルの声が聞こえてきます。 山頂からは東・西・北の三方に、ササ原のゆったりと広がる大きな尾根が延びています。北に山稜を下り切ったところが杉峠で、この峠は滋賀県側のフジキリ谷と愛知川源流から根の平峠を越えて三重県側へ至る千種越の道です。時間に余裕があり1泊2日の行程とする場合は、フジキリ谷へ下れば途中に2箇所の簡易避難小屋があります。また愛知川源流へ下れば鉱山跡やコクイ谷出合の良いテント場があります。山頂からは他にも西へ尾根を辿って大峠からフジキリ谷へ下るコースや、東雨乞岳とのコルから稲ヶ谷へ下るコースがありますが、いずれも山慣れた人向きのコースです。ここでは武平峠へ往復するコースとするため、往路を戻ります。 -
表参道〜綿向山〜竜王山
- 5時間10分
表参道〜綿向山〜竜王山
- 5時間10分
西南側の北畑や熊野から綿向山、竜王山へと続くいくつかの登山コースがあります。メインコースは表参道で、ほかに水無尾根、文三ハゲコース、竜王山からの縦走コースなどがあります。綿向山表参道コースはよく踏まれた植林帯の中の歩きやすい道で、上部の行者コバ周辺にはブナ林も残されています。頂上には馬見岡綿向神社の奥宮があり、抜群の眺望が広がっています。 車の場合は西明寺口から少し進んだところに駐車場があり、さらに林道終点まで歩くと登山口のヒミズ谷出合小屋があります。右に杉林を登るのが水無尾根道で、表参道はヒミズ谷を鉄製の橋で渡り、植林帯の中をジグザグに登っていきます。斜面を何度も折り返す単調な道を30分ほど登ると山腹を横切る林道に出ます。林道を右に進むと再び登山道が続いています。 少し登ったところに小屋があり、ジグザグの登りを繰り返します。五合目まで登ると広い範囲が伐採され、明るい斜面が広がっています。ここにも小屋があり、林道から来る別の登山道が合流しています。五合目を過ぎると左山の山腹道となり、自然林も混じるようになって、ようやく植林帯を抜けて彩り豊かな道となります。七合目の行者コバまで来ると大きなブナが現れ、原生の森の香りがわずかに残された美しい自然林の中に入ります。ここには祠があり、その両側に役行者像と不動明王像が祀られています。 行者コバでいったん尾根の上に出て、再び山腹を縫う道が続いていきます。この山頂直下一帯はブナが一部分に残されているだけで、鈴鹿特有の雑木林に包まれています。水無尾根道と合流してすぐ右に道があり、少し下ったところに金明水が湧き出ています。 金明水を過ぎると道は切り返すようになり、ササが出てきます。もう頂上は近いです。最後は急なコンクリートの階段で、見上げると鳥居が見えます。これをくぐると綿向馬見岡神社奥宮の大嶽神社が鎮座する頂上に着きます。頂上にはコンクリートで固めた大きなケルンがあり、南北に長くササが刈り開かれています。頂上からの展望は素晴らしく、とくに北西側が開けて鈴鹿中西部の大パノラマが広がっています。 綿向山から稜線を北に向かうとすぐ右に雨乞岳への分岐があります。ここを真っ直ぐに急な下りの道を進みます。この下りはいったん少し緩やかになりますが、もう一度急降下の下りとなります。岩混じりのところにはシャクナゲが多く、春は美しい道となります。 下りきったコルからは歩く人が少ないのか、少し道が荒れてきます。登りが続く道は北から西へと振り、左正面に綿向山の巨体を見上げるようになります。アップダウンを繰り返し、鉄塔のあるピークから樹林の中を進むと竜王山に着きます。頂上には石仏のような石が祀られています。 階段状の道から何度もジグザグを切って下ると林道に出て、右に進むと西明寺の分岐があり、左に取ります。すぐに人家があり棚田の間の道を下っていくと西明寺口に着きます。車の場合はここで道を左に取り駐車場に戻ります。西南側の北畑や熊野から綿向山、竜王山へと続くいくつかの登山コースがあります。メインコースは表参道で、ほかに水無尾根、文三ハゲコース、竜王山からの縦走コースなどがあります。綿向山表参道コースはよく踏まれた植林帯の中の歩きやすい道で、上部の行者コバ周辺にはブナ林も残されています。頂上には馬見岡綿向神社の奥宮があり、抜群の眺望が広がっています。 車の場合は西明寺口から少し進んだところに駐車場があり、さらに林道終点まで歩くと登山口のヒミズ谷出合小屋があります。右に杉林を登るのが水無尾根道で、表参道はヒミズ谷を鉄製の橋で渡り、植林帯の中をジグザグに登っていきます。斜面を何度も折り返す単調な道を30分ほど登ると山腹を横切る林道に出ます。林道を右に進むと再び登山道が続いています。 少し登ったところに小屋があり、ジグザグの登りを繰り返します。五合目まで登ると広い範囲が伐採され、明るい斜面が広がっています。ここにも小屋があり、林道から来る別の登山道が合流しています。五合目を過ぎると左山の山腹道となり、自然林も混じるようになって、ようやく植林帯を抜けて彩り豊かな道となります。七合目の行者コバまで来ると大きなブナが現れ、原生の森の香りがわずかに残された美しい自然林の中に入ります。ここには祠があり、その両側に役行者像と不動明王像が祀られています。 行者コバでいったん尾根の上に出て、再び山腹を縫う道が続いていきます。この山頂直下一帯はブナが一部分に残されているだけで、鈴鹿特有の雑木林に包まれています。水無尾根道と合流してすぐ右に道があり、少し下ったところに金明水が湧き出ています。 金明水を過ぎると道は切り返すようになり、ササが出てきます。もう頂上は近いです。最後は急なコンクリートの階段で、見上げると鳥居が見えます。これをくぐると綿向馬見岡神社奥宮の大嶽神社が鎮座する頂上に着きます。頂上にはコンクリートで固めた大きなケルンがあり、南北に長くササが刈り開かれています。頂上からの展望は素晴らしく、とくに北西側が開けて鈴鹿中西部の大パノラマが広がっています。 綿向山から稜線を北に向かうとすぐ右に雨乞岳への分岐があります。ここを真っ直ぐに急な下りの道を進みます。この下りはいったん少し緩やかになりますが、もう一度急降下の下りとなります。岩混じりのところにはシャクナゲが多く、春は美しい道となります。 下りきったコルからは歩く人が少ないのか、少し道が荒れてきます。登りが続く道は北から西へと振り、左正面に綿向山の巨体を見上げるようになります。アップダウンを繰り返し、鉄塔のあるピークから樹林の中を進むと竜王山に着きます。頂上には石仏のような石が祀られています。 階段状の道から何度もジグザグを切って下ると林道に出て、右に進むと西明寺の分岐があり、左に取ります。すぐに人家があり棚田の間の道を下っていくと西明寺口に着きます。車の場合はここで道を左に取り駐車場に戻ります。 -
入道ヶ岳北尾根道〜二本松尾根
- 3時間50分
入道ヶ岳北尾根道〜二本松尾根
- 3時間50分
入道ヶ岳には、宮妻峡、椿大神社、小岐須渓谷の三方からの登山道があり、コースには恵まれています。さらに県境尾根へと続くイワクラ尾根をたどれば、いっそうバリエーションが広がり、コース選定も多様になります。ここでは椿大神社から登る一番ポピュラーなコースを紹介します。 椿大神社横のキャンプ場への道を進むと、右に愛宕社への石段があります。ここが北尾根道の取り付きで、登山道は石段の左にジグザグの道が登っています。取り付きはかなり急登で、暗い檜の植林地の中を30分ほど登ると尾根の上に出ます。ここからゆるやかに下ると鉄塔があり、このすぐ先で右に大久保へと下る道が分かれています。もう少し下りが続いてコルとなると、ここからまたきつい登りが始まります。木の根を掴んだり、張ってあるロープにたよりながらの登りとなります。 いったん少し下ってから先は、緩急があるものの登りが続きます。避難小屋を過ぎると樹相は変わり、短いササの下生えの明るい雑木林の道となります。明るい疎林の斜面の気持ちのいい道ですが、やがてアセビの木が次第に増えてきて、アセビの純林と変わるほどになります。 樹林帯からアセビの群落がまだらに固まる原となると北の頭も近いです。やがて右には水沢岳、鎌ヶ岳、御在所岳などを望める眺望が広がってきます。丸い北の頭に登りきるとさらに大きな展望が広がり、鞍部をへだててササ原の丸いピークの上に鳥居の立つ、入道ヶ岳の頂上が向かい合っています。ゆったりとしたササ原と黒いアセビの群落が散らばる中を5分ほど進むと頂上に着きます。 頂上にはいつきてもグループの輪がいくつも広がり、賑やかな声が響き合っています。展望の良い山が多い鈴鹿ですが、これだけ明るくおおらかな山も珍しいです。県境の山々は言うに及ばず、眼下には平野が広がり、その先には伊勢の海が光っています。知多半島やその先に浮かぶ神島と、天気の良い日の眺望は見飽きることがありません。 下山コースは椿大神社に戻るなら、北尾根、井戸谷道、二本松尾根のコースがあり、小岐須渓谷へと下るなら池ヶ谷道がありますが、ここではよく歩かれている二本松尾根コースを紹介します。 頂上の鳥居の下から道が始まっています。ササ原からアセビの樹林の中の道となりますが、上部は急な下りです。ロープの張られている斜面を15分ほど下ると、道は落ち着いてきます。ねじれ広がったアセビの純林は、下るにつれて雑木が混じる林となり、やがて二本松尾根避難小屋に出合います。 ここから少し下ったところが滝ヶ谷道との分岐で、右の滝ヶ谷道は小岐須渓谷へと下るので、左の椿大神社への道をとります。 左山の山腹道で大きな檜や杉の植林地の中を下って行きます。鬱蒼とした針葉樹林の中の道は、谷道となったり山腹道へと移ったりしながら、歩きやすい道に導かれます。最後は井戸谷の大きな堰堤の上の広い伏流した河原に飛び出します。谷は広く何段にも堰堤が続き、その上に入道ヶ岳の斜面が大きくのぞいています。渡ったところはアスファルト道で、もう椿大神社は近いです。入道ヶ岳には、宮妻峡、椿大神社、小岐須渓谷の三方からの登山道があり、コースには恵まれています。さらに県境尾根へと続くイワクラ尾根をたどれば、いっそうバリエーションが広がり、コース選定も多様になります。ここでは椿大神社から登る一番ポピュラーなコースを紹介します。 椿大神社横のキャンプ場への道を進むと、右に愛宕社への石段があります。ここが北尾根道の取り付きで、登山道は石段の左にジグザグの道が登っています。取り付きはかなり急登で、暗い檜の植林地の中を30分ほど登ると尾根の上に出ます。ここからゆるやかに下ると鉄塔があり、このすぐ先で右に大久保へと下る道が分かれています。もう少し下りが続いてコルとなると、ここからまたきつい登りが始まります。木の根を掴んだり、張ってあるロープにたよりながらの登りとなります。 いったん少し下ってから先は、緩急があるものの登りが続きます。避難小屋を過ぎると樹相は変わり、短いササの下生えの明るい雑木林の道となります。明るい疎林の斜面の気持ちのいい道ですが、やがてアセビの木が次第に増えてきて、アセビの純林と変わるほどになります。 樹林帯からアセビの群落がまだらに固まる原となると北の頭も近いです。やがて右には水沢岳、鎌ヶ岳、御在所岳などを望める眺望が広がってきます。丸い北の頭に登りきるとさらに大きな展望が広がり、鞍部をへだててササ原の丸いピークの上に鳥居の立つ、入道ヶ岳の頂上が向かい合っています。ゆったりとしたササ原と黒いアセビの群落が散らばる中を5分ほど進むと頂上に着きます。 頂上にはいつきてもグループの輪がいくつも広がり、賑やかな声が響き合っています。展望の良い山が多い鈴鹿ですが、これだけ明るくおおらかな山も珍しいです。県境の山々は言うに及ばず、眼下には平野が広がり、その先には伊勢の海が光っています。知多半島やその先に浮かぶ神島と、天気の良い日の眺望は見飽きることがありません。 下山コースは椿大神社に戻るなら、北尾根、井戸谷道、二本松尾根のコースがあり、小岐須渓谷へと下るなら池ヶ谷道がありますが、ここではよく歩かれている二本松尾根コースを紹介します。 頂上の鳥居の下から道が始まっています。ササ原からアセビの樹林の中の道となりますが、上部は急な下りです。ロープの張られている斜面を15分ほど下ると、道は落ち着いてきます。ねじれ広がったアセビの純林は、下るにつれて雑木が混じる林となり、やがて二本松尾根避難小屋に出合います。 ここから少し下ったところが滝ヶ谷道との分岐で、右の滝ヶ谷道は小岐須渓谷へと下るので、左の椿大神社への道をとります。 左山の山腹道で大きな檜や杉の植林地の中を下って行きます。鬱蒼とした針葉樹林の中の道は、谷道となったり山腹道へと移ったりしながら、歩きやすい道に導かれます。最後は井戸谷の大きな堰堤の上の広い伏流した河原に飛び出します。谷は広く何段にも堰堤が続き、その上に入道ヶ岳の斜面が大きくのぞいています。渡ったところはアスファルト道で、もう椿大神社は近いです。 -
仙ヶ谷道〜仙鶏尾根〜仙ヶ岳
- 5時間0分
仙ヶ谷道〜仙鶏尾根〜仙ヶ岳
- 5時間0分
仙ヶ岳へは石水渓の南尾根、白谷道、小岐須渓谷の仙ヶ谷道があり、どのコースも変化のある山歩きが楽しめます。石水渓、小岐須渓谷のどちらを起点としても多様なコースがあり、仙ヶ岳に隣接する野登山や宮指路岳と組み合わせるとさらに多くのコースが考えられますが、距離が長くハードになります。また、頂上から県境尾根を南下すると御所平があり、ササやススキのゆったりと傾いた広い台地状の変わった地形が開けていますが、踏み跡があまりしっかりとしていないため、経験者向きのコースとなっています。 どこから取り付いても登りごたえのあるコースに囲まれ、美しい山容を持つこの山は、1000m級の山に匹敵する魅力があります。ここでは小岐須渓谷からのコースをとります。車の場合は、小岐須渓谷の石大神展望台駐車場に置くか、林道を歩いた大石橋の少し先にもスペースがあります。石大神展望台駐車場から林道を1時間ほど歩くと堰堤があり、林道終点となります。 登山道に入ると左からの支流を横切り、流れを左岸に渡ります。仙ヶ谷はナメ滝が連なり、美しい流れを見せています。谷の山腹道を登っていくと、左に流れを渡って仙鶏尾根に取り付く道があるので、この道に入ります。ここは植林帯の中の少しわかりにくい分岐ですが、道標があり、流れを渡るところはナメ滝となっています。 道は小さな尾根に付いており、急な斜面を登ると小さなコルに出て、左の谷側が開けます。ここから尾根の左側の山腹に道が続いています。しばらく細い山腹道をたどっていくと、次第に左に谷が近づいてきます。ところどころで崖崩れや支流を渡る部分で道が抜けているところがあり、トラロープが張られています。下の谷にはナメ滝が続く流れが見えています。 山腹をたどってきた道はいったん流れに下り、また山腹道に戻ってから再び流れを渡ると、急斜面の山腹を登るようになります。少しの登りで仙鶏尾根上のコルに着きます。 ここは仙ヶ岳への急登にかかる基部となるところで、岩やガレの急な登りが仙ヶ岳東峰まで続いています。仙鶏尾根を少し登ると背後に野登山が大きく、右にずんぐりとした入道ヶ岳が見え、鈴鹿中部の山々の展望が開けてきます。急登を登りきったところに右側が開けた展望台があり、北から西側の眺望が広がっています。特に鎌ヶ岳の尖峰が印象的です。ここからはもう仙ヶ岳の頂上も近いです。 最初に出合うピークが仙ヶ岳東峰で、ここには面白い形の仙の石があります。前面が大きく開けた好展望の岩場で、うってつけの休み場となっています。ここからいったん少し下って登り返したところが仙ヶ岳頂上で、眺望はありますが、小さく刈り払われた狭い頂上です。 北へ小社峠(大峠)へは植林の急斜面となっています。滑りやすい道に注意して下ると滋賀県側の雑木林のT字路となった小社峠に着き、右へ仙ヶ谷への道を下ります。道はしっかりしていますが、流れを渡るところでは見失いやすいです。しかし踏み跡を確かめながら下れば間違うことはなく、仙鶏尾根分岐を過ぎて元の林道終点に出て、林道を下ります。仙ヶ岳へは石水渓の南尾根、白谷道、小岐須渓谷の仙ヶ谷道があり、どのコースも変化のある山歩きが楽しめます。石水渓、小岐須渓谷のどちらを起点としても多様なコースがあり、仙ヶ岳に隣接する野登山や宮指路岳と組み合わせるとさらに多くのコースが考えられますが、距離が長くハードになります。また、頂上から県境尾根を南下すると御所平があり、ササやススキのゆったりと傾いた広い台地状の変わった地形が開けていますが、踏み跡があまりしっかりとしていないため、経験者向きのコースとなっています。 どこから取り付いても登りごたえのあるコースに囲まれ、美しい山容を持つこの山は、1000m級の山に匹敵する魅力があります。ここでは小岐須渓谷からのコースをとります。車の場合は、小岐須渓谷の石大神展望台駐車場に置くか、林道を歩いた大石橋の少し先にもスペースがあります。石大神展望台駐車場から林道を1時間ほど歩くと堰堤があり、林道終点となります。 登山道に入ると左からの支流を横切り、流れを左岸に渡ります。仙ヶ谷はナメ滝が連なり、美しい流れを見せています。谷の山腹道を登っていくと、左に流れを渡って仙鶏尾根に取り付く道があるので、この道に入ります。ここは植林帯の中の少しわかりにくい分岐ですが、道標があり、流れを渡るところはナメ滝となっています。 道は小さな尾根に付いており、急な斜面を登ると小さなコルに出て、左の谷側が開けます。ここから尾根の左側の山腹に道が続いています。しばらく細い山腹道をたどっていくと、次第に左に谷が近づいてきます。ところどころで崖崩れや支流を渡る部分で道が抜けているところがあり、トラロープが張られています。下の谷にはナメ滝が続く流れが見えています。 山腹をたどってきた道はいったん流れに下り、また山腹道に戻ってから再び流れを渡ると、急斜面の山腹を登るようになります。少しの登りで仙鶏尾根上のコルに着きます。 ここは仙ヶ岳への急登にかかる基部となるところで、岩やガレの急な登りが仙ヶ岳東峰まで続いています。仙鶏尾根を少し登ると背後に野登山が大きく、右にずんぐりとした入道ヶ岳が見え、鈴鹿中部の山々の展望が開けてきます。急登を登りきったところに右側が開けた展望台があり、北から西側の眺望が広がっています。特に鎌ヶ岳の尖峰が印象的です。ここからはもう仙ヶ岳の頂上も近いです。 最初に出合うピークが仙ヶ岳東峰で、ここには面白い形の仙の石があります。前面が大きく開けた好展望の岩場で、うってつけの休み場となっています。ここからいったん少し下って登り返したところが仙ヶ岳頂上で、眺望はありますが、小さく刈り払われた狭い頂上です。 北へ小社峠(大峠)へは植林の急斜面となっています。滑りやすい道に注意して下ると滋賀県側の雑木林のT字路となった小社峠に着き、右へ仙ヶ谷への道を下ります。道はしっかりしていますが、流れを渡るところでは見失いやすいです。しかし踏み跡を確かめながら下れば間違うことはなく、仙鶏尾根分岐を過ぎて元の林道終点に出て、林道を下ります。 -
油日岳・那須ヶ原山・高畑山縦走
- 5時間40分
油日岳・那須ヶ原山・高畑山縦走
- 5時間40分
この三山は小さいながらも、均整のとれた美しい山容を見せています。いずれの山もそれぞれに登山道がありますが、三山縦走も楽しいコースとなります。少しハードですが、那須ヶ原山や坂下峠でエスケープすることもできるので、体力や時間の調整も可能です。ただし縦走はJR、バス、マイカーのいずれの場合でも問題が多いため、事前の確認が必要です。 JR利用での登山の場合、油日駅から登山口まで徒歩ではかなりの距離がありますので、油日駅から登山口まではタクシーで入ることをおすすめします。 登山口には参籠所があり、この少し先で林道が終わります。谷に沿った道がしばらく続くと、右の小さな谷に入り、やがて道は斜面を登っていきます。かなりの急登が稜線に出るまで続いていますが、登山口から登り始めてからわずか30分ほどの辛抱です。右に稜線を5分ほど進むと、油日神社奥宮の祠のある頂上に着きます。北側にも参籠所があり、休憩できます。ここからは西側の丘と平野が入り組む甲賀の里の眺望が開けています。 登ってきたコルの分岐に戻り稜線を進みます。稜線は常緑の樹林帯で、風化した花崗岩のやせた尾根が続いています。道は急な登下降の小さなアップダウンが多いので、一定のペースを守って歩くことが重要なポイントとなります。また、 三国山までの小さなピークでは道が分かれており、枝道に入り込まないように注意が必要です。 三国山を過ぎたところで切れ込んだ岩場があり、ここでは右側を巻いて通過します。このアップダウンが連続する尾根も那須ヶ原山に近づくにつれて幾分穏やかになりますが、那須ヶ原山の山容にもそれが表れており、見上げながら近づくその姿はどっしりとして美しいです。 那須ヶ原山の頂上手前で縦走する県境尾根は右に振っています。この分岐から少し先が那須ヶ原山の頂上となります。頂上には石室があり、南側の眺望が開けています。 分岐に戻り三頭山まではゆったりとした道ですが、ここを過ぎると再びアップダウンが激しくなります。そして唐木岳のピークを過ぎたところでキレットがあり、右側を下りながら大きく巻いていきます。もう坂下峠も近く急な下りとなって峠に下り立ちます。峠は車道が越えていますが、峠付近が崩壊しており、車は通過できません。 ここで余裕があればさらに縦走を続けましょう。峠からはいきなりの急登で、途中ガレ場の右を巻く道を通って溝干山に着きます。ここからは登下降があるものの、もう強い登りはなく高畑山の頂上に出ます。頂上は抜群の展望で、長い縦走を終えた最後の峰らしく、実に気分の良い広やかな頂上です。高畑山は双耳峰で、この頂上は南峰にあたります。 鈴鹿峠まで下る間にもアップダウンがあり、キレットも一箇所あります。しかしトラロープがフィックスされており、そんなに危険な箇所ではありません。 最後の下りが続くようになると、次第に国道の車の音が高く響いてきます。ゆるやかな植林帯に入り右に鏡岩の分岐を過ぎると、茶畑が広がって鈴鹿峠に着きます。鈴鹿峠にはバスは運行されていないので、事前にタクシーに連絡しておくことをおすすめします。この三山は小さいながらも、均整のとれた美しい山容を見せています。いずれの山もそれぞれに登山道がありますが、三山縦走も楽しいコースとなります。少しハードですが、那須ヶ原山や坂下峠でエスケープすることもできるので、体力や時間の調整も可能です。ただし縦走はJR、バス、マイカーのいずれの場合でも問題が多いため、事前の確認が必要です。 JR利用での登山の場合、油日駅から登山口まで徒歩ではかなりの距離がありますので、油日駅から登山口まではタクシーで入ることをおすすめします。 登山口には参籠所があり、この少し先で林道が終わります。谷に沿った道がしばらく続くと、右の小さな谷に入り、やがて道は斜面を登っていきます。かなりの急登が稜線に出るまで続いていますが、登山口から登り始めてからわずか30分ほどの辛抱です。右に稜線を5分ほど進むと、油日神社奥宮の祠のある頂上に着きます。北側にも参籠所があり、休憩できます。ここからは西側の丘と平野が入り組む甲賀の里の眺望が開けています。 登ってきたコルの分岐に戻り稜線を進みます。稜線は常緑の樹林帯で、風化した花崗岩のやせた尾根が続いています。道は急な登下降の小さなアップダウンが多いので、一定のペースを守って歩くことが重要なポイントとなります。また、 三国山までの小さなピークでは道が分かれており、枝道に入り込まないように注意が必要です。 三国山を過ぎたところで切れ込んだ岩場があり、ここでは右側を巻いて通過します。このアップダウンが連続する尾根も那須ヶ原山に近づくにつれて幾分穏やかになりますが、那須ヶ原山の山容にもそれが表れており、見上げながら近づくその姿はどっしりとして美しいです。 那須ヶ原山の頂上手前で縦走する県境尾根は右に振っています。この分岐から少し先が那須ヶ原山の頂上となります。頂上には石室があり、南側の眺望が開けています。 分岐に戻り三頭山まではゆったりとした道ですが、ここを過ぎると再びアップダウンが激しくなります。そして唐木岳のピークを過ぎたところでキレットがあり、右側を下りながら大きく巻いていきます。もう坂下峠も近く急な下りとなって峠に下り立ちます。峠は車道が越えていますが、峠付近が崩壊しており、車は通過できません。 ここで余裕があればさらに縦走を続けましょう。峠からはいきなりの急登で、途中ガレ場の右を巻く道を通って溝干山に着きます。ここからは登下降があるものの、もう強い登りはなく高畑山の頂上に出ます。頂上は抜群の展望で、長い縦走を終えた最後の峰らしく、実に気分の良い広やかな頂上です。高畑山は双耳峰で、この頂上は南峰にあたります。 鈴鹿峠まで下る間にもアップダウンがあり、キレットも一箇所あります。しかしトラロープがフィックスされており、そんなに危険な箇所ではありません。 最後の下りが続くようになると、次第に国道の車の音が高く響いてきます。ゆるやかな植林帯に入り右に鏡岩の分岐を過ぎると、茶畑が広がって鈴鹿峠に着きます。鈴鹿峠にはバスは運行されていないので、事前にタクシーに連絡しておくことをおすすめします。 -
正面登山道
- 3時間50分
正面登山道
- 3時間50分
伊吹山は、本冊子で紹介している正面登山道のほかに北尾根コースや岐阜県側の笹又コースがありますが、歩行禁止のドライブウェイに阻まれて山頂まで登ることができず、正面登山道が山頂までの唯一の登山コースとなっています。 正面登山道は一合目から山頂まで草原と低灌木が続く南斜面にあり、中腹の三合目からは頂上まで一望できる大パノラマが開けています。ただし、まったく日陰がないため、夏は帽子の着用やこまめな水分補給など暑さ対策が必要です。 登山口で入山協力金300円を納め、植林地の中を登っていくと草地が開けた一合目に着きます。ここから四合目まではスキー場跡の草原が広がり、比較的緩やかな斜面が続いていますが、五合目からは石が転がるジグザグ道になります。避難小屋のある六合目を過ぎると傾斜も強くなり、眼下の湖北の平野や琵琶湖、鈴鹿の山々の眺望が広がってきます。大きな木がないため高度感は抜群で、花が咲き乱れる夏の登山道は中部山岳の3000m級の山を思わせます。 登るにつれて咲く花の種類も多く鮮やかになります。八合目あたりが最も急で、ジグザグを繰り返しながら、緩やかに広がる頂上台地の一角にある九合目に登り着きます。お花畑の中の道を進むと、夏の最盛期にはドライブウェイを登ってきた人たちの列と合流し、山頂に着きます。 広々とした頂上一帯では、山小屋が営業する夏は多くの人でにぎわっています。山頂台地にはドライブウェイの駐車場と結んで周遊路が設けられているので、時間が許せばお花畑を巡ってから往路を下ることをおすすめします。伊吹山は、本冊子で紹介している正面登山道のほかに北尾根コースや岐阜県側の笹又コースがありますが、歩行禁止のドライブウェイに阻まれて山頂まで登ることができず、正面登山道が山頂までの唯一の登山コースとなっています。 正面登山道は一合目から山頂まで草原と低灌木が続く南斜面にあり、中腹の三合目からは頂上まで一望できる大パノラマが開けています。ただし、まったく日陰がないため、夏は帽子の着用やこまめな水分補給など暑さ対策が必要です。 登山口で入山協力金300円を納め、植林地の中を登っていくと草地が開けた一合目に着きます。ここから四合目まではスキー場跡の草原が広がり、比較的緩やかな斜面が続いていますが、五合目からは石が転がるジグザグ道になります。避難小屋のある六合目を過ぎると傾斜も強くなり、眼下の湖北の平野や琵琶湖、鈴鹿の山々の眺望が広がってきます。大きな木がないため高度感は抜群で、花が咲き乱れる夏の登山道は中部山岳の3000m級の山を思わせます。 登るにつれて咲く花の種類も多く鮮やかになります。八合目あたりが最も急で、ジグザグを繰り返しながら、緩やかに広がる頂上台地の一角にある九合目に登り着きます。お花畑の中の道を進むと、夏の最盛期にはドライブウェイを登ってきた人たちの列と合流し、山頂に着きます。 広々とした頂上一帯では、山小屋が営業する夏は多くの人でにぎわっています。山頂台地にはドライブウェイの駐車場と結んで周遊路が設けられているので、時間が許せばお花畑を巡ってから往路を下ることをおすすめします。 -
養老山・笙ヶ岳
- 6時間15分
養老山・笙ヶ岳
- 6時間15分
草原状の養老山と樹林の深い笙ヶ岳は対照的な山で、養老山系の主峰である養老山と最高峰の笙ヶ岳を一日で楽しむことができます。登山道はよく整備された歩きやすい道が続いていますが、大洞谷から笙ヶ岳への間は道があまりよくないので注意が必要です。笙ヶ岳まで歩くとかなりハードなコースとなるため、時間や体力に合わせてコースを短縮できるようになっています。 一番短いコースは養老山の往復で、次に段階的に、もみじ峠手前の旧牧場跡のあせび平まで、さらに足を延ばせば笙ヶ岳まで行けるという3段階に分けられます。また、逆コースをとって笙ヶ岳だけを目指すこともできるため、体力や経験に応じて歩くことができるコースとなっています。 公共交通機関を利用する場合は、養老鉄道の養老駅から歩きますが、登山口の養老ノ滝まではかなり距離があるため、養老山のみの往復コースとなることが多いです。 登山口は養老ノ滝の上にある駐車場から上る林道で、駐車場の横から林道に入り、すぐ左に谷に下りる道に入ります。ここは養老ノ滝の上で堰堤があり、流れを渡ったところから登山道が始まります。 最初は急な雑木林の斜面をジグザグに登る道で、よく整備されており、何度もターンを繰り返してベンチが2基ある明瞭な尾根に出ます。丸太の階段状の歩きやすい尾根道を進み、やがてもう一度大きな尾根に出ます。ここが三方山手前の分岐で、左に1分ほど進むと濃尾平野の眺望が大きく広がる三方山に着きます。素晴らしい展望が楽しめます。分岐に戻り10分ほど登ると、養老山脈主稜の笹原峠に出ます。峠はササが刈り開かれていますが、周囲は灌木に囲まれています。 左へ養老山への道を少し登ると、左に濃尾平野の眺望が開け、樹林の背も低くなって明るい草原状の稜線になります。道を登りきったところが小倉山で、山頂には東屋やベンチがあり、公園のように整備されています。山頂からの眺望は素晴らしく、眼前にはこれから登る三角の端正な姿の笙ヶ岳が見えます。 小倉山から小さなアップダウンを越え、右から上ってきている林道と出合うとすぐ、登山道が右に分かれており、これを登ると養老山の頂上に着きます。頂上は刈り開かれていますが、眺望はあまり良くありません。 笹原峠に戻り、主稜線を直進します。稜線の道はアップダウンが多い暗い雑木林の道で、何度も上下を繰り返してあせび平に出て、さらに下ってもみじ峠に着きます。時間や体力の余裕がなければ、あせび平から右に林道を下ることもできます。 笙ヶ岳へは峠から大洞谷登山道を下ります。鬱蒼とした樹林の道で、右から流れる大きな支流と出合ったところで右に分かれる道があり、右に入ります。流れを渡り斜面の山腹道を通って最後に浅い谷を詰め上がると笙ヶ岳の東のコルに出ますが、分岐からの道はあまり良くありません。植林された北側が開けた稜線を登ると笙ヶ岳に着きます。頂上は植林が伸びてきており、眺望は次第にきかなくなってきています。 下山はあせび平から長い林道を歩いて登山口に戻ります。草原状の養老山と樹林の深い笙ヶ岳は対照的な山で、養老山系の主峰である養老山と最高峰の笙ヶ岳を一日で楽しむことができます。登山道はよく整備された歩きやすい道が続いていますが、大洞谷から笙ヶ岳への間は道があまりよくないので注意が必要です。笙ヶ岳まで歩くとかなりハードなコースとなるため、時間や体力に合わせてコースを短縮できるようになっています。 一番短いコースは養老山の往復で、次に段階的に、もみじ峠手前の旧牧場跡のあせび平まで、さらに足を延ばせば笙ヶ岳まで行けるという3段階に分けられます。また、逆コースをとって笙ヶ岳だけを目指すこともできるため、体力や経験に応じて歩くことができるコースとなっています。 公共交通機関を利用する場合は、養老鉄道の養老駅から歩きますが、登山口の養老ノ滝まではかなり距離があるため、養老山のみの往復コースとなることが多いです。 登山口は養老ノ滝の上にある駐車場から上る林道で、駐車場の横から林道に入り、すぐ左に谷に下りる道に入ります。ここは養老ノ滝の上で堰堤があり、流れを渡ったところから登山道が始まります。 最初は急な雑木林の斜面をジグザグに登る道で、よく整備されており、何度もターンを繰り返してベンチが2基ある明瞭な尾根に出ます。丸太の階段状の歩きやすい尾根道を進み、やがてもう一度大きな尾根に出ます。ここが三方山手前の分岐で、左に1分ほど進むと濃尾平野の眺望が大きく広がる三方山に着きます。素晴らしい展望が楽しめます。分岐に戻り10分ほど登ると、養老山脈主稜の笹原峠に出ます。峠はササが刈り開かれていますが、周囲は灌木に囲まれています。 左へ養老山への道を少し登ると、左に濃尾平野の眺望が開け、樹林の背も低くなって明るい草原状の稜線になります。道を登りきったところが小倉山で、山頂には東屋やベンチがあり、公園のように整備されています。山頂からの眺望は素晴らしく、眼前にはこれから登る三角の端正な姿の笙ヶ岳が見えます。 小倉山から小さなアップダウンを越え、右から上ってきている林道と出合うとすぐ、登山道が右に分かれており、これを登ると養老山の頂上に着きます。頂上は刈り開かれていますが、眺望はあまり良くありません。 笹原峠に戻り、主稜線を直進します。稜線の道はアップダウンが多い暗い雑木林の道で、何度も上下を繰り返してあせび平に出て、さらに下ってもみじ峠に着きます。時間や体力の余裕がなければ、あせび平から右に林道を下ることもできます。 笙ヶ岳へは峠から大洞谷登山道を下ります。鬱蒼とした樹林の道で、右から流れる大きな支流と出合ったところで右に分かれる道があり、右に入ります。流れを渡り斜面の山腹道を通って最後に浅い谷を詰め上がると笙ヶ岳の東のコルに出ますが、分岐からの道はあまり良くありません。植林された北側が開けた稜線を登ると笙ヶ岳に着きます。頂上は植林が伸びてきており、眺望は次第にきかなくなってきています。 下山はあせび平から長い林道を歩いて登山口に戻ります。 -
能勢電鉄妙見口駅から妙見山へ
- 日帰り
- 3時間0分
- 9.4km
能勢電鉄妙見口駅から妙見山へ
- 日帰り
- 3時間0分
- 9.4km
能勢電鉄妙見口駅改札を出て右へ進み、国道に出て信号を渡ります。保育園の前を通り、道なりに田畑の中を進み、道標を左へ。橋を渡ると、林道が始まります。右手にトーテムポールと「大阪みどりの百選」の標柱が現れ、青いフェンスが終わると堰堤の上の広場に到着。卵や角のオブジェをすぎると、幾度も渡渉を繰り返します。岩場の谷を進み傾斜がなだらかになると県道に出ます。県道を左へ進むと左手に入る登山道が現れ、これより急登です。車道を渡り石段、木の根が多い登りを上がると石の鳥居に到着。砂利道に出て右折すると大阪自然環状道の看板があり、左手が妙見山上です。山頂は本堂を過ぎ山門を越え、信徒会館星嶺を過ぎた左手の小高いところにあります。 下りは陣馬、鳥居を過ぎると正面に大きな駐車場があり、その奥に上杉尾根の取付きがあります。里山の雑木林の中を楽しみながら進むと南方向の景色が開ける場所があります。里山の気持ちのいい道です。終盤の疲れが出る頃にガレているところがあるので注意を。信号を渡り、もと来た集落を下って妙見口駅に到着です。能勢電鉄妙見口駅改札を出て右へ進み、国道に出て信号を渡ります。保育園の前を通り、道なりに田畑の中を進み、道標を左へ。橋を渡ると、林道が始まります。右手にトーテムポールと「大阪みどりの百選」の標柱が現れ、青いフェンスが終わると堰堤の上の広場に到着。卵や角のオブジェをすぎると、幾度も渡渉を繰り返します。岩場の谷を進み傾斜がなだらかになると県道に出ます。県道を左へ進むと左手に入る登山道が現れ、これより急登です。車道を渡り石段、木の根が多い登りを上がると石の鳥居に到着。砂利道に出て右折すると大阪自然環状道の看板があり、左手が妙見山上です。山頂は本堂を過ぎ山門を越え、信徒会館星嶺を過ぎた左手の小高いところにあります。 下りは陣馬、鳥居を過ぎると正面に大きな駐車場があり、その奥に上杉尾根の取付きがあります。里山の雑木林の中を楽しみながら進むと南方向の景色が開ける場所があります。里山の気持ちのいい道です。終盤の疲れが出る頃にガレているところがあるので注意を。信号を渡り、もと来た集落を下って妙見口駅に到着です。 -
能勢電鉄妙見口駅から大堂越を経て妙見山へ
- 日帰り
- 2時間45分
- 7.5km
能勢電鉄妙見口駅から大堂越を経て妙見山へ
- 日帰り
- 2時間45分
- 7.5km
能勢電鉄妙見口駅改札を出て左へ、旧妙見の森ケーブル黒川駅跡の左の道へ入ります。橋を渡り、沢を越えて長い登りを終えると砂防堰堤に到着。しばらくすると右手に「台場クヌギ」の森が現れます。地域の名産品「菊炭」を作るための切り株から細い幹が出たクヌギです。(※先の道中に炭焼き窯の跡があります)次に針葉樹の谷間を登ります。杉林を登りきった鞍部が大堂越です。南東方向の木の根が露出したジグザクの急登を進みます。林道のヘアピンカーブに合流、左手登り方向へ進みます。旧リフト妙見山駅跡を経てすぐ左手の階段を上がり妙見山上へ向かいます。能勢妙見山ブナ林は北摂に残る唯一の林で、200本以上のブナがお寺の境内に広がっていて、ブナ守の会の皆さんが保全活動をされています。信徒会館星嶺の前を通り左手の坂の上に山頂三角点があります。 下山は山上駐車場の南端に取り付きのある上杉尾根を使います。下り始めと後半に急斜面もありますが、展望の良い場所もあるので、休憩をとりつつ丁寧に下ります。石灯篭や茶屋跡の看板などがあり、歴史を感じることができます。国道を渡り妙見口駅へ戻ります。能勢電鉄妙見口駅改札を出て左へ、旧妙見の森ケーブル黒川駅跡の左の道へ入ります。橋を渡り、沢を越えて長い登りを終えると砂防堰堤に到着。しばらくすると右手に「台場クヌギ」の森が現れます。地域の名産品「菊炭」を作るための切り株から細い幹が出たクヌギです。(※先の道中に炭焼き窯の跡があります)次に針葉樹の谷間を登ります。杉林を登りきった鞍部が大堂越です。南東方向の木の根が露出したジグザクの急登を進みます。林道のヘアピンカーブに合流、左手登り方向へ進みます。旧リフト妙見山駅跡を経てすぐ左手の階段を上がり妙見山上へ向かいます。能勢妙見山ブナ林は北摂に残る唯一の林で、200本以上のブナがお寺の境内に広がっていて、ブナ守の会の皆さんが保全活動をされています。信徒会館星嶺の前を通り左手の坂の上に山頂三角点があります。 下山は山上駐車場の南端に取り付きのある上杉尾根を使います。下り始めと後半に急斜面もありますが、展望の良い場所もあるので、休憩をとりつつ丁寧に下ります。石灯篭や茶屋跡の看板などがあり、歴史を感じることができます。国道を渡り妙見口駅へ戻ります。 -
森上バス停から三草山へ
- 日帰り
- 2時間50分
- 8km
森上バス停から三草山へ
- 日帰り
- 2時間50分
- 8km
森上バス停から少し南へ戻り、長谷川沿いを西へ進みます。三草山登山口・棚田駐車場(有料)の右手の坂道を登ると慈眼寺があります。慈眼寺を右へ、丁字の分岐を左にしばらく農地間の舗装路を登ります。峠に至るといよいよ山道に。稜線に出るとオートバイ止めの杭がありここを西へ。急な斜面が始まると山頂は間もなくです。三草山からは川西方面が望め、広くて休憩に適しています。 山頂から西へ15分ほど下るとサイノカミ峠に到着。峠には能勢路最古の年号が刻まれた道標、庚申塔があり、南に下れば屏風岩、西へ進めば滝王山です。地図上では六叉路のように見えますが、降りてきた道の右手から二つ目を下ります。日本の棚田百選「長谷の棚田」を眺め山里の風景を楽しみながら森上バス停に戻ります。バスの待ち時間がある際は道の駅 能勢(くりの郷)に立ち寄り、平野口よりバス乗車にて能勢電鉄山下駅を目指すのも良いでしょう。森上バス停から少し南へ戻り、長谷川沿いを西へ進みます。三草山登山口・棚田駐車場(有料)の右手の坂道を登ると慈眼寺があります。慈眼寺を右へ、丁字の分岐を左にしばらく農地間の舗装路を登ります。峠に至るといよいよ山道に。稜線に出るとオートバイ止めの杭がありここを西へ。急な斜面が始まると山頂は間もなくです。三草山からは川西方面が望め、広くて休憩に適しています。 山頂から西へ15分ほど下るとサイノカミ峠に到着。峠には能勢路最古の年号が刻まれた道標、庚申塔があり、南に下れば屏風岩、西へ進めば滝王山です。地図上では六叉路のように見えますが、降りてきた道の右手から二つ目を下ります。日本の棚田百選「長谷の棚田」を眺め山里の風景を楽しみながら森上バス停に戻ります。バスの待ち時間がある際は道の駅 能勢(くりの郷)に立ち寄り、平野口よりバス乗車にて能勢電鉄山下駅を目指すのも良いでしょう。 -
能勢温泉から剣尾山へ
- 日帰り
- 4時間10分
- 9.7km
能勢温泉から剣尾山へ
- 日帰り
- 4時間10分
- 9.7km
バスの場合は森上バス停で下車、浮峠を経て金谷橋へ。玉泉寺の横を通りキャンプ場を左手に見ながら登っていくとトイレがあります。ここからが登山道です。階段を進んでいくと巨岩が現れ、大日如来が祀られています。奈良時代に役行者が開いたとされる行者山は道中に行場が現れ、中にはボルトが打たれている岩もあります。岩場を上り切ったところが行者山の山頂です。ここからは雑木林の中の整備された登山道を進みます。六地蔵で右手から道が合流。月峯寺跡を過ぎ急坂を登ると剣尾山の山頂です。三角点はなく大きな岩が点在していて、天気が良ければ大阪平野、京都・亀岡方面が望めます。 山頂からは進路を北にとり、京都府との境界で二又の分岐を左手へ進み、30分ほどで横尾山です。山頂をさらに西へ、鹿除けのネット沿いに尾根を下り、21世紀の森へ(この森は近年整備されていないので、道迷いに注意)。下りきると、能勢温泉に至ります。マイカーの場合は能勢温泉のハイカー用有料駐車場を事前に申し出て利用するのがよいでしょう。バスの場合は森上バス停で下車、浮峠を経て金谷橋へ。玉泉寺の横を通りキャンプ場を左手に見ながら登っていくとトイレがあります。ここからが登山道です。階段を進んでいくと巨岩が現れ、大日如来が祀られています。奈良時代に役行者が開いたとされる行者山は道中に行場が現れ、中にはボルトが打たれている岩もあります。岩場を上り切ったところが行者山の山頂です。ここからは雑木林の中の整備された登山道を進みます。六地蔵で右手から道が合流。月峯寺跡を過ぎ急坂を登ると剣尾山の山頂です。三角点はなく大きな岩が点在していて、天気が良ければ大阪平野、京都・亀岡方面が望めます。 山頂からは進路を北にとり、京都府との境界で二又の分岐を左手へ進み、30分ほどで横尾山です。山頂をさらに西へ、鹿除けのネット沿いに尾根を下り、21世紀の森へ(この森は近年整備されていないので、道迷いに注意)。下りきると、能勢温泉に至ります。マイカーの場合は能勢温泉のハイカー用有料駐車場を事前に申し出て利用するのがよいでしょう。 -
箕面公園
- 日帰り
- 2時間20分
- 6.4km
箕面公園
- 日帰り
- 2時間20分
- 6.4km
箕面駅から北に滝道を進みます。もみじの天ぷらの有名店や箕面温泉スパーガーデンの前を通り、一の橋を渡った階段から山道へ進み、桜広場へ。広場から50mほどで左手に谷沿いを上がる道があり、しばらくは急な登りです。2つ目の分岐をハート広場方面へ左折、トラバースしながら鞍部を越えると休憩にも好適なハート広場に到着。南へ林道を進むとわくわく展望台へ。ガーランドが下げられており撮影スポットとしても人気です。展望台をあとにD23の標識を北西方向に進み、六個山山頂へ。小道が多いので方角を確認しつつ「緊急ポイント」の看板を目印に進みます。六個山は別名松尾山。大阪の市街地が一望できる山頂です。 山頂からは南へ。下りも小道が多数あるので確認しながらオルタナの森・Minoh(青少年教学の森野外活動センター)を目指します。カフェもあり休憩に最適です。オルタナの森からは舗装路歩き。長い坂を下り切ると府道9号です。左折して道沿いを進み、箕面7丁目交差点を左へ、信号を右折し箕面駅に到着。駅の2階にあるアウトドアショップ「UNITE」で山の情報やギアを見るのもよいでしょう。箕面駅から北に滝道を進みます。もみじの天ぷらの有名店や箕面温泉スパーガーデンの前を通り、一の橋を渡った階段から山道へ進み、桜広場へ。広場から50mほどで左手に谷沿いを上がる道があり、しばらくは急な登りです。2つ目の分岐をハート広場方面へ左折、トラバースしながら鞍部を越えると休憩にも好適なハート広場に到着。南へ林道を進むとわくわく展望台へ。ガーランドが下げられており撮影スポットとしても人気です。展望台をあとにD23の標識を北西方向に進み、六個山山頂へ。小道が多いので方角を確認しつつ「緊急ポイント」の看板を目印に進みます。六個山は別名松尾山。大阪の市街地が一望できる山頂です。 山頂からは南へ。下りも小道が多数あるので確認しながらオルタナの森・Minoh(青少年教学の森野外活動センター)を目指します。カフェもあり休憩に最適です。オルタナの森からは舗装路歩き。長い坂を下り切ると府道9号です。左折して道沿いを進み、箕面7丁目交差点を左へ、信号を右折し箕面駅に到着。駅の2階にあるアウトドアショップ「UNITE」で山の情報やギアを見るのもよいでしょう。 -
塚脇バス停から三好山へ
- 日帰り
- 1時間45分
- 5.4km
塚脇バス停から三好山へ
- 日帰り
- 1時間45分
- 5.4km
JR高槻駅北側市バス「51循環 塚脇」乗車、塚脇バス停で下車し摂津峡方面へ。信号を右折、川沿いの道をすぐ左折します。千念院を右に入り、しばらく進むと右手に林道の登り口があります。緩やかな登りの先に左に大きくカーブする合流点を西へ、柵沿いを進みます。開けたところからは高槻の市街地から交野山までが見渡せます。三好山山頂は摂津・丹波の守護・細川高国により築かれた山城跡です。 先の合流点まで戻り、北の山道を下ります。集落に出て左へ。慶住院を過ぎ左へ下る細い道を進むと摂津峡に出ます。売店跡の角に東海自然歩道の分岐があります。摂津峡は日本三大奇景の一つ・耶馬渓になぞらえて「摂津耶馬渓」とも謳われる北摂の景勝地。季節には桜や紅葉が美しい渓谷歩きが楽しめます。川から離れると舗装道となり摂津峡公園です。この先の美人湯祥風苑もおすすめです。そのまま道なりに進んで塚脇バス停へと戻ります。マイカーの場合は芥川緑地の駐車場が便利です。 ※三好山は私有地です。マナーを守って散策をお願いします。JR高槻駅北側市バス「51循環 塚脇」乗車、塚脇バス停で下車し摂津峡方面へ。信号を右折、川沿いの道をすぐ左折します。千念院を右に入り、しばらく進むと右手に林道の登り口があります。緩やかな登りの先に左に大きくカーブする合流点を西へ、柵沿いを進みます。開けたところからは高槻の市街地から交野山までが見渡せます。三好山山頂は摂津・丹波の守護・細川高国により築かれた山城跡です。 先の合流点まで戻り、北の山道を下ります。集落に出て左へ。慶住院を過ぎ左へ下る細い道を進むと摂津峡に出ます。売店跡の角に東海自然歩道の分岐があります。摂津峡は日本三大奇景の一つ・耶馬渓になぞらえて「摂津耶馬渓」とも謳われる北摂の景勝地。季節には桜や紅葉が美しい渓谷歩きが楽しめます。川から離れると舗装道となり摂津峡公園です。この先の美人湯祥風苑もおすすめです。そのまま道なりに進んで塚脇バス停へと戻ります。マイカーの場合は芥川緑地の駐車場が便利です。 ※三好山は私有地です。マナーを守って散策をお願いします。 -
神峰山口バス停からポンポン山へ
- 日帰り
- 3時間40分
- 11.4km
神峰山口バス停からポンポン山へ
- 日帰り
- 3時間40分
- 11.4km
神峰山口バス停すぐの信号を渡った集落の中に道標があります。獣害防止柵の扉を開けて進むと、高速下に山門が現れ神峯山寺に到着します。ここから本山寺までは、長いアスファルトの道をひたすら進みます(道中「東海自然歩道は舗装路をすすみます」と書いてあり、自然歩道とはなんぞや?と自問自答…)。 本山寺の山門で道は二手に分かれます。右は登山道、左は本山寺を経ます。本コースの山道歩きはここから、天狗杉を過ぎると針葉樹の中を抜けて進みます。ここからポンポン山までの道は歩きやすく森を楽しみながら進みましょう。山頂を足で踏み鳴らせばポンポンと音がしたことから名付けられたユニークな名前のポンポン山。東側の展望が開けています。山頂からは東へ進み、大原野森林公園への分岐の後、すぐに釈迦岳と東海自然歩道の分岐があります。ここを左、東海自然歩道を進みます。下り終えると車道に出ます。右折して善峯寺へ下山したあたりから、阪急バスで東向日駅へ出られます。冬季は善峯寺からのバスは運休のため、もう20分先へ下った小塩バス停から乗車します。神峰山口バス停すぐの信号を渡った集落の中に道標があります。獣害防止柵の扉を開けて進むと、高速下に山門が現れ神峯山寺に到着します。ここから本山寺までは、長いアスファルトの道をひたすら進みます(道中「東海自然歩道は舗装路をすすみます」と書いてあり、自然歩道とはなんぞや?と自問自答…)。 本山寺の山門で道は二手に分かれます。右は登山道、左は本山寺を経ます。本コースの山道歩きはここから、天狗杉を過ぎると針葉樹の中を抜けて進みます。ここからポンポン山までの道は歩きやすく森を楽しみながら進みましょう。山頂を足で踏み鳴らせばポンポンと音がしたことから名付けられたユニークな名前のポンポン山。東側の展望が開けています。山頂からは東へ進み、大原野森林公園への分岐の後、すぐに釈迦岳と東海自然歩道の分岐があります。ここを左、東海自然歩道を進みます。下り終えると車道に出ます。右折して善峯寺へ下山したあたりから、阪急バスで東向日駅へ出られます。冬季は善峯寺からのバスは運休のため、もう20分先へ下った小塩バス停から乗車します。 -
太閤道
- 日帰り
- 2時間55分
- 9.4km
太閤道
- 日帰り
- 2時間55分
- 9.4km
JR高槻駅、阪急高槻市駅より東へ進み安満遺跡公園を目指します。これから歩く山を一望しながら、公園内の展示館を過ぎて車道を北へ進みJRの線路をくぐります。突き当たりを左へ、名神高速を北へくぐり次の信号を右、緑水会病院の裏手から山道が始まります。三好大明神から金龍寺跡まではしっかりした登りが続きます。白馬岩、坐禅石を経て金龍寺跡(天台宗の古刹だったが昭和58年にハイカーの失火で全焼)に到着。新緑の緑、秋は紅葉が美しい場所です。分岐点を左に進むと、なだらかな稜線が気持ち良いです。みはらし台という展望スポットもあります。コースの上を高圧線が2度交差、細かい分岐が沢山あるので迷わぬよう注意。舗装路と合流した先の小屋前のベンチから三川合流点を望むことができます。その先で四ツ辻を右手へ、若山神社方面に進み、ゴルフ場のフェンス沿いの道を進みます。若山神社(北側に公衆トイレあり)から駅まで舗装路を歩き、役場の前を経て、線路沿いに進めばJR島本駅です。踏切を渡り右手に進めば楠公父子訣別之所と言われる桜井駅跡があります。南へ5分ほど進めば阪急水無瀬駅も利用できます。JR高槻駅、阪急高槻市駅より東へ進み安満遺跡公園を目指します。これから歩く山を一望しながら、公園内の展示館を過ぎて車道を北へ進みJRの線路をくぐります。突き当たりを左へ、名神高速を北へくぐり次の信号を右、緑水会病院の裏手から山道が始まります。三好大明神から金龍寺跡まではしっかりした登りが続きます。白馬岩、坐禅石を経て金龍寺跡(天台宗の古刹だったが昭和58年にハイカーの失火で全焼)に到着。新緑の緑、秋は紅葉が美しい場所です。分岐点を左に進むと、なだらかな稜線が気持ち良いです。みはらし台という展望スポットもあります。コースの上を高圧線が2度交差、細かい分岐が沢山あるので迷わぬよう注意。舗装路と合流した先の小屋前のベンチから三川合流点を望むことができます。その先で四ツ辻を右手へ、若山神社方面に進み、ゴルフ場のフェンス沿いの道を進みます。若山神社(北側に公衆トイレあり)から駅まで舗装路を歩き、役場の前を経て、線路沿いに進めばJR島本駅です。踏切を渡り右手に進めば楠公父子訣別之所と言われる桜井駅跡があります。南へ5分ほど進めば阪急水無瀬駅も利用できます。 -
阪急大山崎駅から天王山へ
- 日帰り
- 1時間55分
- 5.2km
阪急大山崎駅から天王山へ
- 日帰り
- 1時間55分
- 5.2km
JR山崎駅からは線路沿いを東へ、阪急大山崎駅からは駅前のコンビ二左手を北へ進み、踏切を渡って宝積寺を目指します。宝積寺からはしばらく登りです。酒解神社の鳥居の前に山崎合戦の地碑があり、三川合流が望めます。十七烈士の墓を経て酒解神社、もうひと登りで天王山山頂に到着。太閤秀吉が山崎合戦の直後に築城した山崎城は天下統一の出発点になった城とされています。 山頂を後に北西に進みます。のんびり歩きやすい道が続きます。小倉神社分岐を右へ向かいますが、この先は急な下りが小倉神社まで続きます。急がず丁寧に下りましょう。小倉神社より住宅街を抜け、バス通りを20分ほど進むと阪急西山天王山駅に到着です。JR山崎駅からは線路沿いを東へ、阪急大山崎駅からは駅前のコンビ二左手を北へ進み、踏切を渡って宝積寺を目指します。宝積寺からはしばらく登りです。酒解神社の鳥居の前に山崎合戦の地碑があり、三川合流が望めます。十七烈士の墓を経て酒解神社、もうひと登りで天王山山頂に到着。太閤秀吉が山崎合戦の直後に築城した山崎城は天下統一の出発点になった城とされています。 山頂を後に北西に進みます。のんびり歩きやすい道が続きます。小倉神社分岐を右へ向かいますが、この先は急な下りが小倉神社まで続きます。急がず丁寧に下りましょう。小倉神社より住宅街を抜け、バス通りを20分ほど進むと阪急西山天王山駅に到着です。 -
阪急嵐山駅から松尾山へ
- 日帰り
- 1時間40分
- 5km
阪急嵐山駅から松尾山へ
- 日帰り
- 1時間40分
- 5km
阪急嵐山駅改札を出て左手のコンビニ角を西へ進み、突き当たりを左へ曲がるとすぐ京都一周トレイルの道標「26」があり、ここが登り口となります。はじめは竹林の中をつづら折れで少し急な登りですが、しばらく進むと尾根に出ます。尾根道はところどころ堆積岩が露出していて滑る箇所があるので雨の後は用心してください。松尾山の頂上手前にベンチが現れ四辻に至ります。この四辻を直進して松尾山の山頂を目指しましょう。山頂から少し北に進むと嵐山へと続く道と出合います。ここを右に進み、先のベンチのある四辻へ戻ります。南に進路を取り西芳寺方面を目指します。ここからの尾根は歩きやすいですが、登り下りを3度繰り返しますので歩きごたえもあります。3度目のピークからの眺望が綺麗です。この先は急な斜面で木の根も出ていますので注意しながら下りましょう。林道に合流、左へ進めば西芳寺(苔寺)へと至ります。鈴虫寺を経由、阪急松尾大社駅でゴールです。阪急嵐山駅改札を出て左手のコンビニ角を西へ進み、突き当たりを左へ曲がるとすぐ京都一周トレイルの道標「26」があり、ここが登り口となります。はじめは竹林の中をつづら折れで少し急な登りですが、しばらく進むと尾根に出ます。尾根道はところどころ堆積岩が露出していて滑る箇所があるので雨の後は用心してください。松尾山の頂上手前にベンチが現れ四辻に至ります。この四辻を直進して松尾山の山頂を目指しましょう。山頂から少し北に進むと嵐山へと続く道と出合います。ここを右に進み、先のベンチのある四辻へ戻ります。南に進路を取り西芳寺方面を目指します。ここからの尾根は歩きやすいですが、登り下りを3度繰り返しますので歩きごたえもあります。3度目のピークからの眺望が綺麗です。この先は急な斜面で木の根も出ていますので注意しながら下りましょう。林道に合流、左へ進めば西芳寺(苔寺)へと至ります。鈴虫寺を経由、阪急松尾大社駅でゴールです。 -
阪急嵐山駅から小倉山へ
- 日帰り
- 2時間35分
- 8.5km
阪急嵐山駅から小倉山へ
- 日帰り
- 2時間35分
- 8.5km
阪急嵐山駅から渡月橋を眺めたときに、後ろにぽっこり見えるのが小倉山です。その麓には、藤原定家が「小倉百人一首」をまとめたとされる小倉山荘があったといわれています。 渡月橋を渡り左岸を進んで亀山公園を経て、トロッコ嵐山駅を目指します。右手には竹林の小径、左手には大河内山荘があります。トロッコ駅を過ぎると蓮の群生で有名な小倉池があり、ここから愛宕神社への鳥居前町、嵯峨鳥居本を抜け一之鳥居へ。六丁峠までは府道50号のアスファルトの登り坂が続きます。六丁峠は頭上に嵐山高雄パークウェイが走る高架下です。パークウェイ沿いを南西へ進む道が本コースで唯一の少し険しい登りです。木々の切れ間から望む保津峡に癒されつつ、「小倉山を経てハイキングコース」の看板を目印に、ブロック敷の舗装路へ。右手の小倉山のピークへ至る小径を進み登頂です。山頂には眺望はありませんが下りの途中に展望台があり、嵯峨野の風景が一望できます。登山道を下り、亀山公園の展望台から観る保津峡も絶景です。公園を後に嵐山駅まで戻ります。阪急嵐山駅から渡月橋を眺めたときに、後ろにぽっこり見えるのが小倉山です。その麓には、藤原定家が「小倉百人一首」をまとめたとされる小倉山荘があったといわれています。 渡月橋を渡り左岸を進んで亀山公園を経て、トロッコ嵐山駅を目指します。右手には竹林の小径、左手には大河内山荘があります。トロッコ駅を過ぎると蓮の群生で有名な小倉池があり、ここから愛宕神社への鳥居前町、嵯峨鳥居本を抜け一之鳥居へ。六丁峠までは府道50号のアスファルトの登り坂が続きます。六丁峠は頭上に嵐山高雄パークウェイが走る高架下です。パークウェイ沿いを南西へ進む道が本コースで唯一の少し険しい登りです。木々の切れ間から望む保津峡に癒されつつ、「小倉山を経てハイキングコース」の看板を目印に、ブロック敷の舗装路へ。右手の小倉山のピークへ至る小径を進み登頂です。山頂には眺望はありませんが下りの途中に展望台があり、嵯峨野の風景が一望できます。登山道を下り、亀山公園の展望台から観る保津峡も絶景です。公園を後に嵐山駅まで戻ります。 -
るり渓温泉から深山へ
- 日帰り
- 2時間25分
- 6.8km
るり渓温泉から深山へ
- 日帰り
- 2時間25分
- 6.8km
るり渓の奥、山深く遠いことで深山と呼ばれます。奥るり渓バス停から園部能勢線を西へ、アスファルト道を登ります。登山口は、土ヶ畑交差点、るり渓山郷の駅の右手にあります。雑木林の森に癒されながら進みますが、粘度質の土道のため、ズルッと滑りやすい箇所もあるので注意が必要です。1kmほど進むと稜線に出ます。ススキ野原になっていて景色がよく、亀岡方面が見渡せます。緩やかな起伏を楽しみなら歩いていくと車道と合流、目の前にレーダー雨量観測所があります。通用口を過ぎ、その奥にある深山神社が深山山頂です。山頂は展望がよく、大阪方面、篠山方面、京都方面が見渡せます。 深山山頂からは来た道を奥るり渓バス停に戻り、京都るり渓温泉for REST RESORTの温泉に入りサッパリして家路につきましょう。るり渓の奥、山深く遠いことで深山と呼ばれます。奥るり渓バス停から園部能勢線を西へ、アスファルト道を登ります。登山口は、土ヶ畑交差点、るり渓山郷の駅の右手にあります。雑木林の森に癒されながら進みますが、粘度質の土道のため、ズルッと滑りやすい箇所もあるので注意が必要です。1kmほど進むと稜線に出ます。ススキ野原になっていて景色がよく、亀岡方面が見渡せます。緩やかな起伏を楽しみなら歩いていくと車道と合流、目の前にレーダー雨量観測所があります。通用口を過ぎ、その奥にある深山神社が深山山頂です。山頂は展望がよく、大阪方面、篠山方面、京都方面が見渡せます。 深山山頂からは来た道を奥るり渓バス停に戻り、京都るり渓温泉for REST RESORTの温泉に入りサッパリして家路につきましょう。