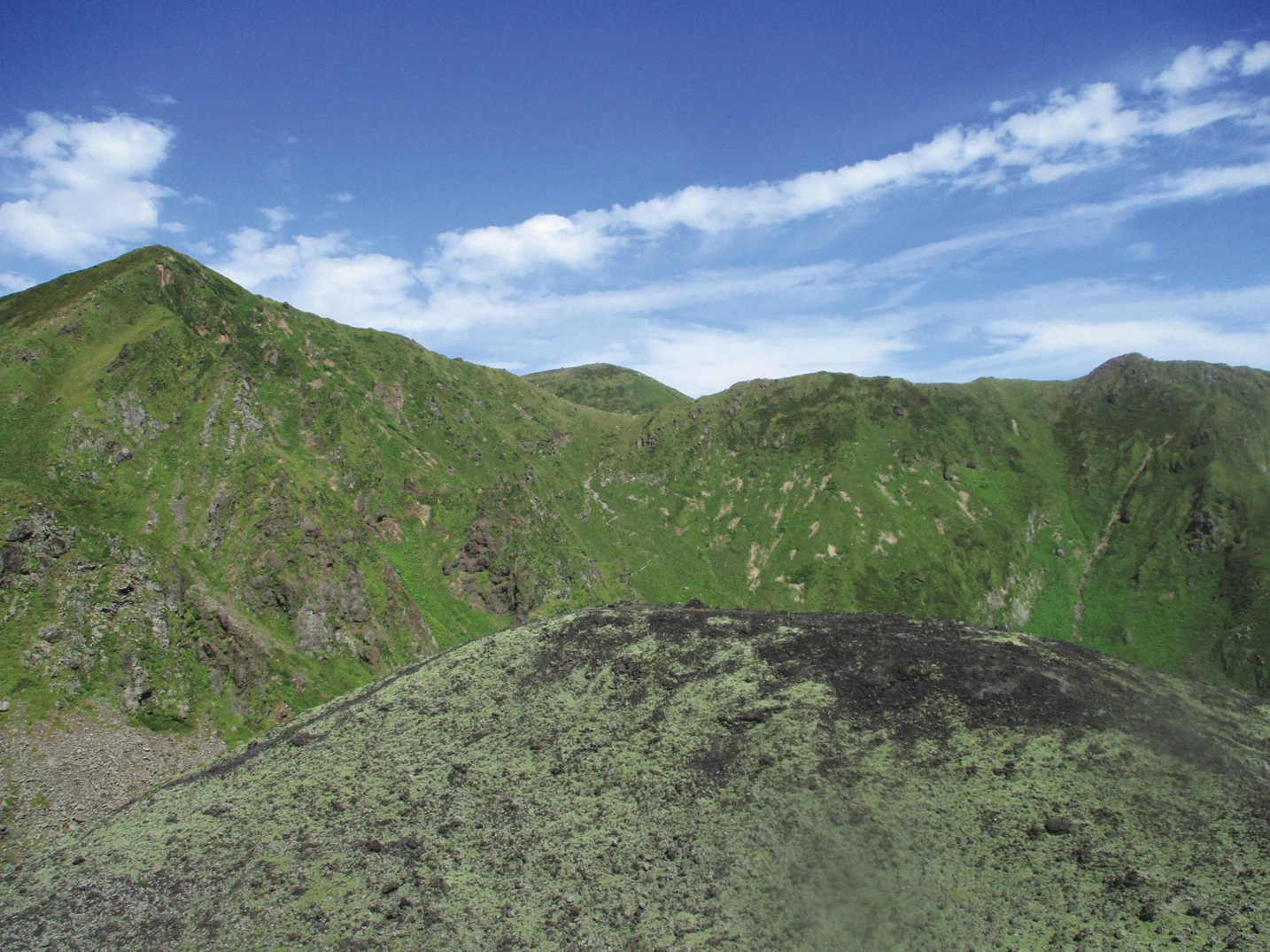【岩手県】の登山コースガイド
岩手県
検索結果22件中
1-20件
-
いわかがみ平から栗駒山
- 日帰り
- 3時間10分
- 6.5km
いわかがみ平から栗駒山
- 日帰り
- 3時間10分
- 6.5km
宮城県側の車道の終点、標高1100mのいわかがみ平は、大駐車場と公営のレストハウスが整備された登山基地です。山頂までの標高差があまりなく、展望と高山植物を手軽に楽しめるため、多くの登山者やハイカーがいわかがみ平を起点に山頂を目指します。 大駐車場からレストハウスへ向かう道を進み、右手に分岐する東栗駒コースに入ります。最初は溝状に掘れた、泥濘の多い歩きにくい道が続きます。大きな岩の段差があるハシゴ場は慎重に登りましょう。30分も登ると灌木帯に入り、少し右手に下るとナメの沢床が続く新湯沢に出ます。沢の右岸(上流に向かって左側)の岩盤の上を100mほど登り、沢の上部に張られたロープを目印に左岸に渡渉します。この渡渉点は6月下旬まで雪渓が残り、視界のないときは接続する登山道を見失う恐れがあるので注意してください。 樹高が低くなった灌木帯を右に回り込むように登ると、砂礫の混じるハイマツ帯に入ります。6月上旬にはミヤマキンバイが咲き誇ります。東栗駒山の頂稜から新湯沢源頭をはさんで栗駒山の優美な山容が望めます。この一帯は9月下旬から10月上旬にかけて息を飲むほどの鮮やかな紅葉が広がります。 ほぼ平坦な東栗駒山の頂稜を過ぎ、少し登ると栗駒草原と呼ばれる湿性のお花畑が始まります。6月中旬から7月中旬までイワカガミ・ヒナザクラ・イワイチョウ・キンコウカが咲き乱れる別天地です。裏掛コース分岐を過ぎ、土砂流失防止の整備が行われた急な階段を登りきると、左から中央コースが合流します。さらにひと登りすれば、多くの登山者が休憩している栗駒山山頂です。 独立峰である山頂からの展望は正に360度。真西に富士山を思わせる山容の鳥海山、北に焼石連峰や早池峰山、南には船形連峰と蔵王連峰、南西には栗駒国定公園の山々の奥に月山や朝日連峰など、東北地方中部の山並みが見渡せます。 帰りは整備されて歩きやすい中央コースを下っていわかがみ平に戻ります。階段を下り、緩い下り坂になると展望の良い小ピークに出ます。振り返ると栗駒本峰が大きく聳えています。ここから石が埋め込まれたコンクリートの道を下り、灌木の背が高くなるころいわかがみ平のレストハウスの前に出ます。 なお、紅葉時期の交通渋滞対策として、9月下旬から10月中旬までの期間、いこいの村栗駒跡地からいわかがみ平まで、終日マイカー規制が行われるようになりました。この期間中はいこいの村栗駒跡地の臨時駐車場から運行するシャトルバスをご利用ください。宮城県側の車道の終点、標高1100mのいわかがみ平は、大駐車場と公営のレストハウスが整備された登山基地です。山頂までの標高差があまりなく、展望と高山植物を手軽に楽しめるため、多くの登山者やハイカーがいわかがみ平を起点に山頂を目指します。 大駐車場からレストハウスへ向かう道を進み、右手に分岐する東栗駒コースに入ります。最初は溝状に掘れた、泥濘の多い歩きにくい道が続きます。大きな岩の段差があるハシゴ場は慎重に登りましょう。30分も登ると灌木帯に入り、少し右手に下るとナメの沢床が続く新湯沢に出ます。沢の右岸(上流に向かって左側)の岩盤の上を100mほど登り、沢の上部に張られたロープを目印に左岸に渡渉します。この渡渉点は6月下旬まで雪渓が残り、視界のないときは接続する登山道を見失う恐れがあるので注意してください。 樹高が低くなった灌木帯を右に回り込むように登ると、砂礫の混じるハイマツ帯に入ります。6月上旬にはミヤマキンバイが咲き誇ります。東栗駒山の頂稜から新湯沢源頭をはさんで栗駒山の優美な山容が望めます。この一帯は9月下旬から10月上旬にかけて息を飲むほどの鮮やかな紅葉が広がります。 ほぼ平坦な東栗駒山の頂稜を過ぎ、少し登ると栗駒草原と呼ばれる湿性のお花畑が始まります。6月中旬から7月中旬までイワカガミ・ヒナザクラ・イワイチョウ・キンコウカが咲き乱れる別天地です。裏掛コース分岐を過ぎ、土砂流失防止の整備が行われた急な階段を登りきると、左から中央コースが合流します。さらにひと登りすれば、多くの登山者が休憩している栗駒山山頂です。 独立峰である山頂からの展望は正に360度。真西に富士山を思わせる山容の鳥海山、北に焼石連峰や早池峰山、南には船形連峰と蔵王連峰、南西には栗駒国定公園の山々の奥に月山や朝日連峰など、東北地方中部の山並みが見渡せます。 帰りは整備されて歩きやすい中央コースを下っていわかがみ平に戻ります。階段を下り、緩い下り坂になると展望の良い小ピークに出ます。振り返ると栗駒本峰が大きく聳えています。ここから石が埋め込まれたコンクリートの道を下り、灌木の背が高くなるころいわかがみ平のレストハウスの前に出ます。 なお、紅葉時期の交通渋滞対策として、9月下旬から10月中旬までの期間、いこいの村栗駒跡地からいわかがみ平まで、終日マイカー規制が行われるようになりました。この期間中はいこいの村栗駒跡地の臨時駐車場から運行するシャトルバスをご利用ください。 -
須川温泉から栗駒山へ
- 日帰り
- 3時間35分
- 8.5km
須川温泉から栗駒山へ
- 日帰り
- 3時間35分
- 8.5km
栗駒山は岩手県では「酢川岳」と呼ばれ、須川温泉を起点に、名残ヶ原の高山植物と、昭和湖や剣岳の荒々しい火山地形を楽しめる本コースは多くの登山者に利用され親しまれています。 登山道は須川高原温泉の建屋と、露天風呂にはさまれた源泉が流れる川の脇から始まります。大日岩を右手に眺めて灌木帯を登ると、オイラン(蒸し)風呂の小屋の横を通り抜けます。地熱の湯気が立つ小さな丘を越えて少し下ると、木道が敷かれた名残ヶ原の湿原に出ます。湿原は乾燥化が進んでいますが、初夏から夏にかけてワタスゲやモウセンゴケ・イワイチョウが咲き誇ります。 湿原南端の分岐は、右折すると賽の河原やゆげ山方面に行く散策路で、登山道は直進します。低木帯を少し登ると苔花台と標識がある産沼コースの分岐ですが、ここも直進。昭和湖から流れてくるゼッタ沢を渡り、火山性ガスの噴出で木々が枯れている地獄谷の左岸を通過します。やがて道が平坦になり青白色の幻想的な水をたたえた昭和湖に着きます。この湖は昭和19年の爆発によってできた火山湖で、湖面に剣岳の荒々しい岩肌を映し出しています。 昭和湖から左手に進み、階段の急坂を登ります。緩い登りに変わりハイマツが出てくると、県境の天狗平の分岐に着きます。ここを左折して山頂を目指しましょう。天狗岩の横を抜け、展望の良い稜線を進むと、登山者で賑わう栗駒山山頂に着きます。 下山路は北東側へ下る産沼コースに入ります。間違って宮城県側の中央コースに入る方が多いので、標識をよく確認してください。下り始めは少し急ですが、やがて傾斜の緩い尾根に入ります。このコースは灌木が茂り視界があまり良くないのが難点です。 山頂から40分で産沼に着きます。右に笊森コースが分岐しますが、笊森避難小屋より下部の登山道は廃道です。産沼から西よりに方向を変えて展望のない低木帯に入ります。ジグザグの急坂を下り、三途の川とゼッタ沢を石飛びで渡渉します。沢から一段登れば苔花台の分岐です。右折し少し下って名残ヶ原南端の散策路の分岐を賽ノ磧方面に進みましょう。少し登った賽ノ磧の火口原は6月初旬にイワカガミの見事なお花畑が見られます。整備された遊歩道を下ると大日岩が見えてきて、すぐに須川温泉に戻れます。栗駒山は岩手県では「酢川岳」と呼ばれ、須川温泉を起点に、名残ヶ原の高山植物と、昭和湖や剣岳の荒々しい火山地形を楽しめる本コースは多くの登山者に利用され親しまれています。 登山道は須川高原温泉の建屋と、露天風呂にはさまれた源泉が流れる川の脇から始まります。大日岩を右手に眺めて灌木帯を登ると、オイラン(蒸し)風呂の小屋の横を通り抜けます。地熱の湯気が立つ小さな丘を越えて少し下ると、木道が敷かれた名残ヶ原の湿原に出ます。湿原は乾燥化が進んでいますが、初夏から夏にかけてワタスゲやモウセンゴケ・イワイチョウが咲き誇ります。 湿原南端の分岐は、右折すると賽の河原やゆげ山方面に行く散策路で、登山道は直進します。低木帯を少し登ると苔花台と標識がある産沼コースの分岐ですが、ここも直進。昭和湖から流れてくるゼッタ沢を渡り、火山性ガスの噴出で木々が枯れている地獄谷の左岸を通過します。やがて道が平坦になり青白色の幻想的な水をたたえた昭和湖に着きます。この湖は昭和19年の爆発によってできた火山湖で、湖面に剣岳の荒々しい岩肌を映し出しています。 昭和湖から左手に進み、階段の急坂を登ります。緩い登りに変わりハイマツが出てくると、県境の天狗平の分岐に着きます。ここを左折して山頂を目指しましょう。天狗岩の横を抜け、展望の良い稜線を進むと、登山者で賑わう栗駒山山頂に着きます。 下山路は北東側へ下る産沼コースに入ります。間違って宮城県側の中央コースに入る方が多いので、標識をよく確認してください。下り始めは少し急ですが、やがて傾斜の緩い尾根に入ります。このコースは灌木が茂り視界があまり良くないのが難点です。 山頂から40分で産沼に着きます。右に笊森コースが分岐しますが、笊森避難小屋より下部の登山道は廃道です。産沼から西よりに方向を変えて展望のない低木帯に入ります。ジグザグの急坂を下り、三途の川とゼッタ沢を石飛びで渡渉します。沢から一段登れば苔花台の分岐です。右折し少し下って名残ヶ原南端の散策路の分岐を賽ノ磧方面に進みましょう。少し登った賽ノ磧の火口原は6月初旬にイワカガミの見事なお花畑が見られます。整備された遊歩道を下ると大日岩が見えてきて、すぐに須川温泉に戻れます。 -
御沢から栗駒山・裏掛コース周回
- 日帰り
- 8時間15分
- 12.9km
御沢から栗駒山・裏掛コース周回
- 日帰り
- 8時間15分
- 12.9km
御沢コースは沢歩き、お花畑、盛夏まで残る雪渓など栗駒山の魅力を凝縮したコースです。裏掛コースを下れば、より充実した山歩きが満喫できます。 ハイルザーム栗駒から2つのスノーシェルターをくぐると御沢コース登山口に着きます。スキー場跡の草原を過ぎ、山腹を横切るように岩魚沢、デロコ沢を越えてブナ林を進むと、明るく開けた御沢に着きます。ここから「石飛八里」と呼ばれる沢通しの登りが約2km続きます。基本的に石飛び伝いに沢を遡上しますが、分かり難いところには黄色のペンキや赤テープでルートが示されています。登山靴より沢タビや長靴を履いた方が効率よく安全に登れます。 2時間ほどの沢歩きで大日沢出合に着きます。左の沢に入り、少し登ると巨岩が積み重なったハシゴ滝が現れ、左手のロープを利用して越えます。滝の上は穏やかな流れになり、小沢を何度か渡って、源流部のロープが下がった急坂を登ると御室下の雪渓に出ます。雪が解けた雪田草原にはヒナザクラ・アオノツガザクラなどの湿性の高山植物が咲き乱れ、栗駒山随一の景観に魅了されます。雪渓は部分的に急なところがあるので軽アイゼンをつけた方が安全です。雪渓を登りつめると御室の岩壁帯に突き当たります。岩壁の付け根に駒形根神社の奥宮とされる御室があり、小さな祠の中に絵馬などが奉納されています。この先、岩壁帯の下をたどりますが、荒れて道が不確かな部分があるので注意しましょう。湯浜コースに合流し、尾根道を登ると天狗平に着き、そこから20分で栗駒山山頂に達します。 下山路は山頂から中央コースを少し下り、東栗駒分岐を左折。栗駒草原中ほどにある裏掛コース分岐も左折します。裏掛コースに入ると道が急に細くなります。この先は6月下旬ごろまで雪渓が残る磐井川と産女川の源頭部を通過します。霧で視界が無い時は道の接続が分かり難いので慎重にルートを探しましょう。雪渓が消えた後にはヒナザクラやキンコウカが咲き誇ります。灌木とササの平坦な道を進むと、眼前に広大なドゾウ沢の斜面が現れます。落石に注意して大きな雪渓を横切り、ワタスゲの群生地を過ぎると、2008年の地震で駒ノ湯温泉を飲み込んだ土石流の発生地点をガイドロープに従って横切ります。その後、東栗駒山から南東に伸びる尾根を越え、ブナの原生林を下り、新湯沢の渡渉点に出ます。石飛びに沢を渡って、少し登り返せば廃小屋があります。そこから荒れた林道を少し歩き、右手へ電柱に沿った道を登ると裏掛コースの登山口に出ます。御沢コースは沢歩き、お花畑、盛夏まで残る雪渓など栗駒山の魅力を凝縮したコースです。裏掛コースを下れば、より充実した山歩きが満喫できます。 ハイルザーム栗駒から2つのスノーシェルターをくぐると御沢コース登山口に着きます。スキー場跡の草原を過ぎ、山腹を横切るように岩魚沢、デロコ沢を越えてブナ林を進むと、明るく開けた御沢に着きます。ここから「石飛八里」と呼ばれる沢通しの登りが約2km続きます。基本的に石飛び伝いに沢を遡上しますが、分かり難いところには黄色のペンキや赤テープでルートが示されています。登山靴より沢タビや長靴を履いた方が効率よく安全に登れます。 2時間ほどの沢歩きで大日沢出合に着きます。左の沢に入り、少し登ると巨岩が積み重なったハシゴ滝が現れ、左手のロープを利用して越えます。滝の上は穏やかな流れになり、小沢を何度か渡って、源流部のロープが下がった急坂を登ると御室下の雪渓に出ます。雪が解けた雪田草原にはヒナザクラ・アオノツガザクラなどの湿性の高山植物が咲き乱れ、栗駒山随一の景観に魅了されます。雪渓は部分的に急なところがあるので軽アイゼンをつけた方が安全です。雪渓を登りつめると御室の岩壁帯に突き当たります。岩壁の付け根に駒形根神社の奥宮とされる御室があり、小さな祠の中に絵馬などが奉納されています。この先、岩壁帯の下をたどりますが、荒れて道が不確かな部分があるので注意しましょう。湯浜コースに合流し、尾根道を登ると天狗平に着き、そこから20分で栗駒山山頂に達します。 下山路は山頂から中央コースを少し下り、東栗駒分岐を左折。栗駒草原中ほどにある裏掛コース分岐も左折します。裏掛コースに入ると道が急に細くなります。この先は6月下旬ごろまで雪渓が残る磐井川と産女川の源頭部を通過します。霧で視界が無い時は道の接続が分かり難いので慎重にルートを探しましょう。雪渓が消えた後にはヒナザクラやキンコウカが咲き誇ります。灌木とササの平坦な道を進むと、眼前に広大なドゾウ沢の斜面が現れます。落石に注意して大きな雪渓を横切り、ワタスゲの群生地を過ぎると、2008年の地震で駒ノ湯温泉を飲み込んだ土石流の発生地点をガイドロープに従って横切ります。その後、東栗駒山から南東に伸びる尾根を越え、ブナの原生林を下り、新湯沢の渡渉点に出ます。石飛びに沢を渡って、少し登り返せば廃小屋があります。そこから荒れた林道を少し歩き、右手へ電柱に沿った道を登ると裏掛コースの登山口に出ます。 -
栗駒山から秣岳へ
- 日帰り
- 4時間20分
- 9.8km
栗駒山から秣岳へ
- 日帰り
- 4時間20分
- 9.8km
秣岳は剣岳を中央火口丘とする崩壊が進んだ旧外輪山の西端に位置する山です。天馬尾根と呼ばれる外輪山の稜線上に点在する雪田草原や高層湿原と、そこに咲き乱れる高山植物、そして秋の紅葉は必見で、最近は入山者が増えています。 須川温泉から昭和湖、天狗平を経て栗駒山へ至るコースは須川温泉から栗駒山へ(コースガイド)を参照ください。天狗平から栗駒山山頂まで35分で往復できますので、初めての方は往復してきたほうが良いでしょう。 天狗平から西へミネカエデ・ミヤマナラ・ドウダンの灌木帯の中を進むと、展望岩頭と呼ばれる北側が切れ落ちた露岩の上に出ます。ここは栗駒山随一の展望地で、眼下に剣岳や昭和湖、須川湖、池塘を散りばめた高層湿原の龍泉ヶ原を見下ろし、秣岳へ続く天馬尾根の背後に端正な山容を見せる鳥海山、そして重畳と連なる山々の奥に焼石連峰が一望できます。この露岩には6月初旬にイワウメやミネズオウ・イワヒゲ・コケモモが咲き誇ります。 展望岩頭を後にして、洗掘されて歩きにくい道を40分下り、秣岳との鞍部に出ます。そこから先は雪田草原と高層湿原が続く、展望の良い穏やかな登りになります。やがて木道が敷かれたしろがね湿原に出ます。平らな湿原の奥の岩峰に向かって真っすぐに伸びる木道の景観から「栗駒のモン・サン=ミッシェル」と称され登山者に親しまれています。岩峰の上に登ると眼前に秣岳が見え、岩峰を取り巻く灌木帯の紅葉は赤、オレンジ、黄、緑の原色に彩られ見事です。 秣岳手前の湿原周辺には栗駒山唯一のオオシラビソの植生が見られます。雪田草原の中の急坂を登ると秣岳山頂に着きます。東側の展望が開け、眼下の樹海の中に須川湖の青い湖面が望めます。 秣岳から北西方面に急坂をジグザグに下り、鞍部から少し登り返して、右へ岩と泥が混じった滑りやすい斜面を降りて行きます。ブナの原生林に入り30分ほどで栗駒道路の秣岳登山口に着きます。ここから車道を1時間歩いて須川温泉に戻ります。時間と体力があれば須川湖の南側にあるシラタマノキ湿原に立ち寄り、泥炭層の露頭を見るのもお勧めです。秣岳は剣岳を中央火口丘とする崩壊が進んだ旧外輪山の西端に位置する山です。天馬尾根と呼ばれる外輪山の稜線上に点在する雪田草原や高層湿原と、そこに咲き乱れる高山植物、そして秋の紅葉は必見で、最近は入山者が増えています。 須川温泉から昭和湖、天狗平を経て栗駒山へ至るコースは須川温泉から栗駒山へ(コースガイド)を参照ください。天狗平から栗駒山山頂まで35分で往復できますので、初めての方は往復してきたほうが良いでしょう。 天狗平から西へミネカエデ・ミヤマナラ・ドウダンの灌木帯の中を進むと、展望岩頭と呼ばれる北側が切れ落ちた露岩の上に出ます。ここは栗駒山随一の展望地で、眼下に剣岳や昭和湖、須川湖、池塘を散りばめた高層湿原の龍泉ヶ原を見下ろし、秣岳へ続く天馬尾根の背後に端正な山容を見せる鳥海山、そして重畳と連なる山々の奥に焼石連峰が一望できます。この露岩には6月初旬にイワウメやミネズオウ・イワヒゲ・コケモモが咲き誇ります。 展望岩頭を後にして、洗掘されて歩きにくい道を40分下り、秣岳との鞍部に出ます。そこから先は雪田草原と高層湿原が続く、展望の良い穏やかな登りになります。やがて木道が敷かれたしろがね湿原に出ます。平らな湿原の奥の岩峰に向かって真っすぐに伸びる木道の景観から「栗駒のモン・サン=ミッシェル」と称され登山者に親しまれています。岩峰の上に登ると眼前に秣岳が見え、岩峰を取り巻く灌木帯の紅葉は赤、オレンジ、黄、緑の原色に彩られ見事です。 秣岳手前の湿原周辺には栗駒山唯一のオオシラビソの植生が見られます。雪田草原の中の急坂を登ると秣岳山頂に着きます。東側の展望が開け、眼下の樹海の中に須川湖の青い湖面が望めます。 秣岳から北西方面に急坂をジグザグに下り、鞍部から少し登り返して、右へ岩と泥が混じった滑りやすい斜面を降りて行きます。ブナの原生林に入り30分ほどで栗駒道路の秣岳登山口に着きます。ここから車道を1時間歩いて須川温泉に戻ります。時間と体力があれば須川湖の南側にあるシラタマノキ湿原に立ち寄り、泥炭層の露頭を見るのもお勧めです。 -
中沼から焼石岳・三合目登山口へ
- 日帰り
- 6時間25分
- 12.6km
中沼から焼石岳・三合目登山口へ
- 日帰り
- 6時間25分
- 12.6km
焼石岳の名前の由来は、薬師岳からの転訛、もしくは山頂一帯に焼けたような黒い岩が積み重なっている様子からついたと言う2つの説があります。 中沼登山口からカラマツ林を過ぎ、ブナ林の急な階段を登って、沢音が聞こえてきたら中沼に着きます。沼越しに横岳から獅子ヶ鼻岳に続く美しいスカイラインが望め、沼の西側の湿原にはリュウキンカやトウゲブキが群生しています。小沢の中の道を登っていくと、ミツガシワが咲く上沼に着きます。再び足場が悪い沢道と、湿原の木道を交互に通過して、つぶ沼分岐にでます。この分岐は残雪でコースが不明確になる時があるので注意してください。この先、トウゲブキやヒオウギアヤメが咲く小湿原と小沢を幾度か越え、登りの傾斜が緩くなるとベンチが置かれた銀明水の水場に着きます。50m先の右手の高台に銀明水避難小屋が建っています。 銀明水から上部に続く道は、雪田草原の中の急な登りに変わりますが、7月初旬まで広大な雪渓が残りますので、ガイドロープに沿って登りましょう。傾斜が緩み、ミネザクラやミヤマナラなどの低木帯をたどると、姥石平分岐に着きます。姥石平は分岐から東焼石岳まで続く広大な草原地帯で、6月初旬にはハクサンイチゲのお花畑が広がります。泉水沼を過ぎ、横岳の鞍部から急坂を登りきれば、岩手山、早池峰山、鳥海山、栗駒山など360度の大展望が広がる、焼石岳に着きます。 展望を楽しんだら山頂から北側へ続く東成瀬コースを下ります。途中の露岩帯は足場に注意して進み、焼石神社から少し下った九合目の変則十字路を左折します。ここから焼石沼までハクサンフウロ・トウゲブキ・タカネナデシコ・クガイソウなどの花々が咲き乱れるお花畑の道です。昔、短角牛の放牧地だった焼石沼周辺はミヤマキンポウゲの大群生地です。長命水の水場を過ぎ、ブナ林を下ると、三界山が大きく望める柳瀞に着きます。さらにブナ林の中を緩く下り、胆沢川を渡渉した先の平坦地が与治兵衛です。ここは県境の尾根を切り崩して西側の醍醐の水田まで水を引こうとした先人の名にちなんだ地名です。この先2箇所の渡渉がありますが、増水時は渡渉に苦労します。緩く登って着いた五合目釈迦ざんげのピークは、土地のマタギたちの集合地と言われ、焼石岳や三界山の稜線が一望できます。このピークを南に巻く道もあります。ブナの茂る大森山南斜面を進んで四合目大森沢を過ぎると県境尾根に出ます。すずこやの森コースを左に分けて、10分下れば東成瀬三合目登山口に着きます。焼石岳の名前の由来は、薬師岳からの転訛、もしくは山頂一帯に焼けたような黒い岩が積み重なっている様子からついたと言う2つの説があります。 中沼登山口からカラマツ林を過ぎ、ブナ林の急な階段を登って、沢音が聞こえてきたら中沼に着きます。沼越しに横岳から獅子ヶ鼻岳に続く美しいスカイラインが望め、沼の西側の湿原にはリュウキンカやトウゲブキが群生しています。小沢の中の道を登っていくと、ミツガシワが咲く上沼に着きます。再び足場が悪い沢道と、湿原の木道を交互に通過して、つぶ沼分岐にでます。この分岐は残雪でコースが不明確になる時があるので注意してください。この先、トウゲブキやヒオウギアヤメが咲く小湿原と小沢を幾度か越え、登りの傾斜が緩くなるとベンチが置かれた銀明水の水場に着きます。50m先の右手の高台に銀明水避難小屋が建っています。 銀明水から上部に続く道は、雪田草原の中の急な登りに変わりますが、7月初旬まで広大な雪渓が残りますので、ガイドロープに沿って登りましょう。傾斜が緩み、ミネザクラやミヤマナラなどの低木帯をたどると、姥石平分岐に着きます。姥石平は分岐から東焼石岳まで続く広大な草原地帯で、6月初旬にはハクサンイチゲのお花畑が広がります。泉水沼を過ぎ、横岳の鞍部から急坂を登りきれば、岩手山、早池峰山、鳥海山、栗駒山など360度の大展望が広がる、焼石岳に着きます。 展望を楽しんだら山頂から北側へ続く東成瀬コースを下ります。途中の露岩帯は足場に注意して進み、焼石神社から少し下った九合目の変則十字路を左折します。ここから焼石沼までハクサンフウロ・トウゲブキ・タカネナデシコ・クガイソウなどの花々が咲き乱れるお花畑の道です。昔、短角牛の放牧地だった焼石沼周辺はミヤマキンポウゲの大群生地です。長命水の水場を過ぎ、ブナ林を下ると、三界山が大きく望める柳瀞に着きます。さらにブナ林の中を緩く下り、胆沢川を渡渉した先の平坦地が与治兵衛です。ここは県境の尾根を切り崩して西側の醍醐の水田まで水を引こうとした先人の名にちなんだ地名です。この先2箇所の渡渉がありますが、増水時は渡渉に苦労します。緩く登って着いた五合目釈迦ざんげのピークは、土地のマタギたちの集合地と言われ、焼石岳や三界山の稜線が一望できます。このピークを南に巻く道もあります。ブナの茂る大森山南斜面を進んで四合目大森沢を過ぎると県境尾根に出ます。すずこやの森コースを左に分けて、10分下れば東成瀬三合目登山口に着きます。 -
夏油温泉から焼石岳・南本内岳登山口へ
- 1泊2日
- 11時間45分
- 19km
夏油温泉から焼石岳・南本内岳登山口へ
- 1泊2日
- 11時間45分
- 19km
古くからの湯治場で、秘湯として知られる夏油温泉が縦走の起点になります。温泉の入口右手にある駐車場北側の登山口から、斜面を斜めに登り古い作業道に出ます。少し下り直進する道は石灰華ドームへ続きますが、登山道は鋭角に右に折れ、10分ほど登り林道に合流します。林道を横切り直進する道は牛形山への登山道で、経塚山は左へ林道を40分歩きます。経塚山二の標識に導かれて夏油川方面へ急坂を下り、2022年秋に再建された歩道橋を渡ります。対岸に渡るとすぐにロープが設置された岩場が現れ、その後、ブナ林の九十九折りの急坂を標高差300m登ります。やがて傾斜が緩んで尾根上の道になり、少し下って水場に着きます。先にある苔むした岩とコメツガの森に囲まれたお坪の庭は、真夏でも風穴の冷気が漂っています。八合目の木道を過ぎ、初夏まで雪渓が残る急な草原を登ります。草原上部の灌木帯を進むと、慈覚大師が経文を埋めたと伝えられる経塚山山頂に着きます。山頂からの展望は圧巻で、天竺山から焼石岳、南本内岳へ連なる主稜線が見渡せます。 山頂から賽ノ河原を経て鞍部まで下り、ピークをふたつ越し、天竺山の北側を巻いて、小沢状の道を下ると金明水に着きます。水場のそばに建つ金明水避難小屋が今宵の宿です。 金明水からワタスゲが群生する雪田草原を登り、灌木帯の稜線のピークを幾つか越えます。六沢山の先は南側が急な崖になっていて、逆に北側は珠玉のような池が点在しています。東焼石岳に着くと、そこから姥石平分岐まで広大な姥石平のお花畑が続きます。横岳鞍部から、急坂を登れば展望抜群の焼石岳山頂に到着です。 下山は北へ九合目・焼石神社まで下り、変則十字路を直進して南本内岳を目指します。南本内川源流の沼から少し登ると、展望が広がる南本内岳(権四郎森)の最高点に着きます。小さな高層湿原の先に分岐があり、左がお花畑コース、右は南本内岳の山頂標識が立つ1486mピークで、ここは花の多いお花畑コースを下ります。正面に三界山を眺めながら灌木の稜線を下り、稜線の途中から右に折れると、リュウキンカやヒナザクラが咲く新倉沢源流域の湿原に出ます。湿原の下部で尾根コースと合流し左折すると、灌木帯からブナ林に入ります。ブナ清水を過ぎ、新倉沢は飛び石で渡ります。スギの植林地に入れば南本内岳登山口は僅かな距離です。古くからの湯治場で、秘湯として知られる夏油温泉が縦走の起点になります。温泉の入口右手にある駐車場北側の登山口から、斜面を斜めに登り古い作業道に出ます。少し下り直進する道は石灰華ドームへ続きますが、登山道は鋭角に右に折れ、10分ほど登り林道に合流します。林道を横切り直進する道は牛形山への登山道で、経塚山は左へ林道を40分歩きます。経塚山二の標識に導かれて夏油川方面へ急坂を下り、2022年秋に再建された歩道橋を渡ります。対岸に渡るとすぐにロープが設置された岩場が現れ、その後、ブナ林の九十九折りの急坂を標高差300m登ります。やがて傾斜が緩んで尾根上の道になり、少し下って水場に着きます。先にある苔むした岩とコメツガの森に囲まれたお坪の庭は、真夏でも風穴の冷気が漂っています。八合目の木道を過ぎ、初夏まで雪渓が残る急な草原を登ります。草原上部の灌木帯を進むと、慈覚大師が経文を埋めたと伝えられる経塚山山頂に着きます。山頂からの展望は圧巻で、天竺山から焼石岳、南本内岳へ連なる主稜線が見渡せます。 山頂から賽ノ河原を経て鞍部まで下り、ピークをふたつ越し、天竺山の北側を巻いて、小沢状の道を下ると金明水に着きます。水場のそばに建つ金明水避難小屋が今宵の宿です。 金明水からワタスゲが群生する雪田草原を登り、灌木帯の稜線のピークを幾つか越えます。六沢山の先は南側が急な崖になっていて、逆に北側は珠玉のような池が点在しています。東焼石岳に着くと、そこから姥石平分岐まで広大な姥石平のお花畑が続きます。横岳鞍部から、急坂を登れば展望抜群の焼石岳山頂に到着です。 下山は北へ九合目・焼石神社まで下り、変則十字路を直進して南本内岳を目指します。南本内川源流の沼から少し登ると、展望が広がる南本内岳(権四郎森)の最高点に着きます。小さな高層湿原の先に分岐があり、左がお花畑コース、右は南本内岳の山頂標識が立つ1486mピークで、ここは花の多いお花畑コースを下ります。正面に三界山を眺めながら灌木の稜線を下り、稜線の途中から右に折れると、リュウキンカやヒナザクラが咲く新倉沢源流域の湿原に出ます。湿原の下部で尾根コースと合流し左折すると、灌木帯からブナ林に入ります。ブナ清水を過ぎ、新倉沢は飛び石で渡ります。スギの植林地に入れば南本内岳登山口は僅かな距離です。 -
夏油温泉から牛形山へ
- 日帰り
- 7時間5分
- 10.3km
夏油温泉から牛形山へ
- 日帰り
- 7時間5分
- 10.3km
秘湯・夏油温泉の西側にそびえる牛形山は、経塚山、駒ヶ岳とともに夏油三山の一座で、山名の由来は残雪が牛の形に見える、牛が伏した姿に見えるなど2つの説があります。 登山口は夏油温泉入口の駐車場北側にあります。温泉の建物を見下ろしながら山腹を横切り、作業道に出て左折、石灰華ドーム遊歩道の入口から右に分岐する道を登り、合流する林道を横切った場所が牛形山への道です。 ブナの原生林の斜面を登って尾根に出ると、尾根を忠実にたどらず、左右の斜面を巻きながら登って行きます。「牛形山五」の標識から標高差150mの急登が続きます。牛形山山頂から北東に伸びる尾根に出ると、梢越しに白っ子森や鷲ヶ森山が見えてきます。この付近からブナの背丈が低くなり、牛形山北側の足場の悪い急な草付き斜面を横切っていきます。ここに残雪がある場合は滑落の危険性が高いので、無理だと思ったら引き返した方がよいでしょう。1箇所脆い岩質の急な岩場があるので、固定ロープを頼りに慎重に登ってください。 水場を経て進むとダケカンバの森になり、丸子峠への縦走コースが分岐する八合目に着きます。分岐を左折すると小さな湿原に出て、その先はロープが張られた粘土質の滑りやすい急坂が、山頂北側の稜線まで続きます。登りきると眺望が一気に広がり、灌木と露岩帯の稜線を10分ほど進むと牛形山山頂に着きます。ミヤマナラやミネカエデの低灌木に囲まれた山頂からは、眼下に赤い屋根の夏油温泉や入畑ダム、夏油三山の駒ヶ岳や経塚山、そして焼石岳や南本内岳など焼石連峰の山々が一望できます。 静かな山頂で展望を楽しんだら、八合目の分岐まで戻り左折して、稜線を丸子峠まで縦走し、夏油温泉に下る周回コースに入ります。このコースは刈払いが不定期なので、北上市商業観光課に問い合わせてから歩く事をお勧めします。 最初は傾斜した湿原の中を登り、灌木が茂る稜線に出ます。白っ子森の山頂には2体の雄坊地蔵が祀られ、白っ子森東斜面のお花畑が広がる急な草付きにはロープが延々と張られています。鷲ヶ森山まで低木帯の道を登り返すと、キャラボクの巨木が登山道に張り出しています。鷲ヶ森山頂は西側に15mほど入った場所で北側の展望が開けます。ブナ林を下り、鞍部から標高差50m登った地点が丸子峠で、右折して夏油温泉へ下ります。ブナの巨木林の中を下り、県道に出て、車道を西へ850m歩けば夏油温泉に戻れます。秘湯・夏油温泉の西側にそびえる牛形山は、経塚山、駒ヶ岳とともに夏油三山の一座で、山名の由来は残雪が牛の形に見える、牛が伏した姿に見えるなど2つの説があります。 登山口は夏油温泉入口の駐車場北側にあります。温泉の建物を見下ろしながら山腹を横切り、作業道に出て左折、石灰華ドーム遊歩道の入口から右に分岐する道を登り、合流する林道を横切った場所が牛形山への道です。 ブナの原生林の斜面を登って尾根に出ると、尾根を忠実にたどらず、左右の斜面を巻きながら登って行きます。「牛形山五」の標識から標高差150mの急登が続きます。牛形山山頂から北東に伸びる尾根に出ると、梢越しに白っ子森や鷲ヶ森山が見えてきます。この付近からブナの背丈が低くなり、牛形山北側の足場の悪い急な草付き斜面を横切っていきます。ここに残雪がある場合は滑落の危険性が高いので、無理だと思ったら引き返した方がよいでしょう。1箇所脆い岩質の急な岩場があるので、固定ロープを頼りに慎重に登ってください。 水場を経て進むとダケカンバの森になり、丸子峠への縦走コースが分岐する八合目に着きます。分岐を左折すると小さな湿原に出て、その先はロープが張られた粘土質の滑りやすい急坂が、山頂北側の稜線まで続きます。登りきると眺望が一気に広がり、灌木と露岩帯の稜線を10分ほど進むと牛形山山頂に着きます。ミヤマナラやミネカエデの低灌木に囲まれた山頂からは、眼下に赤い屋根の夏油温泉や入畑ダム、夏油三山の駒ヶ岳や経塚山、そして焼石岳や南本内岳など焼石連峰の山々が一望できます。 静かな山頂で展望を楽しんだら、八合目の分岐まで戻り左折して、稜線を丸子峠まで縦走し、夏油温泉に下る周回コースに入ります。このコースは刈払いが不定期なので、北上市商業観光課に問い合わせてから歩く事をお勧めします。 最初は傾斜した湿原の中を登り、灌木が茂る稜線に出ます。白っ子森の山頂には2体の雄坊地蔵が祀られ、白っ子森東斜面のお花畑が広がる急な草付きにはロープが延々と張られています。鷲ヶ森山まで低木帯の道を登り返すと、キャラボクの巨木が登山道に張り出しています。鷲ヶ森山頂は西側に15mほど入った場所で北側の展望が開けます。ブナ林を下り、鞍部から標高差50m登った地点が丸子峠で、右折して夏油温泉へ下ります。ブナの巨木林の中を下り、県道に出て、車道を西へ850m歩けば夏油温泉に戻れます。 -
小田越から早池峰山・鶏頭山へ
- 日帰り
- 9時間10分
- 11.4km
小田越から早池峰山・鶏頭山へ
- 日帰り
- 9時間10分
- 11.4km
6月中旬から8月上旬の土・日・祝日、岳から江繋までの間はマイカー規制されシャトルバスが運行されます。また貴重な高山植物の環境保護を目的として、山頂避難小屋のトイレは携帯トイレ専用になっています。携帯トイレは小田越登山口で販売しています。 県道25号の最高地点、小田越から登山道に入ります。オオシラビソの森を緩く登ると、30分ほどで森林限界に達し、一合目御門口に着きます。ここから氷河期の凍結破砕作用によって壊された蛇紋岩の岩塊斜面が続く高山帯に入ります。靴で磨かれた蛇紋岩は非常に滑りやすいので注意して登りましょう。ハヤチネウスユキソウやミヤマオダマキなど様々な花が咲き乱れる登山道の両脇には高山植物保護のロープが張られています。やがて傾斜が緩むと大きな岩塔が立つ五合目御金蔵です。振り返れば薬師岳が綺麗な三角形の姿で望めます。ハイマツ帯の広がる竜ヶ馬場を過ぎると、岩場に設置された2連の鉄ハシゴを登ります。そこから僅かな距離で主稜線の剣ヶ峰分岐に出ます。イワカガミやヨツバシオガマが咲く御田植場の小湿原を通り、門馬コース分岐を過ぎて、すぐに避難小屋や早池峰神社奥宮の建つ早池峰山山頂に着きます。山頂からの展望は360度。秀麗な岩手山、焼石連峰など奥羽山脈の山々が一望でき、南北に北上山地の山並みが連なっています。 この先の縦走路は、視界が利かないときには迷いやすいので注意が必要です。道が不明確な箇所にはガイドロープが延々と張られています。頂上を離れると登山者が少なくなり、それまでの喧騒がウソのように静かになります。咲き乱れる高山植物を愛でながら緩く下ると、中岳の鞍部でコメツガ・オオシラビソの樹林帯に入り、中岳まで幾つかの岩峰を巻いたり、越えたりしながら進みます。中岳山頂は目立たない岩峰で見落としてしまう方も多いです。 中岳から地形図の1518mまでの区間は、露岩や岩峰を越して下ります。数mの本格的な岩場の下りは慎重に。岩峰が終わるとオオシラビソの樹林帯に入ります。1468mピークを越した先に、水場100mの標識があり、少量ながら水を得られます。1415mピークを過ぎた地点は南側が切れ落ちているので慎重に通過しましょう。ひと登りで展望の良い鶏頭山山頂に着きます。ヤセ尾根を下ると、お地蔵様のある前鶏頭の山頂です。その岩峰の下で七折ノ滝へ下る道を右に見送ります。すぐに樹林帯に入り、水場のない鶏頭山避難小屋の前を通って、広葉樹林の小尾根をどんどん下れば、車道に飛び出し、岳集落まで10分で着きます。6月中旬から8月上旬の土・日・祝日、岳から江繋までの間はマイカー規制されシャトルバスが運行されます。また貴重な高山植物の環境保護を目的として、山頂避難小屋のトイレは携帯トイレ専用になっています。携帯トイレは小田越登山口で販売しています。 県道25号の最高地点、小田越から登山道に入ります。オオシラビソの森を緩く登ると、30分ほどで森林限界に達し、一合目御門口に着きます。ここから氷河期の凍結破砕作用によって壊された蛇紋岩の岩塊斜面が続く高山帯に入ります。靴で磨かれた蛇紋岩は非常に滑りやすいので注意して登りましょう。ハヤチネウスユキソウやミヤマオダマキなど様々な花が咲き乱れる登山道の両脇には高山植物保護のロープが張られています。やがて傾斜が緩むと大きな岩塔が立つ五合目御金蔵です。振り返れば薬師岳が綺麗な三角形の姿で望めます。ハイマツ帯の広がる竜ヶ馬場を過ぎると、岩場に設置された2連の鉄ハシゴを登ります。そこから僅かな距離で主稜線の剣ヶ峰分岐に出ます。イワカガミやヨツバシオガマが咲く御田植場の小湿原を通り、門馬コース分岐を過ぎて、すぐに避難小屋や早池峰神社奥宮の建つ早池峰山山頂に着きます。山頂からの展望は360度。秀麗な岩手山、焼石連峰など奥羽山脈の山々が一望でき、南北に北上山地の山並みが連なっています。 この先の縦走路は、視界が利かないときには迷いやすいので注意が必要です。道が不明確な箇所にはガイドロープが延々と張られています。頂上を離れると登山者が少なくなり、それまでの喧騒がウソのように静かになります。咲き乱れる高山植物を愛でながら緩く下ると、中岳の鞍部でコメツガ・オオシラビソの樹林帯に入り、中岳まで幾つかの岩峰を巻いたり、越えたりしながら進みます。中岳山頂は目立たない岩峰で見落としてしまう方も多いです。 中岳から地形図の1518mまでの区間は、露岩や岩峰を越して下ります。数mの本格的な岩場の下りは慎重に。岩峰が終わるとオオシラビソの樹林帯に入ります。1468mピークを越した先に、水場100mの標識があり、少量ながら水を得られます。1415mピークを過ぎた地点は南側が切れ落ちているので慎重に通過しましょう。ひと登りで展望の良い鶏頭山山頂に着きます。ヤセ尾根を下ると、お地蔵様のある前鶏頭の山頂です。その岩峰の下で七折ノ滝へ下る道を右に見送ります。すぐに樹林帯に入り、水場のない鶏頭山避難小屋の前を通って、広葉樹林の小尾根をどんどん下れば、車道に飛び出し、岳集落まで10分で着きます。 -
門馬から早池峰山へ
- 日帰り
- 9時間30分
- 22km
門馬から早池峰山へ
- 日帰り
- 9時間30分
- 22km
早池峰山の小田越コースは、登山者が集中して週末には山頂まで行列が続きます。それに対して北面の門馬コースは盛岡から宮古行きの急行バスが運行され、交通の便が良いにもかかわらず登山者が少なくて、静かな山旅が楽しめます。 国道106号の門馬トンネルから500m東進し、右手の閉伊川にかかる橋を渡って林道を4.5km進むと、10台の駐車スペースがある握沢登山口に着きます。登山口のゲートをくぐり、広い作業道を300mほど進んで左折し登山道に入ります。少し登ると握沢右岸に伸びる古い森林軌道跡の平坦な道が続きます。支沢の落ち込む箇所すべてに鉄製の橋が架けられていますが、一部橋が崩壊して高巻きする箇所もあります。木洩れ日が差し込む沢沿いにはミズナラ・カツラ・ヒノキアスナロの巨木林が続き、早池峰山北面の自然度の高さを感じさせてくれます。 やがて丸太橋を左岸に渡り、神額に早池峰神社と掲げられた鳥居が建つ五合目・垢離取場に着きます。ここから本格的な登りが始まり、六合目の平津戸コース分岐を通過します。平津戸コースは自治体の整備が行われず危険なため通行禁止になりました。そこから鬱蒼としたヒノキアスナロとコメツガの原生林に入り、七合目を過ぎるとさらに傾斜が増します。そしてコメツガの純林を越えれば、石仏が祀られた八合目です。九合目の水場は盛夏に涸れることもあるので期待しない方が良いでしょう。ハイマツ帯まで標高を上げると、右手に累々と黒い岩場を見せる山頂部が見えてきて、主稜線の門馬分岐に着けば早池峰山山頂は目前です。 なお場所は分かりにくいのですが、山頂の西側に開慶水と呼ばれる水が溜まった小さな池(穴)があります。この穴の水はどんなに暑くても涸れることなく、また大雨が降っても溢れることがないそうです。しかし穴の中に手を入れたり、水を飲んだりするとすぐに水は涸れてしまうので、その時は修験者に頼んで祈願してもらえば、立ちどころに水が湧きだすため、別名「早地(はやち)の泉」と呼ばれ、それが早池峰山の山名の由来になったとされています。山頂の展望を楽しんだら往路を戻ります。深い森の逍遥を楽しめるコースなので、もっと多くの人に利用されても良いと感じます。早池峰山の小田越コースは、登山者が集中して週末には山頂まで行列が続きます。それに対して北面の門馬コースは盛岡から宮古行きの急行バスが運行され、交通の便が良いにもかかわらず登山者が少なくて、静かな山旅が楽しめます。 国道106号の門馬トンネルから500m東進し、右手の閉伊川にかかる橋を渡って林道を4.5km進むと、10台の駐車スペースがある握沢登山口に着きます。登山口のゲートをくぐり、広い作業道を300mほど進んで左折し登山道に入ります。少し登ると握沢右岸に伸びる古い森林軌道跡の平坦な道が続きます。支沢の落ち込む箇所すべてに鉄製の橋が架けられていますが、一部橋が崩壊して高巻きする箇所もあります。木洩れ日が差し込む沢沿いにはミズナラ・カツラ・ヒノキアスナロの巨木林が続き、早池峰山北面の自然度の高さを感じさせてくれます。 やがて丸太橋を左岸に渡り、神額に早池峰神社と掲げられた鳥居が建つ五合目・垢離取場に着きます。ここから本格的な登りが始まり、六合目の平津戸コース分岐を通過します。平津戸コースは自治体の整備が行われず危険なため通行禁止になりました。そこから鬱蒼としたヒノキアスナロとコメツガの原生林に入り、七合目を過ぎるとさらに傾斜が増します。そしてコメツガの純林を越えれば、石仏が祀られた八合目です。九合目の水場は盛夏に涸れることもあるので期待しない方が良いでしょう。ハイマツ帯まで標高を上げると、右手に累々と黒い岩場を見せる山頂部が見えてきて、主稜線の門馬分岐に着けば早池峰山山頂は目前です。 なお場所は分かりにくいのですが、山頂の西側に開慶水と呼ばれる水が溜まった小さな池(穴)があります。この穴の水はどんなに暑くても涸れることなく、また大雨が降っても溢れることがないそうです。しかし穴の中に手を入れたり、水を飲んだりするとすぐに水は涸れてしまうので、その時は修験者に頼んで祈願してもらえば、立ちどころに水が湧きだすため、別名「早地(はやち)の泉」と呼ばれ、それが早池峰山の山名の由来になったとされています。山頂の展望を楽しんだら往路を戻ります。深い森の逍遥を楽しめるコースなので、もっと多くの人に利用されても良いと感じます。 -
馬留から薬師岳へ
- 日帰り
- 7時間40分
- 10.8km
馬留から薬師岳へ
- 日帰り
- 7時間40分
- 10.8km
優美な三角形の山容を持つ薬師岳は早池峰山と基盤岩が異なる花崗岩質の山です。山頂から見る早池峰山の迫力ある姿は圧巻で、オサバグサの開花期には、小田越から多くの登山者が登っています。しかし山行の充実度では、民話の故郷として有名な遠野市の馬留から又一の滝を経由して周回するコースが勝ります。 登山口まではマイカー利用が賢明です。上附馬牛大出から大野平の開拓地を過ぎて、林道を500m走行すると馬留登山口に着きます。又一の滝までは遊歩道が整備され、滝川沿いに30分で着きます。又一の滝は上部がナメ状で落差数十m。滝の下には石碑や祠が祀られています。滝の左岸を少し登ると、帰路に使う横通りコースが右に分かれます。薬師岳の直登ルートは分岐を直進して、滝川の左岸をたどり、すぐに右岸に渡渉します。そこから10分ほど急坂を登るとブナの原生林に入ります。標高1400m付近からダケカンバが現れ、やがてコメツガが矮生化した森に変わります。ハイマツ帯に出ると展望が一気に広がり、遠野盆地や薬師岳から西へ続く小白森、白森山のなだらかな稜線が一望できます。ガイドロープに導かれて大岩とハイマツの間を縫うように登り薬師岳山頂に到着します。 岩峰状の山頂からの展望は素晴らしく、正面に早池峰山が大きくそびえ、右手に剣ヶ峰、左手には中岳から鶏頭山に伸びる主稜線の大パノラマが広がります。 眺望を楽しんだら、西へ頂稜をたどり小田越に下ります。岩場にビッシリと張り付いたコケモモやイワヒゲの花が見事です。早池峰山を正面に眺めながらハイマツ帯を下ると、すぐにコメツガやオオシラビソの森に入ります。そこから花崗岩の岩塊とハシゴ場を下りますが、岩穴の奥にはヒカリゴケが怪しく光り、林床には6月下旬にオサバグサが咲き誇ります。傾斜が緩くなり、木道が現れると小田越は間近です。小田越から車道を150mほど東側に下り、右に分岐する横通りに入ります。この登山道は小田越山荘を過ぎ、薬師堂を経て又一の滝まで薬師岳の東側を大きく半周します。途中で右に分岐する薬師岳への登山道は整備されておらず通行禁止です。横通りはコメツガの巨木林をトラバースしていきます。小田越山荘から距離約2.5km進み、薬師岳から東に伸びる尾根を越えます。薬師堂は尾根の頂点から南に200m下った地点に建っています。そこからブナとミズナラの森を1時間10分下って又一の滝に着き、馬留登山口まで往路を戻ります。優美な三角形の山容を持つ薬師岳は早池峰山と基盤岩が異なる花崗岩質の山です。山頂から見る早池峰山の迫力ある姿は圧巻で、オサバグサの開花期には、小田越から多くの登山者が登っています。しかし山行の充実度では、民話の故郷として有名な遠野市の馬留から又一の滝を経由して周回するコースが勝ります。 登山口まではマイカー利用が賢明です。上附馬牛大出から大野平の開拓地を過ぎて、林道を500m走行すると馬留登山口に着きます。又一の滝までは遊歩道が整備され、滝川沿いに30分で着きます。又一の滝は上部がナメ状で落差数十m。滝の下には石碑や祠が祀られています。滝の左岸を少し登ると、帰路に使う横通りコースが右に分かれます。薬師岳の直登ルートは分岐を直進して、滝川の左岸をたどり、すぐに右岸に渡渉します。そこから10分ほど急坂を登るとブナの原生林に入ります。標高1400m付近からダケカンバが現れ、やがてコメツガが矮生化した森に変わります。ハイマツ帯に出ると展望が一気に広がり、遠野盆地や薬師岳から西へ続く小白森、白森山のなだらかな稜線が一望できます。ガイドロープに導かれて大岩とハイマツの間を縫うように登り薬師岳山頂に到着します。 岩峰状の山頂からの展望は素晴らしく、正面に早池峰山が大きくそびえ、右手に剣ヶ峰、左手には中岳から鶏頭山に伸びる主稜線の大パノラマが広がります。 眺望を楽しんだら、西へ頂稜をたどり小田越に下ります。岩場にビッシリと張り付いたコケモモやイワヒゲの花が見事です。早池峰山を正面に眺めながらハイマツ帯を下ると、すぐにコメツガやオオシラビソの森に入ります。そこから花崗岩の岩塊とハシゴ場を下りますが、岩穴の奥にはヒカリゴケが怪しく光り、林床には6月下旬にオサバグサが咲き誇ります。傾斜が緩くなり、木道が現れると小田越は間近です。小田越から車道を150mほど東側に下り、右に分岐する横通りに入ります。この登山道は小田越山荘を過ぎ、薬師堂を経て又一の滝まで薬師岳の東側を大きく半周します。途中で右に分岐する薬師岳への登山道は整備されておらず通行禁止です。横通りはコメツガの巨木林をトラバースしていきます。小田越山荘から距離約2.5km進み、薬師岳から東に伸びる尾根を越えます。薬師堂は尾根の頂点から南に200m下った地点に建っています。そこからブナとミズナラの森を1時間10分下って又一の滝に着き、馬留登山口まで往路を戻ります。 -
馬返し登山口から岩手山へ
- 日帰り
- 8時間20分
- 11.4km
馬返し登山口から岩手山へ
- 日帰り
- 8時間20分
- 11.4km
名峰岩手山の表口と言える代表的なコースで、馬返し登山口(柳沢コース)には100台以上駐車可能な無料の大きな駐車場が三つ、トイレが二つ、鬼又清水という水場、キャンプ場があります。 駐車場から少し上がった広場の案内板から登山道に入ります。ミズナラなどの森に道が続き、やがて大きな一本ブナの立つ0.5合目に着きます。ここで道は二つに分かれ、どちらも一合目で合流します。左は展望のある細い道、右は森の中の広い道です。一合目広場を過ぎると展望の広がる二合目。また森に入り2.5合目。ここから新道と旧道に分かれ七合目で合流します。新道は樹林の道、旧道は展望の道です。三合目、四合目、五合目に100mほどの連絡路があり行き来できます。四合目まで新道を行き、四合目から旧道に出て花と展望を楽しみながら登るのがお勧めです。ただし、足場の悪い岩場、砂礫の崩壊地、割れた大岩などがありますので、よく周囲を観察し白いペンキ印に従い、ルートを外れないようにしましょう。特に視界不良時は要注意です。鉾立(七合目)で道は平坦になり間もなく八合目避難小屋に着きます。小屋前の広場にはベンチ、御成清水の水場、トイレがあり多くの登山者が休憩しています。 小屋から九合目不動平を経て、外輪山へ向かいます。砂礫の道になり途中二又に分かれますが、登りやすい右を行きましょう。外輪に立つと景色が一変、荒々しい火口と火口丘の向こうに山頂の薬師岳が見えます。ここは左へ時計回りに山頂薬師岳を目指します。焼走りへの分岐を直進すると間もなく山頂(薬師岳)です。岩手県最高峰からは360度のパノラマが広がっています。 下りは外輪を焼走りコースの道標まで戻り右へ折れます。砂礫帯を下るとトイレのある平笠不動避難小屋です。ここから斜面を巻くように樹林帯へ。三十六童子の祠を過ぎると道はやや緩やかになり、やがて上坊コースとの分岐のツルハシ分れに着きます。ここを直進するとわずかで、7月には大コマクサ群落となる砂礫帯に出ます。このコマクサ群落はその数、株の大きさが日本一とも言われ一見の価値があります。コマクサ群落を過ぎると第1噴出口跡を経て、最後の休憩地に最適な第2噴出口跡。第2噴出口跡からは江戸時代中期に流れ出たと言われれる熔岩流が眼下に扇状になって見えます。熔岩流の端に沿って下り、やがて緩やかになると焼走り登山口に出ます。広い駐車場、トイレがあります。日帰り温泉焼走りの湯もあり、登山の疲れを癒すのも良いでしょう。名峰岩手山の表口と言える代表的なコースで、馬返し登山口(柳沢コース)には100台以上駐車可能な無料の大きな駐車場が三つ、トイレが二つ、鬼又清水という水場、キャンプ場があります。 駐車場から少し上がった広場の案内板から登山道に入ります。ミズナラなどの森に道が続き、やがて大きな一本ブナの立つ0.5合目に着きます。ここで道は二つに分かれ、どちらも一合目で合流します。左は展望のある細い道、右は森の中の広い道です。一合目広場を過ぎると展望の広がる二合目。また森に入り2.5合目。ここから新道と旧道に分かれ七合目で合流します。新道は樹林の道、旧道は展望の道です。三合目、四合目、五合目に100mほどの連絡路があり行き来できます。四合目まで新道を行き、四合目から旧道に出て花と展望を楽しみながら登るのがお勧めです。ただし、足場の悪い岩場、砂礫の崩壊地、割れた大岩などがありますので、よく周囲を観察し白いペンキ印に従い、ルートを外れないようにしましょう。特に視界不良時は要注意です。鉾立(七合目)で道は平坦になり間もなく八合目避難小屋に着きます。小屋前の広場にはベンチ、御成清水の水場、トイレがあり多くの登山者が休憩しています。 小屋から九合目不動平を経て、外輪山へ向かいます。砂礫の道になり途中二又に分かれますが、登りやすい右を行きましょう。外輪に立つと景色が一変、荒々しい火口と火口丘の向こうに山頂の薬師岳が見えます。ここは左へ時計回りに山頂薬師岳を目指します。焼走りへの分岐を直進すると間もなく山頂(薬師岳)です。岩手県最高峰からは360度のパノラマが広がっています。 下りは外輪を焼走りコースの道標まで戻り右へ折れます。砂礫帯を下るとトイレのある平笠不動避難小屋です。ここから斜面を巻くように樹林帯へ。三十六童子の祠を過ぎると道はやや緩やかになり、やがて上坊コースとの分岐のツルハシ分れに着きます。ここを直進するとわずかで、7月には大コマクサ群落となる砂礫帯に出ます。このコマクサ群落はその数、株の大きさが日本一とも言われ一見の価値があります。コマクサ群落を過ぎると第1噴出口跡を経て、最後の休憩地に最適な第2噴出口跡。第2噴出口跡からは江戸時代中期に流れ出たと言われれる熔岩流が眼下に扇状になって見えます。熔岩流の端に沿って下り、やがて緩やかになると焼走り登山口に出ます。広い駐車場、トイレがあります。日帰り温泉焼走りの湯もあり、登山の疲れを癒すのも良いでしょう。 -
網張スキー場から岩手山へ
- 1泊2日
- 9時間55分
- 16.4km
網張スキー場から岩手山へ
- 1泊2日
- 9時間55分
- 16.4km
網張温泉へはJR盛岡駅からマイカーかタクシー利用が良いでしょう。休暇村網張温泉のすぐ隣が網張スキー場リフト乗り場です。無料の広い駐車場もあります。 リフトを三基乗り継いで約40分、標高1300mの第3リフト降場から歩き始めます。階段状の道を登ると稜線に出ます。右手に網張温泉の源泉を見下ろす展望地を過ぎると間もなく三ツ石山への分岐です。ここを右へ進むとわずかでまた分岐。ここは犬倉山を巻いて左へ進みます。木道を下ると小さな広場があり、左へわずかに下ると水場、犬倉清水があります。広場からは樹林の中のなだらかに道が続き、樹林を抜けて尾根に上がると姥倉山分岐です。展望が開け、東に鬼ヶ城から岩手山へ続く稜線が見え、登山意欲がかき立てられます。左に八幡平の山々を見て、噴気の上がる黒倉山分岐は右へ巻き道を進み、黒倉山からの道と合流すると切通分岐です。ここはまっすぐ鬼ヶ城コースへ進みます。左手の枝越しに荒々しい屏風尾根を見ながら登っていくと、やがて灌木帯を抜けて鬼ヶ城に入って行きます。ダイナミックな景色が広がる、起伏と変化に富んだ岩場が続きます。アップダウンが激しく、滑落転落注意の箇所も随所にあり、通過に時間がかかりますので余裕を持って歩きましょう。やがて岩手山の山頂部が大きく迫り、右からの御神坂コースと出会い、左下に見える不動平に下ると瀟洒な造りの不動平避難小屋があります。ここに宿泊するのも良いのですが、ここでは八合目避難小屋へ。水場があり、夜は一晩中LED照明が灯ります。約100人泊まることができ、夏のシーズン中は管理人が常駐するので登山者には安心の快適な小屋です。 二日目は早朝に出発し、不動平から山頂を目指します。外輪に出たら火口へ下り、岩手山神社奥宮を通って反対側の外輪へ登り返し左へ折れて頂上へ。岩手県最高峰の頂からご来光を拝みましょう。山頂(薬師岳)を踏んだら反時計回りに不動平へ戻り、鬼ヶ城コースへ登り返して分岐から御神坂コースへ。古くはお山掛けに使われた急坂で、笠締、わらじ脱ぎ場など信仰登山の名残りを感じさせる箇所があります。標高1200m付近の大滝展望地からは、雪解けの水が流れる大滝が見られます。林道に出たら、案内看板に従うと御神坂登山口に出ます。タクシーを利用しましょう。網張温泉へはJR盛岡駅からマイカーかタクシー利用が良いでしょう。休暇村網張温泉のすぐ隣が網張スキー場リフト乗り場です。無料の広い駐車場もあります。 リフトを三基乗り継いで約40分、標高1300mの第3リフト降場から歩き始めます。階段状の道を登ると稜線に出ます。右手に網張温泉の源泉を見下ろす展望地を過ぎると間もなく三ツ石山への分岐です。ここを右へ進むとわずかでまた分岐。ここは犬倉山を巻いて左へ進みます。木道を下ると小さな広場があり、左へわずかに下ると水場、犬倉清水があります。広場からは樹林の中のなだらかに道が続き、樹林を抜けて尾根に上がると姥倉山分岐です。展望が開け、東に鬼ヶ城から岩手山へ続く稜線が見え、登山意欲がかき立てられます。左に八幡平の山々を見て、噴気の上がる黒倉山分岐は右へ巻き道を進み、黒倉山からの道と合流すると切通分岐です。ここはまっすぐ鬼ヶ城コースへ進みます。左手の枝越しに荒々しい屏風尾根を見ながら登っていくと、やがて灌木帯を抜けて鬼ヶ城に入って行きます。ダイナミックな景色が広がる、起伏と変化に富んだ岩場が続きます。アップダウンが激しく、滑落転落注意の箇所も随所にあり、通過に時間がかかりますので余裕を持って歩きましょう。やがて岩手山の山頂部が大きく迫り、右からの御神坂コースと出会い、左下に見える不動平に下ると瀟洒な造りの不動平避難小屋があります。ここに宿泊するのも良いのですが、ここでは八合目避難小屋へ。水場があり、夜は一晩中LED照明が灯ります。約100人泊まることができ、夏のシーズン中は管理人が常駐するので登山者には安心の快適な小屋です。 二日目は早朝に出発し、不動平から山頂を目指します。外輪に出たら火口へ下り、岩手山神社奥宮を通って反対側の外輪へ登り返し左へ折れて頂上へ。岩手県最高峰の頂からご来光を拝みましょう。山頂(薬師岳)を踏んだら反時計回りに不動平へ戻り、鬼ヶ城コースへ登り返して分岐から御神坂コースへ。古くはお山掛けに使われた急坂で、笠締、わらじ脱ぎ場など信仰登山の名残りを感じさせる箇所があります。標高1200m付近の大滝展望地からは、雪解けの水が流れる大滝が見られます。林道に出たら、案内看板に従うと御神坂登山口に出ます。タクシーを利用しましょう。 -
七滝登山口から岩手山へ
- 1泊2日
- 9時間50分
- 14.7km
七滝登山口から岩手山へ
- 1泊2日
- 9時間50分
- 14.7km
不動平避難小屋に一泊しゆったりと歩いてみましょう。岩手山の懐の深さが感じられる水と緑と花の道を辿ります。 県民の森の七滝登山口には駐車場があり、5台ほど駐車可能です。路線バスはありますが本数が少なく、タクシー利用が良いでしょう。登山口看板の横から登山道に入ります。ミズナラの森を道標に従い緩やかに登って行くと右手に落差20mほどの七滝があります。焼切沢には七つの滝があると言われ、一番大きなものが七滝です。道は一服峠から湯華採取跡へ、ブナからコメツガなどへ変わる美林の中に続きます。焼切沢上流を渡り返し、黒倉山が大きく迫り、視界が開けると大地獄谷で、それまでの緑豊かな森から一気に鬼ヶ城や屏風尾根の断崖に囲まれたダイナミックな景観の中に入り込みます。急で狭く滑りやすい道を硫黄臭や噴気に注意して登り、大地獄分岐を左折しお花畑へと向かいます。足場の悪い道を進み、沢へ下って登り返すとお花畑のある八ッ目湿原へ出ます。御苗代湖への分岐を直進し、岩手山へ向かって森の中へ入って行きます。段差の続く急斜面を登り切ると森を抜けて平たんになり、木のテーブルとイスが並ぶ広い不動平です。十字分岐があり左は外輪へ、正面は八合目避難小屋へ、右は鬼ヶ城へ続きます。今宵の宿の不動平避難小屋は鬼ヶ城コースへの登り口にあります。この小屋には20人ほどが宿泊でき、トイレはありますが水場はありません。20分ほど先の八合目避難小屋の御成清水で調達しましょう。晴れた夜なら不動平の木のイスに仰向けになり、満天の星空を眺めるのも良いでしょう。 二日目は小屋から十字分岐へ戻り、岩手山外輪を目指します。二又道の右を登り外輪へ出たら反時計回りにお鉢巡りをしましょう。緩やかな砂礫の外輪は最後に急になり登り切ると山頂(薬師岳)です。また反時計回りに外輪を下り、焼走りへの分岐を直進し不動平にもどります。十字分岐から左へ折れ八合目避難小屋を過ぎ、少し行くと鉾立(七合目)です。ここは旧道へは下らず、新道へ祠の左を進みます。すぐ灌木帯になり一合目までゴーロ、ザレ、段差、根張り、階段状の急な道を下って行きます。一合目で道が二又に分かれますが、どちらを選んでも一本ブナの0.5合目で合流します。0.5合目から道は緩やかになり馬返し登山口に着きます。不動平避難小屋に一泊しゆったりと歩いてみましょう。岩手山の懐の深さが感じられる水と緑と花の道を辿ります。 県民の森の七滝登山口には駐車場があり、5台ほど駐車可能です。路線バスはありますが本数が少なく、タクシー利用が良いでしょう。登山口看板の横から登山道に入ります。ミズナラの森を道標に従い緩やかに登って行くと右手に落差20mほどの七滝があります。焼切沢には七つの滝があると言われ、一番大きなものが七滝です。道は一服峠から湯華採取跡へ、ブナからコメツガなどへ変わる美林の中に続きます。焼切沢上流を渡り返し、黒倉山が大きく迫り、視界が開けると大地獄谷で、それまでの緑豊かな森から一気に鬼ヶ城や屏風尾根の断崖に囲まれたダイナミックな景観の中に入り込みます。急で狭く滑りやすい道を硫黄臭や噴気に注意して登り、大地獄分岐を左折しお花畑へと向かいます。足場の悪い道を進み、沢へ下って登り返すとお花畑のある八ッ目湿原へ出ます。御苗代湖への分岐を直進し、岩手山へ向かって森の中へ入って行きます。段差の続く急斜面を登り切ると森を抜けて平たんになり、木のテーブルとイスが並ぶ広い不動平です。十字分岐があり左は外輪へ、正面は八合目避難小屋へ、右は鬼ヶ城へ続きます。今宵の宿の不動平避難小屋は鬼ヶ城コースへの登り口にあります。この小屋には20人ほどが宿泊でき、トイレはありますが水場はありません。20分ほど先の八合目避難小屋の御成清水で調達しましょう。晴れた夜なら不動平の木のイスに仰向けになり、満天の星空を眺めるのも良いでしょう。 二日目は小屋から十字分岐へ戻り、岩手山外輪を目指します。二又道の右を登り外輪へ出たら反時計回りにお鉢巡りをしましょう。緩やかな砂礫の外輪は最後に急になり登り切ると山頂(薬師岳)です。また反時計回りに外輪を下り、焼走りへの分岐を直進し不動平にもどります。十字分岐から左へ折れ八合目避難小屋を過ぎ、少し行くと鉾立(七合目)です。ここは旧道へは下らず、新道へ祠の左を進みます。すぐ灌木帯になり一合目までゴーロ、ザレ、段差、根張り、階段状の急な道を下って行きます。一合目で道が二又に分かれますが、どちらを選んでも一本ブナの0.5合目で合流します。0.5合目から道は緩やかになり馬返し登山口に着きます。 -
安比高原スキー場から八幡平へ
- 日帰り
- 7時間0分
- 13.7km
安比高原スキー場から八幡平へ
- 日帰り
- 7時間0分
- 13.7km
安比リゾートセンターからセントラルゲレンデに出ると左手に安比ゴンドラ乗り場があります。ゴンドラ(運行期間等はお問合せください)に乗って約15分、標高1300mのゴンドラ山頂駅に着きます。散策路山頂パノラマコースの階段を登ると前森山頂上です。広い山頂には展望デッキがあり、岩手山と裏岩手連峰、これから歩く山なみが一望できます。ここから西森山、屋棟岳、大黒森、恵比須森、そして茶臼岳へとアップダウンの尾根歩きが始まります。 散策路は東へ下りゴンドラへ周回しますが、登山道は西へ下って行きます。下り切るとブナの巨木が立つ三本ぶな分岐。ここへは、ゴンドラが運行されていない日はリゾートセンターからやまばとコースを歩いて登って来ることもできます。この分岐を直進し、急な広葉樹の森を登り返すとまた分岐で、右へ折れわずかで西森山です。前森山方面に展望があります。分岐へ戻り右へ折れ、しばらく行くとまた分岐で中のまきばからの道と合流します。左へ進み、オオシラビソの中の道を小さくアップダウンしながら行きます。展望はありません。道が狭くなり灌木の中を行くと分岐になり、左へわずかで屋棟岳。北に少し展望があります。分岐へ戻って左へ進み、時おり岩手山を左に見て登り返すと大黒森です。広い道に出たら右折し、まっすぐな道を登って行くと、やがて恵比須森を経て赤川登山口からの茶臼岳コースとぶつかります。左へ折れしばらく登ると茶臼山荘に出ます。 山荘から約5分で八幡平三大展望所の一つ茶臼岳。岩手山と裏岩手連峰が一望できます。山荘に戻って左へ緩やかに下り黒谷地湿原へ。黒谷地バス停方向へ少し行くと熊ノ泉です。往復して水を補給するのも良いでしょう。掘れた道を緩やかに登って行き、安比岳コースとの分岐を直進しお花畑を巻くと道は平たんになり間もなく右に一段高く源太森です。三大展望地の一つで、オオシラビソに囲まれた湿原や八幡沼、北には八甲田連峰も見えます。登山道へ戻り、木道を進むと広々とした湿原が広がります。八幡沼周回路の分岐を右折し、湿原の中の木道をのんびり歩きましょう。やがて左に避難小屋陵雲荘を見て、道は石畳になり少し登ると展望デッキ。岩手山、オオシラビソの森、八幡沼が一望です。道標に従いガマ沼を左に見て石畳をわずかで八幡平山頂です。 蒸ノ湯への道には進まず、道標に従ってめがね沼、鏡沼を左に見て石畳を下ると八幡平アスピーテラインの岩手秋田県境、八幡平登山口です。安比リゾートセンターからセントラルゲレンデに出ると左手に安比ゴンドラ乗り場があります。ゴンドラ(運行期間等はお問合せください)に乗って約15分、標高1300mのゴンドラ山頂駅に着きます。散策路山頂パノラマコースの階段を登ると前森山頂上です。広い山頂には展望デッキがあり、岩手山と裏岩手連峰、これから歩く山なみが一望できます。ここから西森山、屋棟岳、大黒森、恵比須森、そして茶臼岳へとアップダウンの尾根歩きが始まります。 散策路は東へ下りゴンドラへ周回しますが、登山道は西へ下って行きます。下り切るとブナの巨木が立つ三本ぶな分岐。ここへは、ゴンドラが運行されていない日はリゾートセンターからやまばとコースを歩いて登って来ることもできます。この分岐を直進し、急な広葉樹の森を登り返すとまた分岐で、右へ折れわずかで西森山です。前森山方面に展望があります。分岐へ戻り右へ折れ、しばらく行くとまた分岐で中のまきばからの道と合流します。左へ進み、オオシラビソの中の道を小さくアップダウンしながら行きます。展望はありません。道が狭くなり灌木の中を行くと分岐になり、左へわずかで屋棟岳。北に少し展望があります。分岐へ戻って左へ進み、時おり岩手山を左に見て登り返すと大黒森です。広い道に出たら右折し、まっすぐな道を登って行くと、やがて恵比須森を経て赤川登山口からの茶臼岳コースとぶつかります。左へ折れしばらく登ると茶臼山荘に出ます。 山荘から約5分で八幡平三大展望所の一つ茶臼岳。岩手山と裏岩手連峰が一望できます。山荘に戻って左へ緩やかに下り黒谷地湿原へ。黒谷地バス停方向へ少し行くと熊ノ泉です。往復して水を補給するのも良いでしょう。掘れた道を緩やかに登って行き、安比岳コースとの分岐を直進しお花畑を巻くと道は平たんになり間もなく右に一段高く源太森です。三大展望地の一つで、オオシラビソに囲まれた湿原や八幡沼、北には八甲田連峰も見えます。登山道へ戻り、木道を進むと広々とした湿原が広がります。八幡沼周回路の分岐を右折し、湿原の中の木道をのんびり歩きましょう。やがて左に避難小屋陵雲荘を見て、道は石畳になり少し登ると展望デッキ。岩手山、オオシラビソの森、八幡沼が一望です。道標に従いガマ沼を左に見て石畳をわずかで八幡平山頂です。 蒸ノ湯への道には進まず、道標に従ってめがね沼、鏡沼を左に見て石畳を下ると八幡平アスピーテラインの岩手秋田県境、八幡平登山口です。 -
秋田駒ヶ岳八合目から最高峰の男女岳へ
- 日帰り
- 4時間10分
- 6.5km
秋田駒ヶ岳八合目から最高峰の男女岳へ
- 日帰り
- 4時間10分
- 6.5km
駒ヶ岳八合目まで登山シーズン中は車両規制があり、シャトルバスが運行されます。運行日、時間を確認して利用しましょう。八合目小屋のホワイトボードで花の情報などを確認し、トイレを済ませて歩き始めます。 水場の右の案内板の前が登山口です。すぐに焼森への分岐、少し登って浄土平への分岐ですがいずれも直進します。段差の続く右側が切れ落ちた細い道を、山を巻くように登ると田沢湖の見える広場、片倉岳展望台です。なおも男女岳を巻くように溶岩の露出した道を進み、木道になると阿弥陀池に出ます。左は男女岳、右は馬の背に挟まれた池で夏は木道の両側に様々な高山植物が咲き乱れます。池を回るように木道がありますが、ここは反時計回りに進みます。回り込むと木のベンチ、避難小屋、トイレがあります。 一休みしたら目の前にある本峰男女岳を目指しましょう。丸石が敷き詰められた道を行くと間もなく階段になります。段差が大きなところもありますのでゆっくり行きましょう。ひと登りで広場になった男女岳山頂です。男岳、馬の背、横岳、焼森はもちろん、岩手山や乳頭山、森吉山、田沢湖など全方位の展望が広がります。 阿弥陀池へ戻って木道を反時計回りに進み、男岳と馬の背の鞍部に登ります。ここは十字路交差点、直進して急斜面を下ればムーミン谷、左は馬の背、ここは右の男岳へ。溶岩の露出した段差の登りが続きます。左側が切れ落ちている箇所もあり、つまずき転倒注意です。高度感が増し尾根が平らになると間もなく鳥居と祠のある男岳頂上です。眼下に金十郎長嶺やムーミン谷、遠く鳥海山や岩手山、和賀山塊など眺望抜群です。 足元に注意し馬の背の鞍部に戻ります。馬の背は両側が切れ落ちた高度感のある足場の悪い狭い尾根で、大きな岩をよじ登る箇所もあり注意が必要です。道が平たんになると阿弥陀池からの道と合流し、間もなく灌木に囲まれた木のベンチがある横岳です。ここは三差路、左折して焼森へ下ります。右は国見温泉への道です。灌木を抜けると夏はコマクサの群落が現れる火山砂礫地帯に出てすぐにケルンのある焼森です。左に男女岳、左後方を振り返ると男岳や馬の背、阿弥陀池避難小屋が見上げる高さになっています。前方には笊森山や乳頭山へ続くたおやかな山なみ、そして遠く岩手山や八幡平、森吉山などを見渡す広々とした景色が広がっています。 砂礫の斜面を下ると三差路で、右は笊森山へ続く縦走路。ここは左折で八合目を目指します。焼森を少し巻くように進んで足場の悪い階段状の急な道を下り、小沢を渡って登り返します。尾根に続く灌木帯の中の狭い道を下って行くと駒ヶ岳八合目に出ます。駒ヶ岳八合目まで登山シーズン中は車両規制があり、シャトルバスが運行されます。運行日、時間を確認して利用しましょう。八合目小屋のホワイトボードで花の情報などを確認し、トイレを済ませて歩き始めます。 水場の右の案内板の前が登山口です。すぐに焼森への分岐、少し登って浄土平への分岐ですがいずれも直進します。段差の続く右側が切れ落ちた細い道を、山を巻くように登ると田沢湖の見える広場、片倉岳展望台です。なおも男女岳を巻くように溶岩の露出した道を進み、木道になると阿弥陀池に出ます。左は男女岳、右は馬の背に挟まれた池で夏は木道の両側に様々な高山植物が咲き乱れます。池を回るように木道がありますが、ここは反時計回りに進みます。回り込むと木のベンチ、避難小屋、トイレがあります。 一休みしたら目の前にある本峰男女岳を目指しましょう。丸石が敷き詰められた道を行くと間もなく階段になります。段差が大きなところもありますのでゆっくり行きましょう。ひと登りで広場になった男女岳山頂です。男岳、馬の背、横岳、焼森はもちろん、岩手山や乳頭山、森吉山、田沢湖など全方位の展望が広がります。 阿弥陀池へ戻って木道を反時計回りに進み、男岳と馬の背の鞍部に登ります。ここは十字路交差点、直進して急斜面を下ればムーミン谷、左は馬の背、ここは右の男岳へ。溶岩の露出した段差の登りが続きます。左側が切れ落ちている箇所もあり、つまずき転倒注意です。高度感が増し尾根が平らになると間もなく鳥居と祠のある男岳頂上です。眼下に金十郎長嶺やムーミン谷、遠く鳥海山や岩手山、和賀山塊など眺望抜群です。 足元に注意し馬の背の鞍部に戻ります。馬の背は両側が切れ落ちた高度感のある足場の悪い狭い尾根で、大きな岩をよじ登る箇所もあり注意が必要です。道が平たんになると阿弥陀池からの道と合流し、間もなく灌木に囲まれた木のベンチがある横岳です。ここは三差路、左折して焼森へ下ります。右は国見温泉への道です。灌木を抜けると夏はコマクサの群落が現れる火山砂礫地帯に出てすぐにケルンのある焼森です。左に男女岳、左後方を振り返ると男岳や馬の背、阿弥陀池避難小屋が見上げる高さになっています。前方には笊森山や乳頭山へ続くたおやかな山なみ、そして遠く岩手山や八幡平、森吉山などを見渡す広々とした景色が広がっています。 砂礫の斜面を下ると三差路で、右は笊森山へ続く縦走路。ここは左折で八合目を目指します。焼森を少し巻くように進んで足場の悪い階段状の急な道を下り、小沢を渡って登り返します。尾根に続く灌木帯の中の狭い道を下って行くと駒ヶ岳八合目に出ます。 -
金十郎長根を登り地熱湧く溶岩の山、女岳へ
- 日帰り
- 6時間5分
- 10.6km
金十郎長根を登り地熱湧く溶岩の山、女岳へ
- 日帰り
- 6時間5分
- 10.6km
国見温泉が登山口です。路線バスはありません。マイカーかタクシー利用となります。登山口には30台ほどの駐車場がありますが、花や紅葉の時期は休日平日問わず早朝すぐ満車になります。タクシー利用が良いでしょう。森山荘の横が登り口で、ルートや時間を記した案内看板と登山届箱があります。急な道をひと登りでブナの森に入ります。初夏はイワカガミロードとなる道を登って行くとやがて急な階段が現れ、登り切ると秋田駒大外輪山に乗り、休憩に適した横長根です。ブナの枝越しにこれから歩く金十郎長根と目指す女岳が見えます。 横長根を左折し大外輪を下って行きます。岩手秋田県境の道標を過ぎ、最低鞍部まで下り切って少し登り返すと休憩に適した御坪分岐です。ここからいよいよ金十郎長根の登りです。笹やブナの灌木帯を抜けると視界が開け、これから歩く尾根と女岳、その奥に男岳、木々で覆われた火口原とその向こうに大外輪の対岸が目に飛び込みます。振り向くと眼下に田沢湖が光り、爽快な眺めの中の急な道をさらに登って行くと、やがて休憩に適した平たんな水沢分岐です。 水沢分岐からわずかで岩が板状に切り立った五百羅漢です。道は岩壁の右側へ迂回します。崩れた岩の散らばる急斜面を慎重に下り、ロープのある草付きを登り返すとテラス状の平たん地に出ます。ここが女岳への分岐ですが道標はありません。足場の悪いザレた道を右に下って行きます。やや低いヤブになっていますが道はしっかりしています。右に溶岩流を見ながら錫杖頭の裾を巻くように登り返して行くと分岐になりますが、ここにも道標はありません。直進がムーミン谷で、ここは溶岩に付けられた白いペンキ印と踏み跡を確認して右へ進み、女岳へ取り付きます。 道は溶岩の中に続き、道標はありませんが途中で右回りと左回りに分かれます。どちらを選んでも構いませんが道を外れないこと。ひと登りで地熱が湧く女岳山頂です。展望は全方位。目の前には天を突くような男岳と横岳へ続く馬の背の稜線が迫り、眼下には馬場の小路、通称ムーミン谷が見えます。アルペンムード満点の眺めを楽しんだらムーミン谷への分岐へ戻り右折します。足場の悪い岩場を下り、馬の背への分岐を過ぎるとムーミン谷です。ムーミン谷を抜けると夏、タカネスミレやコマクサが咲き乱れる火山砂礫の大焼砂に出ます。 大焼砂分岐で横岳からの道と合流したら右折し、外輪山を下って行きます。道が平たんになると横長根で、このルートをひと回りしてきたことになります。最後の休憩を取ったら国見温泉へ下りましょう。国見温泉が登山口です。路線バスはありません。マイカーかタクシー利用となります。登山口には30台ほどの駐車場がありますが、花や紅葉の時期は休日平日問わず早朝すぐ満車になります。タクシー利用が良いでしょう。森山荘の横が登り口で、ルートや時間を記した案内看板と登山届箱があります。急な道をひと登りでブナの森に入ります。初夏はイワカガミロードとなる道を登って行くとやがて急な階段が現れ、登り切ると秋田駒大外輪山に乗り、休憩に適した横長根です。ブナの枝越しにこれから歩く金十郎長根と目指す女岳が見えます。 横長根を左折し大外輪を下って行きます。岩手秋田県境の道標を過ぎ、最低鞍部まで下り切って少し登り返すと休憩に適した御坪分岐です。ここからいよいよ金十郎長根の登りです。笹やブナの灌木帯を抜けると視界が開け、これから歩く尾根と女岳、その奥に男岳、木々で覆われた火口原とその向こうに大外輪の対岸が目に飛び込みます。振り向くと眼下に田沢湖が光り、爽快な眺めの中の急な道をさらに登って行くと、やがて休憩に適した平たんな水沢分岐です。 水沢分岐からわずかで岩が板状に切り立った五百羅漢です。道は岩壁の右側へ迂回します。崩れた岩の散らばる急斜面を慎重に下り、ロープのある草付きを登り返すとテラス状の平たん地に出ます。ここが女岳への分岐ですが道標はありません。足場の悪いザレた道を右に下って行きます。やや低いヤブになっていますが道はしっかりしています。右に溶岩流を見ながら錫杖頭の裾を巻くように登り返して行くと分岐になりますが、ここにも道標はありません。直進がムーミン谷で、ここは溶岩に付けられた白いペンキ印と踏み跡を確認して右へ進み、女岳へ取り付きます。 道は溶岩の中に続き、道標はありませんが途中で右回りと左回りに分かれます。どちらを選んでも構いませんが道を外れないこと。ひと登りで地熱が湧く女岳山頂です。展望は全方位。目の前には天を突くような男岳と横岳へ続く馬の背の稜線が迫り、眼下には馬場の小路、通称ムーミン谷が見えます。アルペンムード満点の眺めを楽しんだらムーミン谷への分岐へ戻り右折します。足場の悪い岩場を下り、馬の背への分岐を過ぎるとムーミン谷です。ムーミン谷を抜けると夏、タカネスミレやコマクサが咲き乱れる火山砂礫の大焼砂に出ます。 大焼砂分岐で横岳からの道と合流したら右折し、外輪山を下って行きます。道が平たんになると横長根で、このルートをひと回りしてきたことになります。最後の休憩を取ったら国見温泉へ下りましょう。 -
八合目から乳頭山へ
- 日帰り
- 6時間15分
- 11.9km
八合目から乳頭山へ
- 日帰り
- 6時間15分
- 11.9km
このコースは秋田駒ヶ岳山頂には登らず、秋田県側八合目から笊森山へ向かう縦走路に入り、千沼ヶ原から乳頭山へ登り返して孫六温泉に下る健脚向きです。路線バスなどのアクセスも比較的容易なことから、逆ルートで歩く人も多くいます。 八合目まで登山シーズン中は車両規制があります。麓のアルパこまくさからシャトルバスで上がりましょう。休憩所兼避難小屋、トイレのある駒ヶ岳八合目の標高は1300mです。場合によっては防風防寒対策をし、水場の左側にある千沼ヶ原への縦走路へ入ります。沢へ下って階段状の道を登り返すと、7月はニッコウキスゲが咲き乱れる笹森山斜面の花畑です。 笹森山と休暇村乳頭温泉郷への分岐を直進し、灌木帯の中を湯森山へと登ります。焼森分岐を直進して少し行くと視界が開け、広々とした緩やかな尾根の中にこれから歩く縦走路が見えます。爽快な眺めです。足場の悪い道を下ると木道の敷かれた湿地帯、お花畑の熊見平。ここから道は登りになりハイマツ帯の中に巨岩の岩宿が現れます。岩の上に立って景色を楽しむのも良いでしょう。膝まで藪になった道は緩やかに続き、砂礫の歩きやすい道になって振り返ると秋田駒がはるか遠くになっています。やがて笊森山に着き、広い山頂からは岩手山、眼下に千沼ヶ原、すぐ隣には乳頭山が見えます。 少し下った分岐で右に折れ、朽ちた木道を注意して下ると1000もの池塘が点在すると言われれる千沼ヶ原です。わずか半世紀ほど前に知られるようになり原始性が保たれていることなどから、貴重な湿原と言われています。ここは左へ折れオオシラビソの森を進みます。小さなアップダウンを繰り返し笊森山からの道と合流すると乳頭山が前方に見えてきます。ガレ場を登り滝ノ上温泉からの道と合流し、左側が切れ落ちた急斜面をひと登りで乳頭山頂上です。森吉山、裏岩手連峰、秋田駒など展望良好です。南東側は断崖で、板状節理の岩が崩壊していますので要注意です。 北西側はなだらかな斜面で、その樹林の中に小さく見える田代平山荘へ向かいます。黒湯温泉への分岐を右折しオオシラビソの中を進むと田代平山荘に着きます。木道を西へ進み、田代平湿原の中の分岐を左折して乳頭山を見納めし、樹林の中へ入って行きます。荒れた道をスリップ転倒に注意して進むと、オオシラビソからブナの森に変わります。道は緩急を繰り返して下り、小ピークを過ぎると最後の急斜面になります。沢沿いを巻いて間もなく孫六温泉(休業中、2025年は要確認)の入り口に出ます。 砂利道を右へ約10分で乳頭温泉バス停です。このコースは秋田駒ヶ岳山頂には登らず、秋田県側八合目から笊森山へ向かう縦走路に入り、千沼ヶ原から乳頭山へ登り返して孫六温泉に下る健脚向きです。路線バスなどのアクセスも比較的容易なことから、逆ルートで歩く人も多くいます。 八合目まで登山シーズン中は車両規制があります。麓のアルパこまくさからシャトルバスで上がりましょう。休憩所兼避難小屋、トイレのある駒ヶ岳八合目の標高は1300mです。場合によっては防風防寒対策をし、水場の左側にある千沼ヶ原への縦走路へ入ります。沢へ下って階段状の道を登り返すと、7月はニッコウキスゲが咲き乱れる笹森山斜面の花畑です。 笹森山と休暇村乳頭温泉郷への分岐を直進し、灌木帯の中を湯森山へと登ります。焼森分岐を直進して少し行くと視界が開け、広々とした緩やかな尾根の中にこれから歩く縦走路が見えます。爽快な眺めです。足場の悪い道を下ると木道の敷かれた湿地帯、お花畑の熊見平。ここから道は登りになりハイマツ帯の中に巨岩の岩宿が現れます。岩の上に立って景色を楽しむのも良いでしょう。膝まで藪になった道は緩やかに続き、砂礫の歩きやすい道になって振り返ると秋田駒がはるか遠くになっています。やがて笊森山に着き、広い山頂からは岩手山、眼下に千沼ヶ原、すぐ隣には乳頭山が見えます。 少し下った分岐で右に折れ、朽ちた木道を注意して下ると1000もの池塘が点在すると言われれる千沼ヶ原です。わずか半世紀ほど前に知られるようになり原始性が保たれていることなどから、貴重な湿原と言われています。ここは左へ折れオオシラビソの森を進みます。小さなアップダウンを繰り返し笊森山からの道と合流すると乳頭山が前方に見えてきます。ガレ場を登り滝ノ上温泉からの道と合流し、左側が切れ落ちた急斜面をひと登りで乳頭山頂上です。森吉山、裏岩手連峰、秋田駒など展望良好です。南東側は断崖で、板状節理の岩が崩壊していますので要注意です。 北西側はなだらかな斜面で、その樹林の中に小さく見える田代平山荘へ向かいます。黒湯温泉への分岐を右折しオオシラビソの中を進むと田代平山荘に着きます。木道を西へ進み、田代平湿原の中の分岐を左折して乳頭山を見納めし、樹林の中へ入って行きます。荒れた道をスリップ転倒に注意して進むと、オオシラビソからブナの森に変わります。道は緩急を繰り返して下り、小ピークを過ぎると最後の急斜面になります。沢沿いを巻いて間もなく孫六温泉(休業中、2025年は要確認)の入り口に出ます。 砂利道を右へ約10分で乳頭温泉バス停です。 -
畚岳から嶮岨森を踏み、大深湿原を通って松川温泉へ
- 日帰り
- 6時間35分
- 13.1km
畚岳から嶮岨森を踏み、大深湿原を通って松川温泉へ
- 日帰り
- 6時間35分
- 13.1km
八幡平アスピーテラインの岩手秋田県境から八幡平樹海ラインを約1㎞下ったところが裏岩手連峰縦走路の入口で、標高は1460mです。路線バスが走っていますが、本数が少なくタクシー利用が良いでしょう。マイカーなら縦走路入口に数台、入口から樹海ラインを約100m下がった所に10台ほどの駐車場があります。 案内図と道標がある裏岩手連峰登山口から、目の前にこれから登る畚岳、はるか南東に岩手山が見え踏破意欲がかき立てられます。はやる気持ちを抑え、緩やかな道を進むと間もなく畚岳分岐です。急な坂をひと登りで茶臼岳、源太森と並ぶ八幡平三大展望地の一つ、畚岳の頂上です。山名の由来は、山容が昔の土木作業で使われた運搬用具の畚に似ているからなのでしょうか。標高は1578m、このルートでは最も高い山です。 全方位の展望を楽しんだら分岐にもどり、右に折れてオオシラビソの森に続く道を下って行きます。徐々に登り返し平たんな諸桧岳を通ってまた下り、石沼に出ます。再び登りになって前諸桧を過ぎると左に展望が開け、岩手山や眼下のオオシラビソの森の中に鏡沼や樹海ライン、前方に嶮岨森が見える絶景が広がります。八幡平のオオシラビソの植生密度は日本一と言われています。 左側が切れ落ちたザレた足場に注意して急な段差の道を下って行くと、天を突くような鋭い峰の嶮岨森を見上げるようになります。下り切ったら急斜面をひと登りで最後のピーク、嶮岨森です。嶮岨とは切り立った、険しいという意味です。山頂は狭いですが、展望は抜群です。道はまた下って緩やかに登り返すと大深山荘に着きます。手入れの行き届いたきれいな小屋で、夏休みの期間や紅葉の時期は小屋泊の登山者でにぎわいます。小屋のすぐ先の分岐を左折すると、すぐ通称大深湿原に出ます。緩やかな斜面に木道が続き、ニッコウキスゲなどの様々な高山植物が咲くお花畑です。中でもひっそりと咲く深い紫のミヤマアケボノソウは印象的です。冷たい湧水があるので喉を潤しましょう。 大深湿原を抜けて森に入り、また別の湿原を通って緩やかに下ると分岐に出ます。右へ登ると源太ヶ岳へ。ここは左へ下って行きます。掘れて溝になったり根張りの滑りやすい急な道を行くと左手に水場があります。ブナの巨木が現れ、丸森川にかけられた橋を渡ると次第に緩やかになり、樹林越しに松川地熱発電所から上がる白煙が見え始めます。やがて発電施設の管理道に出て右折し少し行くと、八幡平樹海ラインの基点にある源太ヶ岳登山口に出ます。松川温泉峡雲荘はすぐそばです。温泉で縦走の疲れを癒すのも良いでしょう。タクシー利用になります。八幡平アスピーテラインの岩手秋田県境から八幡平樹海ラインを約1㎞下ったところが裏岩手連峰縦走路の入口で、標高は1460mです。路線バスが走っていますが、本数が少なくタクシー利用が良いでしょう。マイカーなら縦走路入口に数台、入口から樹海ラインを約100m下がった所に10台ほどの駐車場があります。 案内図と道標がある裏岩手連峰登山口から、目の前にこれから登る畚岳、はるか南東に岩手山が見え踏破意欲がかき立てられます。はやる気持ちを抑え、緩やかな道を進むと間もなく畚岳分岐です。急な坂をひと登りで茶臼岳、源太森と並ぶ八幡平三大展望地の一つ、畚岳の頂上です。山名の由来は、山容が昔の土木作業で使われた運搬用具の畚に似ているからなのでしょうか。標高は1578m、このルートでは最も高い山です。 全方位の展望を楽しんだら分岐にもどり、右に折れてオオシラビソの森に続く道を下って行きます。徐々に登り返し平たんな諸桧岳を通ってまた下り、石沼に出ます。再び登りになって前諸桧を過ぎると左に展望が開け、岩手山や眼下のオオシラビソの森の中に鏡沼や樹海ライン、前方に嶮岨森が見える絶景が広がります。八幡平のオオシラビソの植生密度は日本一と言われています。 左側が切れ落ちたザレた足場に注意して急な段差の道を下って行くと、天を突くような鋭い峰の嶮岨森を見上げるようになります。下り切ったら急斜面をひと登りで最後のピーク、嶮岨森です。嶮岨とは切り立った、険しいという意味です。山頂は狭いですが、展望は抜群です。道はまた下って緩やかに登り返すと大深山荘に着きます。手入れの行き届いたきれいな小屋で、夏休みの期間や紅葉の時期は小屋泊の登山者でにぎわいます。小屋のすぐ先の分岐を左折すると、すぐ通称大深湿原に出ます。緩やかな斜面に木道が続き、ニッコウキスゲなどの様々な高山植物が咲くお花畑です。中でもひっそりと咲く深い紫のミヤマアケボノソウは印象的です。冷たい湧水があるので喉を潤しましょう。 大深湿原を抜けて森に入り、また別の湿原を通って緩やかに下ると分岐に出ます。右へ登ると源太ヶ岳へ。ここは左へ下って行きます。掘れて溝になったり根張りの滑りやすい急な道を行くと左手に水場があります。ブナの巨木が現れ、丸森川にかけられた橋を渡ると次第に緩やかになり、樹林越しに松川地熱発電所から上がる白煙が見え始めます。やがて発電施設の管理道に出て右折し少し行くと、八幡平樹海ラインの基点にある源太ヶ岳登山口に出ます。松川温泉峡雲荘はすぐそばです。温泉で縦走の疲れを癒すのも良いでしょう。タクシー利用になります。 -
松川温泉から三ツ石山へ
- 1泊2日
- 9時間20分
- 16.5km
松川温泉から三ツ石山へ
- 1泊2日
- 9時間20分
- 16.5km
常に岩手山に見守られ、歩を進めるにつれて次々に姿を現す八幡平、森吉山、秋田駒、乳頭山、和賀山塊など北奥羽の名峰を眺めながらの、まさしく稜線漫歩が楽しめます。 松川温泉バス停の少し上、八幡平樹海ラインの基点に源太ヶ岳登山口があります。峡雲荘から少し下ったところにある、無料の広い駐車場にはトイレもあります。 道標に従って登山道に入り、丸森川を渡って急な登りを行くと右手に水場があります。大深湿原への分岐を直進すると、以前は夏になるとお花畑になる斜面でしたが、土砂崩れのため登山道が流されてしまいました。足場の悪い土砂の上に作られた応急の道をピンクテープにしたがって慎重に登って行くと源太ヶ岳に出ます。これから歩く稜線と三ツ石山、そして岩手山へ続く山なみが視界に飛び込んできます。南側が切れ落ちた崖ですので要注意。展望の良いハイマツ帯の中の道を進み、裏岩手縦走路とぶつかって左折すると灌木帯に囲まれた大深岳。八瀬森への分岐を直進し、大下りして登り返すと小畚山です。360度の爽快な眺めです。広々とした稜線の中の緩やかな道を進むとやがて三ツ石山の大岩が近づきます。裏岩手連峰の核心部三ツ石山に立つと、全方位の絶景が広がっています。 岩手山遠望の道を三ツ石湿原に下ると、今宵の宿三ツ石山荘に着きます。きちんと管理され、三ツ石山を眺めるデッキやベンチ、利用自由な暖炉もあるとても快適な避難小屋です。近くの水場は雪解け水利用のため、夏以降は枯れることがあります。ハイシーズンの土日祝日は、日帰りや宿泊の登山者で大賑わいの小屋です。 二日目は山荘から東へ向かいます。山荘を出てすぐ、松川温泉への分岐を直進し灌木帯の中を登って行きます。ひと登りで大松倉山稜線の西端に出て、右に視界が開けます。眼下に葛根田川の谷、乳頭山などが見えます。わずかで展望のない大松倉山頂上です。なだらかな稜線を時おり前方に岩手山を見ながら下って行き、オオシラビソの樹林の中を登り返して行きます。ぬかるみはありますが、地元のボランティアによって定期的に整備されています。やがて犬倉山との分岐に出たら右に折れます。リフトへの分岐を直進し、網張温泉スキー場のゲレンデ内へ入ります。急な道はリフト沿いに続き、やがて第一リフト乗り場の横に下って広い駐車場に出れば、ゴールの網張温泉に到着です。常に岩手山に見守られ、歩を進めるにつれて次々に姿を現す八幡平、森吉山、秋田駒、乳頭山、和賀山塊など北奥羽の名峰を眺めながらの、まさしく稜線漫歩が楽しめます。 松川温泉バス停の少し上、八幡平樹海ラインの基点に源太ヶ岳登山口があります。峡雲荘から少し下ったところにある、無料の広い駐車場にはトイレもあります。 道標に従って登山道に入り、丸森川を渡って急な登りを行くと右手に水場があります。大深湿原への分岐を直進すると、以前は夏になるとお花畑になる斜面でしたが、土砂崩れのため登山道が流されてしまいました。足場の悪い土砂の上に作られた応急の道をピンクテープにしたがって慎重に登って行くと源太ヶ岳に出ます。これから歩く稜線と三ツ石山、そして岩手山へ続く山なみが視界に飛び込んできます。南側が切れ落ちた崖ですので要注意。展望の良いハイマツ帯の中の道を進み、裏岩手縦走路とぶつかって左折すると灌木帯に囲まれた大深岳。八瀬森への分岐を直進し、大下りして登り返すと小畚山です。360度の爽快な眺めです。広々とした稜線の中の緩やかな道を進むとやがて三ツ石山の大岩が近づきます。裏岩手連峰の核心部三ツ石山に立つと、全方位の絶景が広がっています。 岩手山遠望の道を三ツ石湿原に下ると、今宵の宿三ツ石山荘に着きます。きちんと管理され、三ツ石山を眺めるデッキやベンチ、利用自由な暖炉もあるとても快適な避難小屋です。近くの水場は雪解け水利用のため、夏以降は枯れることがあります。ハイシーズンの土日祝日は、日帰りや宿泊の登山者で大賑わいの小屋です。 二日目は山荘から東へ向かいます。山荘を出てすぐ、松川温泉への分岐を直進し灌木帯の中を登って行きます。ひと登りで大松倉山稜線の西端に出て、右に視界が開けます。眼下に葛根田川の谷、乳頭山などが見えます。わずかで展望のない大松倉山頂上です。なだらかな稜線を時おり前方に岩手山を見ながら下って行き、オオシラビソの樹林の中を登り返して行きます。ぬかるみはありますが、地元のボランティアによって定期的に整備されています。やがて犬倉山との分岐に出たら右に折れます。リフトへの分岐を直進し、網張温泉スキー場のゲレンデ内へ入ります。急な道はリフト沿いに続き、やがて第一リフト乗り場の横に下って広い駐車場に出れば、ゴールの網張温泉に到着です。 -
一本杉登山口から姫神山へ
- 日帰り
- 3時間15分
- 5.6km
一本杉登山口から姫神山へ
- 日帰り
- 3時間15分
- 5.6km
北上川を挟んで岩手山の東方に美しい三角の形で静かに佇んでいるのが姫神山。どこから見てもそのピラミダルな山容は女性らしく秀麗で、昔話で岩手山が愛したこともうなずけます。登ってみると急な坂道が続く侮れない山ですが、四季を通して登山者が訪れ、冬でも多くの人がスノーハイクを楽しむ人気の山です。 一本杉コースが定番のコースで、地元ではマイカーを一本杉登山口駐車場に置き、山頂を往復する日帰り登山が楽しまれています。ここではその一本杉登山口から登り、こわ坂コースを下って一本杉登山口に戻る周回コースを紹介します。 好摩駅か渋民駅からタクシーで約20〜30分、一本杉登山口に着きます。姫神山登山コース案内図の看板とトイレの間から野芝の緩い斜面を登ります。振り返ると岩手山と安比高原へ続く山なみが見えます。樹林帯に入りスギの展示林を右手に見ながら進むと右側に樹齢250年とも言われるに大きな杉が立っています。湧水もありますが、飲用には適していません。少し行くとざんげ坂となり、急な階段状の登りになります。階段が終わると五合目の広場に着きます。 ここからやや傾斜は緩みますが六合目、七合目の道標とともに徐々に急になっていきます。八合目は平らで大岩と「下ルニハ右へ」と刻まれた古い石柱のある休憩ポイント。また道は急になり、山頂まで500m、300mの看板を過ぎダケカンバの樹林帯を抜けて岩場に出ると一気に展望が開けます。土場コース、岩場コースの分岐を直進し岩場コースへ。累々と重なる花崗岩の大岩を乗り越え、城内コース分岐を直進すると思いのほか広い姫神山山頂です。江戸時代、岩手山、早池峰山とともに「南部三霊山」と呼ばれた姫神山の頂上からは、その岩手山、早池峰山が望め、360度の展望が広がります。 下山は北へ、こわ坂コースを下ります。急な滑りやすい道には要所にロープや階段が整備されています。ブナ、ミズナラなどの森の中を下り「山頂まで980m」の看板を過ぎると徐々に傾斜が緩みます。カラマツの林から伐採地に出ると間もなくこわ坂登山口に出ます。ここから舗装された車道を歩き、一本杉登山口へ戻ります。登山口駐車場からは好摩駅、または渋民駅へタクシーを利用します。北上川を挟んで岩手山の東方に美しい三角の形で静かに佇んでいるのが姫神山。どこから見てもそのピラミダルな山容は女性らしく秀麗で、昔話で岩手山が愛したこともうなずけます。登ってみると急な坂道が続く侮れない山ですが、四季を通して登山者が訪れ、冬でも多くの人がスノーハイクを楽しむ人気の山です。 一本杉コースが定番のコースで、地元ではマイカーを一本杉登山口駐車場に置き、山頂を往復する日帰り登山が楽しまれています。ここではその一本杉登山口から登り、こわ坂コースを下って一本杉登山口に戻る周回コースを紹介します。 好摩駅か渋民駅からタクシーで約20〜30分、一本杉登山口に着きます。姫神山登山コース案内図の看板とトイレの間から野芝の緩い斜面を登ります。振り返ると岩手山と安比高原へ続く山なみが見えます。樹林帯に入りスギの展示林を右手に見ながら進むと右側に樹齢250年とも言われるに大きな杉が立っています。湧水もありますが、飲用には適していません。少し行くとざんげ坂となり、急な階段状の登りになります。階段が終わると五合目の広場に着きます。 ここからやや傾斜は緩みますが六合目、七合目の道標とともに徐々に急になっていきます。八合目は平らで大岩と「下ルニハ右へ」と刻まれた古い石柱のある休憩ポイント。また道は急になり、山頂まで500m、300mの看板を過ぎダケカンバの樹林帯を抜けて岩場に出ると一気に展望が開けます。土場コース、岩場コースの分岐を直進し岩場コースへ。累々と重なる花崗岩の大岩を乗り越え、城内コース分岐を直進すると思いのほか広い姫神山山頂です。江戸時代、岩手山、早池峰山とともに「南部三霊山」と呼ばれた姫神山の頂上からは、その岩手山、早池峰山が望め、360度の展望が広がります。 下山は北へ、こわ坂コースを下ります。急な滑りやすい道には要所にロープや階段が整備されています。ブナ、ミズナラなどの森の中を下り「山頂まで980m」の看板を過ぎると徐々に傾斜が緩みます。カラマツの林から伐採地に出ると間もなくこわ坂登山口に出ます。ここから舗装された車道を歩き、一本杉登山口へ戻ります。登山口駐車場からは好摩駅、または渋民駅へタクシーを利用します。