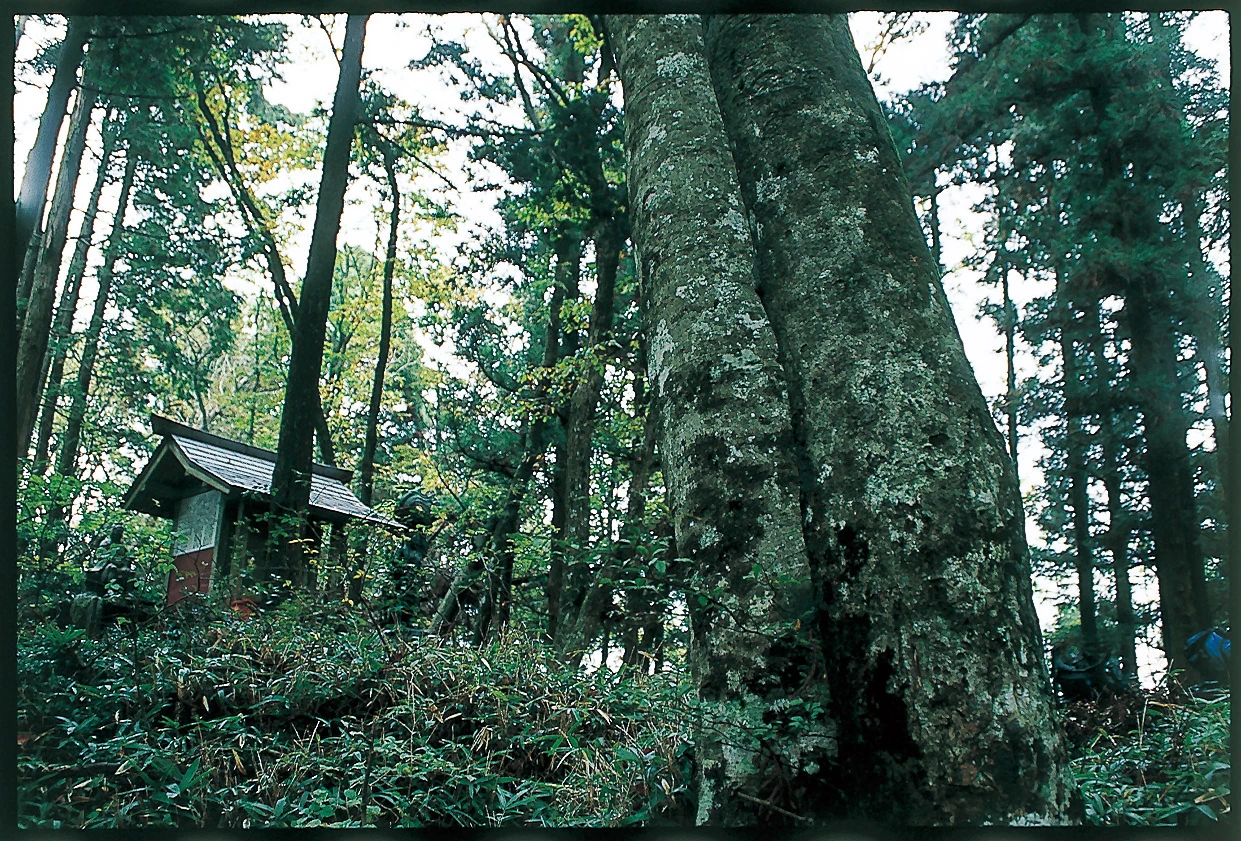【中級者向け】の登山コースガイド
中級者向け
検索結果603件中
121-140件
-
表参道〜綿向山〜竜王山
- 5時間10分
表参道〜綿向山〜竜王山
- 5時間10分
西南側の北畑や熊野から綿向山、竜王山へと続くいくつかの登山コースがあります。メインコースは表参道で、ほかに水無尾根、文三ハゲコース、竜王山からの縦走コースなどがあります。綿向山表参道コースはよく踏まれた植林帯の中の歩きやすい道で、上部の行者コバ周辺にはブナ林も残されています。頂上には馬見岡綿向神社の奥宮があり、抜群の眺望が広がっています。 車の場合は西明寺口から少し進んだところに駐車場があり、さらに林道終点まで歩くと登山口のヒミズ谷出合小屋があります。右に杉林を登るのが水無尾根道で、表参道はヒミズ谷を鉄製の橋で渡り、植林帯の中をジグザグに登っていきます。斜面を何度も折り返す単調な道を30分ほど登ると山腹を横切る林道に出ます。林道を右に進むと再び登山道が続いています。 少し登ったところに小屋があり、ジグザグの登りを繰り返します。五合目まで登ると広い範囲が伐採され、明るい斜面が広がっています。ここにも小屋があり、林道から来る別の登山道が合流しています。五合目を過ぎると左山の山腹道となり、自然林も混じるようになって、ようやく植林帯を抜けて彩り豊かな道となります。七合目の行者コバまで来ると大きなブナが現れ、原生の森の香りがわずかに残された美しい自然林の中に入ります。ここには祠があり、その両側に役行者像と不動明王像が祀られています。 行者コバでいったん尾根の上に出て、再び山腹を縫う道が続いていきます。この山頂直下一帯はブナが一部分に残されているだけで、鈴鹿特有の雑木林に包まれています。水無尾根道と合流してすぐ右に道があり、少し下ったところに金明水が湧き出ています。 金明水を過ぎると道は切り返すようになり、ササが出てきます。もう頂上は近いです。最後は急なコンクリートの階段で、見上げると鳥居が見えます。これをくぐると綿向馬見岡神社奥宮の大嶽神社が鎮座する頂上に着きます。頂上にはコンクリートで固めた大きなケルンがあり、南北に長くササが刈り開かれています。頂上からの展望は素晴らしく、とくに北西側が開けて鈴鹿中西部の大パノラマが広がっています。 綿向山から稜線を北に向かうとすぐ右に雨乞岳への分岐があります。ここを真っ直ぐに急な下りの道を進みます。この下りはいったん少し緩やかになりますが、もう一度急降下の下りとなります。岩混じりのところにはシャクナゲが多く、春は美しい道となります。 下りきったコルからは歩く人が少ないのか、少し道が荒れてきます。登りが続く道は北から西へと振り、左正面に綿向山の巨体を見上げるようになります。アップダウンを繰り返し、鉄塔のあるピークから樹林の中を進むと竜王山に着きます。頂上には石仏のような石が祀られています。 階段状の道から何度もジグザグを切って下ると林道に出て、右に進むと西明寺の分岐があり、左に取ります。すぐに人家があり棚田の間の道を下っていくと西明寺口に着きます。車の場合はここで道を左に取り駐車場に戻ります。西南側の北畑や熊野から綿向山、竜王山へと続くいくつかの登山コースがあります。メインコースは表参道で、ほかに水無尾根、文三ハゲコース、竜王山からの縦走コースなどがあります。綿向山表参道コースはよく踏まれた植林帯の中の歩きやすい道で、上部の行者コバ周辺にはブナ林も残されています。頂上には馬見岡綿向神社の奥宮があり、抜群の眺望が広がっています。 車の場合は西明寺口から少し進んだところに駐車場があり、さらに林道終点まで歩くと登山口のヒミズ谷出合小屋があります。右に杉林を登るのが水無尾根道で、表参道はヒミズ谷を鉄製の橋で渡り、植林帯の中をジグザグに登っていきます。斜面を何度も折り返す単調な道を30分ほど登ると山腹を横切る林道に出ます。林道を右に進むと再び登山道が続いています。 少し登ったところに小屋があり、ジグザグの登りを繰り返します。五合目まで登ると広い範囲が伐採され、明るい斜面が広がっています。ここにも小屋があり、林道から来る別の登山道が合流しています。五合目を過ぎると左山の山腹道となり、自然林も混じるようになって、ようやく植林帯を抜けて彩り豊かな道となります。七合目の行者コバまで来ると大きなブナが現れ、原生の森の香りがわずかに残された美しい自然林の中に入ります。ここには祠があり、その両側に役行者像と不動明王像が祀られています。 行者コバでいったん尾根の上に出て、再び山腹を縫う道が続いていきます。この山頂直下一帯はブナが一部分に残されているだけで、鈴鹿特有の雑木林に包まれています。水無尾根道と合流してすぐ右に道があり、少し下ったところに金明水が湧き出ています。 金明水を過ぎると道は切り返すようになり、ササが出てきます。もう頂上は近いです。最後は急なコンクリートの階段で、見上げると鳥居が見えます。これをくぐると綿向馬見岡神社奥宮の大嶽神社が鎮座する頂上に着きます。頂上にはコンクリートで固めた大きなケルンがあり、南北に長くササが刈り開かれています。頂上からの展望は素晴らしく、とくに北西側が開けて鈴鹿中西部の大パノラマが広がっています。 綿向山から稜線を北に向かうとすぐ右に雨乞岳への分岐があります。ここを真っ直ぐに急な下りの道を進みます。この下りはいったん少し緩やかになりますが、もう一度急降下の下りとなります。岩混じりのところにはシャクナゲが多く、春は美しい道となります。 下りきったコルからは歩く人が少ないのか、少し道が荒れてきます。登りが続く道は北から西へと振り、左正面に綿向山の巨体を見上げるようになります。アップダウンを繰り返し、鉄塔のあるピークから樹林の中を進むと竜王山に着きます。頂上には石仏のような石が祀られています。 階段状の道から何度もジグザグを切って下ると林道に出て、右に進むと西明寺の分岐があり、左に取ります。すぐに人家があり棚田の間の道を下っていくと西明寺口に着きます。車の場合はここで道を左に取り駐車場に戻ります。 -
仙ヶ谷道〜仙鶏尾根〜仙ヶ岳
- 5時間0分
仙ヶ谷道〜仙鶏尾根〜仙ヶ岳
- 5時間0分
仙ヶ岳へは石水渓の南尾根、白谷道、小岐須渓谷の仙ヶ谷道があり、どのコースも変化のある山歩きが楽しめます。石水渓、小岐須渓谷のどちらを起点としても多様なコースがあり、仙ヶ岳に隣接する野登山や宮指路岳と組み合わせるとさらに多くのコースが考えられますが、距離が長くハードになります。また、頂上から県境尾根を南下すると御所平があり、ササやススキのゆったりと傾いた広い台地状の変わった地形が開けていますが、踏み跡があまりしっかりとしていないため、経験者向きのコースとなっています。 どこから取り付いても登りごたえのあるコースに囲まれ、美しい山容を持つこの山は、1000m級の山に匹敵する魅力があります。ここでは小岐須渓谷からのコースをとります。車の場合は、小岐須渓谷の石大神展望台駐車場に置くか、林道を歩いた大石橋の少し先にもスペースがあります。石大神展望台駐車場から林道を1時間ほど歩くと堰堤があり、林道終点となります。 登山道に入ると左からの支流を横切り、流れを左岸に渡ります。仙ヶ谷はナメ滝が連なり、美しい流れを見せています。谷の山腹道を登っていくと、左に流れを渡って仙鶏尾根に取り付く道があるので、この道に入ります。ここは植林帯の中の少しわかりにくい分岐ですが、道標があり、流れを渡るところはナメ滝となっています。 道は小さな尾根に付いており、急な斜面を登ると小さなコルに出て、左の谷側が開けます。ここから尾根の左側の山腹に道が続いています。しばらく細い山腹道をたどっていくと、次第に左に谷が近づいてきます。ところどころで崖崩れや支流を渡る部分で道が抜けているところがあり、トラロープが張られています。下の谷にはナメ滝が続く流れが見えています。 山腹をたどってきた道はいったん流れに下り、また山腹道に戻ってから再び流れを渡ると、急斜面の山腹を登るようになります。少しの登りで仙鶏尾根上のコルに着きます。 ここは仙ヶ岳への急登にかかる基部となるところで、岩やガレの急な登りが仙ヶ岳東峰まで続いています。仙鶏尾根を少し登ると背後に野登山が大きく、右にずんぐりとした入道ヶ岳が見え、鈴鹿中部の山々の展望が開けてきます。急登を登りきったところに右側が開けた展望台があり、北から西側の眺望が広がっています。特に鎌ヶ岳の尖峰が印象的です。ここからはもう仙ヶ岳の頂上も近いです。 最初に出合うピークが仙ヶ岳東峰で、ここには面白い形の仙の石があります。前面が大きく開けた好展望の岩場で、うってつけの休み場となっています。ここからいったん少し下って登り返したところが仙ヶ岳頂上で、眺望はありますが、小さく刈り払われた狭い頂上です。 北へ小社峠(大峠)へは植林の急斜面となっています。滑りやすい道に注意して下ると滋賀県側の雑木林のT字路となった小社峠に着き、右へ仙ヶ谷への道を下ります。道はしっかりしていますが、流れを渡るところでは見失いやすいです。しかし踏み跡を確かめながら下れば間違うことはなく、仙鶏尾根分岐を過ぎて元の林道終点に出て、林道を下ります。仙ヶ岳へは石水渓の南尾根、白谷道、小岐須渓谷の仙ヶ谷道があり、どのコースも変化のある山歩きが楽しめます。石水渓、小岐須渓谷のどちらを起点としても多様なコースがあり、仙ヶ岳に隣接する野登山や宮指路岳と組み合わせるとさらに多くのコースが考えられますが、距離が長くハードになります。また、頂上から県境尾根を南下すると御所平があり、ササやススキのゆったりと傾いた広い台地状の変わった地形が開けていますが、踏み跡があまりしっかりとしていないため、経験者向きのコースとなっています。 どこから取り付いても登りごたえのあるコースに囲まれ、美しい山容を持つこの山は、1000m級の山に匹敵する魅力があります。ここでは小岐須渓谷からのコースをとります。車の場合は、小岐須渓谷の石大神展望台駐車場に置くか、林道を歩いた大石橋の少し先にもスペースがあります。石大神展望台駐車場から林道を1時間ほど歩くと堰堤があり、林道終点となります。 登山道に入ると左からの支流を横切り、流れを左岸に渡ります。仙ヶ谷はナメ滝が連なり、美しい流れを見せています。谷の山腹道を登っていくと、左に流れを渡って仙鶏尾根に取り付く道があるので、この道に入ります。ここは植林帯の中の少しわかりにくい分岐ですが、道標があり、流れを渡るところはナメ滝となっています。 道は小さな尾根に付いており、急な斜面を登ると小さなコルに出て、左の谷側が開けます。ここから尾根の左側の山腹に道が続いています。しばらく細い山腹道をたどっていくと、次第に左に谷が近づいてきます。ところどころで崖崩れや支流を渡る部分で道が抜けているところがあり、トラロープが張られています。下の谷にはナメ滝が続く流れが見えています。 山腹をたどってきた道はいったん流れに下り、また山腹道に戻ってから再び流れを渡ると、急斜面の山腹を登るようになります。少しの登りで仙鶏尾根上のコルに着きます。 ここは仙ヶ岳への急登にかかる基部となるところで、岩やガレの急な登りが仙ヶ岳東峰まで続いています。仙鶏尾根を少し登ると背後に野登山が大きく、右にずんぐりとした入道ヶ岳が見え、鈴鹿中部の山々の展望が開けてきます。急登を登りきったところに右側が開けた展望台があり、北から西側の眺望が広がっています。特に鎌ヶ岳の尖峰が印象的です。ここからはもう仙ヶ岳の頂上も近いです。 最初に出合うピークが仙ヶ岳東峰で、ここには面白い形の仙の石があります。前面が大きく開けた好展望の岩場で、うってつけの休み場となっています。ここからいったん少し下って登り返したところが仙ヶ岳頂上で、眺望はありますが、小さく刈り払われた狭い頂上です。 北へ小社峠(大峠)へは植林の急斜面となっています。滑りやすい道に注意して下ると滋賀県側の雑木林のT字路となった小社峠に着き、右へ仙ヶ谷への道を下ります。道はしっかりしていますが、流れを渡るところでは見失いやすいです。しかし踏み跡を確かめながら下れば間違うことはなく、仙鶏尾根分岐を過ぎて元の林道終点に出て、林道を下ります。 -
油日岳・那須ヶ原山・高畑山縦走
- 5時間40分
油日岳・那須ヶ原山・高畑山縦走
- 5時間40分
この三山は小さいながらも、均整のとれた美しい山容を見せています。いずれの山もそれぞれに登山道がありますが、三山縦走も楽しいコースとなります。少しハードですが、那須ヶ原山や坂下峠でエスケープすることもできるので、体力や時間の調整も可能です。ただし縦走はJR、バス、マイカーのいずれの場合でも問題が多いため、事前の確認が必要です。 JR利用での登山の場合、油日駅から登山口まで徒歩ではかなりの距離がありますので、油日駅から登山口まではタクシーで入ることをおすすめします。 登山口には参籠所があり、この少し先で林道が終わります。谷に沿った道がしばらく続くと、右の小さな谷に入り、やがて道は斜面を登っていきます。かなりの急登が稜線に出るまで続いていますが、登山口から登り始めてからわずか30分ほどの辛抱です。右に稜線を5分ほど進むと、油日神社奥宮の祠のある頂上に着きます。北側にも参籠所があり、休憩できます。ここからは西側の丘と平野が入り組む甲賀の里の眺望が開けています。 登ってきたコルの分岐に戻り稜線を進みます。稜線は常緑の樹林帯で、風化した花崗岩のやせた尾根が続いています。道は急な登下降の小さなアップダウンが多いので、一定のペースを守って歩くことが重要なポイントとなります。また、 三国山までの小さなピークでは道が分かれており、枝道に入り込まないように注意が必要です。 三国山を過ぎたところで切れ込んだ岩場があり、ここでは右側を巻いて通過します。このアップダウンが連続する尾根も那須ヶ原山に近づくにつれて幾分穏やかになりますが、那須ヶ原山の山容にもそれが表れており、見上げながら近づくその姿はどっしりとして美しいです。 那須ヶ原山の頂上手前で縦走する県境尾根は右に振っています。この分岐から少し先が那須ヶ原山の頂上となります。頂上には石室があり、南側の眺望が開けています。 分岐に戻り三頭山まではゆったりとした道ですが、ここを過ぎると再びアップダウンが激しくなります。そして唐木岳のピークを過ぎたところでキレットがあり、右側を下りながら大きく巻いていきます。もう坂下峠も近く急な下りとなって峠に下り立ちます。峠は車道が越えていますが、峠付近が崩壊しており、車は通過できません。 ここで余裕があればさらに縦走を続けましょう。峠からはいきなりの急登で、途中ガレ場の右を巻く道を通って溝干山に着きます。ここからは登下降があるものの、もう強い登りはなく高畑山の頂上に出ます。頂上は抜群の展望で、長い縦走を終えた最後の峰らしく、実に気分の良い広やかな頂上です。高畑山は双耳峰で、この頂上は南峰にあたります。 鈴鹿峠まで下る間にもアップダウンがあり、キレットも一箇所あります。しかしトラロープがフィックスされており、そんなに危険な箇所ではありません。 最後の下りが続くようになると、次第に国道の車の音が高く響いてきます。ゆるやかな植林帯に入り右に鏡岩の分岐を過ぎると、茶畑が広がって鈴鹿峠に着きます。鈴鹿峠にはバスは運行されていないので、事前にタクシーに連絡しておくことをおすすめします。この三山は小さいながらも、均整のとれた美しい山容を見せています。いずれの山もそれぞれに登山道がありますが、三山縦走も楽しいコースとなります。少しハードですが、那須ヶ原山や坂下峠でエスケープすることもできるので、体力や時間の調整も可能です。ただし縦走はJR、バス、マイカーのいずれの場合でも問題が多いため、事前の確認が必要です。 JR利用での登山の場合、油日駅から登山口まで徒歩ではかなりの距離がありますので、油日駅から登山口まではタクシーで入ることをおすすめします。 登山口には参籠所があり、この少し先で林道が終わります。谷に沿った道がしばらく続くと、右の小さな谷に入り、やがて道は斜面を登っていきます。かなりの急登が稜線に出るまで続いていますが、登山口から登り始めてからわずか30分ほどの辛抱です。右に稜線を5分ほど進むと、油日神社奥宮の祠のある頂上に着きます。北側にも参籠所があり、休憩できます。ここからは西側の丘と平野が入り組む甲賀の里の眺望が開けています。 登ってきたコルの分岐に戻り稜線を進みます。稜線は常緑の樹林帯で、風化した花崗岩のやせた尾根が続いています。道は急な登下降の小さなアップダウンが多いので、一定のペースを守って歩くことが重要なポイントとなります。また、 三国山までの小さなピークでは道が分かれており、枝道に入り込まないように注意が必要です。 三国山を過ぎたところで切れ込んだ岩場があり、ここでは右側を巻いて通過します。このアップダウンが連続する尾根も那須ヶ原山に近づくにつれて幾分穏やかになりますが、那須ヶ原山の山容にもそれが表れており、見上げながら近づくその姿はどっしりとして美しいです。 那須ヶ原山の頂上手前で縦走する県境尾根は右に振っています。この分岐から少し先が那須ヶ原山の頂上となります。頂上には石室があり、南側の眺望が開けています。 分岐に戻り三頭山まではゆったりとした道ですが、ここを過ぎると再びアップダウンが激しくなります。そして唐木岳のピークを過ぎたところでキレットがあり、右側を下りながら大きく巻いていきます。もう坂下峠も近く急な下りとなって峠に下り立ちます。峠は車道が越えていますが、峠付近が崩壊しており、車は通過できません。 ここで余裕があればさらに縦走を続けましょう。峠からはいきなりの急登で、途中ガレ場の右を巻く道を通って溝干山に着きます。ここからは登下降があるものの、もう強い登りはなく高畑山の頂上に出ます。頂上は抜群の展望で、長い縦走を終えた最後の峰らしく、実に気分の良い広やかな頂上です。高畑山は双耳峰で、この頂上は南峰にあたります。 鈴鹿峠まで下る間にもアップダウンがあり、キレットも一箇所あります。しかしトラロープがフィックスされており、そんなに危険な箇所ではありません。 最後の下りが続くようになると、次第に国道の車の音が高く響いてきます。ゆるやかな植林帯に入り右に鏡岩の分岐を過ぎると、茶畑が広がって鈴鹿峠に着きます。鈴鹿峠にはバスは運行されていないので、事前にタクシーに連絡しておくことをおすすめします。 -
養老山・笙ヶ岳
- 6時間15分
養老山・笙ヶ岳
- 6時間15分
草原状の養老山と樹林の深い笙ヶ岳は対照的な山で、養老山系の主峰である養老山と最高峰の笙ヶ岳を一日で楽しむことができます。登山道はよく整備された歩きやすい道が続いていますが、大洞谷から笙ヶ岳への間は道があまりよくないので注意が必要です。笙ヶ岳まで歩くとかなりハードなコースとなるため、時間や体力に合わせてコースを短縮できるようになっています。 一番短いコースは養老山の往復で、次に段階的に、もみじ峠手前の旧牧場跡のあせび平まで、さらに足を延ばせば笙ヶ岳まで行けるという3段階に分けられます。また、逆コースをとって笙ヶ岳だけを目指すこともできるため、体力や経験に応じて歩くことができるコースとなっています。 公共交通機関を利用する場合は、養老鉄道の養老駅から歩きますが、登山口の養老ノ滝まではかなり距離があるため、養老山のみの往復コースとなることが多いです。 登山口は養老ノ滝の上にある駐車場から上る林道で、駐車場の横から林道に入り、すぐ左に谷に下りる道に入ります。ここは養老ノ滝の上で堰堤があり、流れを渡ったところから登山道が始まります。 最初は急な雑木林の斜面をジグザグに登る道で、よく整備されており、何度もターンを繰り返してベンチが2基ある明瞭な尾根に出ます。丸太の階段状の歩きやすい尾根道を進み、やがてもう一度大きな尾根に出ます。ここが三方山手前の分岐で、左に1分ほど進むと濃尾平野の眺望が大きく広がる三方山に着きます。素晴らしい展望が楽しめます。分岐に戻り10分ほど登ると、養老山脈主稜の笹原峠に出ます。峠はササが刈り開かれていますが、周囲は灌木に囲まれています。 左へ養老山への道を少し登ると、左に濃尾平野の眺望が開け、樹林の背も低くなって明るい草原状の稜線になります。道を登りきったところが小倉山で、山頂には東屋やベンチがあり、公園のように整備されています。山頂からの眺望は素晴らしく、眼前にはこれから登る三角の端正な姿の笙ヶ岳が見えます。 小倉山から小さなアップダウンを越え、右から上ってきている林道と出合うとすぐ、登山道が右に分かれており、これを登ると養老山の頂上に着きます。頂上は刈り開かれていますが、眺望はあまり良くありません。 笹原峠に戻り、主稜線を直進します。稜線の道はアップダウンが多い暗い雑木林の道で、何度も上下を繰り返してあせび平に出て、さらに下ってもみじ峠に着きます。時間や体力の余裕がなければ、あせび平から右に林道を下ることもできます。 笙ヶ岳へは峠から大洞谷登山道を下ります。鬱蒼とした樹林の道で、右から流れる大きな支流と出合ったところで右に分かれる道があり、右に入ります。流れを渡り斜面の山腹道を通って最後に浅い谷を詰め上がると笙ヶ岳の東のコルに出ますが、分岐からの道はあまり良くありません。植林された北側が開けた稜線を登ると笙ヶ岳に着きます。頂上は植林が伸びてきており、眺望は次第にきかなくなってきています。 下山はあせび平から長い林道を歩いて登山口に戻ります。草原状の養老山と樹林の深い笙ヶ岳は対照的な山で、養老山系の主峰である養老山と最高峰の笙ヶ岳を一日で楽しむことができます。登山道はよく整備された歩きやすい道が続いていますが、大洞谷から笙ヶ岳への間は道があまりよくないので注意が必要です。笙ヶ岳まで歩くとかなりハードなコースとなるため、時間や体力に合わせてコースを短縮できるようになっています。 一番短いコースは養老山の往復で、次に段階的に、もみじ峠手前の旧牧場跡のあせび平まで、さらに足を延ばせば笙ヶ岳まで行けるという3段階に分けられます。また、逆コースをとって笙ヶ岳だけを目指すこともできるため、体力や経験に応じて歩くことができるコースとなっています。 公共交通機関を利用する場合は、養老鉄道の養老駅から歩きますが、登山口の養老ノ滝まではかなり距離があるため、養老山のみの往復コースとなることが多いです。 登山口は養老ノ滝の上にある駐車場から上る林道で、駐車場の横から林道に入り、すぐ左に谷に下りる道に入ります。ここは養老ノ滝の上で堰堤があり、流れを渡ったところから登山道が始まります。 最初は急な雑木林の斜面をジグザグに登る道で、よく整備されており、何度もターンを繰り返してベンチが2基ある明瞭な尾根に出ます。丸太の階段状の歩きやすい尾根道を進み、やがてもう一度大きな尾根に出ます。ここが三方山手前の分岐で、左に1分ほど進むと濃尾平野の眺望が大きく広がる三方山に着きます。素晴らしい展望が楽しめます。分岐に戻り10分ほど登ると、養老山脈主稜の笹原峠に出ます。峠はササが刈り開かれていますが、周囲は灌木に囲まれています。 左へ養老山への道を少し登ると、左に濃尾平野の眺望が開け、樹林の背も低くなって明るい草原状の稜線になります。道を登りきったところが小倉山で、山頂には東屋やベンチがあり、公園のように整備されています。山頂からの眺望は素晴らしく、眼前にはこれから登る三角の端正な姿の笙ヶ岳が見えます。 小倉山から小さなアップダウンを越え、右から上ってきている林道と出合うとすぐ、登山道が右に分かれており、これを登ると養老山の頂上に着きます。頂上は刈り開かれていますが、眺望はあまり良くありません。 笹原峠に戻り、主稜線を直進します。稜線の道はアップダウンが多い暗い雑木林の道で、何度も上下を繰り返してあせび平に出て、さらに下ってもみじ峠に着きます。時間や体力の余裕がなければ、あせび平から右に林道を下ることもできます。 笙ヶ岳へは峠から大洞谷登山道を下ります。鬱蒼とした樹林の道で、右から流れる大きな支流と出合ったところで右に分かれる道があり、右に入ります。流れを渡り斜面の山腹道を通って最後に浅い谷を詰め上がると笙ヶ岳の東のコルに出ますが、分岐からの道はあまり良くありません。植林された北側が開けた稜線を登ると笙ヶ岳に着きます。頂上は植林が伸びてきており、眺望は次第にきかなくなってきています。 下山はあせび平から長い林道を歩いて登山口に戻ります。 -
千蛇谷コースから新山へ
- 1泊2日
- 10時間40分
- 15.4km
千蛇谷コースから新山へ
- 1泊2日
- 10時間40分
- 15.4km
路肩部分に駐車帯がある大平登山口から伝石坂に入っていきます。登山口右手に登山届提出用のボックスがあります。コンクリートの階段で始まり、いきなりの急坂で戸惑うかもしれませんが、ここは鳥海屈指の急坂、ゆっくりと自分のリズムで歩きましょう。周囲はブナ林の森林限界にあたり、しばらくは森の中を歩きます。二ノ宿でいったん呼吸を整えてから見晴台を目指します。見晴台では休憩を取りながら、眼下に広がる風景を楽しみましょう。 森林限界を抜けると、傾斜が緩やかな雪田植物帯の山道となり、高山の花たちが見られるようになります。清水大神の湿原に出てひと息入れ、とよで一休み。チングルマの咲く山道を登り詰めると河原宿に出ます。雪渓を横断し愛宕坂手前の分岐から右に折れ長坂道を目指します。 長坂道T字分岐は最良の展望所、しばらく風景を楽しんで行きましょう。花にかこまれた稜線の道を御浜に向かい、まもなく鳥海湖への分岐に出ます。鳥海湖への道が整備され、木道になっているため、間違えて木道に入っていかないように。ここは稜線を忠実にたどります。まもなく眼下に鳥海湖が見えるビューポイントとなります。御浜小屋に着いたらひと休み。小屋を過ぎると岩場になり、足場の不安定な道になります。ここを登り切ると扇子森の頂上部、花畑に包まれた御田ヶ原に出ます。7月上旬頃であればヒナウスユキソウに出会えます。下り道となり鞍部の御田ヶ原分岐を過ぎて、八丁坂の登りにかかります。御苗代の湿地をすぎると、まもなく七五三掛に着きます。ここからは新道の木道を進みます。登り詰めて分岐を左に進むと目の前に千蛇谷雪渓が広がり、新山が見えてきます。雪渓上は落石の危険があるので頭上注意です。雪渓を速やかに横断して、対岸の夏道に入ります。ふたつ目の雪渓をロープを目印に、横断しながら登ります。夏道が大きな岩の塊を行くようになってきたら御室はまもなくです。 新山へは神社横の岩場を登ります。ペンキを目印に山頂に出ます。下りは巻くようにして胎内くぐりを経て小屋裏に出られます。小屋に1泊した翌日はスノーブリッジを渡って七高山に登り、外輪稜線を行者岳、伏拝岳、文殊岳とめぐり、七五三掛に出ます。晴れていれば気持ちのよい天上の山道ですが、風が強く天気の悪いときは御室から千蛇谷コースを戻り、七五三掛に出るのがいいでしょう。御浜からは小屋の前を通過して賽ノ河原に下り、鉾立に下ります。路肩部分に駐車帯がある大平登山口から伝石坂に入っていきます。登山口右手に登山届提出用のボックスがあります。コンクリートの階段で始まり、いきなりの急坂で戸惑うかもしれませんが、ここは鳥海屈指の急坂、ゆっくりと自分のリズムで歩きましょう。周囲はブナ林の森林限界にあたり、しばらくは森の中を歩きます。二ノ宿でいったん呼吸を整えてから見晴台を目指します。見晴台では休憩を取りながら、眼下に広がる風景を楽しみましょう。 森林限界を抜けると、傾斜が緩やかな雪田植物帯の山道となり、高山の花たちが見られるようになります。清水大神の湿原に出てひと息入れ、とよで一休み。チングルマの咲く山道を登り詰めると河原宿に出ます。雪渓を横断し愛宕坂手前の分岐から右に折れ長坂道を目指します。 長坂道T字分岐は最良の展望所、しばらく風景を楽しんで行きましょう。花にかこまれた稜線の道を御浜に向かい、まもなく鳥海湖への分岐に出ます。鳥海湖への道が整備され、木道になっているため、間違えて木道に入っていかないように。ここは稜線を忠実にたどります。まもなく眼下に鳥海湖が見えるビューポイントとなります。御浜小屋に着いたらひと休み。小屋を過ぎると岩場になり、足場の不安定な道になります。ここを登り切ると扇子森の頂上部、花畑に包まれた御田ヶ原に出ます。7月上旬頃であればヒナウスユキソウに出会えます。下り道となり鞍部の御田ヶ原分岐を過ぎて、八丁坂の登りにかかります。御苗代の湿地をすぎると、まもなく七五三掛に着きます。ここからは新道の木道を進みます。登り詰めて分岐を左に進むと目の前に千蛇谷雪渓が広がり、新山が見えてきます。雪渓上は落石の危険があるので頭上注意です。雪渓を速やかに横断して、対岸の夏道に入ります。ふたつ目の雪渓をロープを目印に、横断しながら登ります。夏道が大きな岩の塊を行くようになってきたら御室はまもなくです。 新山へは神社横の岩場を登ります。ペンキを目印に山頂に出ます。下りは巻くようにして胎内くぐりを経て小屋裏に出られます。小屋に1泊した翌日はスノーブリッジを渡って七高山に登り、外輪稜線を行者岳、伏拝岳、文殊岳とめぐり、七五三掛に出ます。晴れていれば気持ちのよい天上の山道ですが、風が強く天気の悪いときは御室から千蛇谷コースを戻り、七五三掛に出るのがいいでしょう。御浜からは小屋の前を通過して賽ノ河原に下り、鉾立に下ります。 -
祓川から直登コースで七高山へ
- 日帰り
- 6時間10分
- 8.9km
祓川から直登コースで七高山へ
- 日帰り
- 6時間10分
- 8.9km
トイレと水場がある広い祓川の駐車場から、竜ヶ原湿原に向かう道に入っていきます。登山届ポストは登山道入口と湿原入口に立つ祓川ヒュッテ内にあります。小屋の前に広がる竜ヶ原湿原を横断するように木道がまっすぐ山頂方向に向かっています。 湿原を渡ると、直登の道が始まります。雪のある時期はここからアイゼンを着用した方がいいでしょう。地を這うようなダケカンバのタッチラ坂に入っていきます。やがて、傾斜が緩くなり賽ノ河原に出ます。御田の雪田地帯は遅くまで雪が残り、狭いカールが一面、シラネニンジンの群落でおおわれたりします。ここを登り切ると、左手に七ツ釜避難小屋があります。まもなく康ケルンに出て、猿倉コース・熊ノ森からの道と合流するのでひと息入れましょう。ここから登山道は次のステージに入っていきます。 康新道の分岐をすぎると大きな雪渓、大雪路に入ります。右の山側に沿って最大傾斜線を詰め、ケルンを目印に夏道が出ていれば、それを足がかりに高度を上げていくといいでしょう。氷ノ薬師を過ぎ舎利坂に入っていくと、しばらくは石段の整備された道が続きますが、次第に火山礫の足場の安定しない道になります。クサリ場が出てきてまもなく康新道の道と合流して外輪山北のピーク、七高山山頂に出ます。 目の前に展開するすばらしい展望に、登頂の喜びが心に染みるでしょう。時間があれば新山まで足をのばしてもよいですが、帰路は七高山からやや下ったところの分岐に出て左に折れ、康新道に入っていきます。途中、登山道がえぐれていたり悪路もありますが、丁寧に高度を下げていきます。この斜面は雪解けも早く、夏の早い時期から岩場にはイワウメ、チョウカイフスマなどが見られます。大雪路下の分岐で合流して康ケルンに出ます。ここからは往路をゆったりと祓川へと戻ります。 もう1泊のプランで、竜ヶ原湿原に咲くヒオウギアヤメなどを愛でながら、ゆったりとくつろぐのもよいでしょう。トイレと水場がある広い祓川の駐車場から、竜ヶ原湿原に向かう道に入っていきます。登山届ポストは登山道入口と湿原入口に立つ祓川ヒュッテ内にあります。小屋の前に広がる竜ヶ原湿原を横断するように木道がまっすぐ山頂方向に向かっています。 湿原を渡ると、直登の道が始まります。雪のある時期はここからアイゼンを着用した方がいいでしょう。地を這うようなダケカンバのタッチラ坂に入っていきます。やがて、傾斜が緩くなり賽ノ河原に出ます。御田の雪田地帯は遅くまで雪が残り、狭いカールが一面、シラネニンジンの群落でおおわれたりします。ここを登り切ると、左手に七ツ釜避難小屋があります。まもなく康ケルンに出て、猿倉コース・熊ノ森からの道と合流するのでひと息入れましょう。ここから登山道は次のステージに入っていきます。 康新道の分岐をすぎると大きな雪渓、大雪路に入ります。右の山側に沿って最大傾斜線を詰め、ケルンを目印に夏道が出ていれば、それを足がかりに高度を上げていくといいでしょう。氷ノ薬師を過ぎ舎利坂に入っていくと、しばらくは石段の整備された道が続きますが、次第に火山礫の足場の安定しない道になります。クサリ場が出てきてまもなく康新道の道と合流して外輪山北のピーク、七高山山頂に出ます。 目の前に展開するすばらしい展望に、登頂の喜びが心に染みるでしょう。時間があれば新山まで足をのばしてもよいですが、帰路は七高山からやや下ったところの分岐に出て左に折れ、康新道に入っていきます。途中、登山道がえぐれていたり悪路もありますが、丁寧に高度を下げていきます。この斜面は雪解けも早く、夏の早い時期から岩場にはイワウメ、チョウカイフスマなどが見られます。大雪路下の分岐で合流して康ケルンに出ます。ここからは往路をゆったりと祓川へと戻ります。 もう1泊のプランで、竜ヶ原湿原に咲くヒオウギアヤメなどを愛でながら、ゆったりとくつろぐのもよいでしょう。 -
大清水から七高山へ
- 日帰り
- 7時間10分
- 11.7km
大清水から七高山へ
- 日帰り
- 7時間10分
- 11.7km
広い駐車場があり山小屋が整備された一大園地、大清水から歩き始めます。周囲はブナの原生林に覆われ、しばらくは尾根道。大倉に出ると、眼下に広がるブナの森の広大さに驚きます。タッチラ坂でダケカンバの林を過ぎ、森林限界を抜け、屏風岩に出て、ひと息入れます。振り返れば、出羽の山並みがどこまでも続いていて、この広がりが生態系の維持に欠かせないことを改めて実感できます。途中水場があるので、補給して進みましょう。 さらに登ると大きな獅子岩がある唐獅子平避難小屋に出て、雪渓が残る霧ヶ平に入り、高度を上げていきます。虫穴が大きく見えてきたら、まもなく稜線に出ます。新山が目前に大きく現れます。外輪ケルン分岐を右に折れ、まもなく左手、新山からの道と合流して虫穴の脇を抜けて七高山に立ちます。帰路は忠実に来た道を戻ります。広い駐車場があり山小屋が整備された一大園地、大清水から歩き始めます。周囲はブナの原生林に覆われ、しばらくは尾根道。大倉に出ると、眼下に広がるブナの森の広大さに驚きます。タッチラ坂でダケカンバの林を過ぎ、森林限界を抜け、屏風岩に出て、ひと息入れます。振り返れば、出羽の山並みがどこまでも続いていて、この広がりが生態系の維持に欠かせないことを改めて実感できます。途中水場があるので、補給して進みましょう。 さらに登ると大きな獅子岩がある唐獅子平避難小屋に出て、雪渓が残る霧ヶ平に入り、高度を上げていきます。虫穴が大きく見えてきたら、まもなく稜線に出ます。新山が目前に大きく現れます。外輪ケルン分岐を右に折れ、まもなく左手、新山からの道と合流して虫穴の脇を抜けて七高山に立ちます。帰路は忠実に来た道を戻ります。 -
滝ノ小屋から伏拝岳へ
- 日帰り
- 6時間20分
- 8.2km
滝ノ小屋から伏拝岳へ
- 日帰り
- 6時間20分
- 8.2km
滝ノ小屋下駐車場はブナ林を切り開いてできた駐車場で、トイレと展望施設があります。入山届ボックスは登山口にあります。 歩き始めは森林限界のブナ林の道で、周囲には氷河時代の形質を持ったブナも見られます。やがてミヤマナラの道になり、荒木沢を渡ると、まもなく滝ノ小屋に出ます。澄郷沢を渡り、初夏であれば雪渓の残る道に入って、雪渓の中ほどから左手のトラバース道に入り、分岐に出ます。 ここで湯ノ台口コースに合流して、八丁坂を登っていきます。きつい登りですが、6月下旬〜7月中旬にはミヤマハンショウヅル、トウゲブキ、イワテトウキ、ハクサンシャジンなどの花々が咲き競い見事です。 河原宿からは月山森への分岐を左に見て、ボサ森から流れる沢を渡って心字雪渓に入っていきます。朝早い時間帯は、雪が堅く滑りやすいので、アイゼン着用をおすすめします。 雪渓は大雪路と小雪路とありますが、時期によってはつながっています。大雪路は左寄りに登り、中間地点でロープに導かれて、右に渡ってから小雪路にとりつき高度を上げていきます。登り詰めたところで右に渡り、まもなく薊坂入口に着きます。ここから薊坂の急登が始まります。 高度をぐんぐんと稼いで、心字雪渓がみるみる離れていきます。何度も呼吸を整え、ゆっくりと登ります。やがて、稜線上の伏拝岳の分岐に出ますが、今まで隠れていた新山の全容が、一気に目の前に展開します。この絶景は、本コースを登った人の特権といえましょう。 ここからさらに天上の尾根道を行者岳、七高山まで足をのばしてみるのもいいです。ただ、帰り道に伏拝分岐を見落とし、鉾立方面に行くケースがよくあります。逆の場合もあります。分岐では立ち止まり自分の行くべき方向を確認する必要があります。とくに登山道が平行して走っているので注意を喚起しておきます。伏拝岳で風景を十分に楽しんだら、往路を慎重に滝ノ小屋方面に下ります。復路は、とくに雪渓の下りでのスリップに気をつけましょう。霧が深いときは夏道のある山側の際を下るように心がけましょう。滝ノ小屋下駐車場はブナ林を切り開いてできた駐車場で、トイレと展望施設があります。入山届ボックスは登山口にあります。 歩き始めは森林限界のブナ林の道で、周囲には氷河時代の形質を持ったブナも見られます。やがてミヤマナラの道になり、荒木沢を渡ると、まもなく滝ノ小屋に出ます。澄郷沢を渡り、初夏であれば雪渓の残る道に入って、雪渓の中ほどから左手のトラバース道に入り、分岐に出ます。 ここで湯ノ台口コースに合流して、八丁坂を登っていきます。きつい登りですが、6月下旬〜7月中旬にはミヤマハンショウヅル、トウゲブキ、イワテトウキ、ハクサンシャジンなどの花々が咲き競い見事です。 河原宿からは月山森への分岐を左に見て、ボサ森から流れる沢を渡って心字雪渓に入っていきます。朝早い時間帯は、雪が堅く滑りやすいので、アイゼン着用をおすすめします。 雪渓は大雪路と小雪路とありますが、時期によってはつながっています。大雪路は左寄りに登り、中間地点でロープに導かれて、右に渡ってから小雪路にとりつき高度を上げていきます。登り詰めたところで右に渡り、まもなく薊坂入口に着きます。ここから薊坂の急登が始まります。 高度をぐんぐんと稼いで、心字雪渓がみるみる離れていきます。何度も呼吸を整え、ゆっくりと登ります。やがて、稜線上の伏拝岳の分岐に出ますが、今まで隠れていた新山の全容が、一気に目の前に展開します。この絶景は、本コースを登った人の特権といえましょう。 ここからさらに天上の尾根道を行者岳、七高山まで足をのばしてみるのもいいです。ただ、帰り道に伏拝分岐を見落とし、鉾立方面に行くケースがよくあります。逆の場合もあります。分岐では立ち止まり自分の行くべき方向を確認する必要があります。とくに登山道が平行して走っているので注意を喚起しておきます。伏拝岳で風景を十分に楽しんだら、往路を慎重に滝ノ小屋方面に下ります。復路は、とくに雪渓の下りでのスリップに気をつけましょう。霧が深いときは夏道のある山側の際を下るように心がけましょう。 -
万助道をたどり千畳ヶ原へ
- 1泊2日
- 7時間45分
- 12.8km
万助道をたどり千畳ヶ原へ
- 1泊2日
- 7時間45分
- 12.8km
一ノ滝駐車場で準備をすませたら歩き始めます。しばらくは林道をたどり、林道終点から山道に入っていきます。気持ちのよいブナ林の道を進みます。狭霧橋への道を右手に見て、碇清水の水場でひと息入れましょう。 万助道十字路に出て右に折れ、まもなく行くと檜ノ沢の清流が流れる渡戸に出ます。渡戸は分岐となっていて、沢を渡り進むと長坂道に出ますが、ここでは沢を渡らず、万助道をたどります。沢音が心地よい檜ノ沢の渓谷を左手に見ながら登り道が続きます。沢音が遠くなり、尾根渡りの分岐に出ます。右の下道をたどると湧水の湧く碇に出てブナの道を行きますが、近年、春先の雪崩で樹木が広範囲でなぎ倒され荒れています。ここは左手の尾根道に入り進みます。 周囲にシャクナゲが目立つようになり、ギャップを過ぎて、豊かな湧水の流れを渡って今日の宿泊所、万助平に立つ万助小屋に到着です。万助平の奥に湧水が出ていて、別天地のようです。ゆったりと山の時間を楽しむことにしましょう。晴れていれば、夜の星空のきらめきに驚かされます。 翌朝は、小屋の清掃と水の補給も忘れずに、早立ちを心がけましょう。小屋を出てしばらくはブナの樹林帯の中を進みますが、やがてミネザクラやハクサンシャクナゲの混じる灌木帯になって視界が開け、ドッタリの草地に出ます。再び灌木帯になって、小さな草付きの湿地を越えると、千畳ヶ原の一角、仙人平に着きます。広大な高層湿地の風景の中を進んで、蛇石流分岐に出ます。ここから御浜は近いですが、ここでは千畳ヶ原でのゆったりとした時間の中で過ごすことにして右手に折れてT字分岐に出ます。 ここからは二ノ滝コースに入り馬ノ背のミヤマナラの尾根道を下ります。 月山沢(増水時は計画変更も視野に入れること)を渡り右手に不動滝、やや下って竜頭滝、竜ヶ滝と過ぎて喜助平に出ます。森ノ清水を経て額絵ノ壷、玉粋ノ滝、三ノ滝と続きます。狭霧橋を右に見て、二ノ滝方面に下ります。二ノ滝からは西ノコマイを左に見て下り、一ノ滝神社を過ぎ、やや巻くようにして登りの起点、一ノ滝駐車場に到着です。一ノ滝駐車場で準備をすませたら歩き始めます。しばらくは林道をたどり、林道終点から山道に入っていきます。気持ちのよいブナ林の道を進みます。狭霧橋への道を右手に見て、碇清水の水場でひと息入れましょう。 万助道十字路に出て右に折れ、まもなく行くと檜ノ沢の清流が流れる渡戸に出ます。渡戸は分岐となっていて、沢を渡り進むと長坂道に出ますが、ここでは沢を渡らず、万助道をたどります。沢音が心地よい檜ノ沢の渓谷を左手に見ながら登り道が続きます。沢音が遠くなり、尾根渡りの分岐に出ます。右の下道をたどると湧水の湧く碇に出てブナの道を行きますが、近年、春先の雪崩で樹木が広範囲でなぎ倒され荒れています。ここは左手の尾根道に入り進みます。 周囲にシャクナゲが目立つようになり、ギャップを過ぎて、豊かな湧水の流れを渡って今日の宿泊所、万助平に立つ万助小屋に到着です。万助平の奥に湧水が出ていて、別天地のようです。ゆったりと山の時間を楽しむことにしましょう。晴れていれば、夜の星空のきらめきに驚かされます。 翌朝は、小屋の清掃と水の補給も忘れずに、早立ちを心がけましょう。小屋を出てしばらくはブナの樹林帯の中を進みますが、やがてミネザクラやハクサンシャクナゲの混じる灌木帯になって視界が開け、ドッタリの草地に出ます。再び灌木帯になって、小さな草付きの湿地を越えると、千畳ヶ原の一角、仙人平に着きます。広大な高層湿地の風景の中を進んで、蛇石流分岐に出ます。ここから御浜は近いですが、ここでは千畳ヶ原でのゆったりとした時間の中で過ごすことにして右手に折れてT字分岐に出ます。 ここからは二ノ滝コースに入り馬ノ背のミヤマナラの尾根道を下ります。 月山沢(増水時は計画変更も視野に入れること)を渡り右手に不動滝、やや下って竜頭滝、竜ヶ滝と過ぎて喜助平に出ます。森ノ清水を経て額絵ノ壷、玉粋ノ滝、三ノ滝と続きます。狭霧橋を右に見て、二ノ滝方面に下ります。二ノ滝からは西ノコマイを左に見て下り、一ノ滝神社を過ぎ、やや巻くようにして登りの起点、一ノ滝駐車場に到着です。 -
大平口から長坂道に出て笙ヶ岳へ
- 日帰り
- 6時間20分
- 9.5km
大平口から長坂道に出て笙ヶ岳へ
- 日帰り
- 6時間20分
- 9.5km
路肩部分に駐車帯がある大平登山口から伝石坂に入っていきます。登山口右手に登山届提出用のボックスがあります。 コンクリートの階段で登りが始まり、いきなりの急坂で戸惑うかもしれませんが、ここは鳥海屈指の急坂、ゆっくりと自分のリズムで歩きましょう。周囲はブナ林の森林限界に近く、しばらくは森の中を歩きます。二ノ宿でいったん呼吸を整えてから見晴台を目指します。見晴台では休憩を取りながら、眼下に広がる風景を楽しみましょう。 森林限界を抜けると雪田植物帯の山道となり、傾斜も緩やかで高山植物が見られるようになります。清水大神の湿原に出てひと息入れ、とよで一休み。チングルマの咲く山道を登り詰めると河原宿に出ます。雪渓を横断し愛宕坂下の分岐から右に折れ長坂道を目指します。長坂道T字分岐に出ると、眺望が開け雄大な山岳景観が目に飛び込んできます。左は御浜小屋へのルート。ここは右に折れ笙ヶ岳を目指します。岩峰を右手に見て、登山道を進みます。 三峰、二峰と気持ちのよい稜線の道をたどり、ハクサンイチゲに包まれた笙ヶ岳山頂に着きます。振り返れば雪渓まばゆい新山がお花畑の向こうにそびえています。ここで、ゆったりと昼食もいいでしょう。 下山は気の抜けない下り道になります。ゆっくりと足元を確かめながら進みます。天狗岩を過ぎ、ガラ場で渡戸への道を左に見て、尾根伝いに下ります。森林帯に入って、水場のある堅餅岩に出ます。やや下ると、森の中の交差点、長坂道十字路に出て、ここは直進して山ノ神に向かいます。高瀬峡からの道と合流して左に折れ、まもなく湧水の出る山ノ神に着きます。 バス利用では、ここから30分ほどの林道歩きがあり、長坂口バス停に出ます。 バス停近くに庄内平野が一望できる東屋があり、夕日の絶景ポイントになっています。バスの待ち時間があれば、立ち寄ってみるのもよいでしょう。路肩部分に駐車帯がある大平登山口から伝石坂に入っていきます。登山口右手に登山届提出用のボックスがあります。 コンクリートの階段で登りが始まり、いきなりの急坂で戸惑うかもしれませんが、ここは鳥海屈指の急坂、ゆっくりと自分のリズムで歩きましょう。周囲はブナ林の森林限界に近く、しばらくは森の中を歩きます。二ノ宿でいったん呼吸を整えてから見晴台を目指します。見晴台では休憩を取りながら、眼下に広がる風景を楽しみましょう。 森林限界を抜けると雪田植物帯の山道となり、傾斜も緩やかで高山植物が見られるようになります。清水大神の湿原に出てひと息入れ、とよで一休み。チングルマの咲く山道を登り詰めると河原宿に出ます。雪渓を横断し愛宕坂下の分岐から右に折れ長坂道を目指します。長坂道T字分岐に出ると、眺望が開け雄大な山岳景観が目に飛び込んできます。左は御浜小屋へのルート。ここは右に折れ笙ヶ岳を目指します。岩峰を右手に見て、登山道を進みます。 三峰、二峰と気持ちのよい稜線の道をたどり、ハクサンイチゲに包まれた笙ヶ岳山頂に着きます。振り返れば雪渓まばゆい新山がお花畑の向こうにそびえています。ここで、ゆったりと昼食もいいでしょう。 下山は気の抜けない下り道になります。ゆっくりと足元を確かめながら進みます。天狗岩を過ぎ、ガラ場で渡戸への道を左に見て、尾根伝いに下ります。森林帯に入って、水場のある堅餅岩に出ます。やや下ると、森の中の交差点、長坂道十字路に出て、ここは直進して山ノ神に向かいます。高瀬峡からの道と合流して左に折れ、まもなく湧水の出る山ノ神に着きます。 バス利用では、ここから30分ほどの林道歩きがあり、長坂口バス停に出ます。 バス停近くに庄内平野が一望できる東屋があり、夕日の絶景ポイントになっています。バスの待ち時間があれば、立ち寄ってみるのもよいでしょう。 -
湯ノ台道から八丁坂を経て月山森へ
- 日帰り
- 6時間30分
- 10.1km
湯ノ台道から八丁坂を経て月山森へ
- 日帰り
- 6時間30分
- 10.1km
鳥海高原家族旅行村に向かう車道は開拓集落を過ぎるとまもなく左手に駐車帯があり、ここが登山口になっています。 山道に入りまもなく、湯ノ沢にかかる丸太橋(少し下部に安全に渡れる幅の広い橋もあります。)を渡り登山道に入っていきます。稜線に出てやや道は緩くなり、水場になる沢を渡ってまもなく南高ヒュッテに出ます。小屋前を通過してかくれ山分岐を経て、湯ノ台道の尾根道に入っていきます。このあたりからブナ林の気持ちのよい尾根道が続き、鳳来山を巻くようにして横堂に出ます。 石の祠を脇に見て、登っていきます。一本杉を過ぎ、大黒台のしっとりとしたブナ林を過ぎ、高度を上げると西物見で、眺望が開けます。篭山の岩場を過ぎ、テーブル状のウスメ岩に出ます。樹林帯を抜け出し、ミヤマナラの灌木帯を進み、滝ノ小屋からの分岐を二つ過ぎて、八丁坂に入っていきます。きつい登りですが、周囲に咲く花々が励ましてくれます。所々でひと息入れながら見渡す庄内平野、出羽丘陵の山並みの風景は格別です。 沢音が近づき、外輪山が見えてくると、河原宿はまもなくです。小屋は現在閉鎖されていますが、雪渓からの沢水が冷たく、小屋の前で休憩を入れるのもいいでしょう。少し離れた別棟にトイレがありますので、利用していきましょう。 小屋の前を過ぎて、まもなく分岐に出ます。ここで左に折れ、月山森に向かいます。高層湿地の中を整備された木道を歩き、右手にボタ池が現れます。まもなく月山森分岐に着き、左手の尾根にのびている踏み跡をたどって稜線に出て右折し、ハイマツをかき分けて月山森のピークに出ます。西寄りの露岩に出て腰を下ろし、ひとときの時間を味わいましょう。 帰路は往路を戻り、八丁坂分岐から左手に折れ、雪渓を下って澄郷沢を飛び石で渡れば、滝ノ小屋に出ます。小屋の前を通過して滝ノ小屋下駐車場まではひと歩き、20分ほどで着きます。 マイカーでない場合はここでタクシーを待つことになりますが、駐車場付近は氷河時代の形質を持つ矮性ブナが観察できるので、待ち時間に探してみるのもよいでしょう。鳥海高原家族旅行村に向かう車道は開拓集落を過ぎるとまもなく左手に駐車帯があり、ここが登山口になっています。 山道に入りまもなく、湯ノ沢にかかる丸太橋(少し下部に安全に渡れる幅の広い橋もあります。)を渡り登山道に入っていきます。稜線に出てやや道は緩くなり、水場になる沢を渡ってまもなく南高ヒュッテに出ます。小屋前を通過してかくれ山分岐を経て、湯ノ台道の尾根道に入っていきます。このあたりからブナ林の気持ちのよい尾根道が続き、鳳来山を巻くようにして横堂に出ます。 石の祠を脇に見て、登っていきます。一本杉を過ぎ、大黒台のしっとりとしたブナ林を過ぎ、高度を上げると西物見で、眺望が開けます。篭山の岩場を過ぎ、テーブル状のウスメ岩に出ます。樹林帯を抜け出し、ミヤマナラの灌木帯を進み、滝ノ小屋からの分岐を二つ過ぎて、八丁坂に入っていきます。きつい登りですが、周囲に咲く花々が励ましてくれます。所々でひと息入れながら見渡す庄内平野、出羽丘陵の山並みの風景は格別です。 沢音が近づき、外輪山が見えてくると、河原宿はまもなくです。小屋は現在閉鎖されていますが、雪渓からの沢水が冷たく、小屋の前で休憩を入れるのもいいでしょう。少し離れた別棟にトイレがありますので、利用していきましょう。 小屋の前を過ぎて、まもなく分岐に出ます。ここで左に折れ、月山森に向かいます。高層湿地の中を整備された木道を歩き、右手にボタ池が現れます。まもなく月山森分岐に着き、左手の尾根にのびている踏み跡をたどって稜線に出て右折し、ハイマツをかき分けて月山森のピークに出ます。西寄りの露岩に出て腰を下ろし、ひとときの時間を味わいましょう。 帰路は往路を戻り、八丁坂分岐から左手に折れ、雪渓を下って澄郷沢を飛び石で渡れば、滝ノ小屋に出ます。小屋の前を通過して滝ノ小屋下駐車場まではひと歩き、20分ほどで着きます。 マイカーでない場合はここでタクシーを待つことになりますが、駐車場付近は氷河時代の形質を持つ矮性ブナが観察できるので、待ち時間に探してみるのもよいでしょう。 -
弥陀ヶ原から月山山頂へ
- 日帰り
- 5時間5分
- 9.8km
弥陀ヶ原から月山山頂へ
- 日帰り
- 5時間5分
- 9.8km
鶴岡からの定期バス(季節運行)が入る月山八合目駐車場は、レストハウスやトイレがある登山口ですが、一歩踏みいればそこは高層湿原が広がる、弥陀ヶ原湿原になります。植物外来種防止用のマットで、靴に着いた種子などを落として入山します。大きな看板を前に、道は二手に分かれますが、ここは左手から進み、御田原参篭所(中ノ宮)を経由して本道に入っていきます。御田原参篭所(中ノ宮)を起点にして湿原散策するのもよいでしょう。月山の魅力のひとつはこうした高層湿原のすばらしさにあるともいえます。 散策道を周遊して、御田原参篭所(中ノ宮)上部の分岐から登山道に入ります。緩やかな無量坂、やや勾配のきつい鍋割を過ぎ、畳石の花畑に出ます。周囲の風景は高山の様相を深めていきます。仏生池小屋に出たら、ひと休み。売店、トイレなどがあります。 オモワシ山の肩を過ぎ、灌木帯の岩の上を歩く道になり、行者返の岩場を抜けると、気持ちのよい尾根道になっていきます。大峰を過ぎ、花を愛でながら木道を進むと、まもなく月山山頂神社の建物が見え、石垣を巻くようにして、月山山頂に着きます。山頂は神社の中にあり、お祓いを受けて入ります。三角点のある山頂部は石垣の山頂神社に入る手前で、神社の後ろに張り出している尾根を登り詰めたところにあります。展望のよい、静かな山頂のおもむきがあります。 下りは南西に向かい、頂上小屋の前を抜けて広大な台地上の一角から牛首へと下りていきます。岩場の連続する下り道ですが、目の前に展開する山岳景観は見応えがあります。 牛首の分岐に出て、右の道をとって姥ヶ岳方面に進むと金姥の分岐に出ます。ここを直進すると姥ヶ岳山頂に着きます。 山頂は適度な広さで、月山を振り返るのもよし、南西に朝日連峰を眺めるのにも最良の地点といえます。 姥ヶ岳からは木道が出てきますが、残雪時期はアイゼン着用の箇所です。まもなく階段状の山道になって、牛首からのルートが合流します。ここは休憩スペースもあり展望も良いので、月山を振り返りその大きさを実感できます。 売店、トイレのあるリフト上駅に出て、20分ほどのリフト利用、リフト下駅から車道歩き15分ほどで、月山姥沢バス停に出ます。鶴岡からの定期バス(季節運行)が入る月山八合目駐車場は、レストハウスやトイレがある登山口ですが、一歩踏みいればそこは高層湿原が広がる、弥陀ヶ原湿原になります。植物外来種防止用のマットで、靴に着いた種子などを落として入山します。大きな看板を前に、道は二手に分かれますが、ここは左手から進み、御田原参篭所(中ノ宮)を経由して本道に入っていきます。御田原参篭所(中ノ宮)を起点にして湿原散策するのもよいでしょう。月山の魅力のひとつはこうした高層湿原のすばらしさにあるともいえます。 散策道を周遊して、御田原参篭所(中ノ宮)上部の分岐から登山道に入ります。緩やかな無量坂、やや勾配のきつい鍋割を過ぎ、畳石の花畑に出ます。周囲の風景は高山の様相を深めていきます。仏生池小屋に出たら、ひと休み。売店、トイレなどがあります。 オモワシ山の肩を過ぎ、灌木帯の岩の上を歩く道になり、行者返の岩場を抜けると、気持ちのよい尾根道になっていきます。大峰を過ぎ、花を愛でながら木道を進むと、まもなく月山山頂神社の建物が見え、石垣を巻くようにして、月山山頂に着きます。山頂は神社の中にあり、お祓いを受けて入ります。三角点のある山頂部は石垣の山頂神社に入る手前で、神社の後ろに張り出している尾根を登り詰めたところにあります。展望のよい、静かな山頂のおもむきがあります。 下りは南西に向かい、頂上小屋の前を抜けて広大な台地上の一角から牛首へと下りていきます。岩場の連続する下り道ですが、目の前に展開する山岳景観は見応えがあります。 牛首の分岐に出て、右の道をとって姥ヶ岳方面に進むと金姥の分岐に出ます。ここを直進すると姥ヶ岳山頂に着きます。 山頂は適度な広さで、月山を振り返るのもよし、南西に朝日連峰を眺めるのにも最良の地点といえます。 姥ヶ岳からは木道が出てきますが、残雪時期はアイゼン着用の箇所です。まもなく階段状の山道になって、牛首からのルートが合流します。ここは休憩スペースもあり展望も良いので、月山を振り返りその大きさを実感できます。 売店、トイレのあるリフト上駅に出て、20分ほどのリフト利用、リフト下駅から車道歩き15分ほどで、月山姥沢バス停に出ます。 -
玄海広場から姥ヶ岳へ
- 日帰り
- 4時間5分
- 9.1km
玄海広場から姥ヶ岳へ
- 日帰り
- 4時間5分
- 9.1km
志津野営場前バス停からネイチャーセンターがある自然博物園・玄海広場からスタートです。石跳川に沿って、緩やかに登っていきます。周囲はブナ林に包まれ、気持ちのよい山道が続きます。 途中いくつかの分岐があり、魅力的な森の散策路があります。ここでは川沿いに上流へと向かいます。春木戸跡でひと休み、明るい沢をゆったりと進みます。沢から離れて、木道が現れ、まもなくコルに出ます。湯殿山からの道と合流する装束場です。ここは、湯殿山に参拝する人が装束を整えたところといわれています。分岐を右に折れ、金姥へ。金姥で右に折れ姥ヶ岳山頂を目指します。この分岐から姥ヶ岳山頂への道にはヒナウスユキソウ、イワカガミなどが可憐に咲き競っています。まもなく三角点のある360度展望の姥ヶ岳山頂に着きます。(姥ヶ岳山頂からは弥陀ヶ原から月山山頂へ(コースガイド)を参照ください。)志津野営場前バス停からネイチャーセンターがある自然博物園・玄海広場からスタートです。石跳川に沿って、緩やかに登っていきます。周囲はブナ林に包まれ、気持ちのよい山道が続きます。 途中いくつかの分岐があり、魅力的な森の散策路があります。ここでは川沿いに上流へと向かいます。春木戸跡でひと休み、明るい沢をゆったりと進みます。沢から離れて、木道が現れ、まもなくコルに出ます。湯殿山からの道と合流する装束場です。ここは、湯殿山に参拝する人が装束を整えたところといわれています。分岐を右に折れ、金姥へ。金姥で右に折れ姥ヶ岳山頂を目指します。この分岐から姥ヶ岳山頂への道にはヒナウスユキソウ、イワカガミなどが可憐に咲き競っています。まもなく三角点のある360度展望の姥ヶ岳山頂に着きます。(姥ヶ岳山頂からは弥陀ヶ原から月山山頂へ(コースガイド)を参照ください。) -
湯殿山神社から月山山頂へ
- 日帰り
- 6時間10分
- 10.7km
湯殿山神社から月山山頂へ
- 日帰り
- 6時間10分
- 10.7km
バスターミナルのある湯殿山参籠所からシャトルバスに乗り換え、5分ほどで湯殿山神社に着きます。ここから歩き始めますが、しばらくは参道を登拝者と一緒に進み、仙人沢を渡って左に折れて、登山道に入っていきます。 ここからは沢沿いの道を進み、堰堤が現れると、仙人沢に落ち込むように沢水が激しく流れてきます。この沢水を脇に見て、登りの難所、水月光が始まります。高度を上げていくと、今度は鉄バシゴの連続です。ここが金月光(姥月光)で、垂直に近いような道を体全体を使って登っていきます。 登り切って、ほっと広い空間に出れば、装束場。三方からの道がここで合流します。装束場は、湯殿山に参拝する人たちが、一方は羽黒山を発ち月山を越えて、また一方は志津から石跳沢をたどり、ここでわらじを履き替え装束を整えたところと言われており、まさに参道の交差点と言えます。 ここで左に道をとって月山山頂を目指します。清身川を渡り、ゆるやかに姥ヶ岳の北西面をたどりながら、金姥に出ます。さらに東に向かって気持ちのよい尾根道をたどり、柴灯森を経て牛首に出ます。前方に月山の最後の登りが目の前に迫りますがここでひと息入れましょう。 ここからのきつい岩場の道は鍛冶月光と呼ばれていますが、登り切ったあたりにかつては鍛冶小屋がありました。鍛冶小屋跡を過ぎると、まもなく頂上の一角、おおらかな月山山頂に到着です。右手に本道寺・岩根沢からのルート、肘折温泉からのルートと合流して山頂の月山神社に着きます。宿泊をプランに入れて頂上小屋に泊まるのもいいでしょう。 下山は、神社脇から羽黒コースを下っていきます。花畑が広がる木道道が終わると風衝地の大峰に出て、行者返を経て仏生池小屋に着きます。ここでゆったりと休憩をとりましょう。 畳石を過ぎ鍋割から無量坂を下ると、弥陀ヶ原の十字路に出ます。ここからは弥陀ヶ原湿原散策に時間をあてて周遊するのもよし、月山八合目駐車場に向かうのもいいでしょう。羽黒口からは鶴岡行きのバスが運行しています。バスターミナルのある湯殿山参籠所からシャトルバスに乗り換え、5分ほどで湯殿山神社に着きます。ここから歩き始めますが、しばらくは参道を登拝者と一緒に進み、仙人沢を渡って左に折れて、登山道に入っていきます。 ここからは沢沿いの道を進み、堰堤が現れると、仙人沢に落ち込むように沢水が激しく流れてきます。この沢水を脇に見て、登りの難所、水月光が始まります。高度を上げていくと、今度は鉄バシゴの連続です。ここが金月光(姥月光)で、垂直に近いような道を体全体を使って登っていきます。 登り切って、ほっと広い空間に出れば、装束場。三方からの道がここで合流します。装束場は、湯殿山に参拝する人たちが、一方は羽黒山を発ち月山を越えて、また一方は志津から石跳沢をたどり、ここでわらじを履き替え装束を整えたところと言われており、まさに参道の交差点と言えます。 ここで左に道をとって月山山頂を目指します。清身川を渡り、ゆるやかに姥ヶ岳の北西面をたどりながら、金姥に出ます。さらに東に向かって気持ちのよい尾根道をたどり、柴灯森を経て牛首に出ます。前方に月山の最後の登りが目の前に迫りますがここでひと息入れましょう。 ここからのきつい岩場の道は鍛冶月光と呼ばれていますが、登り切ったあたりにかつては鍛冶小屋がありました。鍛冶小屋跡を過ぎると、まもなく頂上の一角、おおらかな月山山頂に到着です。右手に本道寺・岩根沢からのルート、肘折温泉からのルートと合流して山頂の月山神社に着きます。宿泊をプランに入れて頂上小屋に泊まるのもいいでしょう。 下山は、神社脇から羽黒コースを下っていきます。花畑が広がる木道道が終わると風衝地の大峰に出て、行者返を経て仏生池小屋に着きます。ここでゆったりと休憩をとりましょう。 畳石を過ぎ鍋割から無量坂を下ると、弥陀ヶ原の十字路に出ます。ここからは弥陀ヶ原湿原散策に時間をあてて周遊するのもよし、月山八合目駐車場に向かうのもいいでしょう。羽黒口からは鶴岡行きのバスが運行しています。 -
岩根沢登山口から月山山頂へ
- 1泊2日
- 9時間0分
- 17.9km
岩根沢登山口から月山山頂へ
- 1泊2日
- 9時間0分
- 17.9km
登山口までのアプローチがよくないため、マイカー利用でプランを立てましょう。車道終点に車を置き(駐車スペースはあまりなく、車道脇のスペースなどを利用)、岩根沢登山口から歩き出します。まもなく烏川(サカサ沢)に下る分岐に出ます。右に入ってブナ林の道を下っていきます。 平坦な烏川の河原に出ます。増水時には上流に少し向かい、左手から入り込んでいるナベクラ沢をやり過ごして、本流の烏川を渡ります。ここでは、状況の判断が要求されます。沢を渡り、再び美しいブナ林の道となります。途中、へずり状の箇所があります。気をつけて通過していきます。森林限界を抜け出て灌木の尾根道になり、まもなく清川行人小屋に出ます。ここで休憩を入れて、小屋前に延びる道を5分ほど上がると神社に出ます。神社からは360度の眺望が楽しめ、まだ遙かなりし月山が眺められます。 小屋脇を下り、ドウダン坂に向かう分岐を左に見て、直進して立谷沢川の源流になる清川を渡り、月山への道に入っていきます。ややきつい登りを終えると、月山の雄大な山域に入っていきます。 風景を楽しみながら進み、やがて本道寺からの道と合流して、胎内岩を経ておおらかな月山山頂の台地に出ます。月山山頂神社を往復して、この日は頂上小屋に泊まりましょう。頂上小屋は家族経営で温かさが魅力で、料理もバラエティに富んだ山菜が多くうれしい限りです。翌朝はご来光を楽しんだり、少しのんびりとした朝の時間を過ごすのもいいでしょう。 小屋を発ち、ひとつ目の分岐、肘折道を左に見て進み、まもなく、前日登ってきた道を確認して、本道寺・岩根沢コースに入っていきます。胎内岩をすぎ、本道寺への道を下りドウダン坂分岐に出ます。左手に向かえば、前日通ってきた清川行人小屋に出ますが、ここは直進して、気持ちのよい尾根道を行きます。 郡界で本道寺コースを右に見て直進し、左右に開ける風景を楽しみながら尾根道を淡々と下ります。振り返ると月山が遠くに見えます。地蔵森山をゆるやかに巻いていくとまもなく出発地点の岩根沢登山口に出ます。登山口までのアプローチがよくないため、マイカー利用でプランを立てましょう。車道終点に車を置き(駐車スペースはあまりなく、車道脇のスペースなどを利用)、岩根沢登山口から歩き出します。まもなく烏川(サカサ沢)に下る分岐に出ます。右に入ってブナ林の道を下っていきます。 平坦な烏川の河原に出ます。増水時には上流に少し向かい、左手から入り込んでいるナベクラ沢をやり過ごして、本流の烏川を渡ります。ここでは、状況の判断が要求されます。沢を渡り、再び美しいブナ林の道となります。途中、へずり状の箇所があります。気をつけて通過していきます。森林限界を抜け出て灌木の尾根道になり、まもなく清川行人小屋に出ます。ここで休憩を入れて、小屋前に延びる道を5分ほど上がると神社に出ます。神社からは360度の眺望が楽しめ、まだ遙かなりし月山が眺められます。 小屋脇を下り、ドウダン坂に向かう分岐を左に見て、直進して立谷沢川の源流になる清川を渡り、月山への道に入っていきます。ややきつい登りを終えると、月山の雄大な山域に入っていきます。 風景を楽しみながら進み、やがて本道寺からの道と合流して、胎内岩を経ておおらかな月山山頂の台地に出ます。月山山頂神社を往復して、この日は頂上小屋に泊まりましょう。頂上小屋は家族経営で温かさが魅力で、料理もバラエティに富んだ山菜が多くうれしい限りです。翌朝はご来光を楽しんだり、少しのんびりとした朝の時間を過ごすのもいいでしょう。 小屋を発ち、ひとつ目の分岐、肘折道を左に見て進み、まもなく、前日登ってきた道を確認して、本道寺・岩根沢コースに入っていきます。胎内岩をすぎ、本道寺への道を下りドウダン坂分岐に出ます。左手に向かえば、前日通ってきた清川行人小屋に出ますが、ここは直進して、気持ちのよい尾根道を行きます。 郡界で本道寺コースを右に見て直進し、左右に開ける風景を楽しみながら尾根道を淡々と下ります。振り返ると月山が遠くに見えます。地蔵森山をゆるやかに巻いていくとまもなく出発地点の岩根沢登山口に出ます。 -
肘折登山口から念仏ヶ原へ
- 1泊2日
- 8時間30分
- 16.9km
肘折登山口から念仏ヶ原へ
- 1泊2日
- 8時間30分
- 16.9km
前泊、後泊を肘折温泉でとって、登山口まで宿の方に送迎していただき、歩き始めるのが便利です。マイカーでは駐車スペースに車を置き登山道に入っていきます。 肘折登山口から歩き出してまもなく大森山への登りに入っていきますが、途中から南面をトラバースしながら大森山西鞍部に出ます。ここでひと息入れましょう。周囲は気持ちのよいブナ林に包まれています。 さらに進むと、尾根北面の道になり、トチやミズナラの巨木の道に入っていきます。ここを抜けたあたりに、道の脇に湯殿山碑があります。 ゆるい尾根を越えて沢音が近づくと、猫又沢に出ます。大きなシズオタカラコウの黄色い花が印象的です。ブナの道が続き、やや登りがきつくなると、まもなく赤砂山の南稜に入ります。ここは大蔵村と庄内町の境で、下ると立谷沢の支流、赤沢川に出ます。ここは源頭部にあたるため水量は少なめです。沢を渡ってゆるやかな長い登り道に入っていきます。 鳥海山が遠望できる小岳山頂部を過ぎ、やや下ると花崗岩質がむきでた湿地に出ます。眺望も開け、振り返ると葉山が大きく見えます。木道が整備されていますが滑りやすいので気をつけていきましょう。三日月池の湿地をすぎ、下り道になり、回り込むようにして下ると、念仏ヶ原避難小屋に着きます。 小屋は念仏ヶ原湿原の入口にあり、ここから湿原探索に向かいます。湿原を背景におおらかな月山が望めます。少し足をのばして、立谷沢の本沢、清川の清流まで歩いてみてもいいでしょう。ここでは念仏ヶ原湿原探索を味わい、小屋に泊まってゆったりとした時間を過ごし、翌日も湿原の朝を存分に楽しみます。帰路は往路を忠実に戻ります。前泊、後泊を肘折温泉でとって、登山口まで宿の方に送迎していただき、歩き始めるのが便利です。マイカーでは駐車スペースに車を置き登山道に入っていきます。 肘折登山口から歩き出してまもなく大森山への登りに入っていきますが、途中から南面をトラバースしながら大森山西鞍部に出ます。ここでひと息入れましょう。周囲は気持ちのよいブナ林に包まれています。 さらに進むと、尾根北面の道になり、トチやミズナラの巨木の道に入っていきます。ここを抜けたあたりに、道の脇に湯殿山碑があります。 ゆるい尾根を越えて沢音が近づくと、猫又沢に出ます。大きなシズオタカラコウの黄色い花が印象的です。ブナの道が続き、やや登りがきつくなると、まもなく赤砂山の南稜に入ります。ここは大蔵村と庄内町の境で、下ると立谷沢の支流、赤沢川に出ます。ここは源頭部にあたるため水量は少なめです。沢を渡ってゆるやかな長い登り道に入っていきます。 鳥海山が遠望できる小岳山頂部を過ぎ、やや下ると花崗岩質がむきでた湿地に出ます。眺望も開け、振り返ると葉山が大きく見えます。木道が整備されていますが滑りやすいので気をつけていきましょう。三日月池の湿地をすぎ、下り道になり、回り込むようにして下ると、念仏ヶ原避難小屋に着きます。 小屋は念仏ヶ原湿原の入口にあり、ここから湿原探索に向かいます。湿原を背景におおらかな月山が望めます。少し足をのばして、立谷沢の本沢、清川の清流まで歩いてみてもいいでしょう。ここでは念仏ヶ原湿原探索を味わい、小屋に泊まってゆったりとした時間を過ごし、翌日も湿原の朝を存分に楽しみます。帰路は往路を忠実に戻ります。 -
鉢子から古道をたどり羽黒山頂へ
- 日帰り
- 4時間35分
- 8.1km
鉢子から古道をたどり羽黒山頂へ
- 日帰り
- 4時間35分
- 8.1km
鉢子集落の外れに車道を利用した駐車帯があり、この羽黒古道鉢子登山口から歩き始めます。車道を横断して、民家の脇の道を上がっていきます。右手に水神様の湧水が現れ、少し進むと左手に地蔵堂があり、まもなく皇野分岐に出ます。左手に折れ羽黒古道に入ります。左手の瀬を渡って行者塚、古道に戻り、道脇の稚児塚などを過ぎて車道の終点に出ると山道に。ミズバショウのある湿地を過ぎて、みはらしの丘でひと休み。北方に鳥海山が望めます。林道を横断し杉とブナの混交林になると、出羽三山神社に出ます。標識がないので出口を確認しておきましょう。ここからは賑やかな雰囲気となります。山頂部にある斎館では、予約制で精進料理をいただけます。 羽黒山大鐘、三神合祭殿、鏡池を見て三ノ坂の上部に出ます。ここを下りきると分岐に出ます。本道から離れて、左に入ると南谷別院跡に出ます。ここからは山腹をトラバースするようにブナ林の山道をたどり、荒沢寺への参道に出て左に折れ、再び羽黒山頂を目指します。バスターミナルに出て、左ルートで蜂子皇子墓、羽黒大鐘に出ます。ここからは往路を羽黒古道鉢子登山口まで下ります。鉢子集落の外れに車道を利用した駐車帯があり、この羽黒古道鉢子登山口から歩き始めます。車道を横断して、民家の脇の道を上がっていきます。右手に水神様の湧水が現れ、少し進むと左手に地蔵堂があり、まもなく皇野分岐に出ます。左手に折れ羽黒古道に入ります。左手の瀬を渡って行者塚、古道に戻り、道脇の稚児塚などを過ぎて車道の終点に出ると山道に。ミズバショウのある湿地を過ぎて、みはらしの丘でひと休み。北方に鳥海山が望めます。林道を横断し杉とブナの混交林になると、出羽三山神社に出ます。標識がないので出口を確認しておきましょう。ここからは賑やかな雰囲気となります。山頂部にある斎館では、予約制で精進料理をいただけます。 羽黒山大鐘、三神合祭殿、鏡池を見て三ノ坂の上部に出ます。ここを下りきると分岐に出ます。本道から離れて、左に入ると南谷別院跡に出ます。ここからは山腹をトラバースするようにブナ林の山道をたどり、荒沢寺への参道に出て左に折れ、再び羽黒山頂を目指します。バスターミナルに出て、左ルートで蜂子皇子墓、羽黒大鐘に出ます。ここからは往路を羽黒古道鉢子登山口まで下ります。 -
枝折峠から越後駒ヶ岳へ
- 日帰り
- 11時間10分
- 14.3km
枝折峠から越後駒ヶ岳へ
- 日帰り
- 11時間10分
- 14.3km
枝折峠の南にある登山口からスタートします。頂上との標高差は1000m未満ですが、距離が長いので頂は遠くに見えるでしょう。灌木の中をしばらく登ると、左下の北ノ又川沿いに銀山平湖畔より集団移転した民宿などのログハウスの集落が見えてきます。温泉もあるので帰りに汗を流してもよいでしょう。貸切のログハウスもあるので、登山の基地にはもってこいです。 なだらかな登りが続き、林に入ったところで枝折大明神の小祠に到着します。この祠は5〜6人くらい収容可能なので避難小屋としても利用できます。ここには「銀の道」の標識があり、この道は大湯から銀山平に抜ける道でとして車道が出来るまで人々の生活道路として利用されていました。見晴らしの良い明神峠を過ぎ幾つかのピークを登り下りすると道行山分岐です。天候が良ければピークまで登り、守門、未丈、荒沢、中、兎などの展望を楽しむのもよいでしょう。春にはシャクナゲ、夏にはコメツツジの花が群生して咲いています。 ここから小倉山までは一旦下りになりますが、登山道はぬかるんでいるところが多く歩きにくいので注意が必要です。視界のきかない灌木帯を過ぎると小倉山に到着します。ふり返れば枝折峠が遠くに見え、歩いてきた距離を実感できるでしょう。 灌木の生い茂る視界のきかない緩斜面を登りしばらくすると百草ノ池のある平坦地に出ます。この池の周り一帯は一時裸地化し、池も埋没しそうでしたが、地元の山の関係者の努力により水辺にハクサンコザクラが咲く元の池に戻り、水面に荒沢岳を映すようになりました。 ここから登山道は背丈の低い灌木帯となり、見晴らしの良い急登になります。前駒のピークに着くと道はゆるい岩稜へと変わります。岩場の急登を登り終わると駒ノ小屋に到着です。小屋には5月中旬から10月中旬まで不定期ですが管理人が駐在します。 ここから頂上までは、真夏まで豊富な残雪があり、様々な彩りを添えたお花畑と、残雪のコントラストが見事です。花を堪能しながら30分ほど登ると越後駒ヶ岳頂上に到着します。 視界が良ければ越後三山の八海山、中ノ岳をはじめとし、守門岳、浅草岳、平ヶ岳、燧ヶ岳、会津朝日岳、遠くは北アルプス連峰、飯豊連峰も一望できます。 かつては山岳信仰の対象で、昭和30年代には多くの信者が登りましたが、その後減少し現在賑わう登山者の中に信者の姿を見ることはありません。頂上にある猿田彦大神像が往時を偲ばせるのみです。 下山は往路を枝折峠まで戻ります。枝折峠の南にある登山口からスタートします。頂上との標高差は1000m未満ですが、距離が長いので頂は遠くに見えるでしょう。灌木の中をしばらく登ると、左下の北ノ又川沿いに銀山平湖畔より集団移転した民宿などのログハウスの集落が見えてきます。温泉もあるので帰りに汗を流してもよいでしょう。貸切のログハウスもあるので、登山の基地にはもってこいです。 なだらかな登りが続き、林に入ったところで枝折大明神の小祠に到着します。この祠は5〜6人くらい収容可能なので避難小屋としても利用できます。ここには「銀の道」の標識があり、この道は大湯から銀山平に抜ける道でとして車道が出来るまで人々の生活道路として利用されていました。見晴らしの良い明神峠を過ぎ幾つかのピークを登り下りすると道行山分岐です。天候が良ければピークまで登り、守門、未丈、荒沢、中、兎などの展望を楽しむのもよいでしょう。春にはシャクナゲ、夏にはコメツツジの花が群生して咲いています。 ここから小倉山までは一旦下りになりますが、登山道はぬかるんでいるところが多く歩きにくいので注意が必要です。視界のきかない灌木帯を過ぎると小倉山に到着します。ふり返れば枝折峠が遠くに見え、歩いてきた距離を実感できるでしょう。 灌木の生い茂る視界のきかない緩斜面を登りしばらくすると百草ノ池のある平坦地に出ます。この池の周り一帯は一時裸地化し、池も埋没しそうでしたが、地元の山の関係者の努力により水辺にハクサンコザクラが咲く元の池に戻り、水面に荒沢岳を映すようになりました。 ここから登山道は背丈の低い灌木帯となり、見晴らしの良い急登になります。前駒のピークに着くと道はゆるい岩稜へと変わります。岩場の急登を登り終わると駒ノ小屋に到着です。小屋には5月中旬から10月中旬まで不定期ですが管理人が駐在します。 ここから頂上までは、真夏まで豊富な残雪があり、様々な彩りを添えたお花畑と、残雪のコントラストが見事です。花を堪能しながら30分ほど登ると越後駒ヶ岳頂上に到着します。 視界が良ければ越後三山の八海山、中ノ岳をはじめとし、守門岳、浅草岳、平ヶ岳、燧ヶ岳、会津朝日岳、遠くは北アルプス連峰、飯豊連峰も一望できます。 かつては山岳信仰の対象で、昭和30年代には多くの信者が登りましたが、その後減少し現在賑わう登山者の中に信者の姿を見ることはありません。頂上にある猿田彦大神像が往時を偲ばせるのみです。 下山は往路を枝折峠まで戻ります。 -
十字峡から中ノ岳へ
- 1泊2日
- 17時間45分
- 25.4km
十字峡から中ノ岳へ
- 1泊2日
- 17時間45分
- 25.4km
六日町駅からのバスを野中で降りると、十字峡までは三国川ダムにあるしゃくなげ湖周遊道路の、長い車道歩きが続きます。周遊道の、右回りの県道233号を行きます。ただし十字峡まではタクシーも入り、駐車場も完備されているので車の利用が適切です。黒又沢にかかる橋の手前右側に登山道入口、左側に十字峡登山センターがあります。 十字峡登山センターは無人ですが売店横から2階に上がることができ、素泊まりで泊まれます。登山道は、十字峡登山センター前のコンクリート壁に付けられた階段とクサリから始まります。ジグザグの急坂をしばらく進むと平らな場所に出ます。さらに登り続けると一合目のブナの大木が姿を現します。はっきり尾根らしくなると八海山入道岳がピラミッド形に見えてきます。小憩後、小さな短いクサリ場を登りきると二合目の千本松原で、大きくて形のよいキタゴヨウマツがあります。数本の立派な松があり、振り返るとダムの取水口あたりが見下ろせて、高度感が出てきます。 いったん快適で眺めの良い尾根となり、三合目を難なく過ぎると、左正面に日向山の雨量計測所が遠く小さく見えてきます。ここからはブナ林の中をしばらく登りましょう。ブナ林に入るとすぐに四合目です。そのあとのブナ林はつらい登りですが、一気に高度を稼ぎ、日向山山頂直下の五合目に出ます。下から見えた雨量計測所はこの上です。展望は一気にパノラマの様に開け、正面には中ノ岳、左には御月山、右には兎岳から丹後山へと雄大な眺めに飽きる事はありません。日向山を下ると、池塘のある草地に出ます。一帯は生姜畑と呼ばれる鉱山の跡地です。 池塘と草地を過ぎると六合目。一度鞍部に下り、小ピークをふたつほど越すと七合目の小天上の峰です。左に中ノ岳から八海山に続く険しい稜線を見ながら、池ノ段まできつい登りになります。やせ尾根と転石に注意しながらの登りですが、一歩ずつ確実に高度を上げ展望はますます良くなってきます。やがて一帯の灌木も低くなり、植生はチシマザサに変わります。小さなガレ場を過ぎると、苦しかった急坂も終わり、九合目の池ノ段はすぐです。さらに岩場を進むと中ノ岳頂上へ。下山は往路を野中まで引き返しますが、急な下りと赤土で滑りやすいので、足元には十分注意して下さい。六日町駅からのバスを野中で降りると、十字峡までは三国川ダムにあるしゃくなげ湖周遊道路の、長い車道歩きが続きます。周遊道の、右回りの県道233号を行きます。ただし十字峡まではタクシーも入り、駐車場も完備されているので車の利用が適切です。黒又沢にかかる橋の手前右側に登山道入口、左側に十字峡登山センターがあります。 十字峡登山センターは無人ですが売店横から2階に上がることができ、素泊まりで泊まれます。登山道は、十字峡登山センター前のコンクリート壁に付けられた階段とクサリから始まります。ジグザグの急坂をしばらく進むと平らな場所に出ます。さらに登り続けると一合目のブナの大木が姿を現します。はっきり尾根らしくなると八海山入道岳がピラミッド形に見えてきます。小憩後、小さな短いクサリ場を登りきると二合目の千本松原で、大きくて形のよいキタゴヨウマツがあります。数本の立派な松があり、振り返るとダムの取水口あたりが見下ろせて、高度感が出てきます。 いったん快適で眺めの良い尾根となり、三合目を難なく過ぎると、左正面に日向山の雨量計測所が遠く小さく見えてきます。ここからはブナ林の中をしばらく登りましょう。ブナ林に入るとすぐに四合目です。そのあとのブナ林はつらい登りですが、一気に高度を稼ぎ、日向山山頂直下の五合目に出ます。下から見えた雨量計測所はこの上です。展望は一気にパノラマの様に開け、正面には中ノ岳、左には御月山、右には兎岳から丹後山へと雄大な眺めに飽きる事はありません。日向山を下ると、池塘のある草地に出ます。一帯は生姜畑と呼ばれる鉱山の跡地です。 池塘と草地を過ぎると六合目。一度鞍部に下り、小ピークをふたつほど越すと七合目の小天上の峰です。左に中ノ岳から八海山に続く険しい稜線を見ながら、池ノ段まできつい登りになります。やせ尾根と転石に注意しながらの登りですが、一歩ずつ確実に高度を上げ展望はますます良くなってきます。やがて一帯の灌木も低くなり、植生はチシマザサに変わります。小さなガレ場を過ぎると、苦しかった急坂も終わり、九合目の池ノ段はすぐです。さらに岩場を進むと中ノ岳頂上へ。下山は往路を野中まで引き返しますが、急な下りと赤土で滑りやすいので、足元には十分注意して下さい。 -
十字峡から丹後山を経て中ノ岳へ
- 1泊2日
- 20時間35分
- 31.8km
十字峡から丹後山を経て中ノ岳へ
- 1泊2日
- 20時間35分
- 31.8km
野中〜十字峡登山センターまでは十字峡から中ノ岳へ(コースガイド)を参照して下さい。 十字峡トンネルを出ると右側に丹後山登山口へ通じる林道ゲートに入ります。これより三国川左岸の林道へ。渓谷美を見ながら約2km歩けば栃ノ木橋に着き、50mほど進むと左手に登山口が見えてきます。頂上まで水場はないので本流で十分用意して登りましょう。右に林道を分け登山道に取り付きます。急な登りがしばらく続き、登りきったあたりから松の木が現われ、ようやく二合目に到着です。急登の連続はここまでとなり、しばらく中ノ岳の展望がきくゆるやかな尾根歩きとなります。この尾根一帯がカモエダズンネ(大きな枝のある木が生えた尾根)です。尾根道を進んで行くと、やがてゴヨウマツの大木が現われ、三合目に到着します。 灌木帯の登りを進んで行くと展望が開け、ジャコノ峰に到着。左手には中ノ岳がいちだんと大きく見え、ひと登りすればジャコ平です。ゆるやかに登って行くと、前方にササの群生が一望でき、やがてシシ岩に着くと八合目となります。道は丹後山山腹を巻くようにゆるくトラバースし、右に越後沢山や巻機連峰などを見ながら進むと、標識です。右は巻機山、左が山頂、直進が「水場」となっていますが巻機山へのコースは整備されていません。また「水場」とある群馬県側は立入り禁止区域ですので、水もあてにしないように。 山頂に向かいコースを左にとり、少し登るとすぐ右側に避難小屋があります。小屋のポリタンクに天水が貯められています。山頂は直進してすぐです。丹後山山頂をきわめ、シラネアオイやニッコウキスゲの群生を見ながら進むと、利根川水源碑があり、大水上山はすぐそこです。 大水上山に立つと利根川水源一帯の山々や、平ヶ岳、荒沢岳の素晴らしい眺望が広がります。これより先の道もよく刈り払いされており、灌木と高山植物が咲き競う美しいコースです。丹後山、大水上山間の稜線の群馬県側には、7月まで雪が残ります。 兎岳のピークを過ぎるとすぐに右に荒沢岳へ向かう分岐があります。左の道を進み急坂を下ります。小兎岳の登りにかかりピークに立つと、シラビソの樹林帯へ。樹林帯を過ぎると最低鞍部へと下って行きます。 鞍部を通過しダケカンバ、ネマガリダケの道を注意しながら進むと、中ノ岳への急登です。岩場の切り立つヤセ尾根を通過すると九合目(池ノ段)へ。ここから十字峡に下る道が左手にあります。中ノ岳をきわめ、野中を目指し十字峡登山センターへと下ります。十字峡への下りは急な上、赤土で滑りやすいので、注意が必要です。野中〜十字峡登山センターまでは十字峡から中ノ岳へ(コースガイド)を参照して下さい。 十字峡トンネルを出ると右側に丹後山登山口へ通じる林道ゲートに入ります。これより三国川左岸の林道へ。渓谷美を見ながら約2km歩けば栃ノ木橋に着き、50mほど進むと左手に登山口が見えてきます。頂上まで水場はないので本流で十分用意して登りましょう。右に林道を分け登山道に取り付きます。急な登りがしばらく続き、登りきったあたりから松の木が現われ、ようやく二合目に到着です。急登の連続はここまでとなり、しばらく中ノ岳の展望がきくゆるやかな尾根歩きとなります。この尾根一帯がカモエダズンネ(大きな枝のある木が生えた尾根)です。尾根道を進んで行くと、やがてゴヨウマツの大木が現われ、三合目に到着します。 灌木帯の登りを進んで行くと展望が開け、ジャコノ峰に到着。左手には中ノ岳がいちだんと大きく見え、ひと登りすればジャコ平です。ゆるやかに登って行くと、前方にササの群生が一望でき、やがてシシ岩に着くと八合目となります。道は丹後山山腹を巻くようにゆるくトラバースし、右に越後沢山や巻機連峰などを見ながら進むと、標識です。右は巻機山、左が山頂、直進が「水場」となっていますが巻機山へのコースは整備されていません。また「水場」とある群馬県側は立入り禁止区域ですので、水もあてにしないように。 山頂に向かいコースを左にとり、少し登るとすぐ右側に避難小屋があります。小屋のポリタンクに天水が貯められています。山頂は直進してすぐです。丹後山山頂をきわめ、シラネアオイやニッコウキスゲの群生を見ながら進むと、利根川水源碑があり、大水上山はすぐそこです。 大水上山に立つと利根川水源一帯の山々や、平ヶ岳、荒沢岳の素晴らしい眺望が広がります。これより先の道もよく刈り払いされており、灌木と高山植物が咲き競う美しいコースです。丹後山、大水上山間の稜線の群馬県側には、7月まで雪が残ります。 兎岳のピークを過ぎるとすぐに右に荒沢岳へ向かう分岐があります。左の道を進み急坂を下ります。小兎岳の登りにかかりピークに立つと、シラビソの樹林帯へ。樹林帯を過ぎると最低鞍部へと下って行きます。 鞍部を通過しダケカンバ、ネマガリダケの道を注意しながら進むと、中ノ岳への急登です。岩場の切り立つヤセ尾根を通過すると九合目(池ノ段)へ。ここから十字峡に下る道が左手にあります。中ノ岳をきわめ、野中を目指し十字峡登山センターへと下ります。十字峡への下りは急な上、赤土で滑りやすいので、注意が必要です。