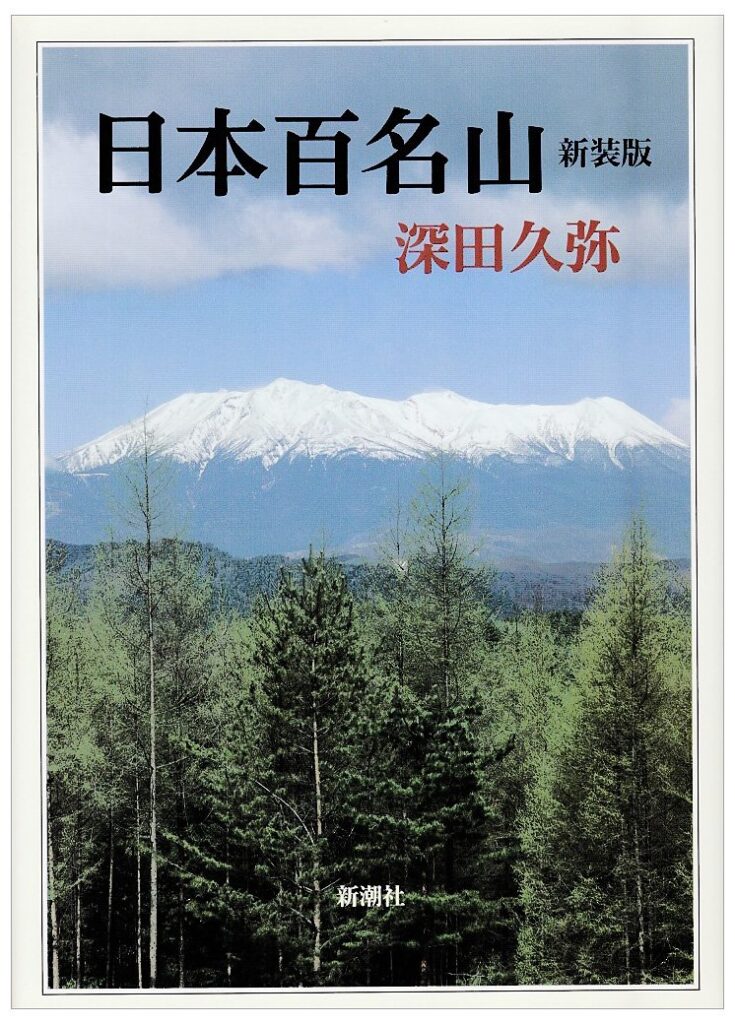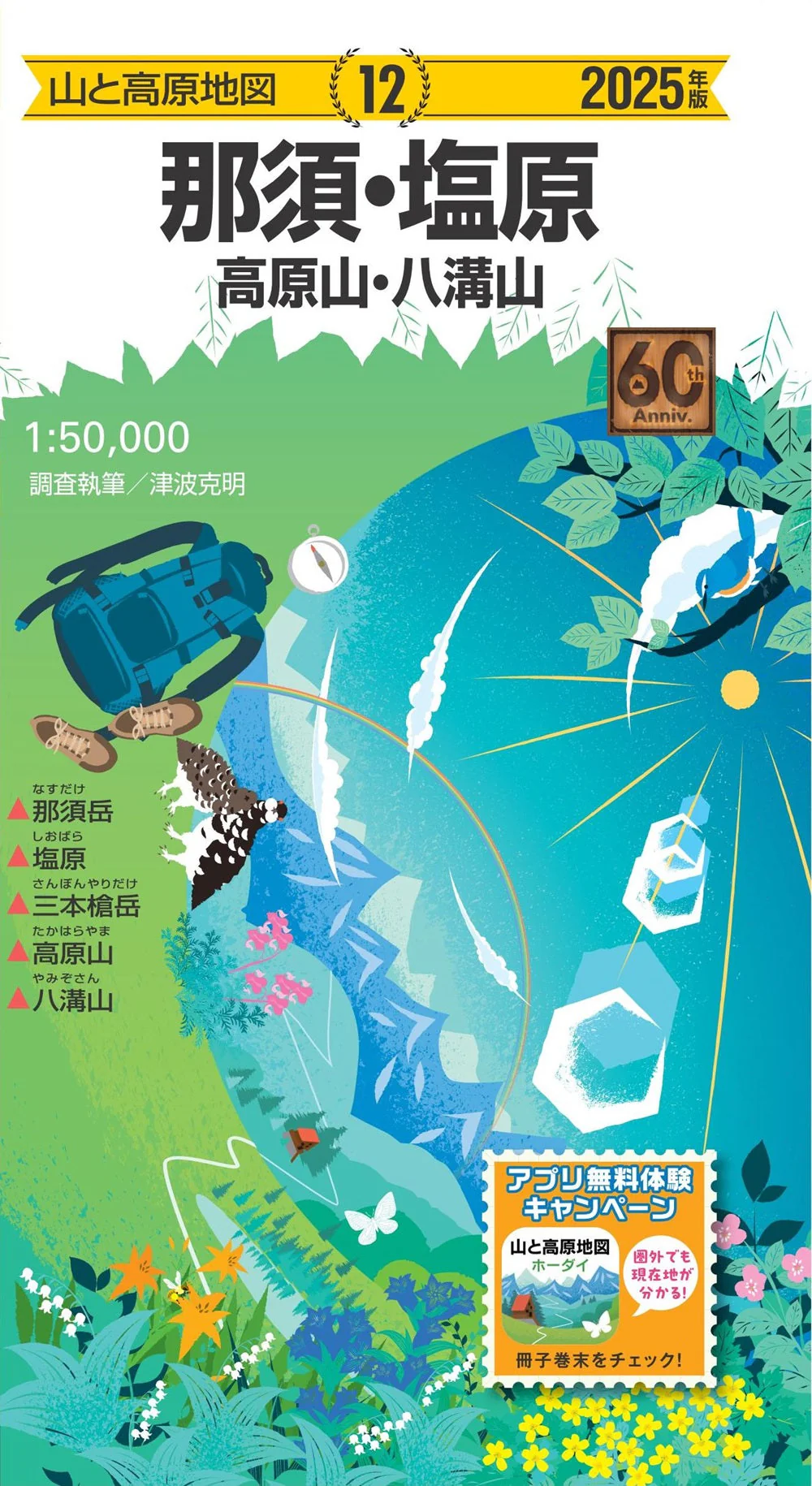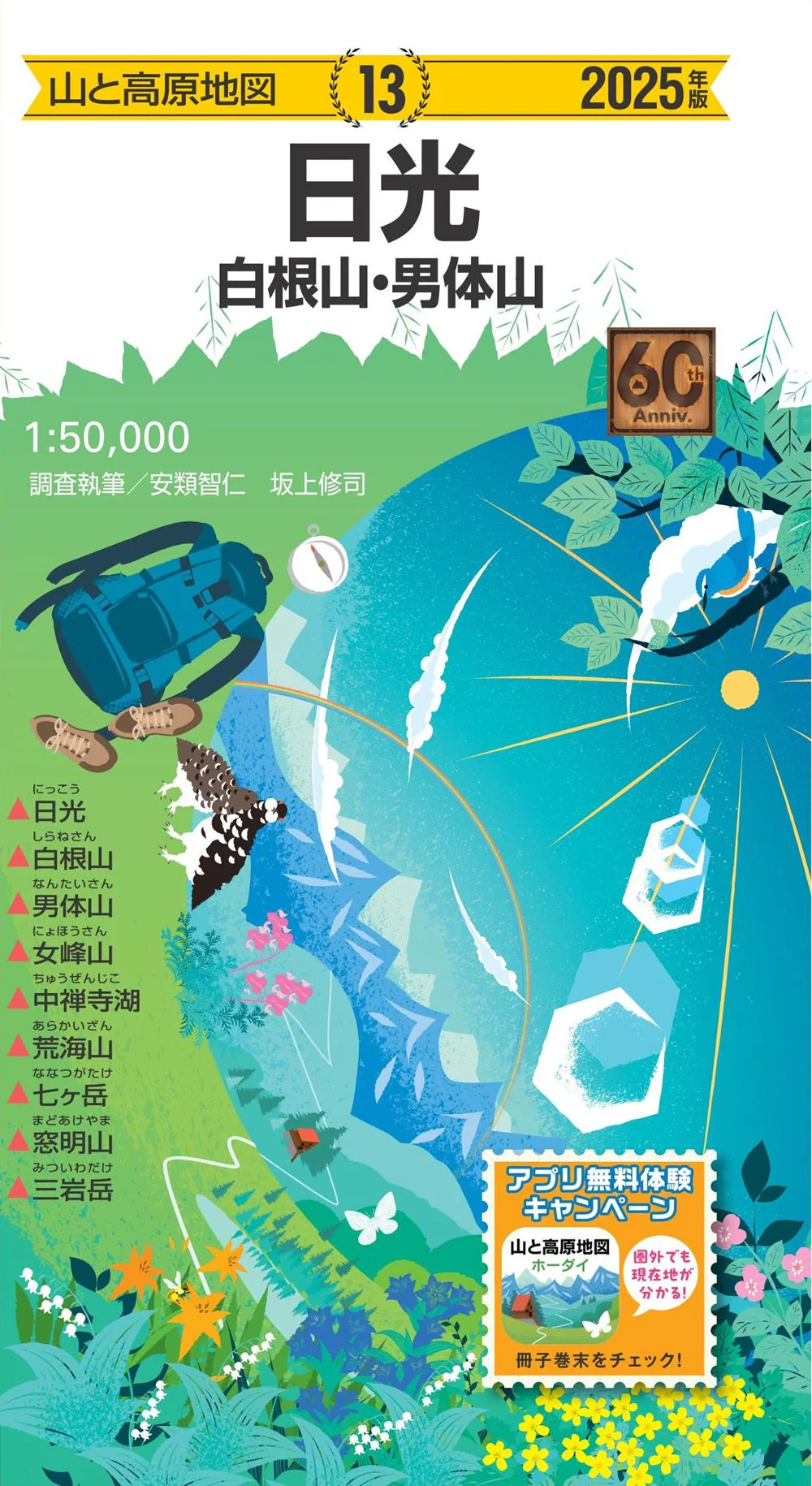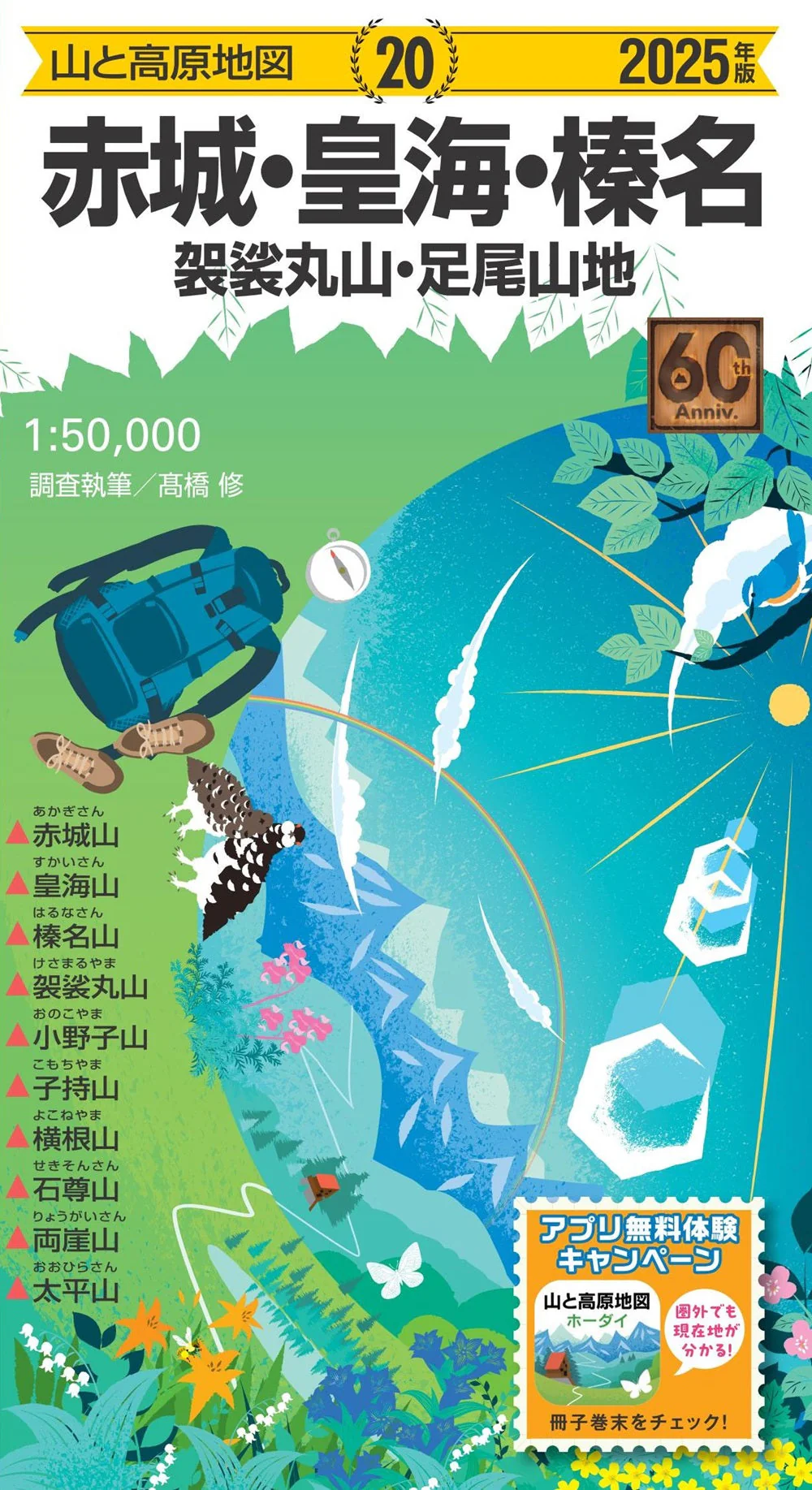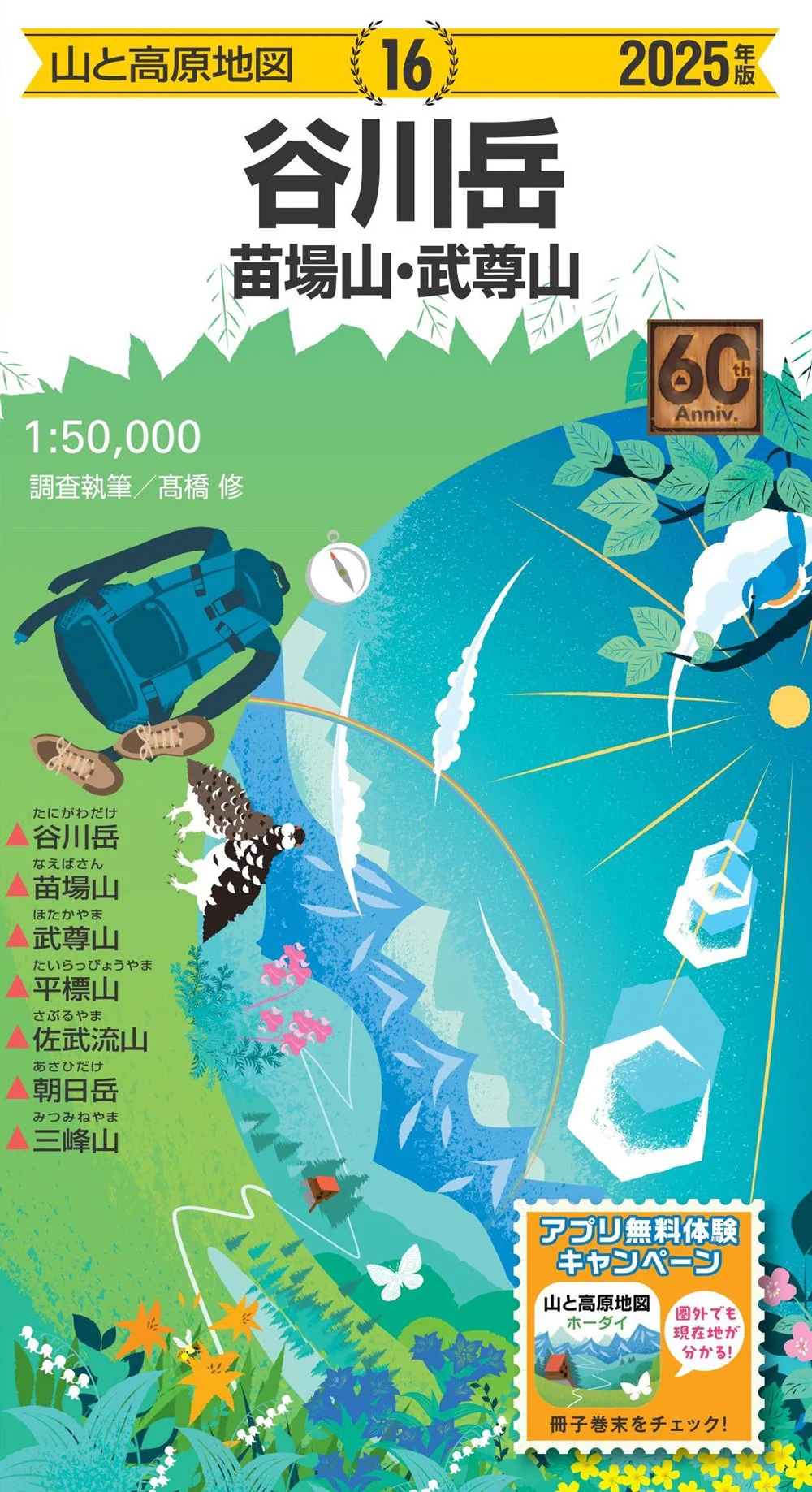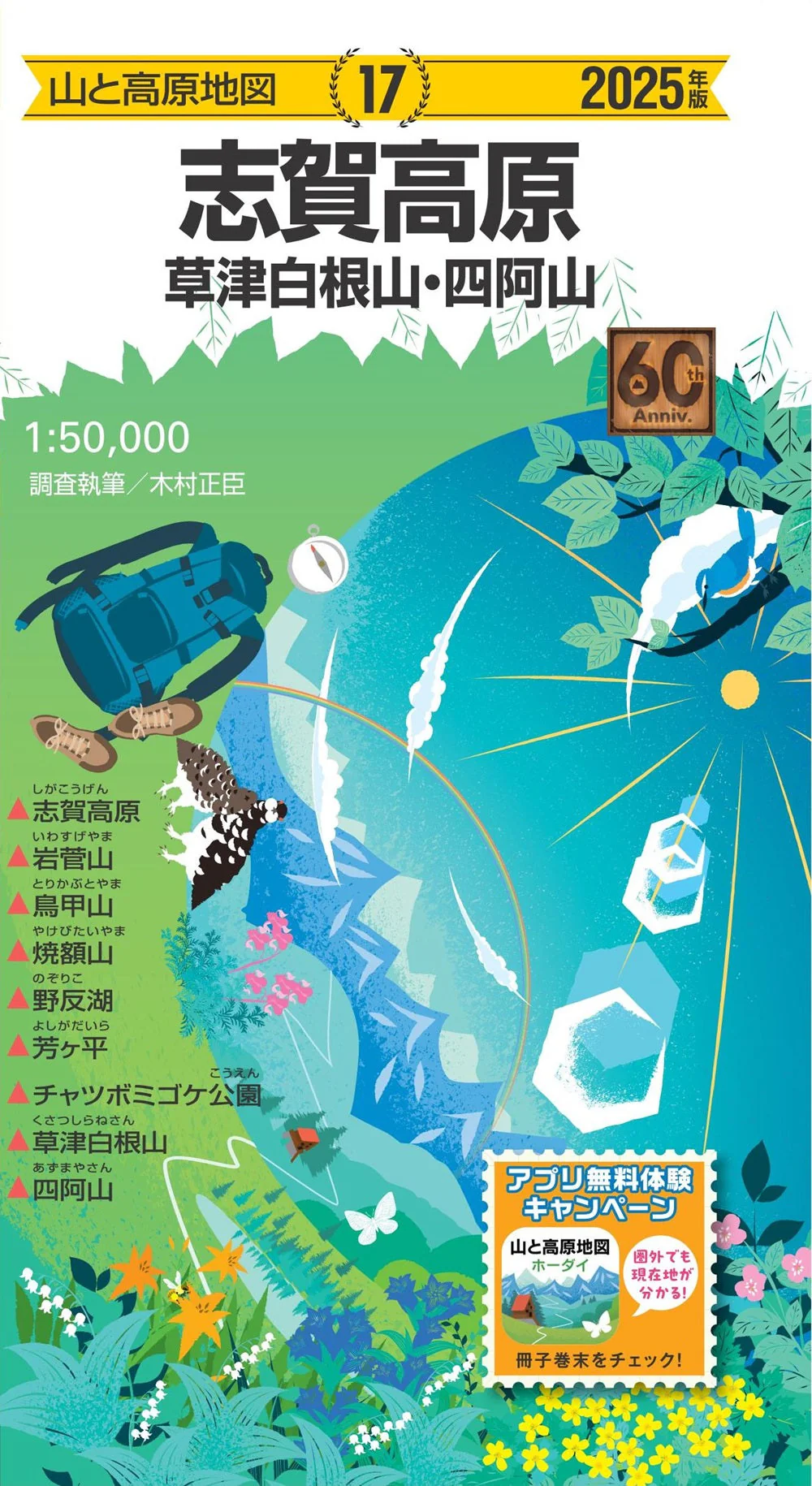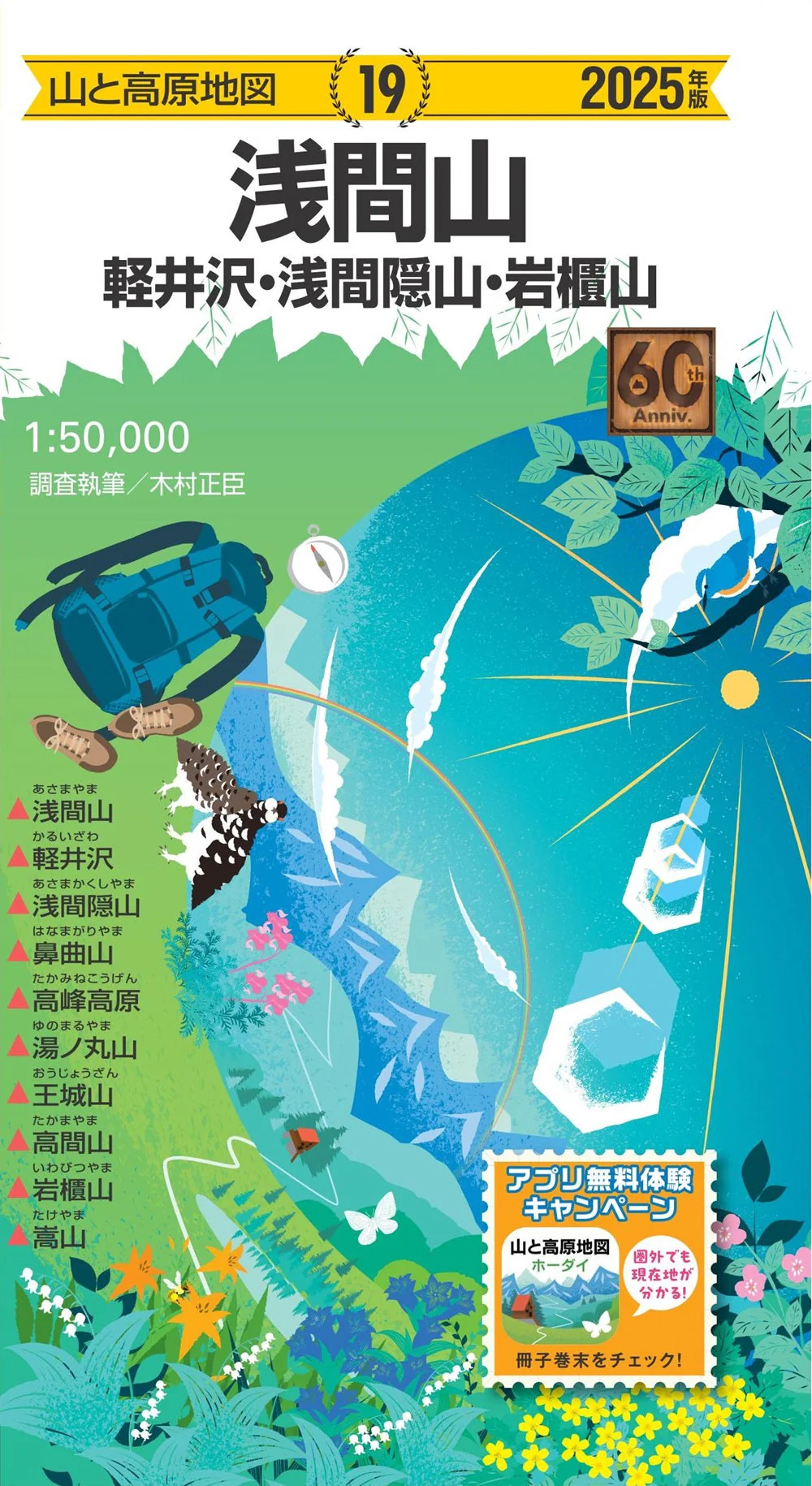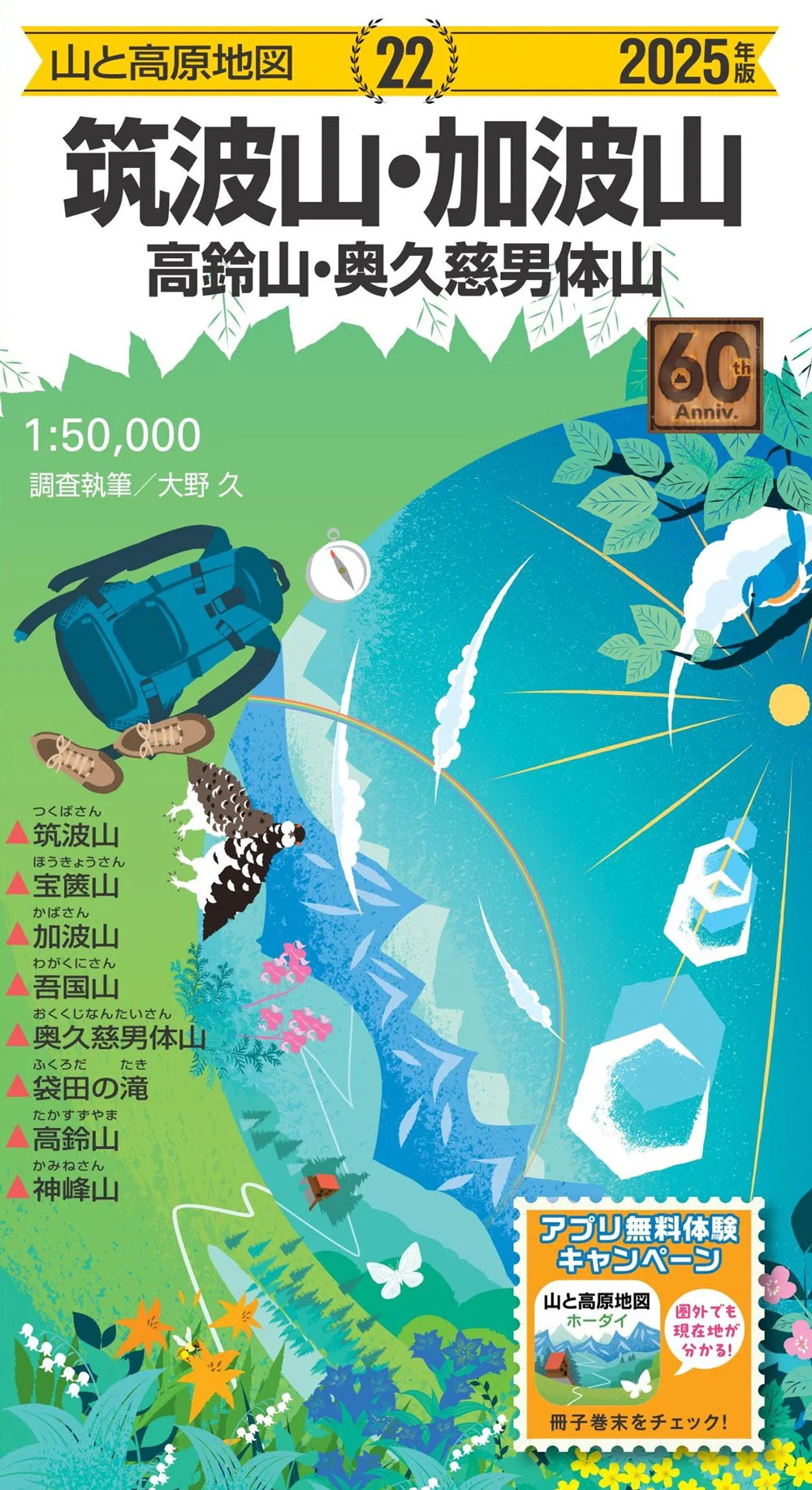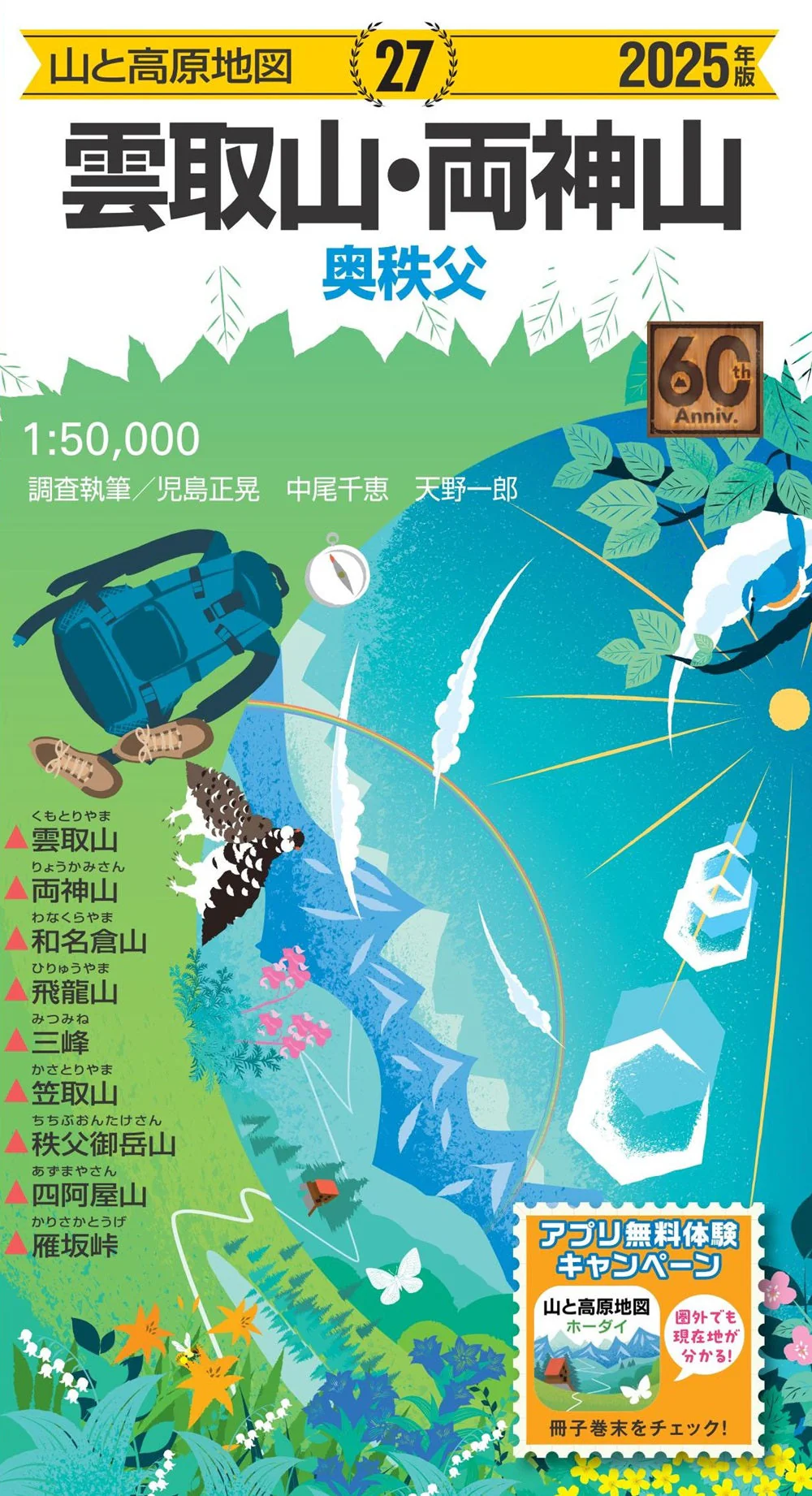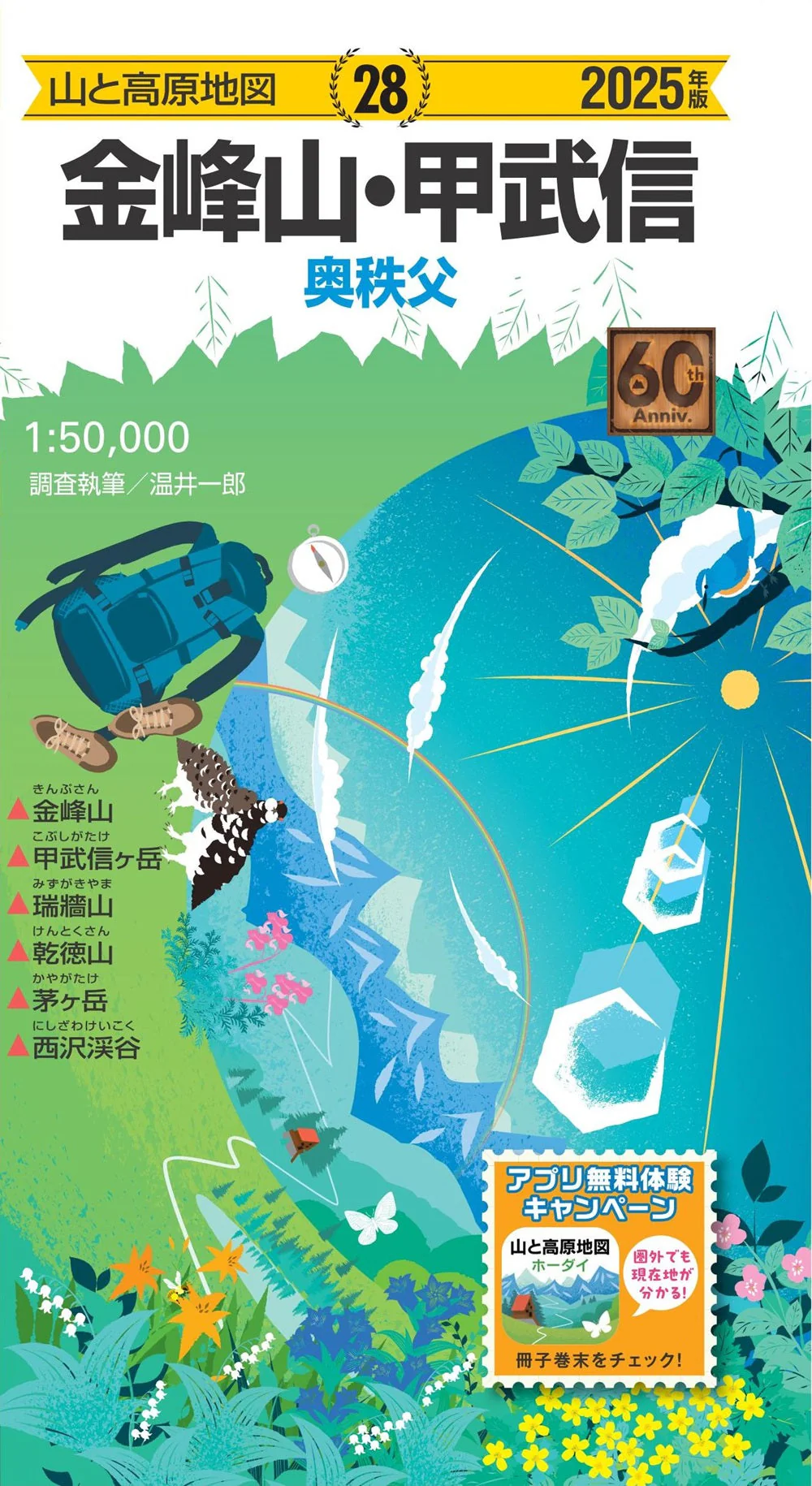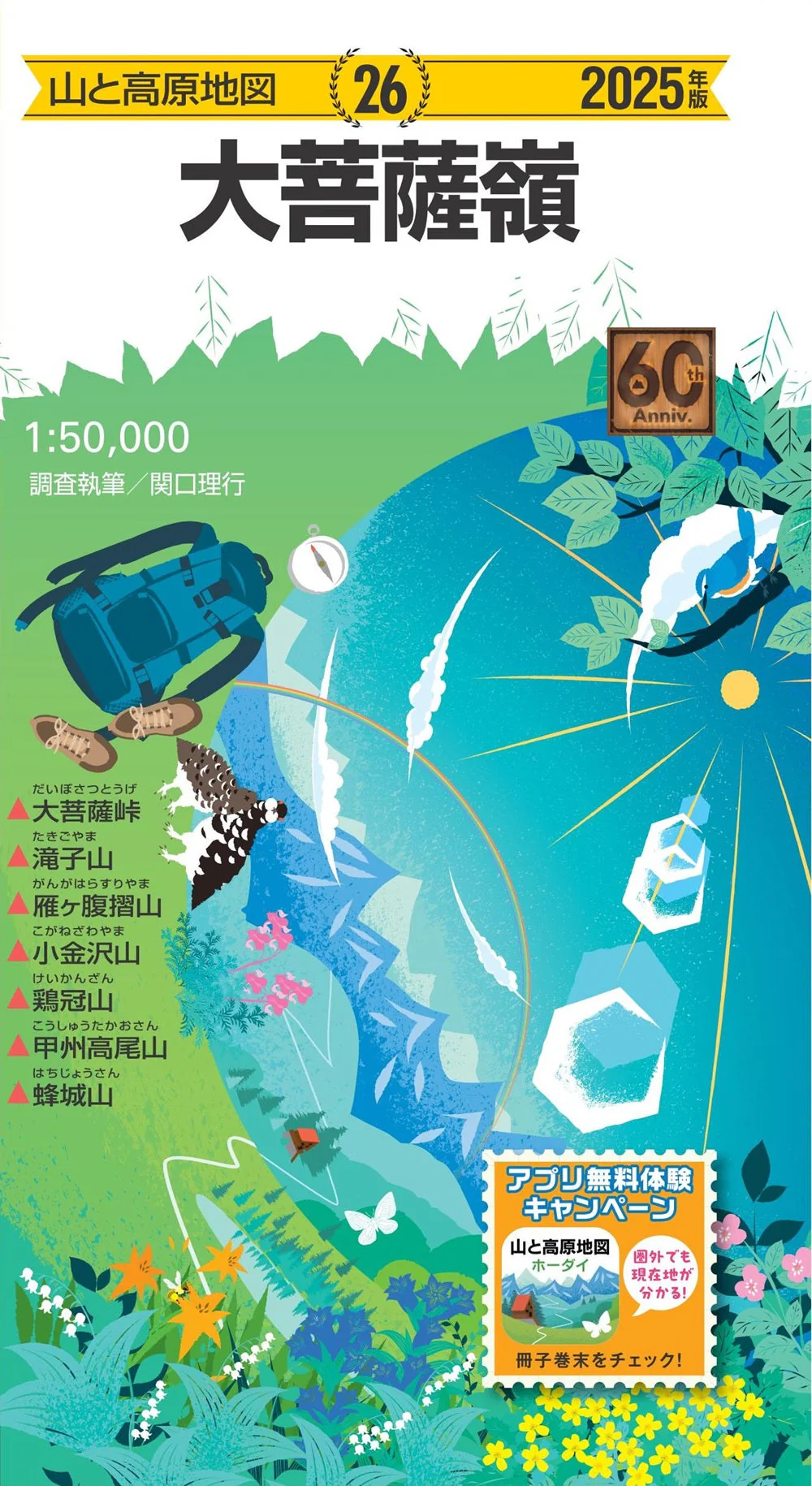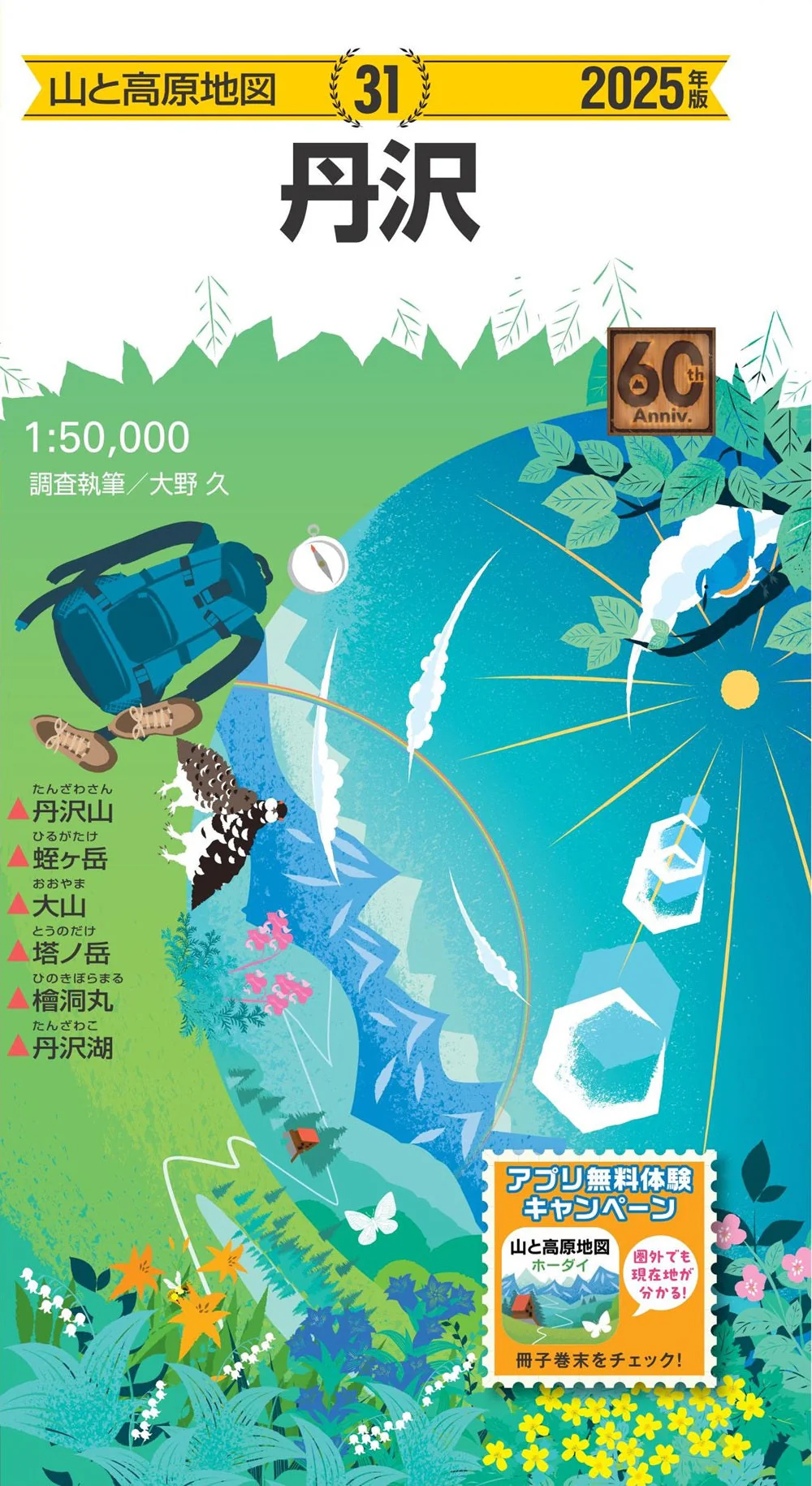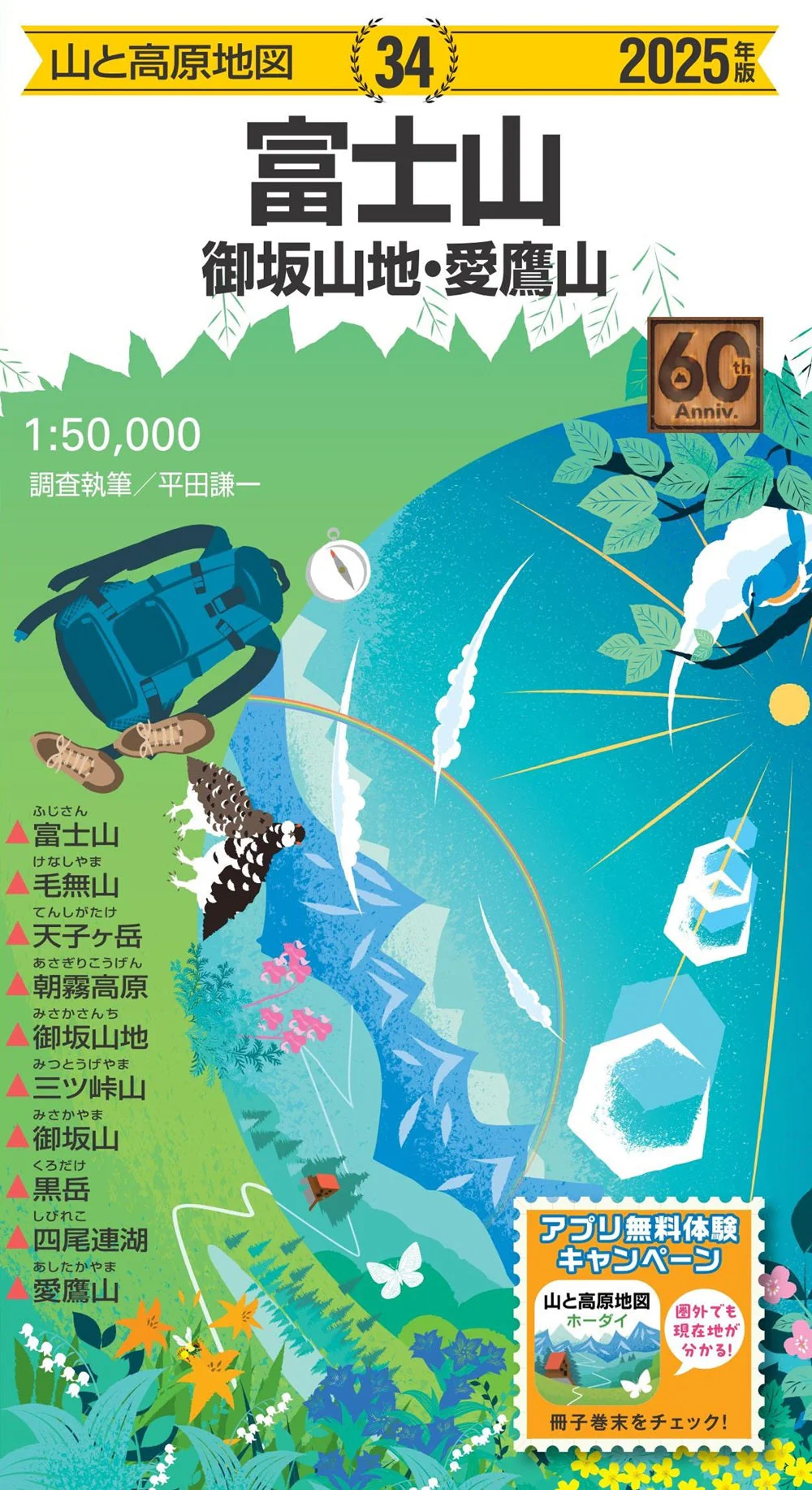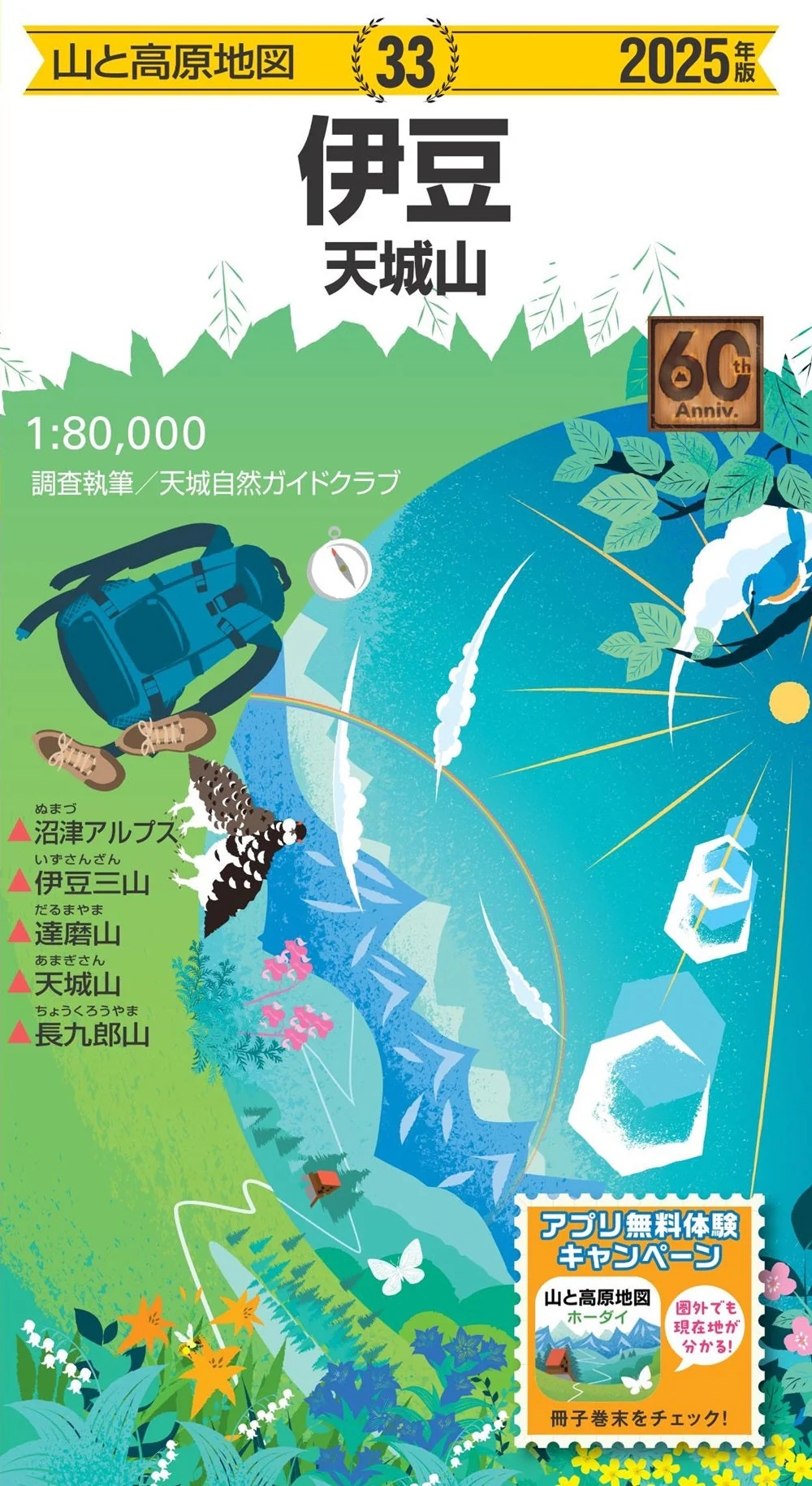関東の百名山19座 名峰に登る、自然と絶景の登山ガイド

関東には日本百名山に選ばれた山が19座あります。火山、岩峰、信仰の山など、個性あふれる山々がそろい、初心者からベテランまで幅広い登山者を魅了しています。
富士山や筑波山のように全国的に知られる名峰に加え、奥多摩や奥秩父の静かな山々、四季の彩りを楽しめる丹沢や赤城など、登山と自然を満喫できる山旅が叶うのも関東の百名山ならではの魅力です。アクセスが良く日帰り可能な山も多く、都市近郊から気軽に出かけられるのもポイントです。
この記事では、関東の百名山19座をすべて紹介。標高や登山シーズン、難易度、アクセス、歴史や山名の由来など、登山の前に知っておきたい情報を詳しく解説します。登山計画の参考に、ぜひ活用してください。
目次
百名山とは?
「日本百名山」とは、作家・深田久弥氏が著書『日本百名山』で選定した、日本を代表する100座の山々のことです。標高の高さだけでなく、「品格・歴史・個性」という基準で選ばれており、それぞれが地理的・文化的な意味を持つ名峰として知られています。
関東の百名山一覧
関東からは全部で19座が選出されており、都市近郊にありながらも、多様な自然と歴史を感じられるのが魅力です。活火山や信仰の山、岩峰の稜線歩きなど、変化に富んだ登山が楽しめるのが関東の百名山ならではの特徴です。
※本記事で紹介する山名と山の番号は、深田久弥著「日本百名山」で紹介されている山名および順番とは異なります
※本記事では関東在住者が登りやすいエリアという視点から、隣接県の百名山も「関東の百名山」に含めて紹介します
北関東の百名山

35.那須岳(茶臼岳) / なすだけ(ちゃうすだけ)
36.男体山 / なんたいさん
37.日光白根山 / にっこうしらねさん
38.皇海山 / すかいさん
39.武尊山 / ほたかやま
40.赤城山(黒檜山) / あかぎさん(くろびさん)
41.草津白根山 / くさつしらねさん
42.四阿山 / あずまやさん
43.浅間山 / あさまやま
44.筑波山 / つくばさん
秩父・南関東の百名山

45.両神山 / りょうかみさん
46.雲取山 / くもとりやま
47.甲武信ヶ岳 / こぶしがたけ
48.金峰山 / きんぷさん
49.瑞牆山 / みずがきやま
50.大菩薩嶺 / だいぼさつれい
51.丹沢山 / たんざわさん
52.富士山(剣ヶ峯) / ふじさん(けんがみね)
53.天城山(万三郎岳) / あまぎさん(ばんざぶろうだけ)
35.那須岳(茶臼岳)|1,915m|中級

栃木県・那須エリアを代表する那須岳は、日本百名山にも選ばれた人気の火山群で、主峰・茶臼岳(ちゃうすだけ)を中心に、朝日岳、三本槍岳などが連なっています。なかでも茶臼岳は、今なお噴煙を上げる活火山。無間地獄(むげんじごく)をはじめとした噴気孔が点在し、火山の鼓動を間近に感じることができます。
ロープウェイで標高約1,680mまでアクセスできるため、初心者でも手軽に登頂できるのが嬉しいポイント。山頂からは那須野が原や関東平野を一望でき、天気が良ければ遠く筑波山まで見渡せる絶景が広がります。
荒々しい岩肌が印象的な朝日岳は「ニセ穂高」とも呼ばれ、アルペン的な雰囲気が漂うエリア。一方、三本槍岳は穏やかな稜線を持ち、広々とした山頂からのパノラマが魅力です。
標高は2,000mに届かないものの、那須岳一帯はハイマツ帯や高山植物が広がり、季節ごとの自然美が楽しめます。春の残雪、夏の新緑、秋の紅葉と、何度訪れても新しい表情に出会える名峰です。
■登山シーズン:6月~10月
■名前の由来:那須岳とは茶臼岳・朝日岳・三本槍岳の総称だが、それに南月山・黒尾谷岳を加えて那須五岳とも呼ぶ。茶臼岳は茶臼に似ていることからその名前がある。三本槍岳は鋭峰を思わせるが、実際は重量感のあるゆったりとした山容。昔、会津と那須・黒羽の3藩が国境を確認するため、5月5日の節句にそれぞれの槍を立てたという故事に由来する。
■アクセス:東北自動車道・那須ICから約17km。
■駐車場:那須ロープウェイ無料駐車場あり(第一、第二、第三駐車場あわせて約150台)。
36.男体山|2,486m|中級

関東一円から美しいプリン型のシルエットで見つけることができる、日光のシンボル的存在の男体山。標高は2486m(※2003年に再測量され、以前より2m高いことが判明)で、その山容の目立つ姿から古くより山岳信仰の対象とされてきました。
山頂には二荒山神社の奥宮が祀られており、登山者を見守るように静かに鎮座しています。男体山の噴火による溶岩が湯川をせき止め、中禅寺湖や戦場ヶ原といった現在の名所をつくり出したともいわれています。
登山道は主に2本。もっとも一般的なのは二荒山神社からの表登山道で、登山期間や入山料の設定があるため、事前の確認は必須です。登山道からは山肌に放射状にのびる“薙(なぎ)”と呼ばれる谷筋や、山頂付近の爆裂火口跡など、火山としてのダイナミックな地形も感じられます。
歴史と自然、そして信仰が深く結びついた男体山は、日光を訪れたらぜひ登っておきたい名峰のひとつです。
■登山シーズン:6月~10月
■名前の由来:男神の大巳貴命(おおなむちのみこと)を祭ることに由来すると思われる。別名にニ荒山、黒髪山、国神山がある。
■アクセス:東北自動車道・宇都宮ICから日光宇都宮道路の清滝ICまで約30km、さらに国道120号を二荒山神社まで約10km。行楽シーズンの土日・祝日は清滝ICからいろは坂が大渋滞することもあります。
■駐車場:二荒山神社境内に無料駐車場あり(70台)。徒歩5分の県営駐車場も。
37.日光白根山|2,578m|中級

栃木県と群馬県の県境にそびえる関東以北の最高峰、標高2,577.6m。日本百名山に選ばれているこの山は、「日光白根山」または「奥白根山」とも呼ばれ、関東周辺からもその堂々としたドーム型の山容がよく目立ちます。
活火山としても知られ、山頂一帯には噴火による爆裂火口跡が広がり、溶岩でできた独特な地形が火山らしい迫力を感じさせます。最後の噴火は1889年(明治22年)と記録されていますが、今もなお生きた山としての存在感を放っています。
登山口としては、丸沼高原や菅沼登山口が人気。どちらのルートも美しい原生林や高山植物に恵まれ、登る楽しみが尽きません。山頂には奥白根神社が祀られており、360度の大パノラマが広がります。周囲の山々や五色沼、さらには日光連山までも見渡せる絶景が魅力です。
■登山シーズン:6月~10月
■名前の由来:周辺の山では積雪量が多く、それに由来する名前であろう。周囲の山が解けてしまった5月でも、たっぷりと雪をまとっている。
■アクセス:関越自動車道・沼田ICから約38km。
■駐車場:丸沼高原スキー場に無料駐車場あり。
38.皇海山|2,144m|上級

群馬・栃木県境に位置し、奥深い足尾山地にたたずむ日本百名山のひとつ。標高2,144.9mで、台形を思わせるなだらかな山容が特徴です。山頂には「渡良瀬川水源碑」が立ち、今なお広大な原生林に守られた貴重な自然環境が残る静寂の山です。
かつては修験道の霊場として信仰を集め、現在も登山道にはその名残として「当山開祖 木林惟一」と刻まれた青銅の剣が山頂直下に残されています。登山ルートは長く、足尾側の庚申山荘に前泊してから登るのが一般的。無人の山小屋ですが整備されており、庚申山や袈裟丸山などを縦走しながら歩くことも可能です。
山域一帯には、信仰の歴史を感じさせる石碑や銅像が点在し、静かな山歩きの中で深い歴史と自然の豊かさに触れられるのが魅力。アクセスや体力的にはやや上級向けながら、静けさと奥深さに満ちた旅が楽しめます。
■登山シーズン:6月~10月
■名前の由来:難読山名である。深田久弥の『日本百名山』によると、小暮理太郎の考証だとして山名の由来があり、それによると、昔はサク山、笄山と呼ばれ、それが皇開に、皇海になり、皇はスメと読めるからスカイになった、という。深田自身は「サク山は笏山からきたのではないか」と述べている。
■アクセス:北関東自動車道・太田桐生ICから約50㎞。国道122号をわたらせ渓谷鐵道沿いに北上、原向駅の先で県道に入り、かじか荘を目指す。
■駐車場:登山口近くに建つ国民宿舎かじか荘を過ぎるとすぐ、登山者用の駐車場がある(20台)。
39.武尊山|2,158m|中級~上級

群馬県北部にそびえる武尊山は、谷川連峰や尾瀬、赤城山に囲まれた山域に位置する大きな火山で、「上州武尊山」とも呼ばれています。その名のとおり、日本武尊(ヤマトタケルノミコト)の東征伝説にまつわる信仰の山でもあり、神秘的な雰囲気を漂わせる山です。
山頂部は複数の峰に分かれ、森林限界を越えた稜線は岩場が連続するスリリングな登山ルートが魅力。標高は2,158mと高く、頂からは谷川連峰や日光連山、遠くに浅間山を望む大パノラマが広がります。
登山道はいくつかありますが、全体的に行程が長く、公共交通の便も限られているため、しっかりとした登山計画が必要です。中腹にはブナ林が広がり、山腹の玉原湿原や鹿俣山、尼ヶ禿山といった周辺の低山もセットで楽しめるエリアとなっています。
■登山シーズン:6月~10月
■名前の由来:北アルプスの穂高岳と区別するために上州武尊山と呼ばれる。山名は、日本武尊が東征の祈りに登ったという伝説に由来するというが、「ほたか」と難読させるのはなぜだろうか。
■アクセス:関越自動車道・沼田ICから約30km。夏山リフト利用者に限り、ほたか牧場キャンプ場下の駐車場まで入ることができます。事前に確認のこと。
■駐車場:武尊牧場周辺に駐車場あり(100台)。
40.赤城山|1,828m|中級

群馬県のほぼ中央、関東平野の北端に位置する赤城山は、広大な裾野を持つ成層火山で、「赤城山」という特定の山頂があるわけではなく、最高峰の黒檜山(くろびさん)をはじめ、地蔵岳や鈴ヶ岳、長七郎山など複数のピークからなる山域全体を指します。
標高1,828mの黒檜山は、赤城山系の主峰で、山頂までの登山道もよく整備されており、初心者から経験者まで多くの登山者に親しまれています。山頂付近まで車でアクセスできるため、気軽に本格的な山の自然に触れられるのも人気の理由です。
春にはアカヤシオやシロヤシオ、レンゲツツジなど多彩なツツジが咲き誇り、夏は深緑、秋は紅葉と、四季折々の表情を見せる花の名所としても知られています。登山ルートのバリエーションが豊富で、静かな森歩きから眺望重視の稜線歩きまで、自分のスタイルに合った楽しみ方ができる一座です。
■登山シーズン:5月~11月
■アクセス:関越自動車道・赤城ICから約32km。駐車場は黒檜山登山口から駒ヶ岳登山口まで数箇所。観光客の迷惑にならないように停めましょう。
■駐車場:黒檜山登山口、駒ヶ岳登山口に駐車場あり(それぞれ数十台)。
41.草津白根山|2,160m

群馬県の名湯・草津温泉の背後にそびえる草津白根山は、逢ノ峰(あいのみね)、本白根山、白根山の三つの峰を総称した活火山で、日本百名山にも名を連ねています。山全体に火山ならではの荒々しい風景が広がり、むき出しの地肌からは今もなお硫黄の香りが立ち込める場所もあります。
なかでも注目したいのが、北東斜面に広がる芳ヶ平湿地群(よしがだいらしっちぐん)。ラムサール条約にも登録されたこの湿地帯では、高山植物と湿原の織りなす豊かな自然美を堪能できます。荒涼とした火山景観とのコントラストが見事で、ハイカーを魅了するスポットです。
本白根山は近年も火山活動を続けており、2018年1月には突発的な水蒸気噴火が発生。そのため、登山の際は気象庁や地元自治体による最新情報の確認が必須となります。安全を確保しながら、唯一無二のダイナミックな火山の風景を楽しんでみてください。
■登山シーズン:5月~10月
■アクセス:関越自動車道・渋川伊香保ICから、約60km。上信越自動車道・上田菅平ICから、約51km。
■駐車場:殺生河原に無料駐車場あり。
42.四阿山|2,354m|中級

長野県と群馬県の県境に位置する四阿山は、なだらかな裾野と端正な山容が特徴の独立峰。標高2,354mを誇り、日本百名山にも名を連ねる名峰です。麓の嬬恋村や菅平高原から仰ぐ姿は美しく、どの角度から見ても山らしい“理想のカタチ”ともいえる風格を備えています。
「四阿山」は長野県側での呼び名で、群馬県側では「吾妻山(あづまやま)」とも呼ばれてきました。いくつもの登山ルートが整備され、季節を問わず多くの登山者が訪れます。特に春から秋にかけては、山麓に広がる高原キャベツ畑や草原が彩りを添え、ハイキング気分でも楽しめるのが魅力です。
山頂には古くから水の神を祀る祠が建ち、今も信仰の山としての面影を色濃く残しています。登山道には「花童子通り」など歴史を感じさせる名が付けられた箇所もあり、道中に点在する石祠や石室からも、かつての人々の祈りが感じられます。
山頂からは浅間山や草津白根山、谷川連峰など、信州・上州の名山を一望。ゆるやかな山容と深い歴史をあわせ持つ、心が洗われるような一座です。
■登山シーズン:6月~10月
■名前の由来:四阿山は山の形が東屋に似ているのでその名が付いた。別綴に吾妻山・吾嬬山などがある。根子岳は、遠くから四阿山と一緒に見ると、猫の耳に似ているのでその名があるという。
■アクセス:上信越自動車道・上田菅平ICを下車。国道144号を真田・菅平方面へ。国道406号を経由して菅平牧場へ。約20km。
■駐車場:駐車場は菅平牧場内、登山口すぐ手前にあり。なお、菅平牧場へ入場する際に入園料200 円(大人1名)が必要。
43.浅間山|2,568m

長野県と群馬県の県境にそびえる浅間山は、標高2,568mのコニーデ型火山で、日本百名山の中でもひときわ存在感を放つ活火山です。均整の取れた美しい山容は、どの方角から眺めても登山者の心を惹きつけ、古くから「火を噴く山=アサマ」として畏れと敬意を集めてきました。
浅間山は、噴火を繰り返してきた歴史を持ち、近年では2009年にも小規模な噴火が確認されています。登山規制が敷かれていることも多いため、登山を計画する際は最新情報の確認が必須です。火口周辺には「千トン岩」と呼ばれる巨大な噴石があり、1950年の噴火で火口から吹き飛ばされたその姿が、浅間山の火山としての力強さを物語ります。
軽井沢や嬬恋、浅間高原からもよく見え、地域のシンボルとして親しまれる一方で、噴火の歴史や火山活動のダイナミズムを肌で感じることができる貴重な山です。近隣には高原のリゾート地も点在し、登山と観光をあわせて楽しむ人も多く訪れます。
■登山シーズン:5月~11月
■名前の由来:地名辞典によると「あさま」は火山や温泉に関係しているという。黒斑山は三ッ尾根山とも呼ばれ、浅間山第一外輪山の最高峰。
■アクセス:上信越自動車道・小諸ICから浅間サンライン(浅間山麓広域農道)、チェリーパークラインをへて車坂峠へ。約16km。
■駐車場:ビジターセンター下に無料駐車場あり(50 台)。
44.筑波山|877m|中級

関東平野の北端にそびえる筑波山は、標高こそ877mと控えめながら、古来より「西の富士、東の筑波」と並び称される名峰です。山頂部は男体山と女体山の2つの峰からなる双耳峰で、山容は見る角度によって姿を変えるのも魅力のひとつ。
古くから山岳信仰の対象とされ、山全体が筑波山神社の御神体とされてきました。主峰の女体山をはじめ、山中には数多くの磐座や祠が点在し、神秘的な雰囲気が漂います。
標高が低いため登りやすく、各方面から複数の登山道が整備されており、四季を通じて多くのハイカーが訪れます。特に春の新緑や秋の紅葉、また梅やツツジといった花のシーズンは、登山道が華やぎます。さらに、山頂付近までロープウェイやケーブルカーでアクセスできるため、体力に自信のない人でも気軽に登頂可能です。
双耳峰の間に広がる御幸ヶ原からは、関東平野を一望でき、晴れた日には東京スカイツリーや富士山まで見渡せることも。自然と信仰、展望が一体となった筑波山は、登山初心者にも、歴史や文化に興味のある人にもおすすめの一座です。
■登山シーズン:1月、3月~6月、9月~12月
■名前の由来:筑波岳、筑波嶺、筑波禰、筑波乃山などの別称があり、「紫の山」の愛称もある。由来は聳え立つ意味のアイヌ語のツクバから来た説、月の神が鎮座する平野の意味からツクハが生まれた説などがある。
■アクセス:常磐自動車道・谷田部ICから約30km。土浦北ICからも便利。つつじが丘に直接行く場合は筑波スカイラインを通っていくルートも。
■駐車場:どちらの登山口にも駐車場あり。ほとんどの駐車場は有料。
45.両神山|1,723m|中級~上級

奥秩父北東部にそびえる両神山(1,723m)は、鋸歯状の岩稜が連なる独特の山容で、どの方角から見てもひと目でわかる存在感を放ちます。標高以上に“カッコいい山”と称され、日本百名山にも選ばれています。
山名の由来には諸説あり、イザナギ・イザナミを祀った「両神説」や、日本武尊が八日間見つめた「八日見説」などが伝わります。登山道には石碑や石像が点在し、古くから信仰の山として親しまれてきた歴史を感じさせます。
最もポピュラーな日向大谷口ルートは、鎖場や岩場が連続する登りごたえのあるルート。八丁峠からのコースはより急峻で、経験者向きです。春のアカヤシオ、初夏の新緑、秋の紅葉と四季の彩りも豊かで、山頂からは奥秩父の山々や遠く北アルプスまで望むことができます。
信仰と自然の厳しさが調和した、奥秩父を代表する名峰です。
■登山シーズン:5月~11月上旬
■名前の由来:イザナミ・イザナギの2神を祭るから両神山だという伝えがあるが、日本武尊が戦勝祈願で筑波山へ登る途中、西方に8日間も見え続けた山に因んだ八日見山という伝えのほかに、竜神山、竜頭山など、多くの呼び名と伝説を秘めた山。
■アクセス:秩父市内から国道299号、小鹿野バイパスから県道37号、県道279号へ。県道279 号は狭くカーブが多いので、山道のドライブに慣れていないと要注意。
■駐車場:日向大谷口の駐車場は4箇所。バス停100m手前とバス停付近、有料の駐車場が林道終点付近にあります。すべての駐車場を合わせて約50台。
46.雲取山|2,017m|中級~上級

雲取山は、東京都・埼玉県・山梨県の三都県境に位置し、標高2,017mで東京都の最高峰。奥多摩と奥秩父をつなぐ縦走の要所にあり、北東には長沢背稜、南東には石尾根、西には奥秩父主脈が延びる、登山道が交差する“山の十字路”です。
山頂付近には原生林が広がり、静かで深い森の中を歩くひとときは、まさに都会の喧騒を忘れさせてくれます。登りきった先に待つ大パノラマは圧巻で、東京都心方面から丹沢、道志、御坂山地、さらには南アルプスや富士山までも望める絶景が広がります。展望の良さはこの山域でも随一といわれ、日本百名山に選ばれているのも納得の名峰です。
登山ルートも豊富で、奥多摩側の鴨沢ルートはアクセスがよく、初めての2000m級にもおすすめ。一方、三峰神社や丹波山村方面からのコースはやや健脚向けで、縦走の起点としても人気があります。
また、この山域は荒川や多摩川の源流域としても重要で、首都・東京の水源を育む役割も担っています。自然と人々の暮らしを支える、奥多摩・奥秩父のランドマークです。
■登山シーズン:5月~11月上旬
■名前の由来:『武蔵名勝図絵』では、日原村の項目で「大雲取山村の西にあり。甲斐丹波村と秩父郡大血川村の堺によれり。この辺は悉く高山なれど、わけてこの山は峻峰にして、雲をも手に取るが如く思うというより斯くは号するなり。」と説明している。古い文献を漁ると「雲取山から導かれた」としたものもあり、「雲採」の文字も見られる。
■アクセス:中央自動車道・上野原ICから約32km。
■駐車場:国道411号から車で5分ほどの場所に村営登山者駐車場あり(30台)。
47.甲武信ヶ岳|2,475m|中級~上級

甲武信ヶ岳は、山梨・埼玉・長野の三県にまたがり、奥秩父主脈のほぼ中央に位置する日本百名山。山名は、甲斐(山梨)、武蔵(埼玉)、信濃(長野)から一字ずつ取って名づけられたものです。かつてはその山容から「拳岳(こぶしだけ)」とも呼ばれた独特な姿をしています。
この山は、日本を代表する三大河川――信濃川(千曲川)、荒川、富士川――の源流域にあたり、水の山としての重要な役割も果たしています。分水嶺となる尾根が三方向から集まり、それぞれが登山道として整備されているため、アクセスルートが豊富なのも特徴です。
特に、南側に源を発する笛吹川東沢は、ナメ滝の流れや広葉樹の美しい森が広がり、沢登りの名ルートとしても知られています。山頂からは奥秩父の山々を一望でき、静かで奥深い山の魅力を存分に味わうことができます。
三宝山や木賊山などに囲まれながらも、甲武信ヶ岳が“奥秩父の中心”として名高いのは、地理的にも登山的にもその存在感が際立っているからこそ。静けさとスケールの大きさが共存する、奥秩父の真髄を感じられる一座です。
■登山シーズン:5月~11月上旬
■名前の由来:別訓を「こうぶしんだけ」とした辞典がある。山名は甲斐・武蔵・信濃の3境の合成説が一般的だが、コブシに似た山容から拳ヶ岳、また三方山、三国山など名前もある。
■アクセス:中央自動車道・勝沼ICから約26km。
■駐車場:西沢渓谷入口の道の駅みとみに無料駐車場あり(30台)。
48.金峰山|2,599m|中級

奥秩父主脈の西部に位置する金峰山は、標高2,599m。わずかに北奥千丈岳に標高こそ及びませんが、その秀麗な山容と変化に富んだ山稜から「奥秩父の盟主」とも称される名峰です。
山頂に立てば、ひときわ目を引く巨岩「五丈岩」が鎮座し、まるで山の守り神のような存在感を放っています。この岩は、周囲の山々からも確認できるほど象徴的で、金峰山のランドマークとして親しまれています。
かつては修験道の霊場として信仰を集めていた歴史もありますが、現在ではその面影は薄れ、登山者たちにとっては雄大な自然を体感できる人気の山となっています。変化に富んだ稜線歩きと大展望が魅力の、何度でも歩きたくなる一座です。
■登山シーズン:5月~11月上旬
■名前の由来:奈良の吉野山の一峰、金峰山の蔵王権現を分祀したことによるという。幾日峰の別称もある。
■アクセス:中央自動車道・勝沼ICから塩山フルーツライン、県営林道川上牧丘線経由で約40km。冬期は通行止めになるので注意。
■駐車場:大弛峠に無料駐車場あり(20台)。
49.瑞牆山|2,230m|中級

標高2,230mの瑞牆山は、金峰山の北西に位置し、奥秩父の中でもひときわ個性的な山容を持つ百名山。針葉樹林に囲まれた山肌から、無数の奇岩・巨岩が突き出すように林立し、圧倒的な存在感を放ちます。全体が花崗岩で形成されたこの山は、どこを見ても独特の景観が楽しめるのが魅力です。
登山口からのアプローチもよく、日帰りで登頂できることから、初心者からベテランまで多くの登山者に親しまれています。特に新緑と紅葉のシーズンには、その美しさを求めて多くの人が訪れます。
山麓には林道や宿泊施設が整備されており、観光拠点としての利便性も抜群。個性的な山を歩いてみたい方にぜひ訪れてほしい、奥秩父の名峰です。
■登山シーズン:5月~11月上旬
■名前の由来:難読山名の代表。『日本の山々』の原全教氏によると、明治時代に山梨県の武田知事が名付け親だそうだ、とある。地元では瘤岩と呼んでいた。麓の金山平は、武田信玄の時代に金山があり、金山千軒と称された。
■アクセス:中央自動車道・須玉IC から約25km。
■駐車場:瑞牆山荘近くに無料駐車場2 箇所あり(約120台)。
50.大菩薩嶺|2,057m|初級~中級

標高2,057mの大菩薩嶺は、百名山にも選ばれている大菩薩山系の主峰。本州のほぼ中央に位置し、富士川・多摩川・相模川の源流域にあたる自然豊かなエリアに広がっています。
花崗岩の地質が風化してできたなだらかな地形が特徴で、山頂付近の稜線は笹原や草原が広がり、夏には多くの高山植物が咲き誇ります。展望も抜群で、稜線からは富士山や南アルプスを望む大パノラマが楽しめます。
上日川峠からのアクセスは良好で、山頂付近まで車道が整備されているため、登山初心者やファミリーでも気軽に訪れることができるのも魅力。ただし、標高2000mを超えるため、天候が急変することもあり、防寒具や雨具などの装備はしっかりと準備しておきましょう。
■登山シーズン:5月~11月
■名前の由来:大菩薩峠周辺は、昔は萩原山と呼ばれていたが、『小菅村郷土誌』では神部山だったという。大菩薩の名前が生まれたのは、源義家の弟新羅三郎義光(甲斐源氏の祖)が、奥州遠征の祈りに「北斗妙見菩薩」を唱えたことからその名前が付いたと伝わる。妙見ノ頭という石碑が現存する。
■アクセス:中央自動車道・勝沼ICから約18km。
■駐車場:上日川峠に無料駐車場あり(120台)。
51.丹沢山|1,567m|上級

神奈川県西部に広がる丹沢山地の一角にある丹沢山は、かつて「三境ノ峰」とも呼ばれた歴史ある山で、秦野市・相模原市緑区・山北町の境に位置しています。標高は1,567mで、展望には恵まれないものの、ブナ林を中心とした原生林に包まれた静かな雰囲気が魅力です。
春のバイケイソウの芽吹き、初夏のツツジ、秋の紅葉、冬の霧氷など、四季を通じて美しい自然が楽しめる丹沢山。首都圏からアクセスしやすく、自然の中でリフレッシュしたい登山者に親しまれています。
なお、百名山に選ばれた「丹沢山」は、山そのものよりも丹沢山地全体を象徴する存在としての評価によるもの。実際には、丹沢山地の最高峰は東隣の蛭ヶ岳(1,673m)ですが、静けさを求めるなら丹沢山のほうが落ち着いた山歩きが楽しめます。
■登山シーズン:4月~11月
■名前の由来:丹沢山の名前は、明治時代の陸地測量で、ここへ1等三角点を置き、仮称として丹沢山の名前を用いたのが定着したという。蛭ヶ岳は、猟師が使う山頭巾をヒルと呼び、それに山容が似ているからという説、山蛭が多かったことに由来する説などがあり、別称に薬師岳がある。これは山頂に薬師如来を祭ったことによる。毘慮ヶ岳の文字も見られる。
■アクセス:東名高速・秦野中井ICから大倉まで約10km。西丹沢自然教室から東名高速・大井松田ICまでは約30km。
■駐車場:大倉に登山者用有料駐車場あり(約150台)。西丹沢ビジターセンターに駐車場あり(20台)。
52.富士山(剣ヶ峯)|3,776m|中級

標高3,776m、日本一の高さを誇る富士山は、誰もが知る国民的な山。円錐形の美しい山容は、成層火山(コニーデ型火山)ならではの優雅さと迫力を兼ね備え、どの方向から眺めても圧倒的な存在感を放ちます。その端正な姿は古くから信仰の対象とされ、多くの絵画や詩歌にも描かれてきました。
登山ルートは吉田・須走・御殿場・富士宮の4ルートが整備されており、いずれも五合目まで車でアクセス可能。登山道の途中には山小屋や休憩所も点在し、初心者から経験者まで幅広く挑戦できます。また、山麓から五合目までを結ぶ旧登山道や、自然休養林内に整備されたハイキングコースもあり、頂を目指さなくとも富士山の自然に触れる楽しみ方も充実しています。
2013年には「富士山―信仰の対象と芸術の源泉」として世界文化遺産に登録され、国内外から多くの登山者・観光客を惹きつけています。一方で、登山時期や入山規制など最新の情報を確認することも重要。自然環境や信仰の歴史に敬意を払いながら、この特別な山に向き合いましょう。
■登山シーズン:7月~8月
■アクセス:中央自動車道・河口湖ICから富士スバルラインで五合目まで28km。
■駐車場:登山口近くに無料駐車場あり(330 台)。
53.天城山(万三郎岳)|1,406m|初級~中級

天城山は、伊豆半島を南北に貫く「天城連山」の総称で、その最高峰が標高1,406mの万三郎岳です。万二郎岳や小岳などの峰々を含み、ゆるやかな山容とブナを中心とした自然林に覆われた静かな山歩きが魅力です。
山頂からは、遠く駿河湾の大海原、そして富士山の雄大な姿を望むことができ、晴れた日には絶好の展望が広がります。登山道の途中では、春のアマギシャクナゲや初夏の新緑、秋の紅葉など、四季折々の自然美にも出会えます。
登山口までの道路は整備されており、アクセスがしやすいのもポイント。周辺には温泉宿や観光施設も点在しており、登山と一緒に旅気分を楽しめるのも天城山ならではの魅力です。自然と癒しが共存する、伊豆の名峰で特別な一日を過ごしてみませんか?
■登山シーズン:4月~12月
■名前の由来:狩野山・尼木山の別名がある。木甘茶を産したので「アマギ」の山の名になったという。天城山と呼ぶ峰はない。
■アクセス:東名高速・沼津IC からスタート地点までは約43km。
■駐車場:二階滝(20台)と天城高原ゴルフ場内(88台)にあります。
関東の百名山で四季の自然と出会おう

関東の百名山は、首都圏からアクセスしやすい立地にありながら、豊かな自然や歴史的な背景を持つ魅力的な山々が揃っています。火山の山肌、信仰の対象となった霊峰、四季折々に表情を変える森林や稜線。どの山にも、それぞれの物語が息づいています。
そして、どの山に挑むにも、安全対策と事前の準備は欠かせません。登山地図ナビアプリ「山と高原地図ホーダイ」を使えば、GPSで現在地を確認しながら登山ができ、初心者でも安心して歩を進められます。
さあ、関東の自然と向き合う山旅へ。心に残る一座との出会いを、ぜひ見つけてみてください。
関連する記事
日本百名山について詳しく知りたい人は

登山の専門家が調査した正確なルートやコースタイム、見どころ情報までを一つにまとめました。
紙地図「山と高原地図」として60年以上の信頼を重ねてきた情報が、アプリ「山と高原地図ホーダイ」で。
今すぐダウンロードして安全登山を楽しみましょう。